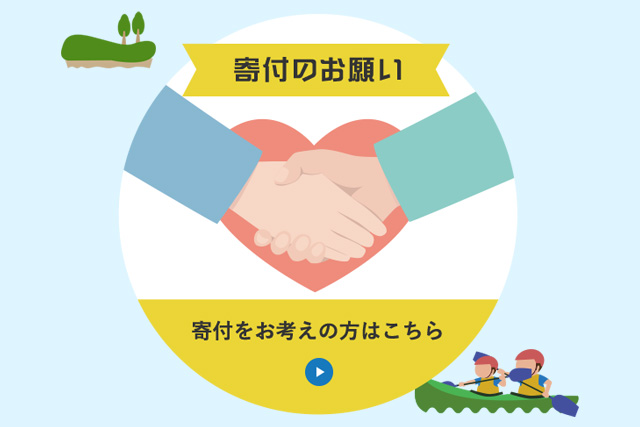マンガふるさとの偉人
郷土ゆかりの偉人を知り、ふるさとへの愛情と理解を育むことを目的に2021年度から実施している「ふるさとゆかりの偉人マンガの製作と活用事業」。21年度の30自治体に加え、22年度に実施する30自治体が決定しました。
それぞれの自治体で、郷土史家や作画者(プロ・アマ問わず)、親族などから成る委員会を組織し、資料収集、シナリオ作成、展開方法などについて協議を行い、偉人マンガを製作。製作に係る費用について300万円を上限に助成を行います。
完成後は、小中学校の総合的な学習の時間や図書館での読み聞かせ会、学芸員による解説と偉人ゆかりの史跡をめぐるツアーなど、各地でさまざまな活用が計画されています。
2022年度実施自治体一覧
| 1. 青森県 弘前市 陸 羯南 |
苦難の前半生をたどりながらも、大日本帝国憲法発布のその日に新聞『日本』を創刊。“国民主義”を掲げて堂々と論陣を張り、“独立不羈”のジャーナリストとして日本の言論界に大きな足跡を残した。 |
|---|---|
| 2. 岩手県 花巻市 佐藤 昌介 |
札幌農学校(現北海道大学)第1期生としてクラーク博士に学び、同校を北海道帝国大学として昇格させ、初代総長となった。 |
| 3. 宮城県 川崎町 支倉 常長 |
伊達政宗の使者として太平洋・大西洋を渡り、日本初となる通商外交の国際舞台で活躍した、世界史に名を残す郷土の偉人。 |
| 4. 秋田県 男鹿市 天野 芳太郎 |
アンデス文明研究家。南米に渡り、農、漁業などの事業を展開し、その資金で古代アンデスの遺跡の発掘・収集・保護に取り組んだ。私財を投じリマ市に「天野博物館」を設立し、ペルー共和国から文化勲章を受章した。 |
| 5. 山形県 尾花沢市 高宮 常太郎 |
大正10年に開田の貯水池として完成した現‣徳良湖の築堤や尾花沢と大石田間を結ぶ尾花沢鉄道敷設に大きく尽力した。尾花沢市初の名誉市民。 |
| 6. 福島県 塙町 白石 禎美 |
東白商事株式会社の創業者で町発展のために私材を惜しまず提供し、その功績につき、平成17年に塙町名誉町民に任命された。 |
| 7. 埼玉県 松伏町 山崎 峯次郎 |
日本で初めて純国産カレー粉の独自製法による製造に成功。日本人の好みに合わせたカレー粉は、国内におけるカレーの普及とカレー文化発展に貢献し、国民食へと押し上げた。 |
| 8. 埼玉県 吉見町 源 範頼 |
平安時代末から鎌倉時代初頭に活躍した武蔵武士。源頼朝の弟。源平の合戦では東軍の総大将を務め、兄頼朝の命を受け全国に転戦した。 |
| 9. 新潟県 胎内市 板額御前 |
鎌倉時代初期に活躍した、城一族(平氏)の女性武将。鎌倉幕府軍と戦い、弓の腕は百発百中と『吾妻鏡』に記されている。日本史における数少ない女武将の一人。 |
| 10. 新潟県 新潟市 田沢 実入 |
信濃川下流域の水害を激減させ、新潟平野を日本有数の豊かな穀倉地帯に変えた大河津分水路の開通に尽力した新潟市南区ゆかりの偉人。 |
| 11. 新潟県 燕市 鈴木 文臺 |
北越を代表する儒学者。1833年に私塾「長善館」を創設し、「済世救民」を大切な教えとして、多くの逸材を輩出した。 |
| 12. 富山県 南砺市 松村 謙三 |
戦後の混乱期に、文部、厚生、農林大臣を歴任し、社会・経済の発展及び中国との国交回復に尽力。農地改革の断行、日中国交正常化の基礎を築いた。 |
| 13. 富山県 砺波市 利波臣志留志 |
東大寺の大仏造営が財政的に行き詰る中、聖武天皇の求めに応じて全国一位となる米3000石を寄付し、大仏完成に大きく貢献。その後、伊賀守に任命され、無位から異例の立身出世を果たした。 |
| 14. 岐阜県 富加町 斎藤 新五 |
織田信長の側近、加治田城主。斎藤道三の末子といわれ、いち早く信長に従って美濃攻略で頭角をあらわす。馬廻衆として各地を転戦し上杉征伐で大きな功績をあげるが、本能寺の変にて討死。 |
| 15 岐阜県 恵那市 山本 芳翠 |
画家を目指して西洋に渡り、本格的に洋画を学び、帰国後、日本にその画法を広めた明治洋画壇の先駆者 |
| 16. 愛知県 西尾市 岩瀬 弥助 |
岩瀬文庫の設立をはじめ、西尾鉄道の敷設、病院や学校の建設資金の寄附など、まちづくりや地域の教育・文化向上に貢献した。 |
| 17. 三重県 菰野町 八重姫 |
菰野藩初代藩主「土方雄氏」の正室。織田信長の孫娘にあたり、信長譲りの気品や器量とその人望の厚さから領民に慕われ、92歳という天寿を全うするまで、菰野藩の藩政に尽くした。 |
|
18.
三重県 亀山市 ヤマトタケル オトタチバナヒメ |
ヤマトタケルは「古事記」「日本書紀」に登場する古代の皇子。天皇の銘を受け九州から東北まで戦いの旅を重ね、現在の亀山市北東部とされる「能褒野」で最期を迎え、その墓から魂が白鳥となって天空へ飛び立ったとの伝承がある。 オトタチバナヒメはヤマトタケルの妃で、市域中央部の出身とされる。ヤマトタケルの旅に同行し、現在の東京湾口において嵐に遭遇したヤマトタケルを救うために海に身を投げたとの伝承がある。 |
| 19. 兵庫県 南あわじ市 鶴澤 友路 |
重要無形文化財「義太夫節三味線」保持者で、日本の「女流義太夫」の第一人者として国内はもとより多くの海外公演を行い、技芸の保存伝承に貢献。淡路島初の人間国宝。 |
| 20. 兵庫県 猪名川町 加茂 守 |
現在、多くの人が当たり前のように手に触れる「たまごパック」。割れやすい卵を守り、大量陳列を可能にする、この便利な製品を発明した。 |
| 21. 京都府 南丹市 井上 堰水 |
幕末に維新の志士として活躍した後、教育に人生を捧げ、当時、学校教育制度が始まったばかりの日本において、学校田や学校林での授業など、地域独自の教育方法を早期から導入するなど画期的な教育を取り入れた、近代教育の第一人者。 |
| 22. 鳥取県 伯耆町 辻 晉堂 |
若くして才能の非凡さを認められ、日本美術院の院友を経て同人に推挙され、木彫の代表的作家として高い評価を受ける。彫刻の世界に新たな領域を開き、彫刻界に多大な足跡を残すとともに、世界的彫刻家として名声を博し、文化の向上・振興に寄与した。京都市文化功労者。 |
| 23. 岡山県 井原市 平櫛 田中 |
明治、大正、昭和の三代にわたり活躍し、近代木彫史に残る数々の名作を生み出した木彫界の巨匠。文化勲章受章者。 |
| 24. 岡山県 奈義町 井戸 泰 |
ワイル病の病原菌を発見し、第6回帝国学士院恩賜賞、1919年にはノーベル賞(医学・生理学賞)にノミネートされるなど、大正時代の日本を代表する医学者。 |
| 25. 岡山県 津山市 箕作 阮甫 |
蘭学の研究を重ね、幕府天文台翻訳員となり、ペリー来航時に米大統領国書を翻訳、また対露交渉団の一員として長崎にも出向くなど、幕末の対外交渉時に活躍した。 |
| 26. 岡山県 赤磐市 永瀬 清子 |
日本を代表する女性詩人、現代詩の母と呼ばれている。岡山県詩人協会設立に尽力し後進の育成に励み、ハンセン病療養所の入所者と詩作による交流を行うほか、世界連邦運動、岡山女性史研究会など、社会活動にも注力した。 |
| 27. 徳島県 阿南市 森 甚五兵衛 |
阿波水軍を率いて、大坂冬の陣で多くの武功をあげ、徳川方についた蜂須賀家躍進の原動力となった。江戸時代に入って、全国的に水軍は弱体化する中、阿波南方の雄として森家の基を築いた。 |
| 28. 福岡県 みやこ町 吉田 健作 吉田 増蔵 |
兄の健作は、明治維新以後の殖産興業、特に製麻業の工業化の技術を学ぶためフランスに留学。近代的な製麻工場を国内の3か所に建設し、明治政府における急速な近代化に尽力した。 弟の増蔵は、宮内省図書寮に勤務し、その長であった森鴎外に才能を高く評価され、鴎外が取り組んでいた「大正」に次ぐ元号の考案作業に携わり、増蔵が考案した「昭和」が選定された。また上皇陛下の御名である「継宮 明仁」など、皇室に関わる称号等の考案作業に深く関わった。 |
| 29. 熊本県 南関町 北原 白秋 |
日本を代表する歌人・詩人。南関町の石井家(母の実家)で誕生し、幼少期に石井家の書物や南関町の自然に触れ文学の基礎を培った。生涯に数多くの詩歌を残し、今なお歌い継がれる童謡を数多く発表した。 |
| 30. 鹿児島県 南さつま市 黒瀬杜氏三人衆 (片平一、黒瀬常吉、黒瀬巳之助) |
明治後期、自家用焼酎の製造が禁止され、焼酎製造の専門技術が酒蔵に求められる時代に、南さつま市笠沙町黒瀬地区の3人の若者を中心に、全国の酒蔵に杜氏や蔵子として入り、醸造技術を日本各地に伝え、現在の焼酎造りの礎を築いた。 |
ふるさとの偉人を知ることで、子どもたちの郷土教育、キャリア教育につなげていきます。
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。