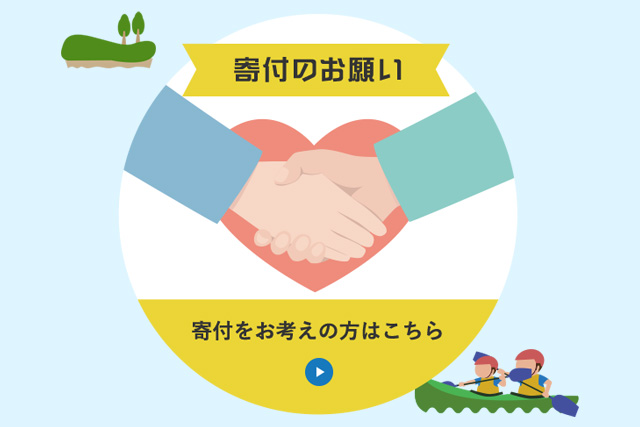スペシャル 夢をつなげ!B&Gアスリート
スペシャル:夢をつなげ!B&Gアアスリートパラカヌー 今井 航一選手 インタビュー前編
2021.07.02 UP
2021.07.02 UP

5月13日(木)~15日(土)ハンガリーで開催された2021 ICF PARACANOE WORLD CUP 1 (PARALYMPIC QUALIFIER) 「パラカヌーワールドカップ パラリンピック選考会」で、B&G高瀬海洋クラブ(香川県三豊市)出身の今井航一選手(株式会社コロプラ、香川県パラカヌー協会、日本障害者カヌー協会所属)が、2020東京パラリンピックの代表選手に内定しました。
出場種目は、カヌー競技男子ヴァーVL3、東京大会から採用された新種目です。
ヴァー種目は、ダブルブレードパドルで長さ5.2mのカヌーを漕ぐカヤック種目に対し、シングルブレードパドルでアウトリガー(アマ)の付いた長さ7.3mのカヌーを漕ぎます。両種目とも平水200mを漕いだ順位を競うカヌースプリント競技です。
女子カヤックKL1種目に瀬立モニカ選手、男子ヴァーVL3種目に今井航一選手、パラリンピックカヌー競技に2名のB&Gアスリートが出場します。 この度、今井航一選手に75分にわたるロングインタビューでお話を伺いました。
B&G財団(以下「BG」と記載):東京大会出場内定おめでとうございます。今日は、全国のパドラーに代わって、一歩踏み込んだ話をお聞きします。今井さんは、小中学生、社会人と永らく剣道を続けていたそうですね。
今井航一選手(以下「今井」と記載):しっかり取り組んだスポーツは、剣道だけでした。
BG:今井さんは歩行中に車に轢かれ左足にケガを負いリハビリを続けましたが、2013年左足に悪性肉腫が見つかり、左大腿部の中程から切断しました。その時の心境を今井さんは「新しいスタートと感じた」と話されています。
今井:事故などで足を切断された方は、突然の喪失感に戸惑ってしまうと思います。私の場合は、治療として「自身の意思で切断を決めた」ので、変化を受け入れることができました。自分が決めた結果なので納得して「片足を失った新しい身体でもう一回人生をスタートしよう」と気持ちを整理しました。

BG:新しいスタートとして、左足切断後の2013年に水泳を始め、2015年和歌山県で開催された「全国障害者スポーツ大会」水泳男子50m自由形で優勝されました。水泳を選んだ理由はありますか?
今井:腫瘍治療の入院が8ヵ月に及び、抗がん剤の影響もあり体力が低下しました。体力回復のため運動したいと思い、慣れない義足でも始められるスポーツとして水泳を選びました。プールに通い始めると、障害を持った方も泳いでいて競泳チームがあったので、チームに加わりました。
BG:プルが重視される自由形でキックの制限も重なる分、上半身や体幹の筋力が求められます。競技歴2年で優勝するには、どのようなトレーニングをしましたか。
今井:水泳も現在のカヌーでも同じなのですが、陸上トレーニングはそれほどしていません。私の練習スタイルは、泳いだり漕いだり実際の競技の動きから技術と必要な筋力を向上させるのが良いと思っています。

BG:全国大会優勝で競泳に区切りをつけ、2017年10月に三豊市高瀬B&G海洋センタープールで初めてB&Gカヌー(普及艇)に乗り、すぐにスプリント競技艇にチャレンジされます。他のインタビューでは、高校時代カヌーで全国優勝の経験がある「奥様の勧め」とありましたが、今井さん自身「鍛えた上半身、自由形とカヌーのストロークや水をつかむ感覚の共通性」に競技の可能性を感じていたのではないですか?
今井:当時、妻からカヌーの話は聞いていましたが、カヌーの実物を見たこともなく、ボートとの違いもよく分かりませんでした。それでもカヌーについて調べてみると、自由形の肩や肩甲骨の動き、水を掴む感覚に共通性があり、水泳の延長線で自身の運動能力が活かせのではないかと思いました。そして、キックに制限のある競泳より高いレベルで戦えるのではないかと、カヌー経験もない状態でしたが直感的に思いました。
BG:ところが実際に競技艇に乗ってみると、4ヵ月もの間 海洋センタープールで「沈」を繰り返して苦しみます。秋冬に冷たいプールで、沈を続けるのはつらいですね。
今井:安定性の高いB&Gカヌーには何の問題もなく乗れましたが、B&G財団がジュニア用に配備した競技艇(JK-1)は設定体重も低く不安定で沈を繰り返しました。カヌーがこんなに乗りにくいものとは全く思っていませんでした。綱渡りのロープの上を歩くような感覚でした。私は、左足切断のため左半身が右半身に比べ6㎏も軽く、静止した状態でもそのままではバランスが取れないのです。その頃は、週1回程度の練習だったので、せっかく覚えた感覚も次の週には忘れていて、何度も冷たいプールで沈を繰り返しました。
BG:4ヵ月の苦闘の後、2ヵ月ほど競技艇で練習を続けていた頃、初めて「パラカヌー」に試乗されます。カヌーは器材スポーツなので、専用の器材に乗った時はどのように感じましたか?
今井:「これならイケる」と手応えを感じました。競技艇で練習を積んだ成果で、パラカヌーを乗り易く感じました。この時、本格的にカヌー競技に取り組む決意が固まりました。
BG:そして、2018年の夏にパラカヌーを入手して本格的な練習が始まります。三豊市高瀬B&G海洋センター艇庫のある国市池では、カヌーの強豪 県立高瀬高校カヌー部が活動し、優れた指導者もいらっしゃったと思いますが、パラカヌーならではの苦労はありましたか?
今井:香川県はカヌーの盛んな地域で、指導者や競技経験者が多く、練習をサポートしてくれました。パラカヌー経験者はいませんでしたが、互いにわからないことは話し合って想像しながら手探りで課題を解決していく関係が生まれたと思います。指導を受けても、私にでき難いこととして、上半身と下半身を連動して艇をコントロールすることがありました。上半身で生み出したパワーを艇に伝える感覚を、指導者と私で共有するのが困難でした。この問題に悩んでいた時、地元の老舗機械メーカー株式会社イナダに「カヌーと足の固定具」を作っていただきました。金属加工のプロとはいえ、固定具を作るのは互いに初めてでしたので、この開発でも意見交換が重要でした。身体の動きをカヌーに伝える固定具は、重要な競技パーツであり今もイナダさんが支援してくれます。
BG:B&G財団も指導者組織「B&G全国指導者会」と協力して、障害者差別解消法に合わせ2015年から、乗降サポートなどの技術を学び、「艇に乗る」対応はできるようになりました。固定具としてビーズクッションを使っていますが、今後利用者から「速く、自在に漕ぎたい」という要望があれば、固定具の改良が必要ですね。

今井:ビーズクッションは様々な障害や体格の方に対応できる良い素材です。香川県パラカヌー協会の体験会でも、ビーズクッションやウレタンを使用しています。さらに高いレベルを目指す方には専用の固定具が必要になります。カヌーを続けるには、「艇に乗れた」ことをきっかけに「上手に漕げた」につなげ「上手くなりたい」と思ってもらうことが大切です。
BG:本格的な練習を始めた直後の9月に、石川県小松市の木場潟カヌー競技場で開催された「平成30年度日本パラカヌー選手権大会」にエントリーされましたが、強風のため大会中止となりました。 今井さんは、スタートを待つ水面待機の状態だったそうですが、デビュー戦のスタート直前で大会中止ではガクッとしますね。
今井:デビュー戦当日は強風で波も高い荒れた水面で、大会中止となった時は、残念な気持ちと正直ホッとした気持ちの半々でした。次の大会に向けて「半年間の練習ができる」と気持ちを切り替えました。
後編では、カヌー選手、カヌー普及、講師として、今井さんの活躍が始まります。