- # リーダー
-
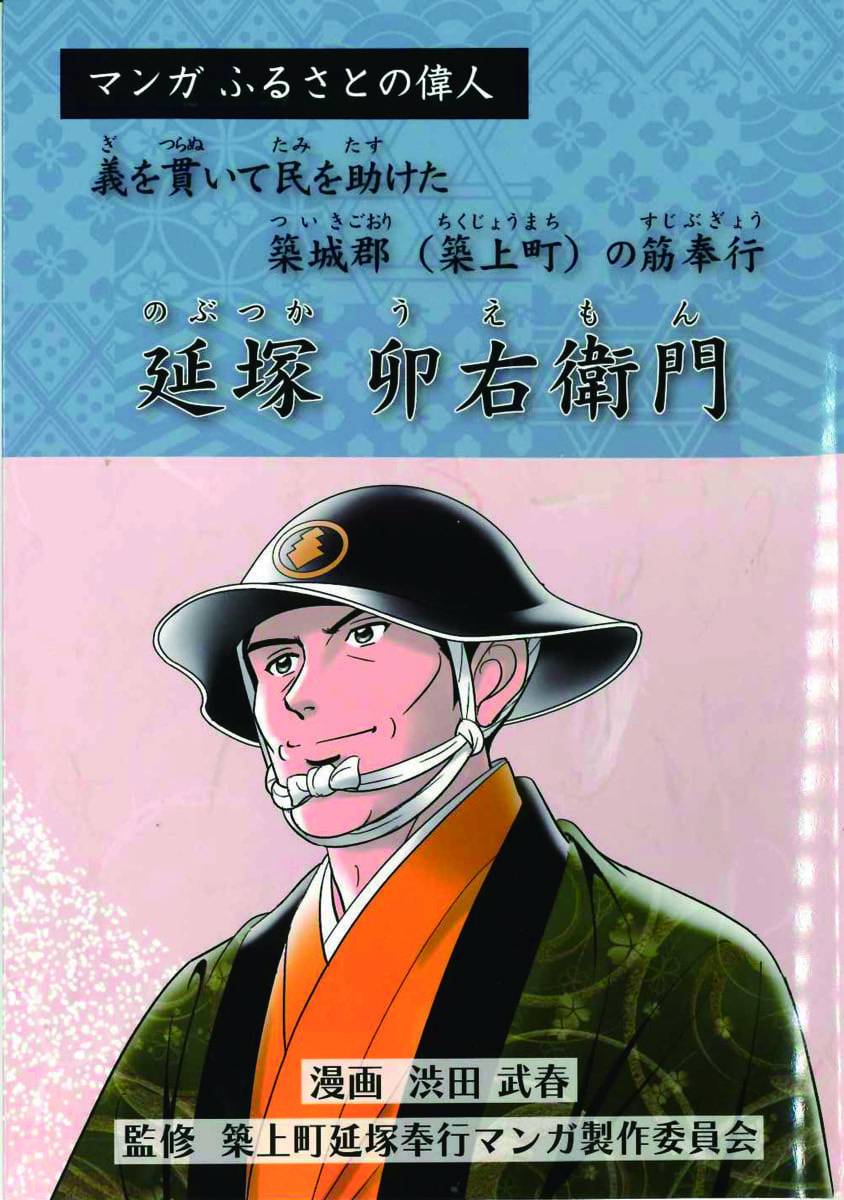
飢饉の農民を助け、切腹した筋奉行 延塚卯右衛門 のぶつか うえもん
福岡県築上町マンガ家:渋田武春延塚卯右衛門(のぶつか うえもん)は、江戸時代中期天明2年(1782年)豊前国京都郡(現福岡県苅田町)に生まれ、天保3年(1832年)51歳で小倉藩築城郡筋奉行として豊前国築城郡(現福岡県築上町)に着任しました。翌天保4年から「天保の大飢饉」が続き、天保7年延塚奉行は藩から農民に貸し付けた根付料の返済を独断で免除し、その責を取って切腹しました。180年以上経った現在も追善供養祭が行われています。
- # 近世(9)
- # 社会貢献(7)
- # ヒーロー・ヒロイン(11)
- # リーダー(23)
- # 愛・献身(18)
- # 武人・サムライ(12)
- # カッコイイ(28)
- # 感動(22)
- # 泣ける(5)
- # 渋田武春(1)
- # 福岡県(2)
-
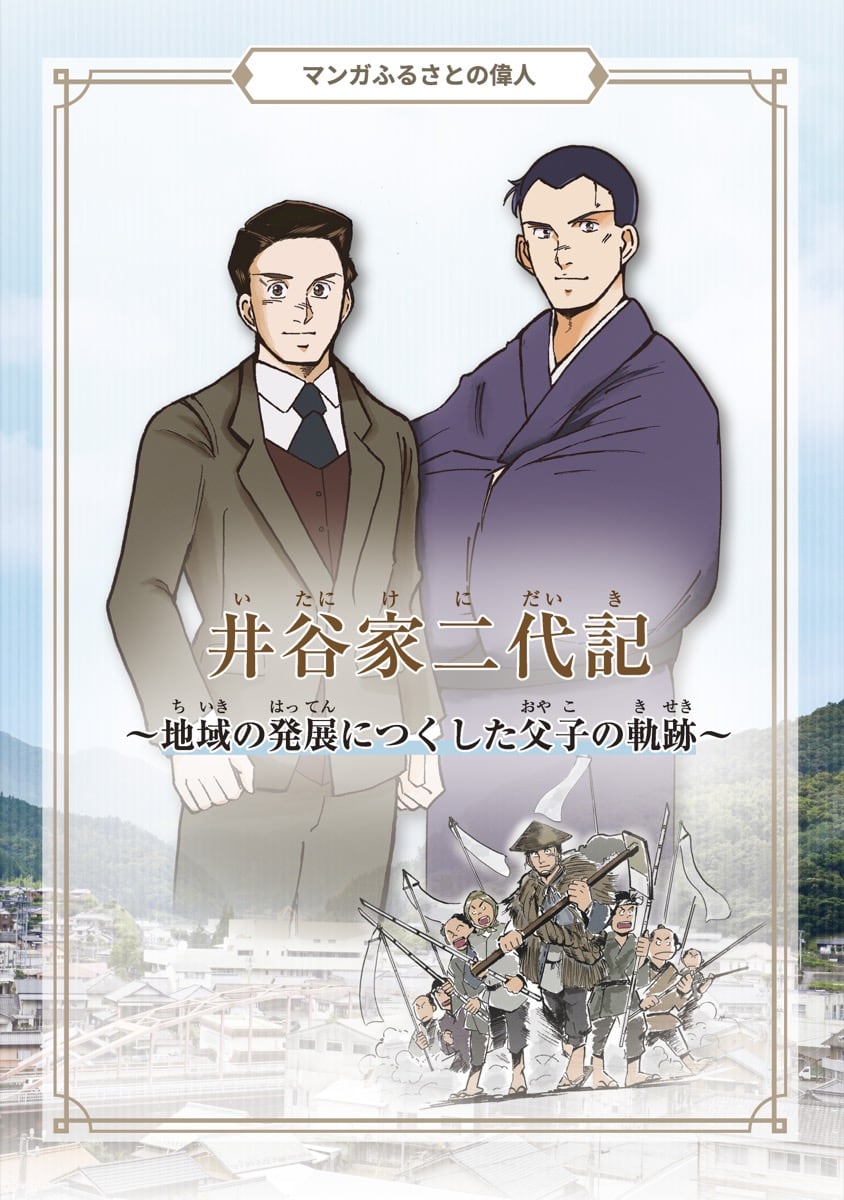
地域の発展に尽くした父子の軌跡 井谷正命、井谷正吉 いたに まさみち、いたに まさよし
愛媛県鬼北町マンガ家:南野しま井谷正命(いたに まさみち)は、江戸時代末期慶応4年(1868年)伊予国日向谷村(現愛媛県鬼北町)に生まれ、初代日吉村長、北宇和郡会議長、愛媛県会議員を歴任し、南予の道路開発に献身、私財を投じて日吉実業学校を設立した。
井谷正吉さん(いたに まさよし)は、明治29年(1896年)井谷正命の長男に生まれ、大正から昭和初期に農民運動で活動、戦後は日本社会党の衆議院議員を4期務め地域発展に尽くした。 -
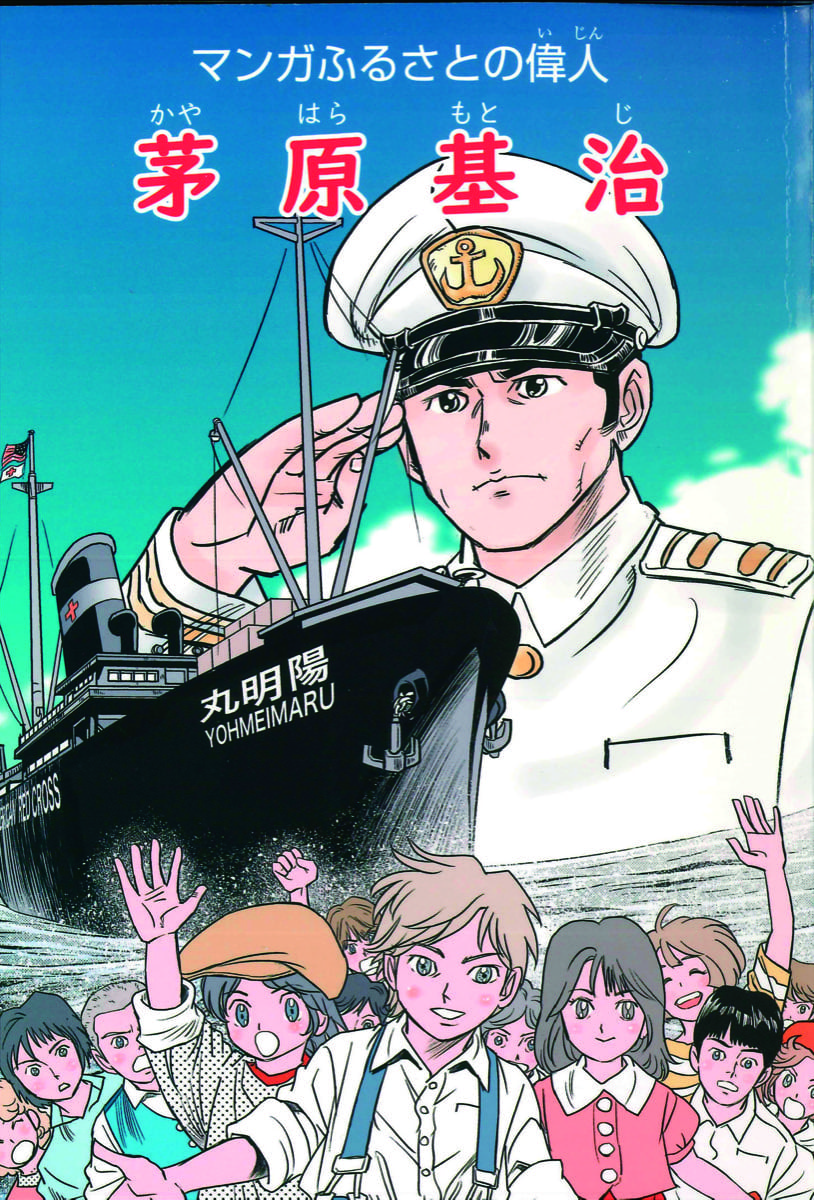
地球半周の航海で800人を救った 茅原基治 かやはら もとじ
岡山県笠岡市マンガ家:南一平茅原基治(かやはら もとじ)は、明治18年(1885年)岡山県小田郡甲弩村(現笠岡市)生まれ。大正9年(1920年)アメリカ赤十字社の依頼により勝田汽船から陽明丸の船長に任命され、ロシア革命の内戦で帰郷できなくなったロシアの子ども約800人を救出。ウラジオストク→室蘭→サンフランシスコ→パナマ運河→ニューヨーク→フランス→フィンランドと3ヵ月間地球半周の航海の末、家族のもとへ送り届けました。
- # 近代(23)
- # 社会貢献(7)
- # リーダー(23)
- # 冒険・チャレンジ(9)
- # 愛・献身(18)
- # 一般市民(7)
- # 世界で活躍(17)
- # びっくり(15)
- # カッコイイ(28)
- # 感動(22)
- # 南一平(4)
- # 岡山県(7)
-
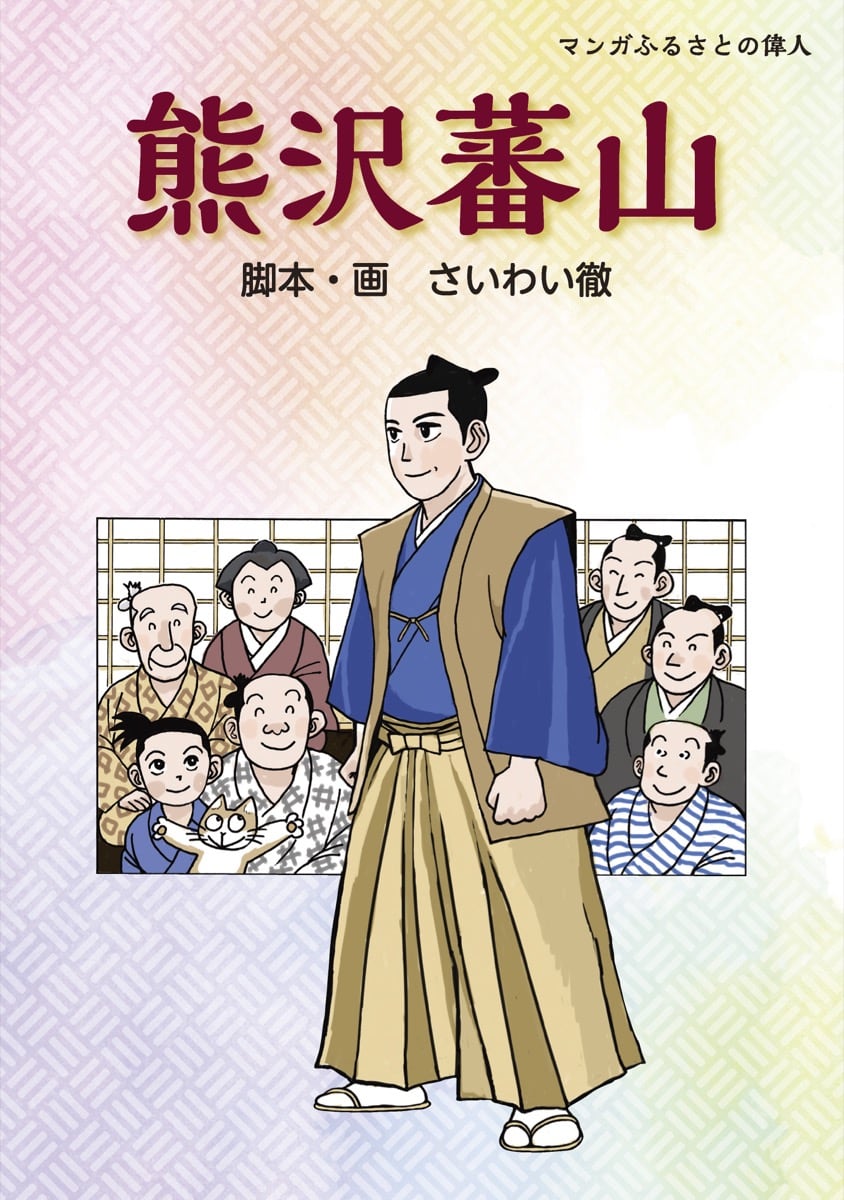
藩主を支え地域発展に尽くした 熊沢蕃山 くまざわ ばんざん
岡山県備前市マンガ家:短編マンガ監修 森熊男、マンガ さいわい徹熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)は、江戸時代初期元和5年(1619年)京都に生まれ、16歳から岡山藩主池田光政に仕えました。20歳で岡山藩を退き陽明学者中江藤樹の弟子として学問に励み、27歳で再び岡山藩に仕え、洪水復興・凶作対策として治山治水事業、飢饉の窮民対策事業で活躍しました。39歳で備前市(旧蕃山村)に隠居した後も、光政と閑谷学校創立に繋がる庶民教育事業や新田開発で地域の発展に貢献しました。
-
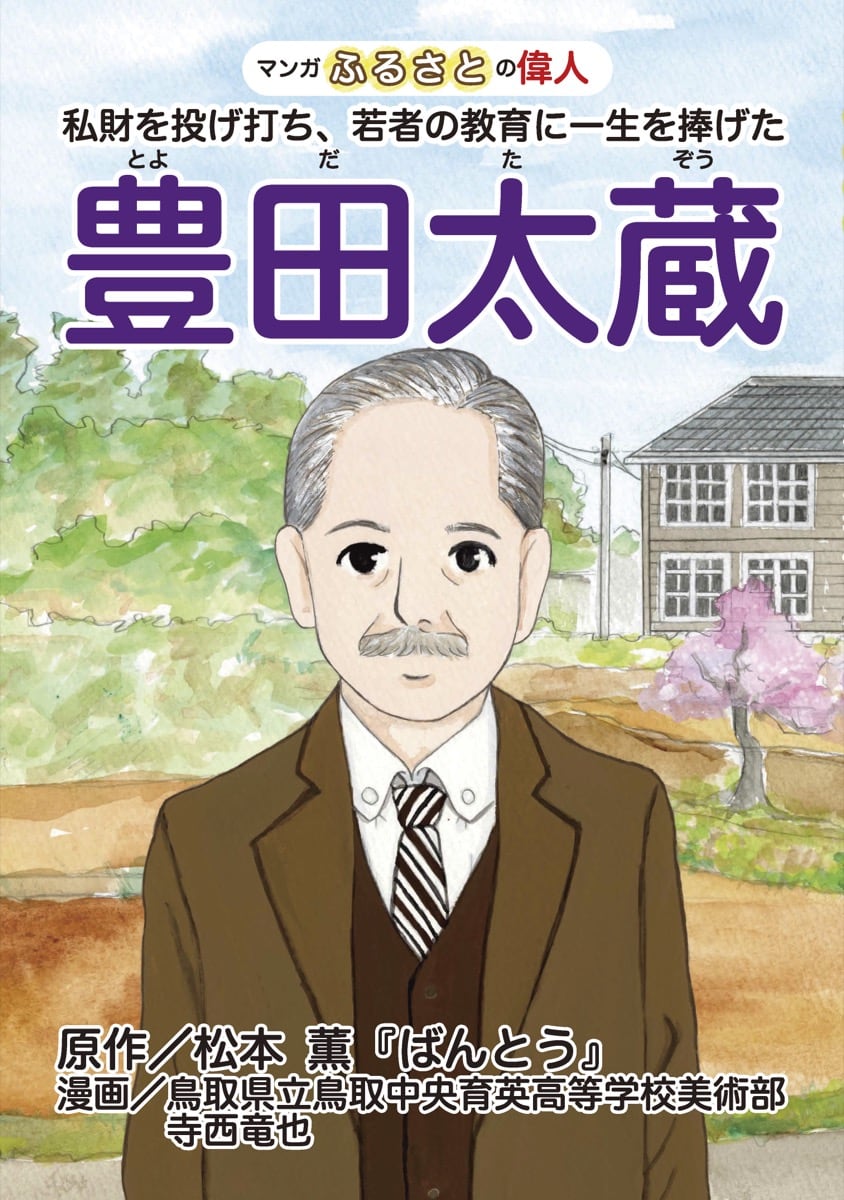
私財を投じ教育に一生を捧げた 豊田太蔵 とよだ たぞう
鳥取県北栄町マンガ家:原作 松本薫、マンガ 長谷川万桜・前美里・寺西竜也豊田太蔵(とよだ たぞう)は、幕末安政3年(1856年)伯耆国鳥取藩由良宿(現鳥取県北栄町)に生まれ、由良村議会議員・由良村長・県会議員などを務めながら、明治40年(1907年)私財を投じて私塾「育英黌」を開き、大正3年(1914年)山陰地方初の私立中学校「由良育英中学校」(現県立鳥取中央育英高等学校)を開校しました。郷土の教育に一生を捧げた太蔵の生涯は、松本薫の小説「ばんとう」に描かれました。
- # 近代(23)
- # 社会貢献(7)
- # リーダー(23)
- # 先駆者(30)
- # 起業家・ビジネスマン(14)
- # 熱血(39)
- # 前美里(1)
- # 寺西竜也(2)
- # 松本薫(1)
- # 長谷川万桜(1)
- # 鳥取県(2)
-
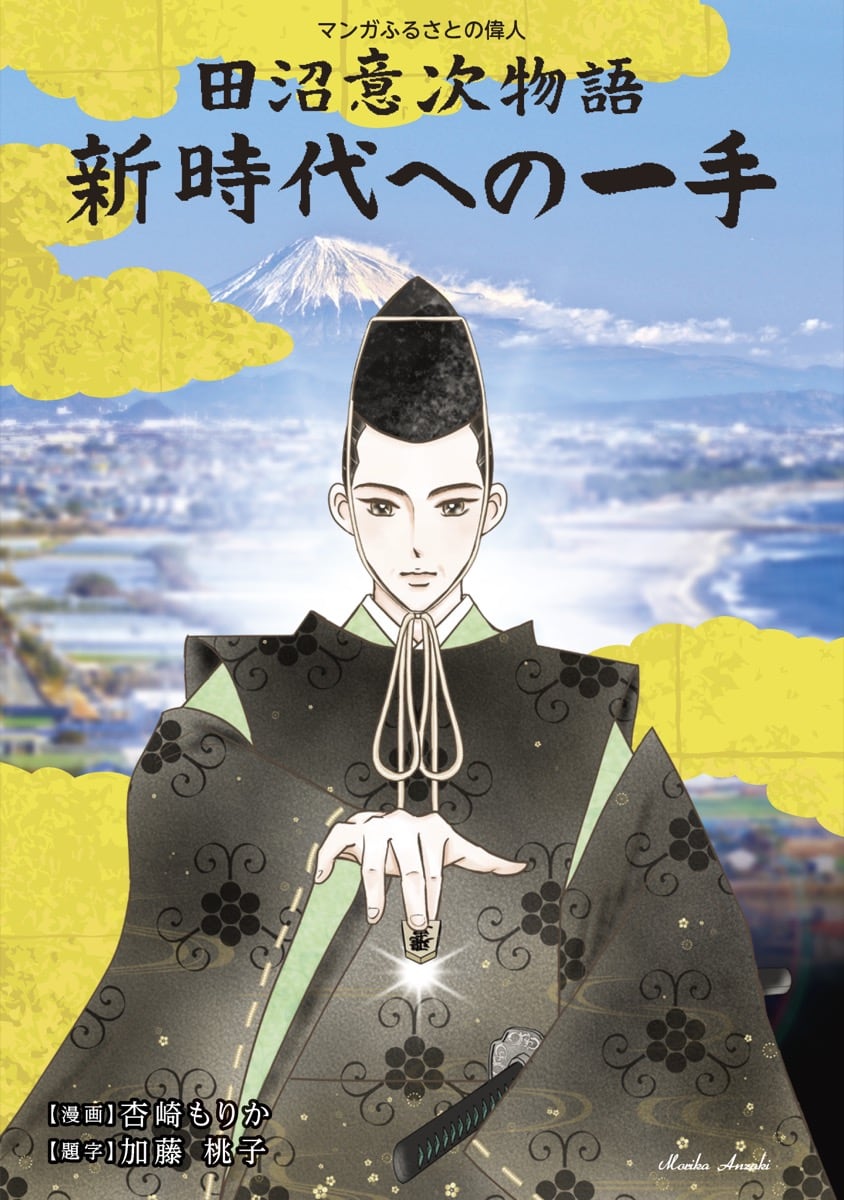
江戸幕政を改革、新時代を開いた 田沼意次 たぬま おきつぐ
静岡県牧之原市マンガ家:マンガ 杏崎もりか、将棋監修 加藤桃子田沼意次(たぬま おきつぐ)は、江戸時代中期享保4年(1719年)600石の旗本の子として江戸に生まれ、9代将軍徳川家重に認められ宝暦8年(1758年)相良藩10,000石(現静岡県牧之原市)を拝領し大名となり、10代将軍家治にも重用され幕府老中を務めました。老中田沼意次は、専売制導入、外国貿易拡大、鉱山や新田開発を行い、幕府財政を改善。貨幣経済が発展し歌舞伎や浮世絵等の江戸文化が花開きました。
- # 近世(9)
- # 政治・経済(12)
- # リーダー(23)
- # 先駆者(30)
- # 型破り(12)
- # 武人・サムライ(12)
- # びっくり(15)
- # 面白い(25)
- # 加藤桃子(1)
- # 杏崎もりか(1)
- # 静岡県(2)
-
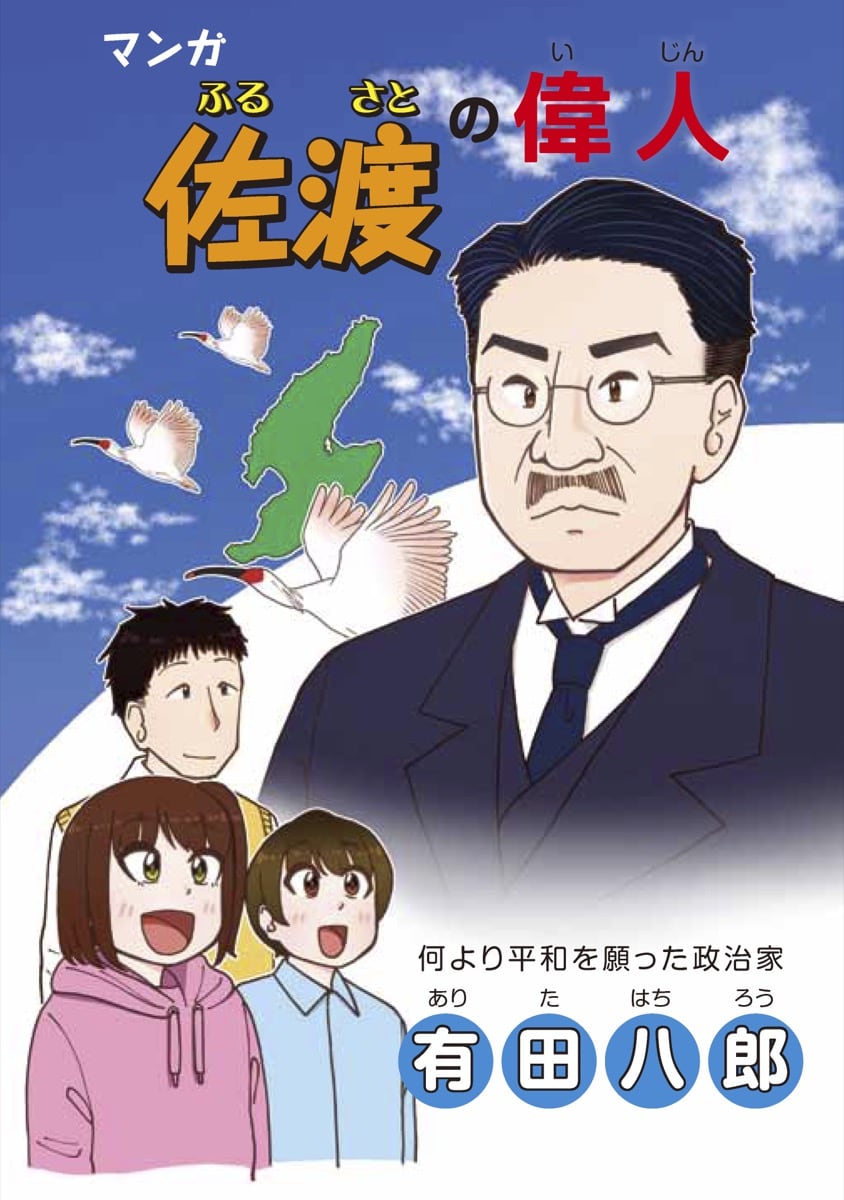
何より平和を願った政治家 有田八郎 ありた はちろう
新潟県佐渡市マンガ家:シカクメガネ有田八郎さん(ありた はちろう)は、明治17年(1884年)新潟県佐渡郡真野村(現佐渡市)に生まれ、明治42年(1909年)外務省入省、外務次官、中国大使を歴任しました。昭和初期、経済と国際社会の混乱を背景に軍が台頭し戦雲が濃くなる中でも、八郎は戦争に反対し続けました。外務大臣を4度務め、天皇に太平洋戦争の早期終結を上奏、戦後もソ連に抑留された日本人の引揚げに尽力するなど平和を愛した政治家です。
-
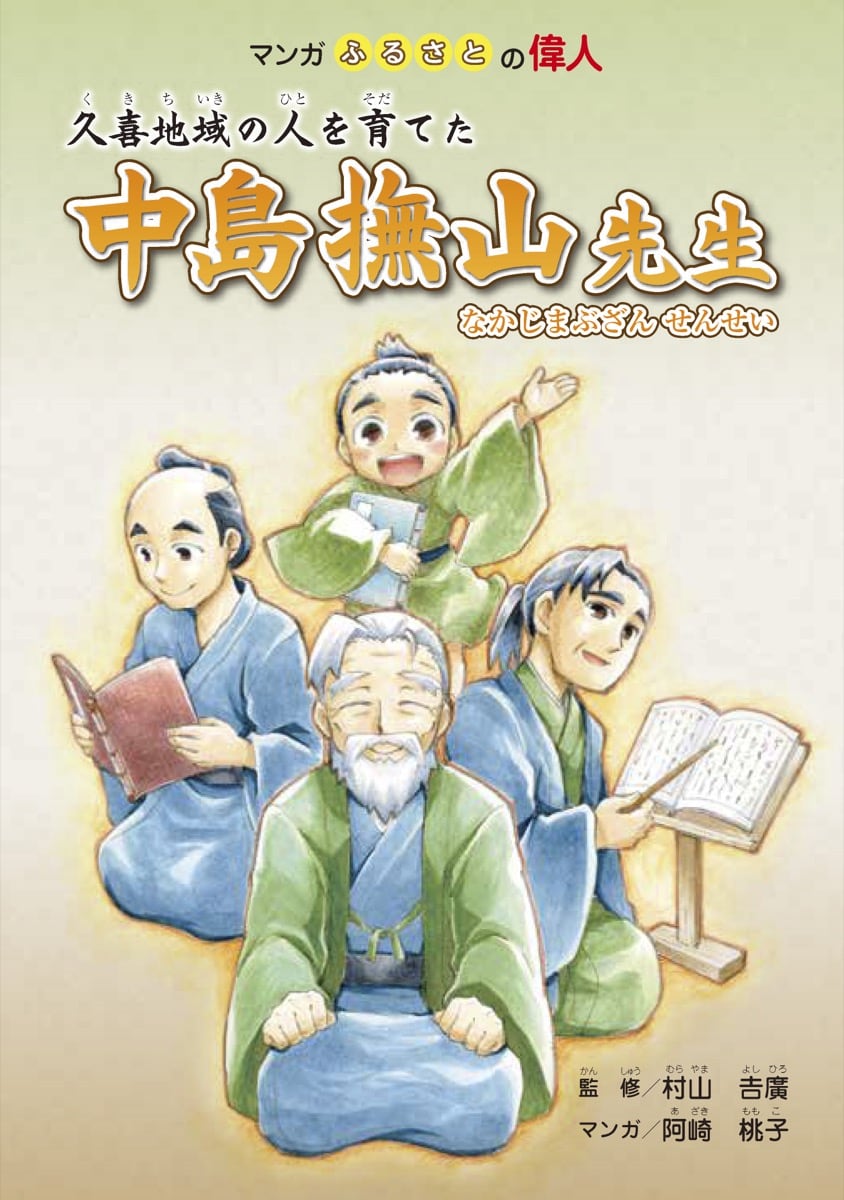
学校を開き、人材を育てた 中島撫山 なかじま ぶざん
埼玉県久喜市マンガ家:監修 村山𠮷廣、マンガ 阿崎桃子中島撫山(なかじまぶざん)は、文政12年(1829年)江戸に生まれ、安政5年(1858年)私塾「演孔堂」を開き、明治維新を経て久喜本町(現埼玉県久喜市)に移り、明治3年(1870年)に私塾「演孔堂」を再開、学制公布に伴い明治6年(1873年)に私立学校「幸魂教舎」を開校し、地域の教育に尽力して多くの人材を育てました。
また孫の「中島敦」は、撫山が晩年暮らした久喜新町宅で幼少期を過ごしました。 -
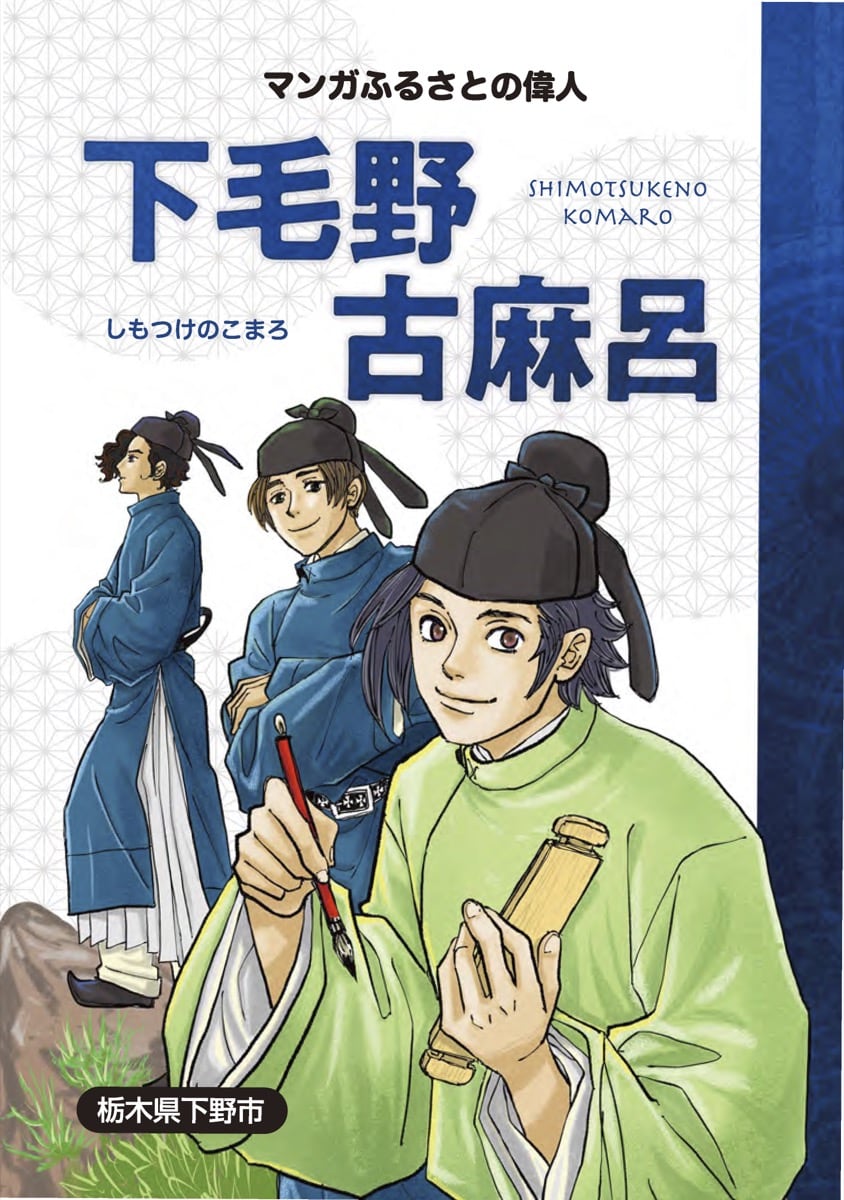
大宝律令をまとめ国家体制を作った 下毛野古麻呂 しもつけのこまろ
栃木県下野市マンガ家:マンガ 朔田浩美・治島カロ、原作 山口耕一下毛野古麻呂(しもつけのこまろ)は、飛鳥時代中期(650年頃)下野国河内郡(現栃木県下野市周辺)を本拠とする豪族下毛野氏に生まれ、都に出て持統・文武・元明3代の天皇に仕え参議・兵部卿・式部卿・大将軍などを歴任しました。特に、文武天皇の命を受け忍壁親王・藤原不比等・粟田真人と共に、大宝元年(701年)大宝律令をまとめ、天皇を中心とする中央集権的な政治制度、地方管制など古代日本の仕組みを作りました。
- # 古代(4)
- # 歴史・伝説(13)
- # リーダー(23)
- # 先駆者(30)
- # 日本初(11)
- # カッコイイ(28)
- # 面白い(25)
- # 山口耕一(1)
- # 朔田浩美(1)
- # 治島カロ(1)
- # 栃木県(1)
-

笠間焼中興の祖 田中友三郎 たなか ともさぶろう
茨城県笠間市マンガ家:シナリオ 矢口圭二、マンガ 稲田ちゃこ田中友三郎(たなか ともさぶろう)は、江戸時代後期天保10年(1839年)美濃国(現岐阜県)に生まれ、江戸に出て陶器の行商を始め、江戸に近い常陸国笠間地方(現茨城県笠間市)の窯場を開拓しました。明治2年(1869年)友三郎は笠間に移住し、自ら陶器作りを始め「笠間焼」の名で全国に売り出すと共に、陶器製造組合や陶器伝習所を設立して、窯業者の助け合いと陶工の技術向上に努め「笠間焼」の振興に貢献しました。
- # 近代(23)
- # 芸術・文化(16)
- # リーダー(23)
- # 先駆者(30)
- # 起業家・ビジネスマン(14)
- # 熱血(39)
- # 面白い(25)
- # 矢口圭二(1)
- # 稲田ちゃこ(1)
- # 茨城県(1)
-

南洋パラオと東北を繋ぐ開拓記 高橋進太郎、村山格一郎 たかはし しんたろう、むらやま かくいちろう
宮城県蔵王町マンガ家:原作 松浦まどか、作画 朝戸ころも宮城県蔵王町の北原尾(きたはらお)地区は、太平洋戦争後の1946年パラオからの引き揚げ者の入植地として開拓が始まりました。元南洋庁拓殖部長高橋進太郎さん、同部村山格一郎さん達の尽力と、32戸の入植者が努力した結果、酪農で成功しました。2001年パラオ共和国トミー・レメンゲサウ大統領の蔵王町訪問を機に、子どもたち相互の訪問事業、東京オリンピックパラオ選手団ホストタウンなどの国際交流が続いています。
- # 近代(23)
- # 歴史・伝説(13)
- # リーダー(23)
- # 愛・献身(18)
- # 一般市民(7)
- # 世界で活躍(17)
- # 感動(22)
- # 熱血(39)
- # 朝戸ころも(1)
- # 松浦まどか(1)
- # 宮城県(2)
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。


