- # 現代
-

徳良湖を作り、花笠音頭が生まれた 髙宮常太郎 たかみや つねたろう
山形県尾花沢市マンガ家:原作 あべ美佳、マンガ 瀧宏一・東北芸術工科大学漫画研究同好会髙宮常太郎さん(たかみや つねたろう)は、明治19年山形県尾花沢村(現尾花沢市)に生まれ、大正8年農業用水確保の人造湖「徳良湖」の築堤を始め、大正10年その完成により荒地が水田や畑に開拓されました。
また、築堤工事の作業歌から全国に知られる「花笠音頭、花笠踊り」が生まれました。
その後も髙宮さんは、尾花沢鉄道開業、尾花沢貨物自動車㈱設立、旧尾花沢町長、山形県議会議員などで地域に貢献しました。- # 現代(35)
- # 社会貢献(14)
- # リーダー(39)
- # 先駆者(43)
- # 愛・献身(36)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 感動(33)
- # 熱血(61)
- # あべ美佳(1)
- # 東北芸術工科大学漫画研究同好会(1)
- # 瀧宏一(1)
- # 山形県(2)
-

ペルーにアンデス文明博物館を開館 天野芳太郎 あまの よしたろう
秋田県男鹿市マンガ家:坂田もち江天野芳太郎さん(あまの よしたろう)は、明治31年(1898年)秋田県脇本村(現男鹿市)に生まれ、昭和3年(1928年)南米に渡り、パナマ、ペルー、などで事業を行うと共に古代アンデス文明の遺跡を調査しました。昭和16年(1941年)第二次世界大戦勃発により、南米の財産を失い日本に帰国しますが、終戦後また南米に渡りペルーで事業を成功させると遺跡調査を行い、収集した遺物を展示する博物館を開きました。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 冒険・チャレンジ(18)
- # 発明・発見(13)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 世界で活躍(31)
- # びっくり(38)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # 坂田もち江(1)
- # 秋田県(2)
-
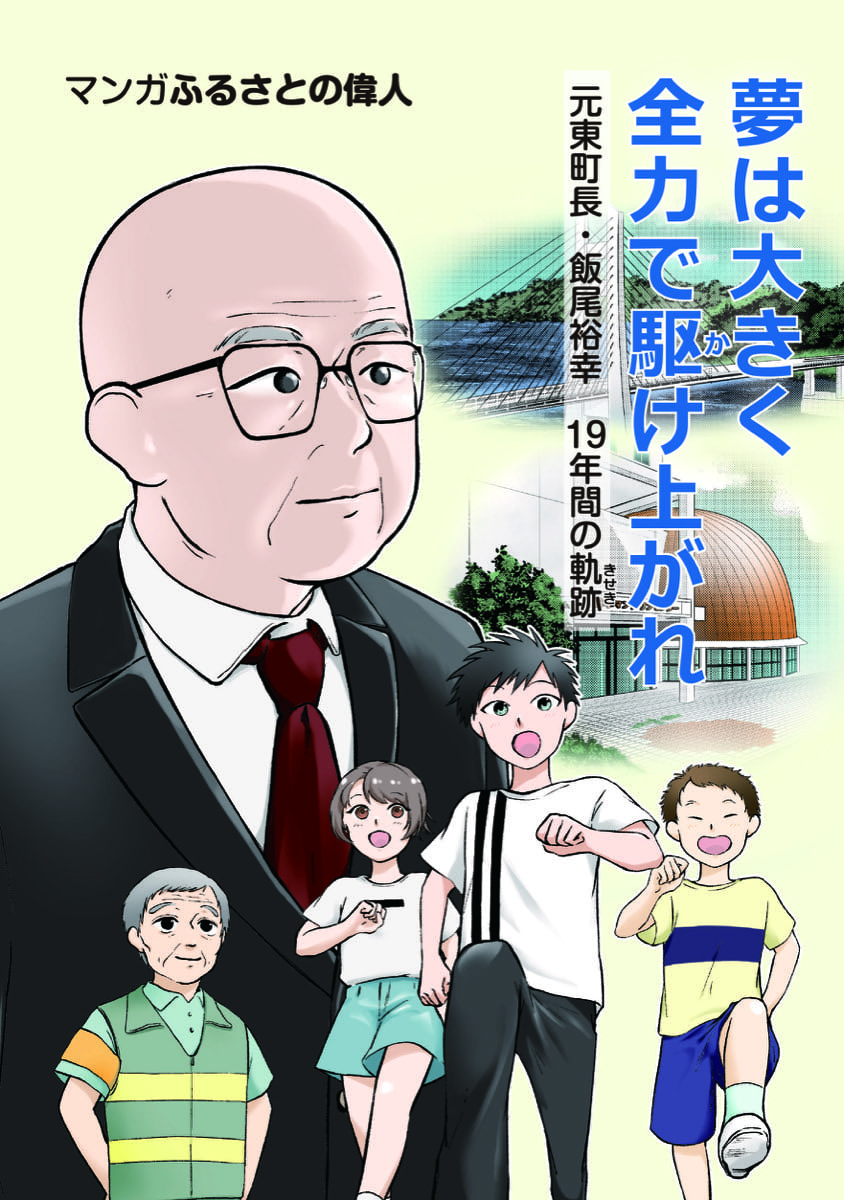
離島振興に19年間尽力した町長 飯尾裕幸 いいお ひろゆき
鹿児島県長島町マンガ家:あさごはん飯尾裕幸さん(いいお ひろゆき)は、大正2年(1913年)鹿児島県出水郡東長島村(現長島町)に生まれ、小学5年生で引越し、昭和46年(1971年)59歳で東町(現長島町)に帰郷しました。昭和49年本土とつなぐ島民念願の黒之瀬戸大橋が完成しますが、同時に離島補助金もなくなりました。この危機に際し、飯尾さんは昭和50年から平成6年までの19年間町長を務め、地域の産業振興・インフラ整備に尽力しました。
-

マンガ家・画家・文化人として活躍 那須良輔 なす りょうすけ
熊本県湯前町マンガ家:原作 橋本博、作画 タネオマコト那須良輔さん(なす りょうすけ)は、大正2年(1913年)熊本県球磨郡湯前村(現湯前町)に生まれ、昭和7年(1932年)洋画家を目指して上京し太平洋美術学校に入学。内職のつもりで描いたマンガが採用されて、昭和8年児童マンガ家としてデビュー。人気マンガ家となり、そこから優れたデッサン力で政治家の特徴を捉えた似顔絵の政治風刺マンガ、釣りや自然を題材とした風景画・随筆などに活動範囲を広げ活躍しました。
-
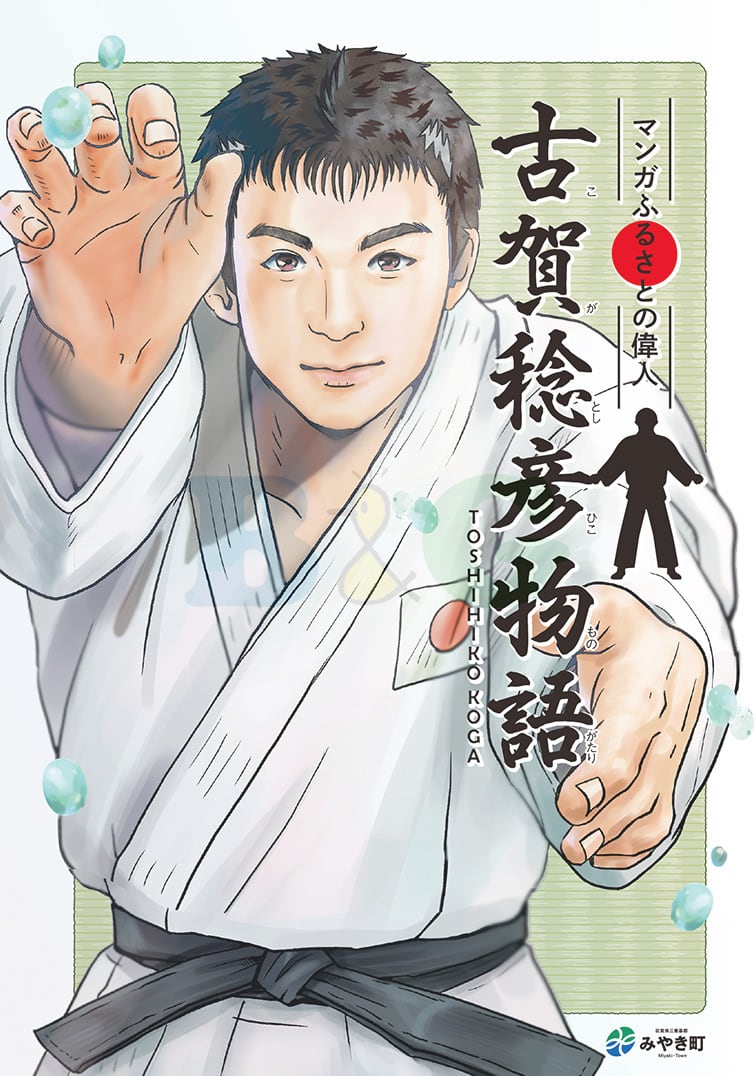
柔道金メダリスト、平成の三四郎 古賀稔彦 こが としひこ
佐賀県みやき町マンガ家:作画 毛利優子・古川渚、原案 フクチマキコ古賀稔彦さん(こが としひこ)は、昭和42年(1967年)佐賀県三養基郡北茂安町(現みやき町)に生まれ、中学1年で上京し柔道私塾講道学舎に入門。高校時代から国内外の大会で活躍。平成2年(1990年)全日本柔道選手権大会で重量級選手に「柔よく剛を制す」柔道精神を体現しての準優勝、1992年バルセロナ五輪金メダル、1996年アトランタ五輪銀メダルなど「平成の三四郎」と称される強さと人気を誇りました。
- # 現代(35)
- # スポーツ(4)
- # ヒーロー・ヒロイン(17)
- # 世界で活躍(31)
- # カッコイイ(40)
- # 泣ける(7)
- # 熱血(61)
- # フクチマキコ(1)
- # 古川渚(1)
- # 毛利優子(1)
- # 佐賀県(2)
-
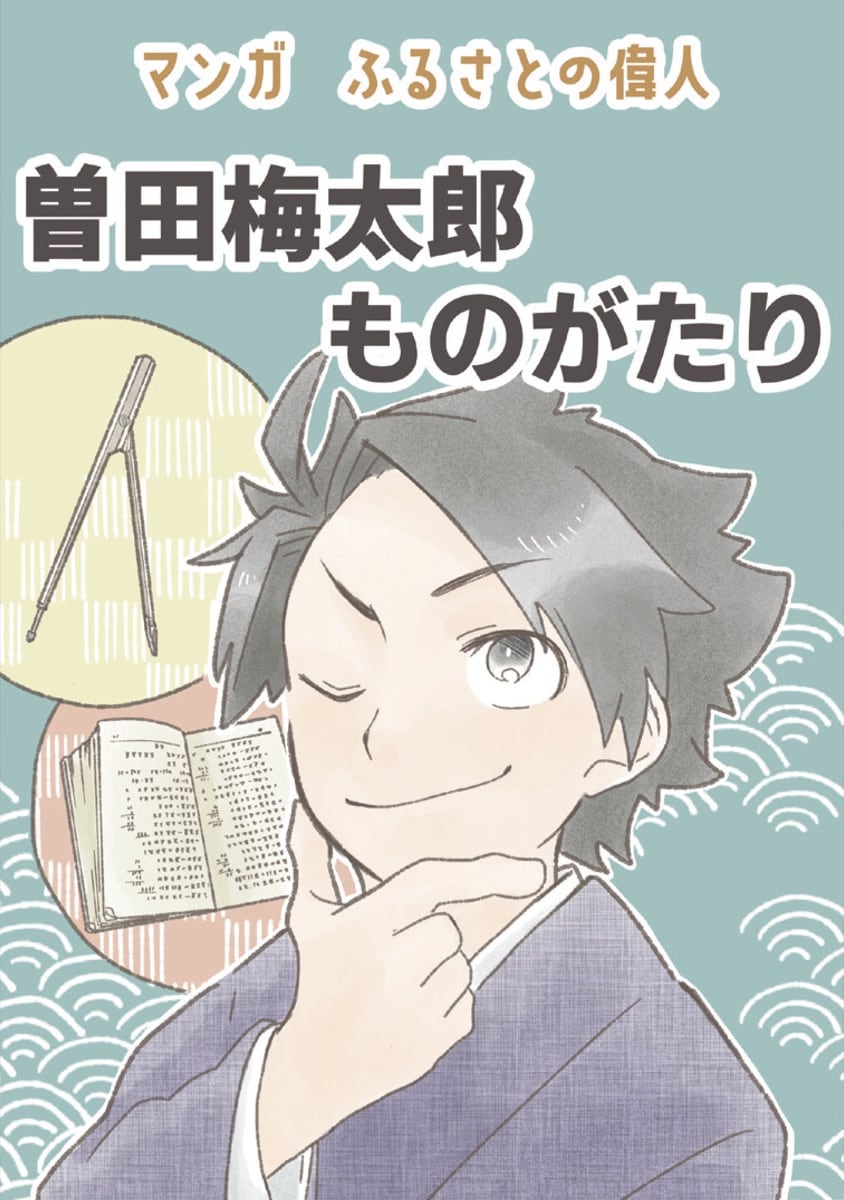
黒板コンパスを発明した教育者 曽田梅太郎 そだ うめたろう
愛知県豊川市マンガ家:監修 今泉孝之、マンガ からたちはじめ曽田梅太郎さん(そだ うめたろう)は、明治19年(1886年)愛知県宝飯郡穂野原村(現豊川市)に生まれ、広島高等師範学校へ進み、教科書の執筆や広島高等師範学校教授、雑誌「学校数学」創刊など数学教育に力を注ぎました。また、黒板用コンパスなど教育用具の発明、欧米の数学教育を学ぶ世界一周の旅を行い、数学教育のみならず学校運営全般について、昭和48年(1973年)87歳で亡くなるまで教育に取組みました。
- # 現代(35)
- # 学者・医師(15)
- # 先駆者(43)
- # 発明・発見(13)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # びっくり(38)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # からたちはじめ(1)
- # 今泉孝之(1)
- # 愛知県(2)
-
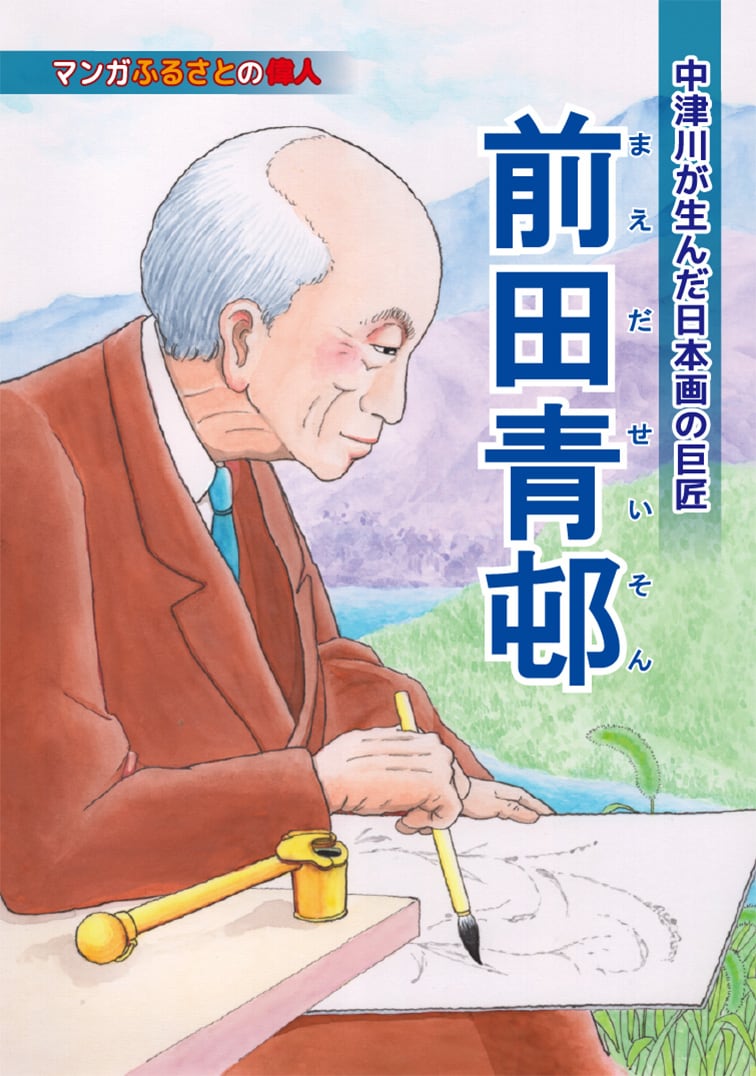
中津川が生んだ日本画の巨匠 前田青邨 まえだ せいそん
岐阜県中津川市マンガ家:島崎朝子前田青邨さん(まえだ せいそん)は、明治18年(1885年)中山道の宿場町中津川村(現中津川市)に生まれ、幼少期から絵の才能を現し16歳で上京して伝統的な日本絵画を学び、歴史画から肖像画・花鳥画など幅広く描き、広く海外にも知られました。また、晩年は法隆寺金堂壁画再現事業・高松塚古墳壁画模写事業など文化財保護にも貢献しました。92歳で亡くなるまで画を描き続け、文化勲章を受章した日本画の巨匠です。
-
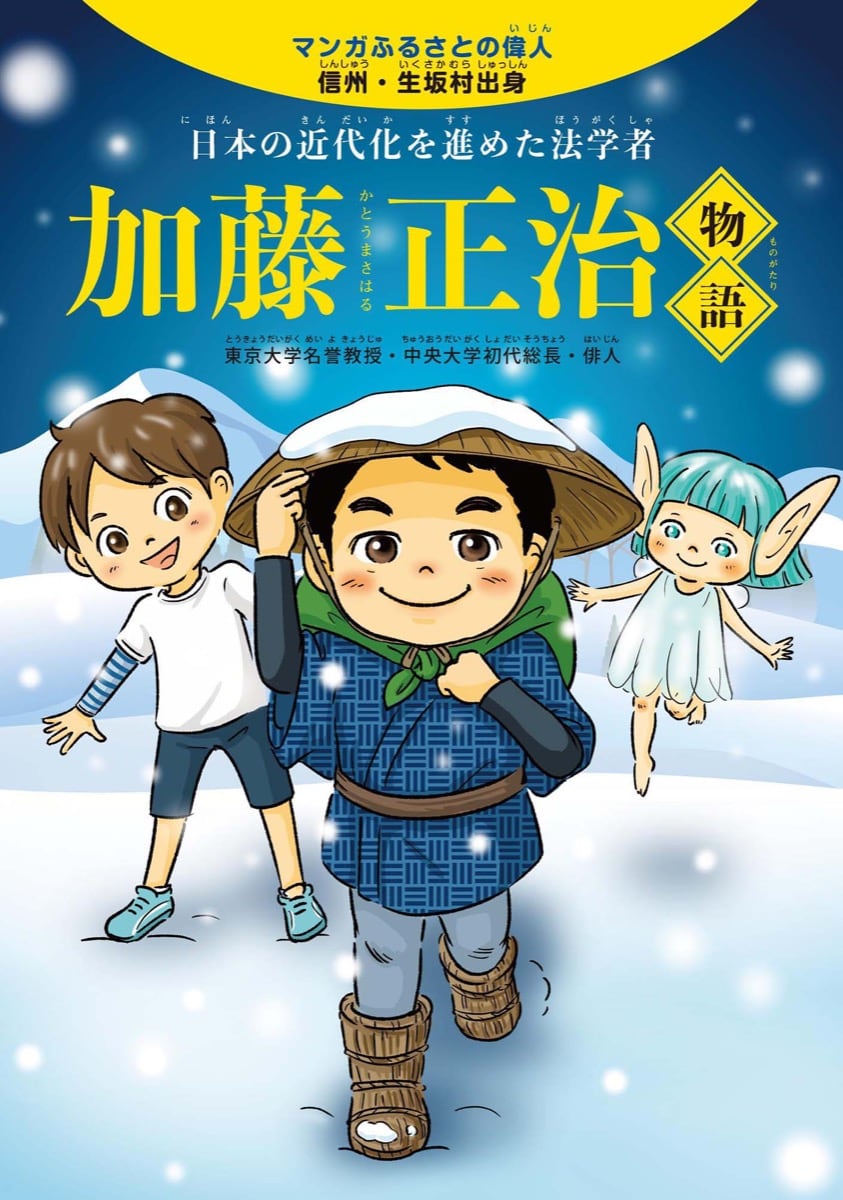
日本の近代化を進めた法学者 加藤正治 かとう まさはる
長野県生坂村マンガ家:作編集 安斎高志、絵 渋沢恵美加藤正治さん(かとう まさはる)は、明治4年(1871年)長野県生坂村に生まれ、明治32年(1899年)民事訴訟法・破産法・海法研究のためドイツ・フランスに留学。明治36年欧州から帰国すると東京帝大法科教授、中央大学講師、中央大学初代総長を務めた法学者です。加藤正治は、大学で教えるだけでなく破産法や民事訴訟法など重要な法律の立法、枢密院顧問官として日本国憲法の審議など日本の法整備に貢献しました。
-
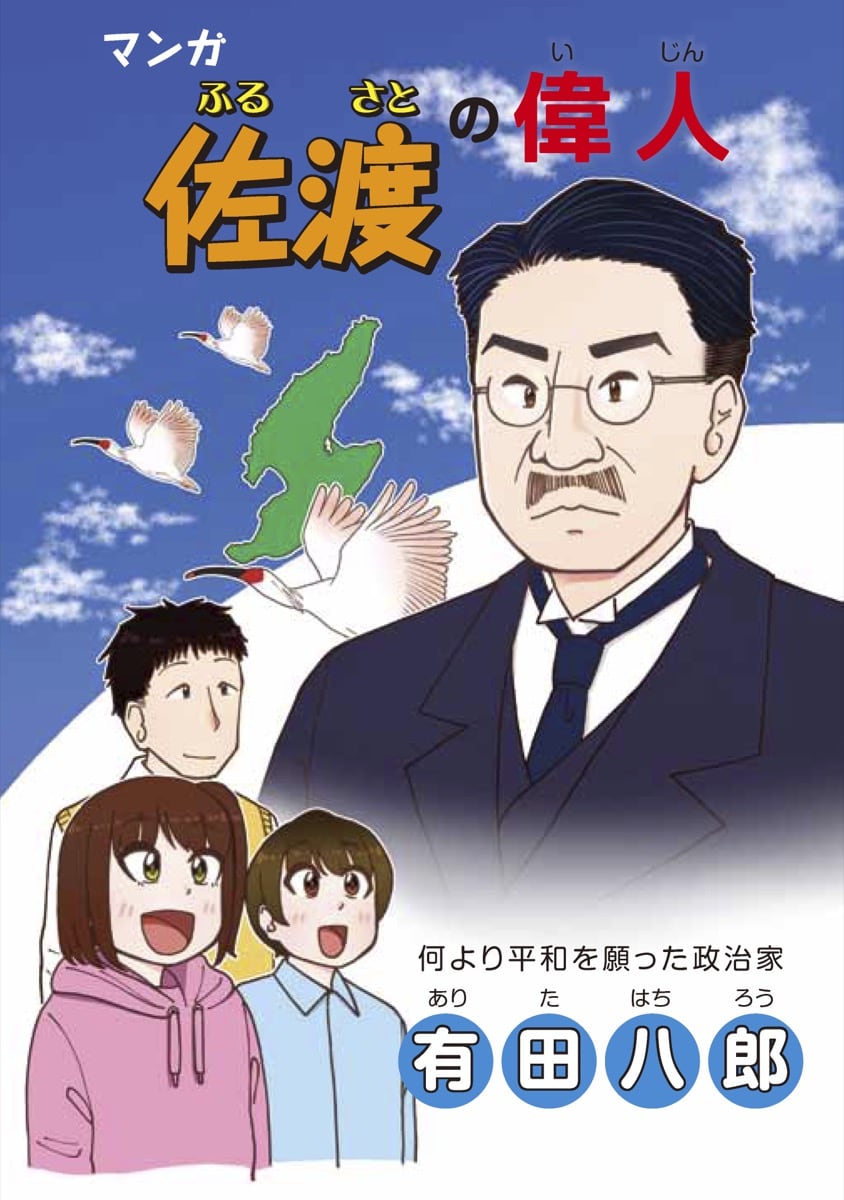
何より平和を願った政治家 有田八郎 ありた はちろう
新潟県佐渡市マンガ家:シカクメガネ有田八郎さん(ありた はちろう)は、明治17年(1884年)新潟県佐渡郡真野村(現佐渡市)に生まれ、明治42年(1909年)外務省入省、外務次官、中国大使を歴任しました。昭和初期、経済と国際社会の混乱を背景に軍が台頭し戦雲が濃くなる中でも、八郎は戦争に反対し続けました。外務大臣を4度務め、天皇に太平洋戦争の早期終結を上奏、戦後もソ連に抑留された日本人の引揚げに尽力するなど平和を愛した政治家です。
-
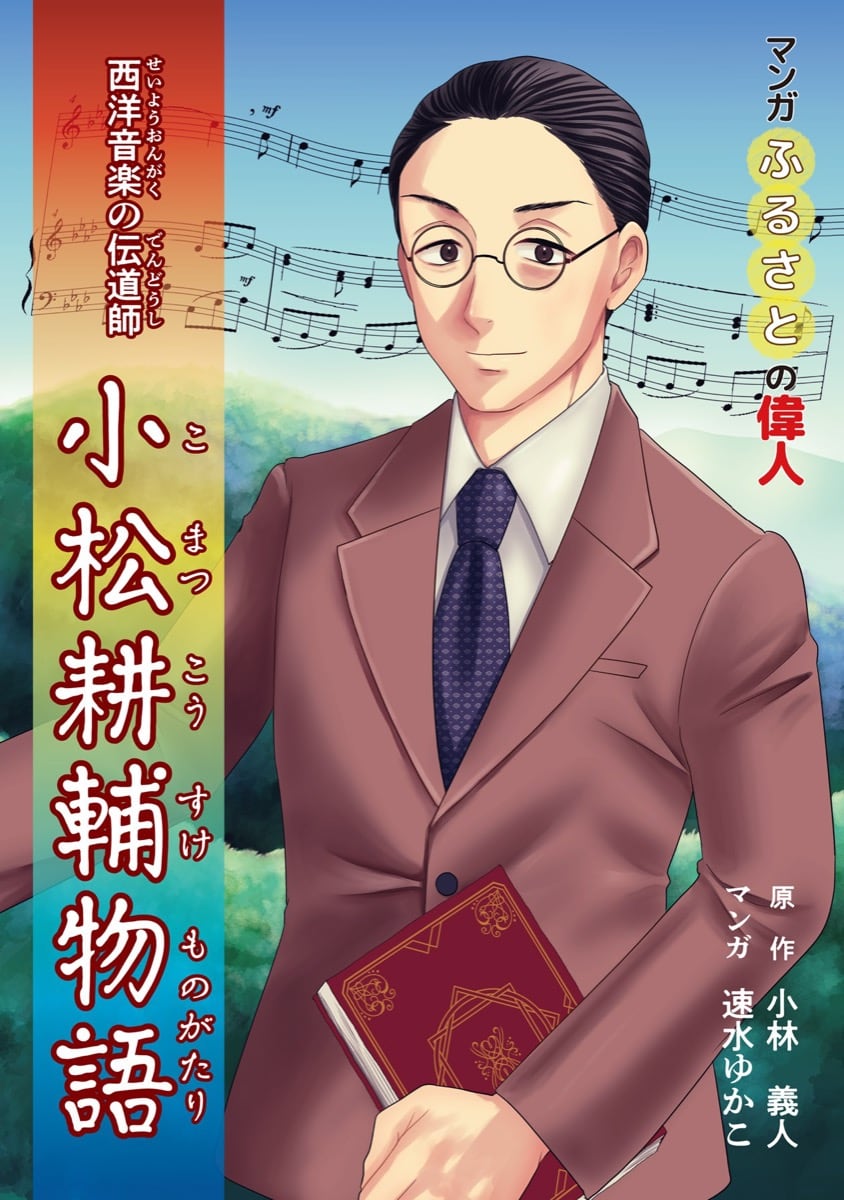
西洋音楽の伝道師 小松耕輔 こまつ こうすけ
秋田県由利本荘市マンガ家:原作 小林義人、マンガ 速水ゆかこ小松耕輔さん(こまつ こうすけ)は、明治17年(1884年)秋田県由利郡舘合村(現由利本荘市)に生まれ、パリ国立音楽院に学び作曲家として活躍する他、国民音楽協会設立、日本初の合唱コンクール開催など音楽の普及に尽力、音楽教育家としても、学習院大学、お茶の水女子大学、日本大学などで教鞭をとり音楽教育に貢献しました。また作曲家の著作権擁護にも努め、現在の一般社団法人日本音楽著作権協会の礎を築きました。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 日本初(20)
- # カッコイイ(40)
- # 感動(33)
- # 小林義人(1)
- # 速水ゆかこ(1)
- # 秋田県(2)
-

女満別空港はじまりのパイロット 根岸錦蔵 ねぎし きんぞう
北海道大空町マンガ家:岩原裕二根岸錦蔵さん(ねぎし きんぞう)は、明治35年(1902年)東京府(現東京都)に生まれ、日本航空界創成期に活躍したパイロットです。
昭和10年冷害に苦しむ北海道女満別村(現大空町)に、村民1,300人の協力を得て、気象観測の基礎となる流氷観測用の滑走路を完成させ、現在の「女満別空港」に続く飛行場を開きました。
流氷観測で得られたデータは、北海道の天気予知に役立ち、農業漁業の発展を支えました。- # 現代(35)
- # 政治・経済(25)
- # 先駆者(43)
- # 冒険・チャレンジ(18)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 日本初(20)
- # カッコイイ(40)
- # 感動(33)
- # 熱血(61)
- # 岩原裕二(1)
- # 北海道(4)
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。



