- # 名人・巨匠
-
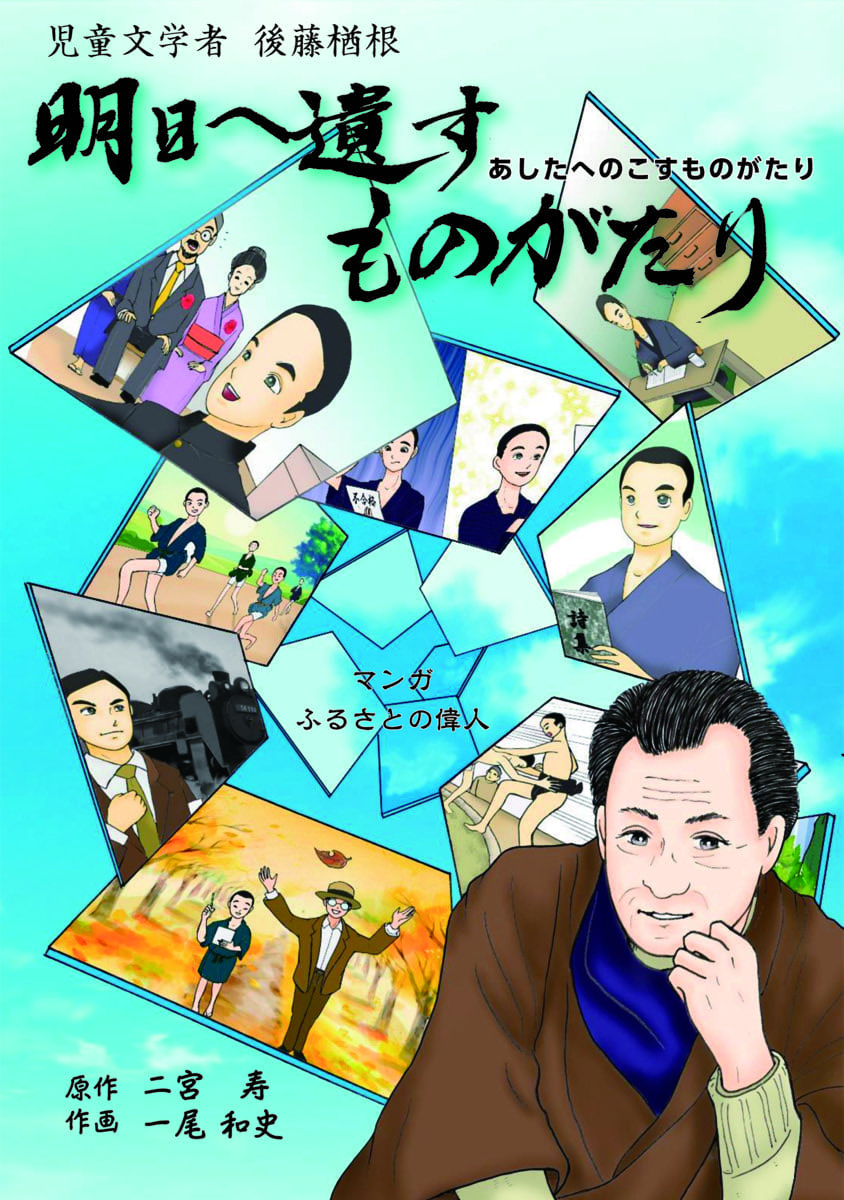
童話の普及と後進作家育成に貢献 後藤楢根 ごとう ならね
大分県由布市マンガ家:原作 二宮寿、作画 一尾和史後藤楢根さん(ごとう ならね)は、明治41年(1908年)大分県挟間町(現由布市挟間町)に生まれ、昭和2年(1927年)大分師範学校在学中に月刊「童謡詩人」を発行、その後小学校教師として童謡運動を行い、昭和13年上京して新聞社に勤務しながら多くの童話童謡を出版しました。終戦の翌年昭和21年に日本童話会を設立、機関誌「童話」から佐藤さとる、那須正幹などの後進が育ち、童話の普及と発展に貢献しました。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # リーダー(39)
- # 名人・巨匠(27)
- # 一般市民(16)
- # 感動(33)
- # 面白い(48)
- # 一尾和史(1)
- # 二宮寿(1)
- # 大分県(2)
-
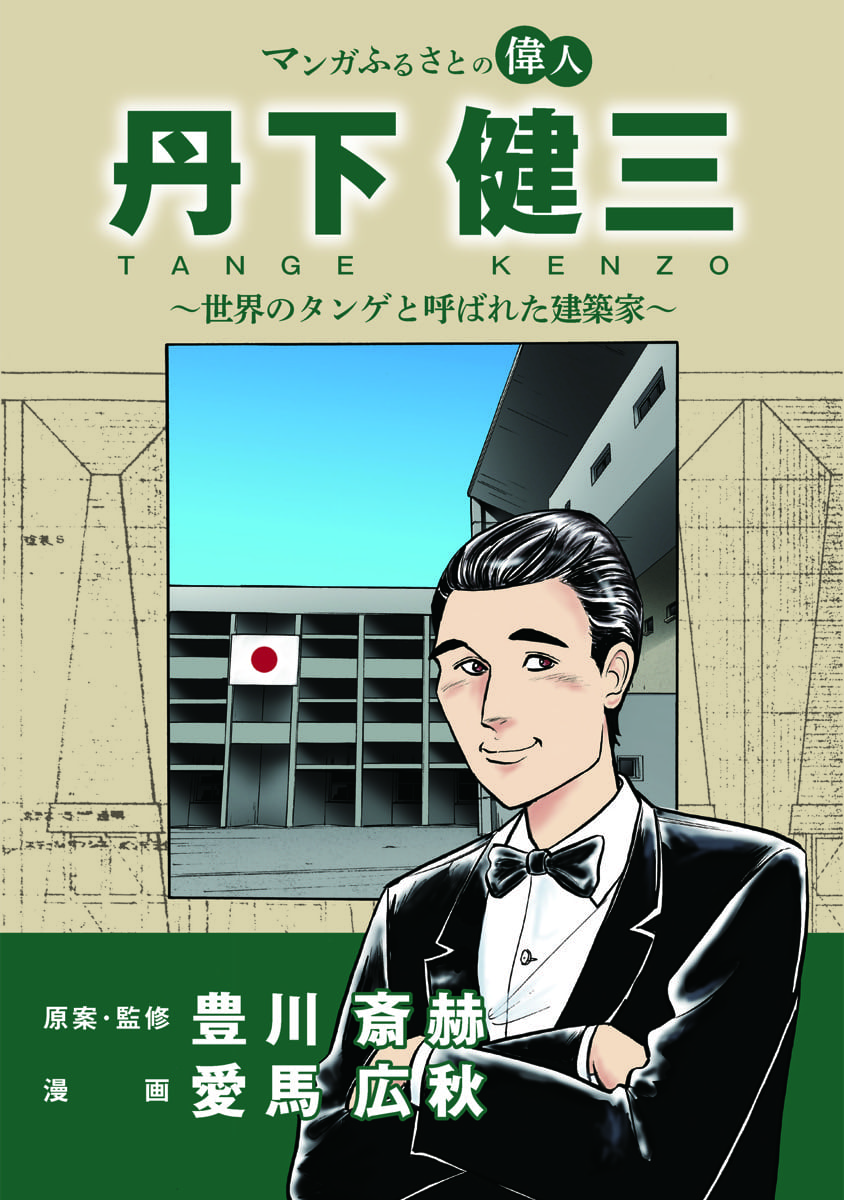
世界のタンゲと呼ばれた建築家 丹下健三 たんげ けんぞう
愛媛県今治市マンガ家:原案・監修 豊川斎赫、マンガ 愛馬広秋丹下健三さん(たんげ けんぞう)は、大正2年(1913年)大阪府堺市に生まれ、生後間もなく中国に渡り、大正9年(1920年)父の出身地である愛媛県今治市に帰国、昭和10年(1935年)東京帝国大学(現東京大学)工学部建築科に入学、同大学院卒業後から昭和49年(1974年)まで、東京大学で教鞭をとり「丹下研究室」を主宰。その建築・都市計画は、世界的に高い評価を得て「世界のタンゲ」と呼ばれています。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # 名人・巨匠(27)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 世界で活躍(31)
- # びっくり(38)
- # 面白い(48)
- # 愛馬広秋(1)
- # 豊川斎赫(1)
- # 愛媛県(2)
-
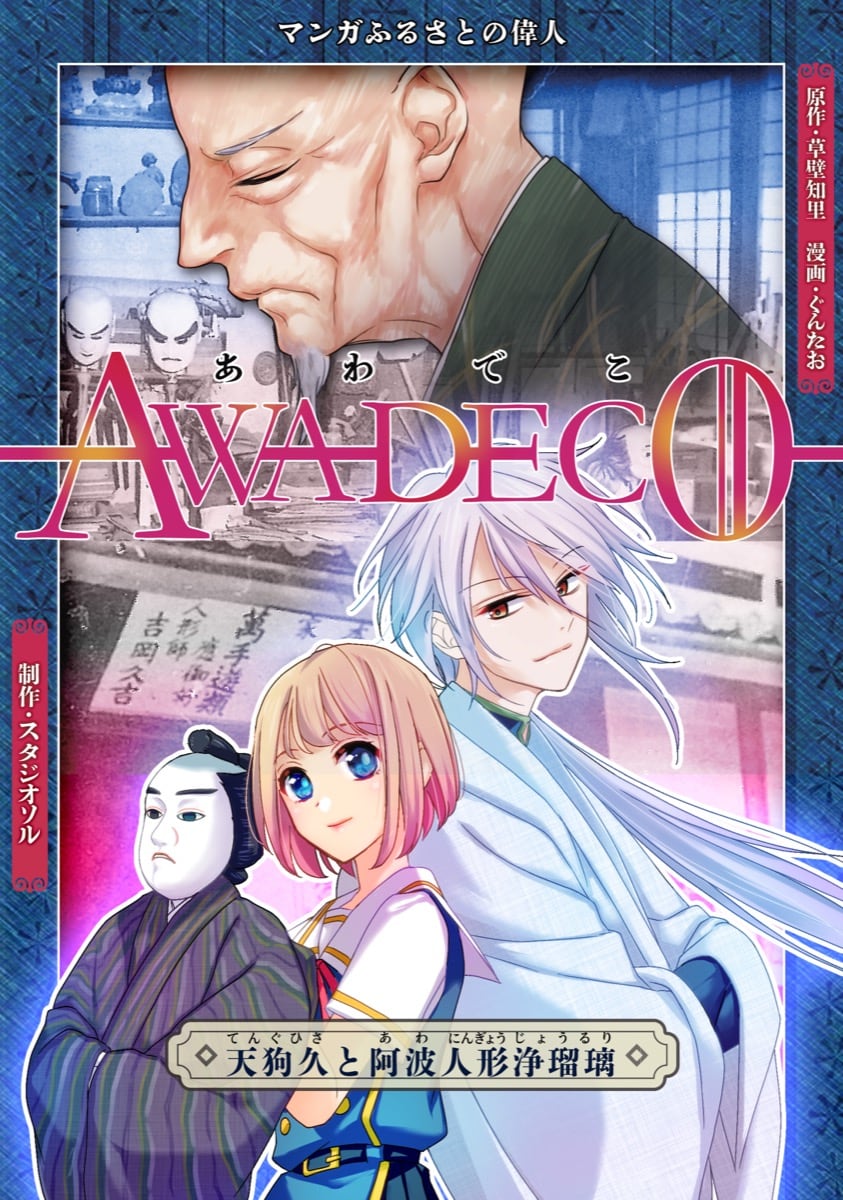
阿波人形浄瑠璃の人形師 天狗久 てんぐひさ
徳島県徳島市マンガ家:原作 草壁知里、マンガ ぐんたお初代天狗久(てんぐひさ)は、幕末安政5年(1858年)阿波国名東郡中村(現徳島県徳島市国府町)に生まれ、16歳で人形師に弟子入りし、「阿波人形浄瑠璃」で使う阿波木偶の伝統的技法を受け継ぎつつ、ガラス眼の採用・頭の大型化など時代に合わせた人形作りに情熱を注いだ。生涯に制作した人形頭は千点を超え、徳島市内にある天狗久の旧工房は「天狗久資料館」として一般公開され、作業場や関連資料など展示されています。
-
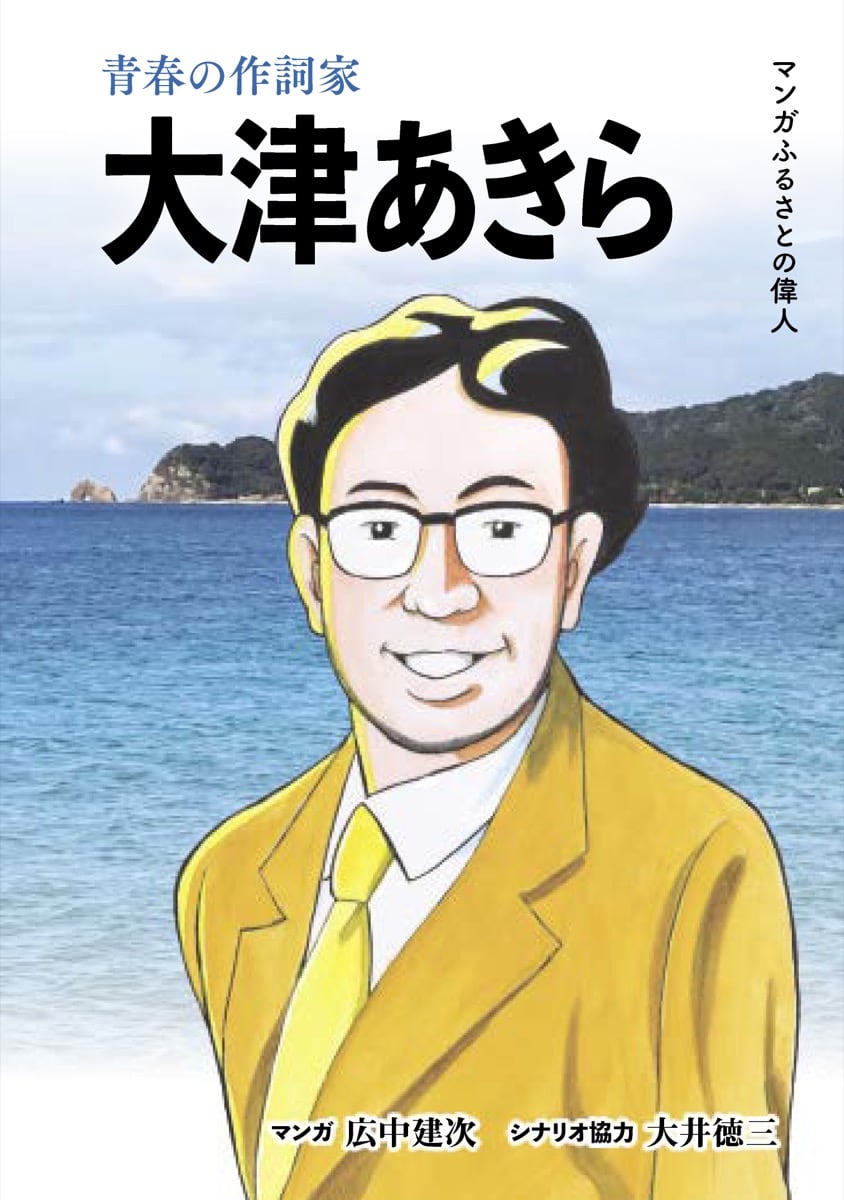
青春の作詞家 大津あきら おおつ あきら
山口県長門市マンガ家:マンガ 広中建次、シナリオ協力 大井徳三大津あきらさん(おおつ あきら)は、昭和25年(1950年)山口県長門市に生まれ、慶応大学進学後つかこうへい劇団の劇中歌の作詞や作曲を手がけ、昭和57年(1982年)中村雅俊「心の色」で第15回日本作詩大賞大衆賞を受賞、以降作詞家として活動し、髙橋真梨子、矢沢永吉、中森明菜等の歌謡曲、超獣戦隊ライブマン、特救指令ソルブレイン、太陽の勇者ファイバード等の特撮・アニメ主題歌に多くの作品を残しました。
-
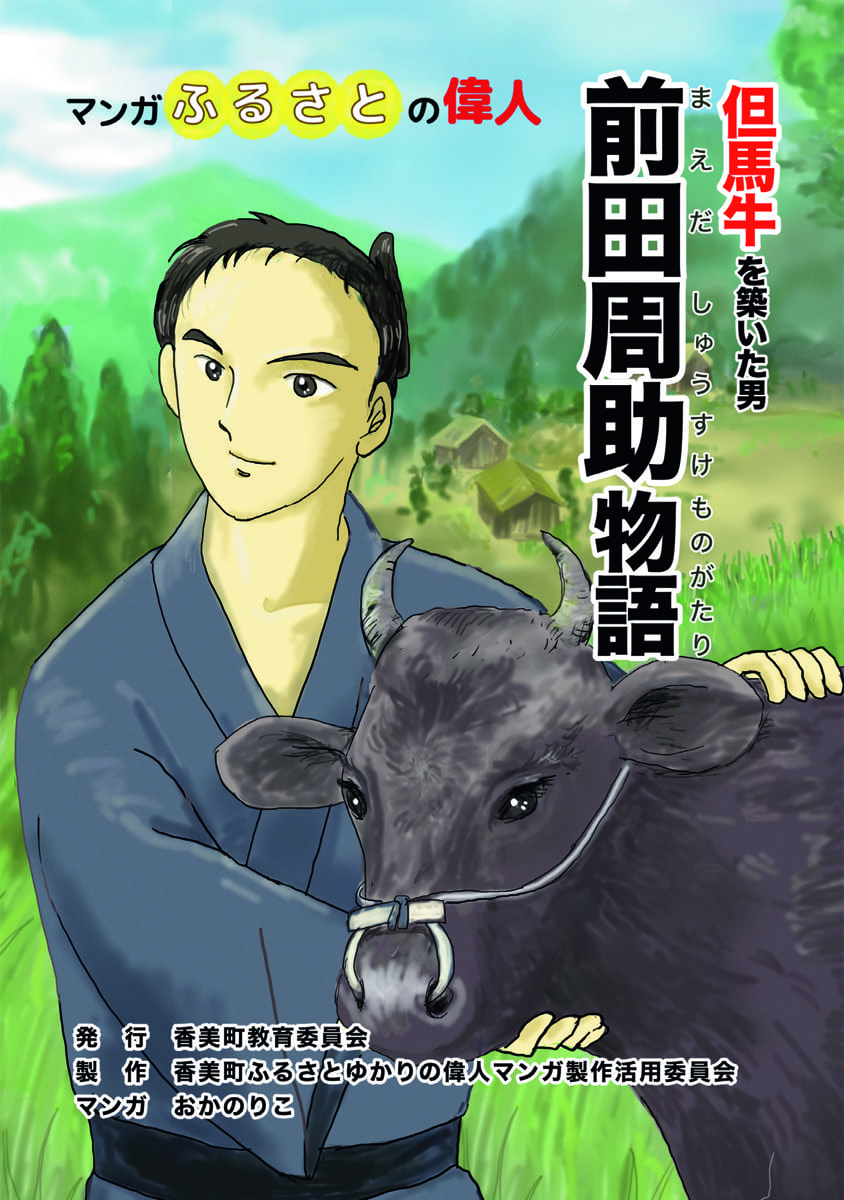
但馬牛を築いた男 前田周助 まえだ しゅうすけ
兵庫県香美町マンガ家:おかのりこ前田周助(まえだ しゅうすけ)は、江戸後期寛政10年(1798年)但馬国七美郡小代村(現兵庫県美方郡香美町小代区)に生まれ、牛を育てる腕と鑑識眼が認められ周助の牛は高値で売れました。周助は、“良い仔牛は良い母牛から生まれる”ことを認識しており、良牛の固定化のため繁殖に努力し、年々続いて良い仔牛を産む「周助蔓」の始祖を作り上げました。周助蔓の優れた形質は、但馬牛を始めとする和牛に伝えられています。
- # 近世(17)
- # 政治・経済(25)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # おかのりこ(1)
- # 兵庫県(5)
-
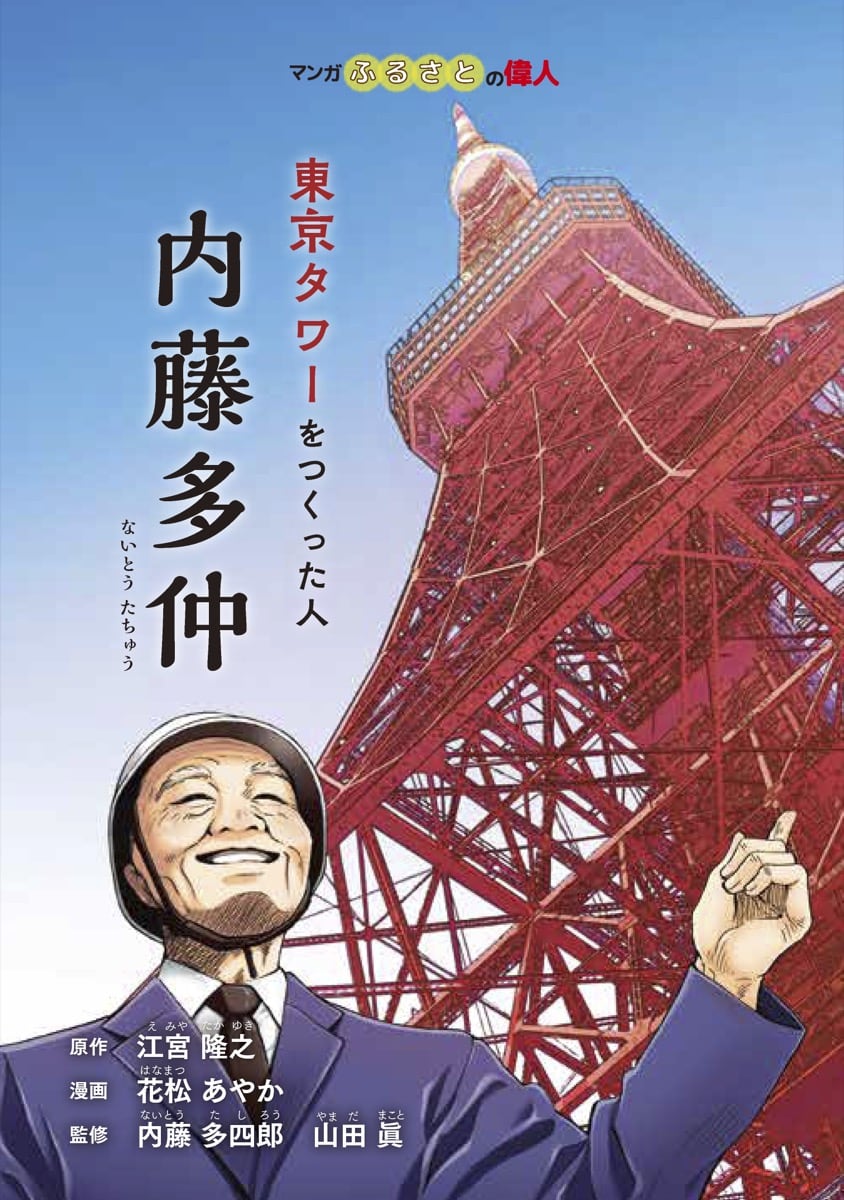
東京タワーをつくった人 内藤多仲 ないとう たちゅう
山梨県南アルプス市マンガ家:原作 江宮隆之、マンガ 花松あやか、監修 内藤多四郎 山田眞内藤多仲さん(ないとう たちゅう)は、明治19年(1886年)山梨県中巨摩郡榊村(現南アルプス市)に生まれた建築構造学者、建築家です。「耐震構造」という地震が起きても建物が壊れにくくなる仕組みを考え、「耐震構造の父」と称されました。また、東京タワーなど多くの塔を設計したことから「塔博士」とも呼ばれています。
- # 現代(35)
- # 学者・医師(15)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 発明・発見(13)
- # 世界で活躍(31)
- # 日本初(20)
- # 感動(33)
- # 面白い(48)
- # 内藤多四郎(1)
- # 山田眞(1)
- # 江宮隆之(2)
- # 花松あやか(1)
- # 山梨県(3)
-
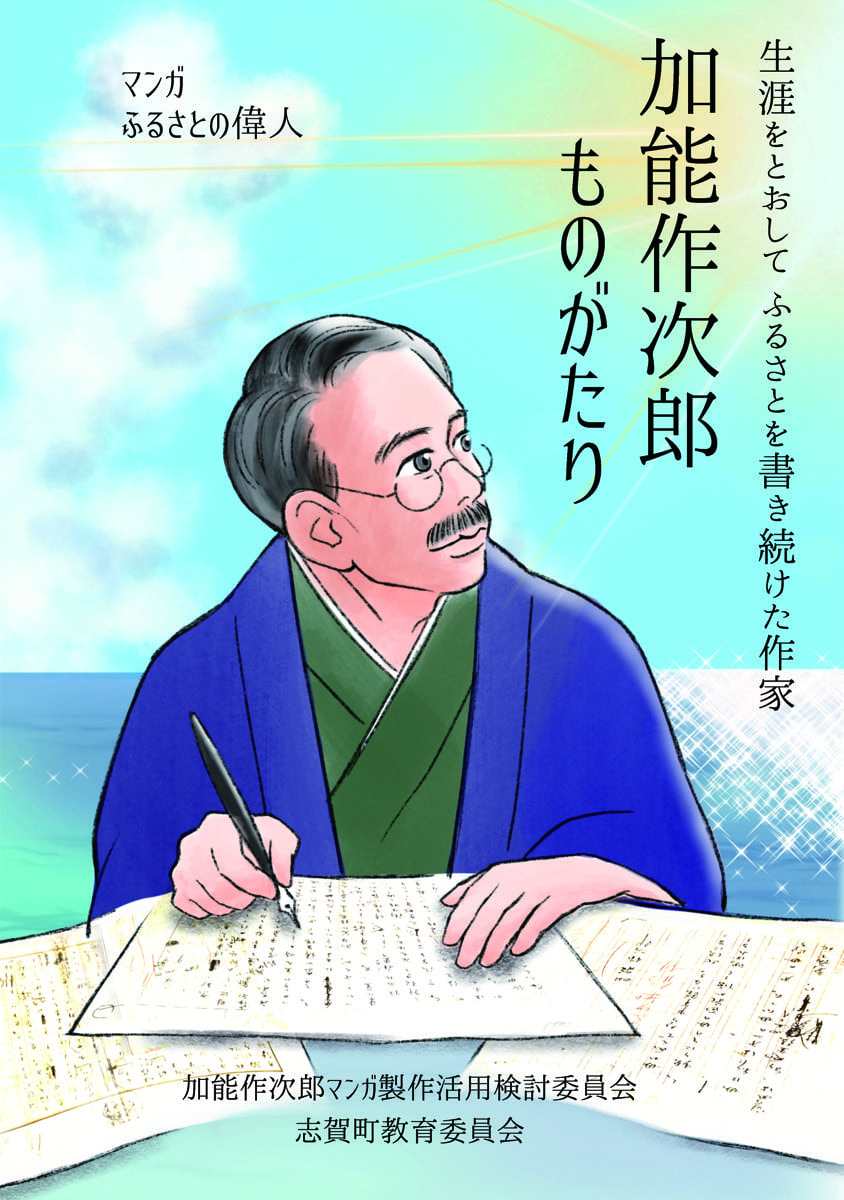
ふるさとを書き続けた作家 加能作次郎 かのう さくじろう
石川県志賀町マンガ家:作・脚本 中居ヒサシ、作画 藤井裕子加能作次郎(かのう さくじろう)は、明治18年(1885年)石川県西海村風戸(現志賀町西海風戸)に生まれ、苦難の少年期を経て、明治41年(1908年)早稲田大学へ入学しました。在学中、処女作『恭三の父』が雑誌『ホトトギス』に掲載され好評を得ました。卒業後、博文社『文章世界』の編集主任として翻訳や文芸時評を発表し、大正7年(1918年)小説『世の中へ』で文壇的地位を確立した自然主義文学作家です。
-
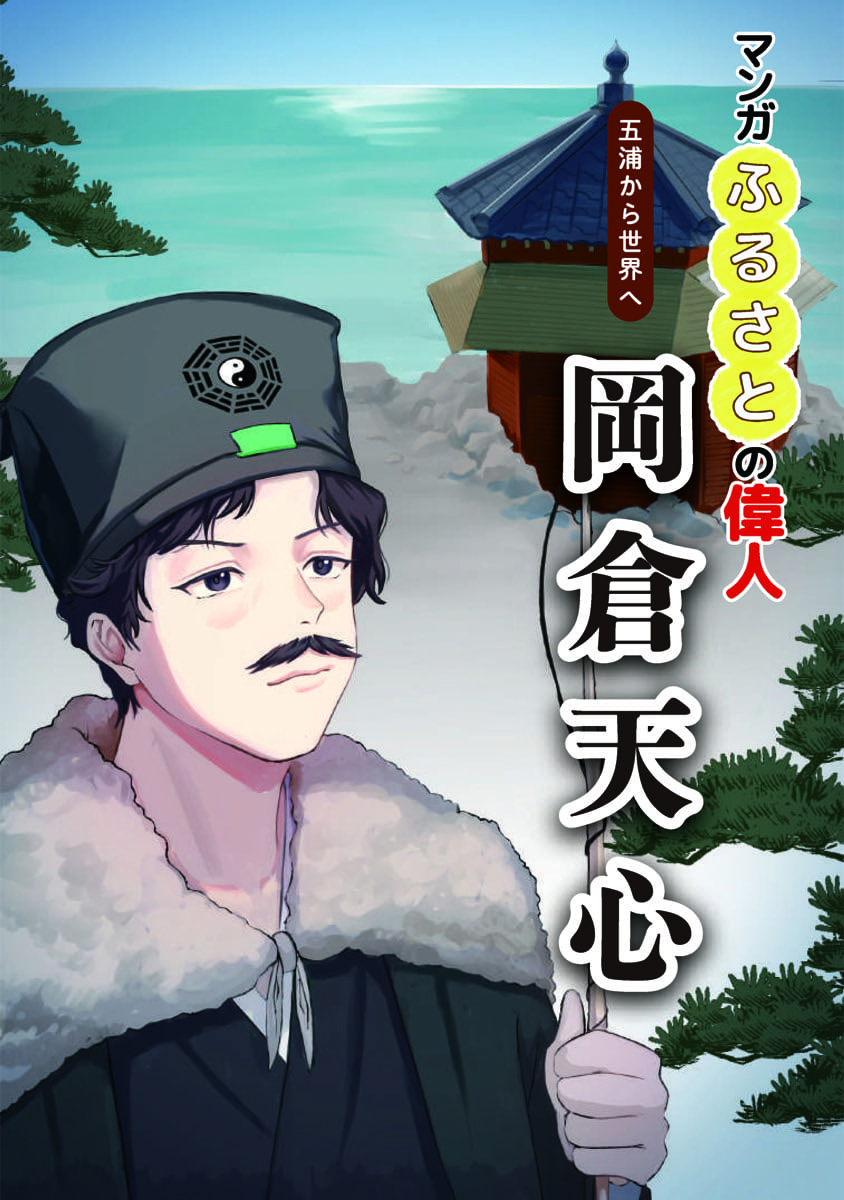
日本美術を世界に紹介した 岡倉天心 おかくら てんしん
茨城県北茨城市マンガ家:監修・原案 小泉晋弥、作画 産本まぐろ岡倉天心(おかくら てんしん)は、幕末文久2年(1863年)横浜に生まれ、明治22年(1889年)東京美術学校(現東京藝術大学美術学部)設立、日本美術院創設、ボストン美術館中国・日本美術部長就任等、日本の美術史学研究の開拓者であり、美術評論、美術家養成に貢献しました。天心は、明治38年(1905年)茨城県大津町(現北茨城市)の五浦海岸に自身の設計による邸宅と六角堂を建築し、活動の拠点としました。
- # 近代(36)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 世界で活躍(31)
- # 日本初(20)
- # びっくり(38)
- # 面白い(48)
- # 小泉晋弥(1)
- # 産本まぐろ(1)
- # 茨城県(4)
-

今も愛される名作を生んだ作詩家 丘灯至夫 おか としお
福島県小野町マンガ家:シナリオ 高見沢功、マンガ 吉川むつみ丘 灯至夫さん(おか としお)は、大正6年(1917年)福島県小野新町(現小野町)に生まれ。詩人・西條八十に師事し、昭和24年(1949年)からは日本コロムビア専属作詩家となり「高校三年生」「高原列車は行く」「ハクション大魔王のうた」など数多くの作品を生み出しました。歌謡曲やアニメソングのほか詩吟も手がけ、生涯にわたり美しい日本語を伝え続けたその作品は、今も多くの人に親しまれ口ずさまれています。
-
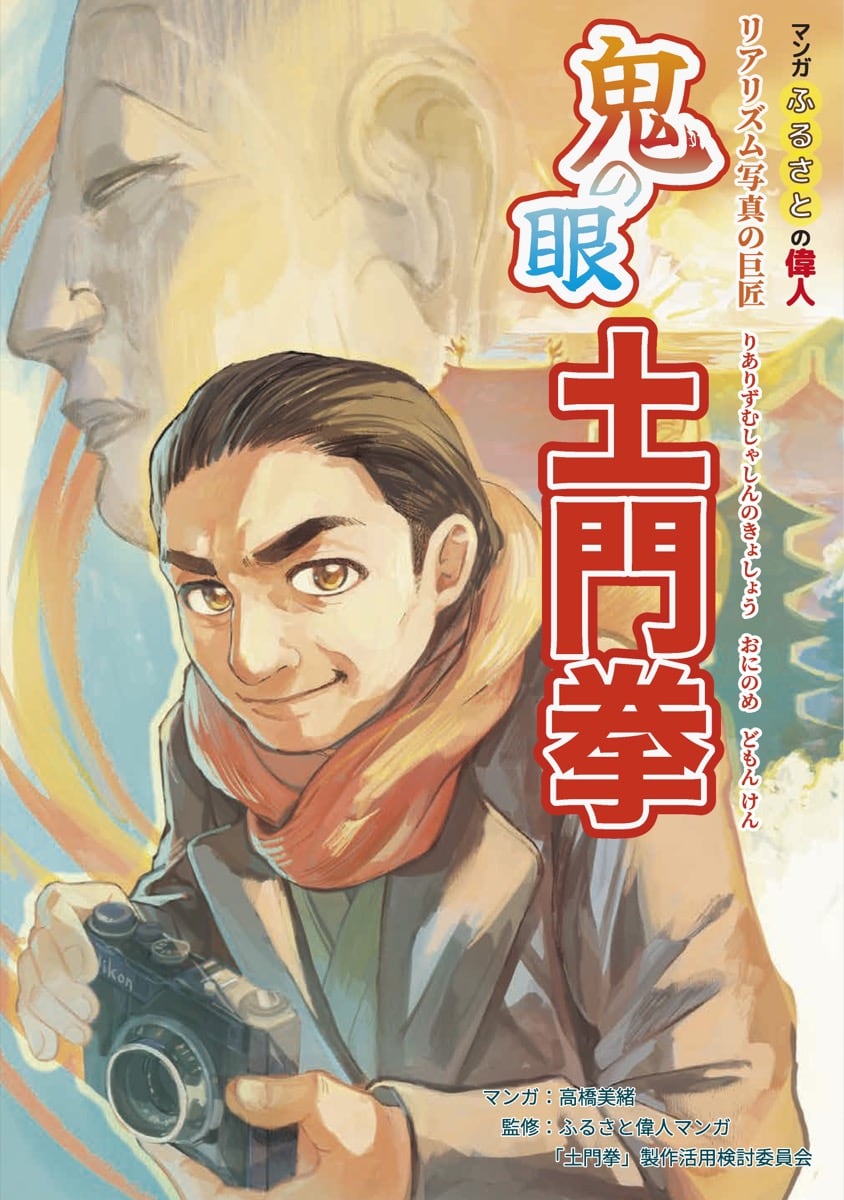
リアリズム写真の巨匠 土門拳 どもん けん
山形県酒田市マンガ家:高橋美緒土門拳さん(どもん けん)は、明治42年(1909年)山形県酒田町(現酒田市)に生まれ、「ヒロシマ」・「筑豊のこどもたち」等リアリズムにこだわった写真集や、「古寺巡礼」・「文楽」等日本の伝統文化を撮影した写真集で、日本の美と日本人の心を追及した写真家です。昭和58年(1983年)酒田市は土門作品約13万5千点の寄贈を受け、作品を収蔵 展示する日本初の写真専門美術館「土門拳記念館」を開館しました。
-
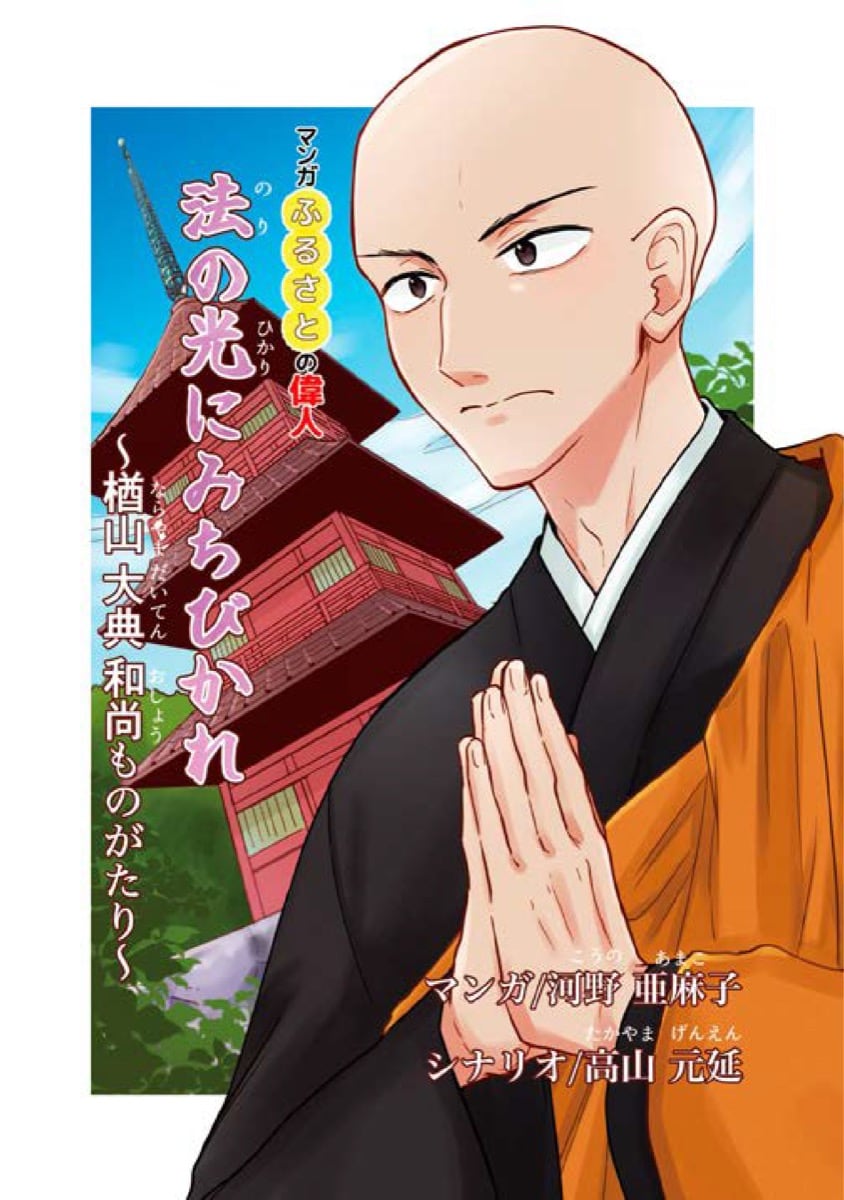
大和尚になったわんぱく小僧 楢山大典 ならやま だいてん
青森県南部町マンガ家:マンガ 河野亜麻子、シナリオ 高山元延楢山大典さん(ならやま だいてん)は、大正3年(1914年)青森県斗川村(現三戸町)に生まれ、昭和13年(1938年)曹洞宗の名刹法光寺(青森県三戸郡南部町)37世住職となり、国内最大級の木造三重塔「承陽塔」等の伽藍を整備、得度・立職・伝法の弟子45名を育てました。曹洞宗では教学部長、宗務総長等の要職を歴任。教育関係でも愛知学院大学、東北福祉大学、駒澤大学、駒澤大学高等学校の理事長を務めました。
-
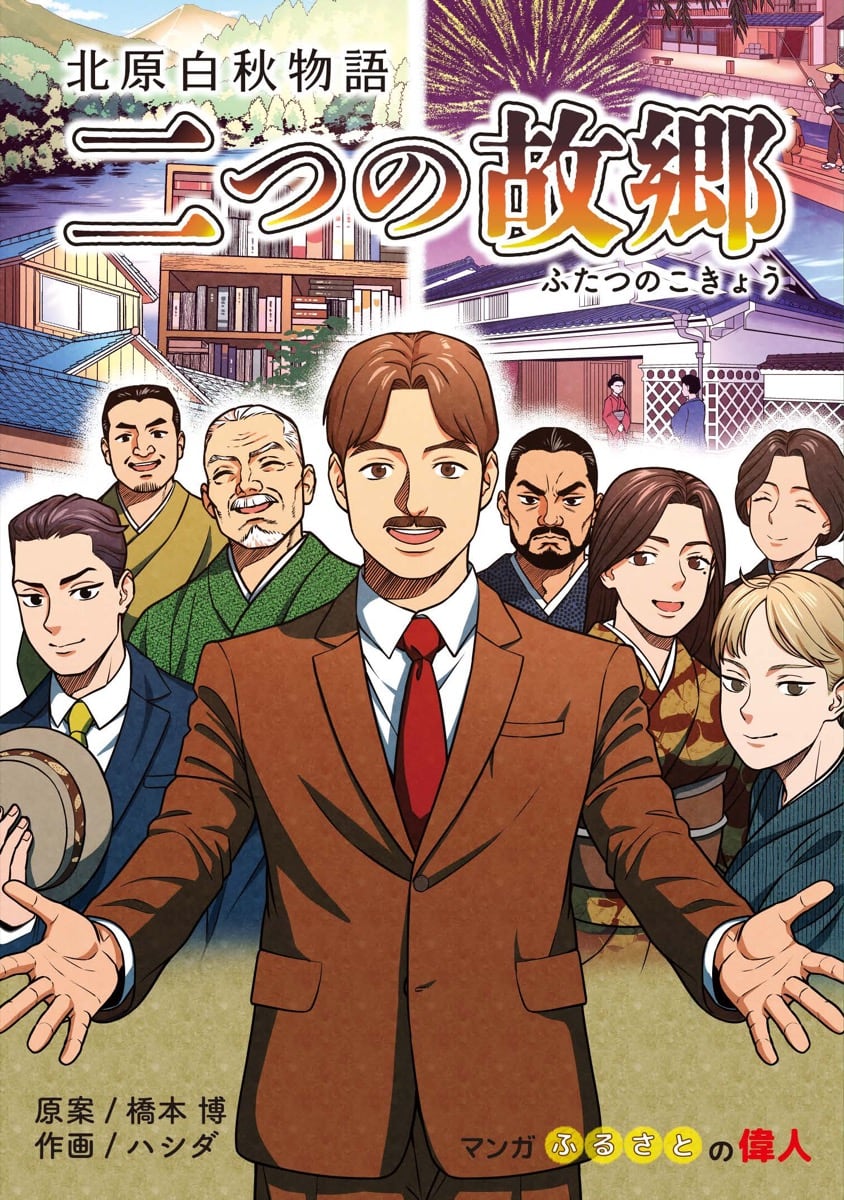
近代日本を代表する詩人、童謡作家 北原白秋 きたはら はくしゅう
熊本県南関町マンガ家:原案 橋本博、作画 ハシダ北原白秋(きたはら はくしゅう)は、明治18年(1885年)母の実家がある熊本県玉名郡関外目村(現南関町)に生まれ、福岡県山門郡沖端村(現福岡県柳川市)に暮らしながら、度々母の実家を訪れ叔父に読書の楽しさを教わりました。白秋は、中学時代から詩歌作りに熱中し、明治37年(1904年)早稲田大学に入学すると詩人として頭角を現し、詩歌集・小説・翻訳・童謡や校歌流行歌の作詞など創作活動で活躍しました。
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。



