- # 芸術・文化
-
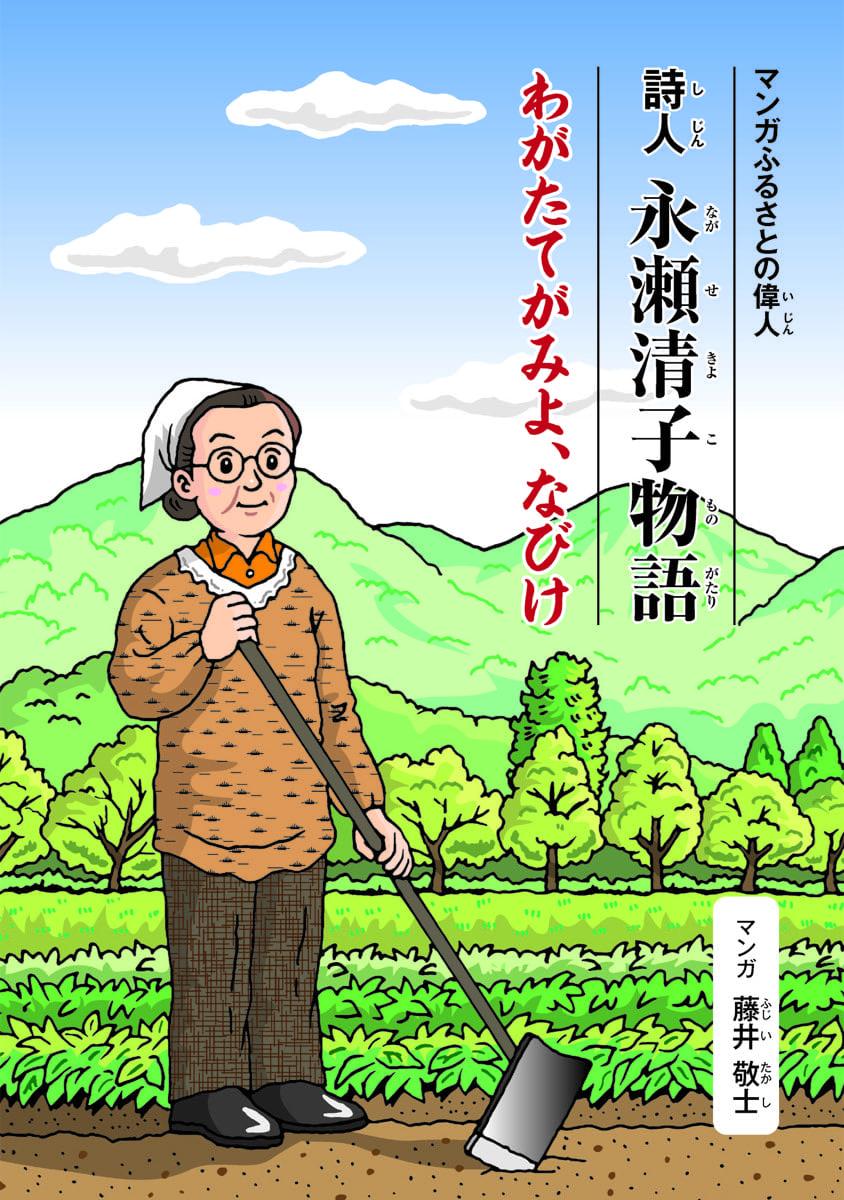
「現代詩の母」と呼ばれる詩人 永瀬清子 ながせ きよこ
岡山県赤磐市マンガ家:マンガ 藤井敬士、シナリオ 和田静夫永瀬清子さん(ながせ きよこ)は、明治39年(1906年)岡山県赤磐郡豊田村(現赤磐市)に生まれ、17歳の頃に詩人を志し、昭和5年(1930年)24歳で第1詩集を刊行、生涯現役を貫き「現代詩の母」と呼ばれています。
また、現在の岡山県詩人協会を設立し後進の育成に努め、岡山家庭裁判所調停委員、世界連邦都市岡山県協議会事務局などで社会活動も行いました。- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # リーダー(39)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 愛・献身(36)
- # 女性(11)
- # 世界で活躍(31)
- # 感動(33)
- # 面白い(48)
- # 和田静夫(1)
- # 藤井敬士(1)
- # 岡山県(8)
-
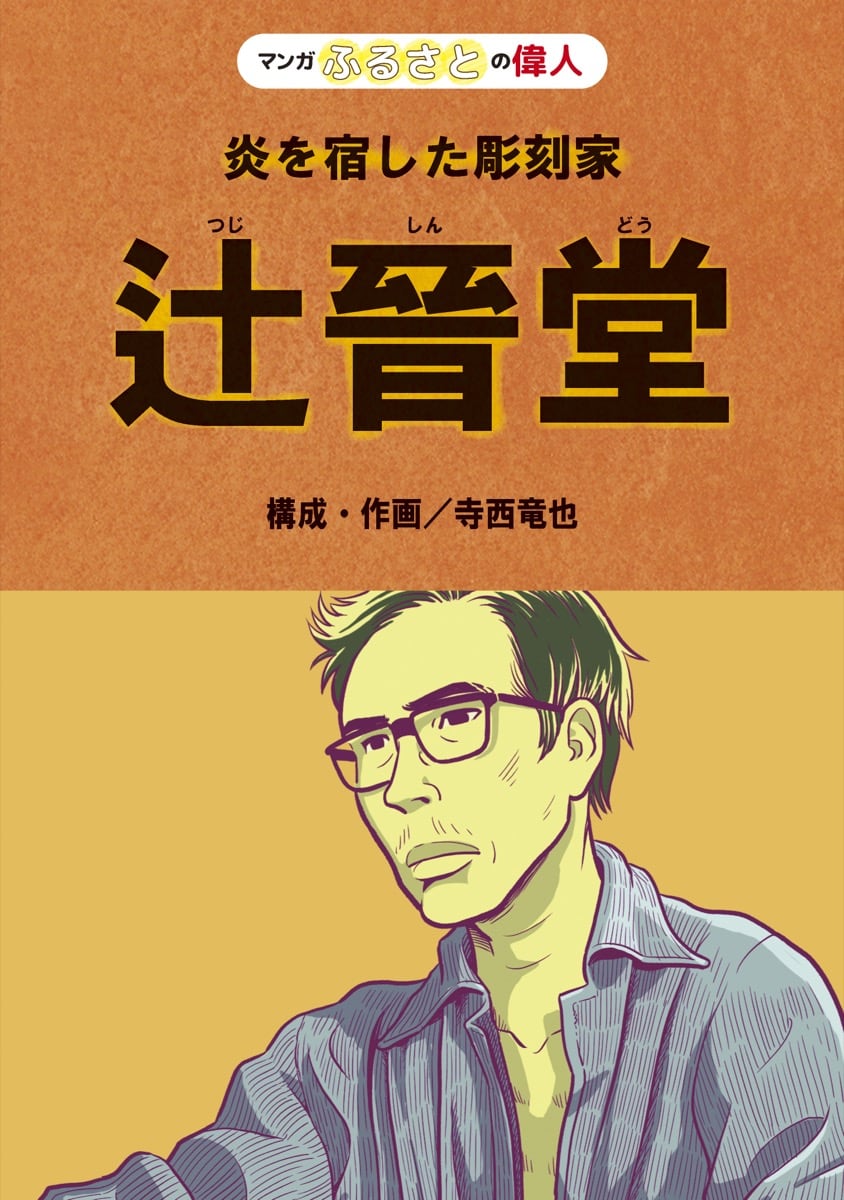
炎を宿した彫刻家 辻晉堂 つじ しんどう
鳥取県伯耆町マンガ家:寺西竜也辻晉堂さん(つじしんどう)は、明治43年(1910年)鳥取県日野郡二部村(現伯耆町)に生まれ、昭和10年(1935年)第22回院展で受賞し、木彫作家として高い評価を受けました。戦後昭和24年(1949年)京都市立美術大学教授に就任、セメント・石膏・ブロンズなどを使った抽象彫刻の制作を始め、昭和30年代からは陶土を使い登り窯で焼成する「陶彫」による抽象作品に独自の世界を拓き国際的な評価を得ました。
-

人間国宝「義太夫節三味線」 鶴澤友路 つるさわ ともじ
兵庫県南あわじ市マンガ家:原案 濱岡きみ子、監修 久堀裕朗、マンガ 青木達哉鶴沢友路さん(つるさわ ともじ)は、大正2年(1913年)兵庫県福良町(現南あわじ市)に生まれ、4歳から三味線を習い、厳しい修行の末、「女流義太夫」の第一人者として国内だけでなく海外でも活動し、平成10年(1998年)重要無形文化財「義太夫節三味線」保持者(人間国宝)となりました。また後継者育成に励み、103歳で亡くなるまで淡路島内の小中高生をはじめ千人以上の弟子たちに惜しみなく芸を伝えました。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # 名人・巨匠(27)
- # 愛・献身(36)
- # 型破り(25)
- # 女性(11)
- # 世界で活躍(31)
- # カッコイイ(40)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # 久堀裕朗(1)
- # 濱岡きみ子(1)
- # 青木達哉(1)
- # 兵庫県(5)
-
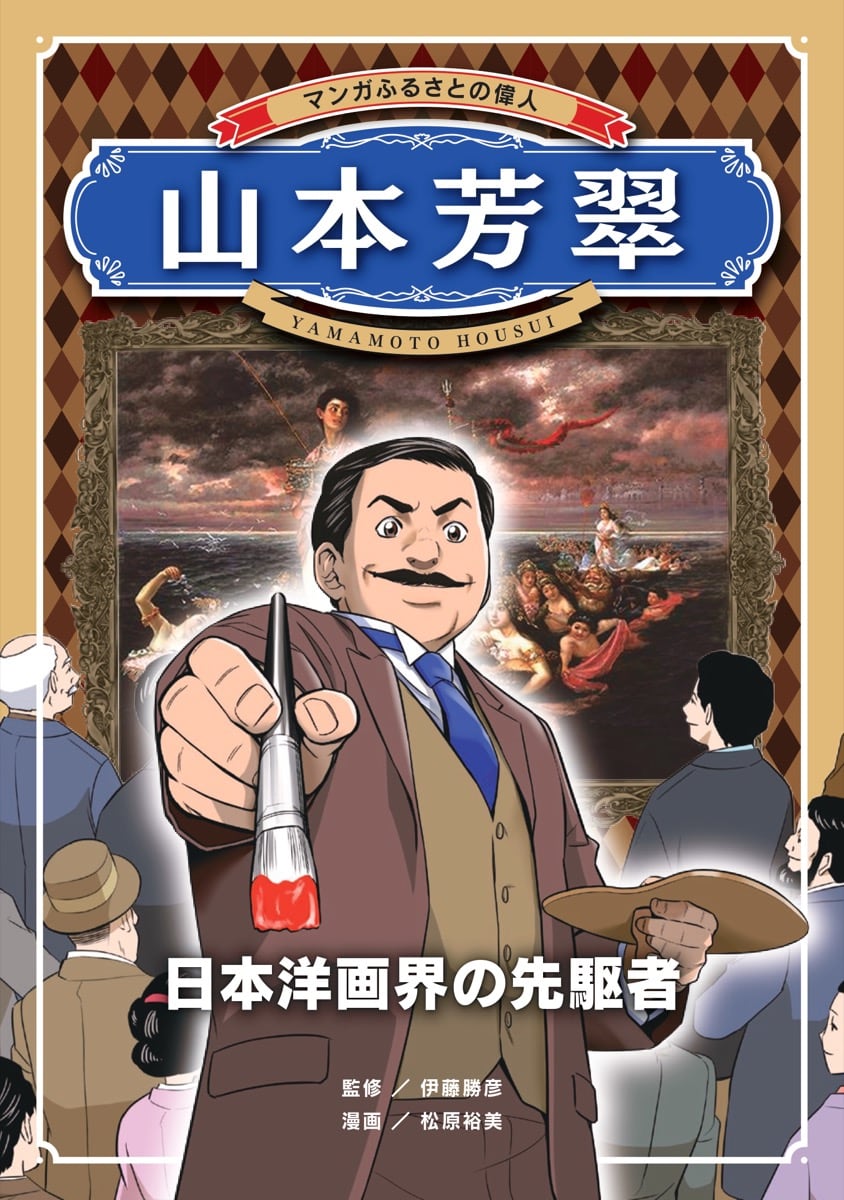
日本洋画界の先駆者 山本芳翠 やまもと ほうすい
岐阜県恵那市マンガ家:マンガ 松原裕美、原案・監修 伊藤勝彦山本芳翠(やまもと ほうすい)は、嘉永3年(1850年)美濃国恵那郡明智村(現岐阜県恵那市)に生まれ、慶応元年(1865年)15歳で画家を目指し京都で南宋画を学びました。明治元年(1868年)横浜で見た洋風画に衝撃を受け、工部美術学校で本格的な油彩を学び、明治11年(1878年)渡仏しパリ美術学校入学、パリ画壇で活動しました。明治20年(1887年)帰国し、日本洋画界の先駆者として活躍しました。
- # 近代(36)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 世界で活躍(31)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # 伊藤勝彦(1)
- # 松原裕美(1)
- # 岐阜県(5)
-

ペルーにアンデス文明博物館を開館 天野芳太郎 あまの よしたろう
秋田県男鹿市マンガ家:坂田もち江天野芳太郎さん(あまの よしたろう)は、明治31年(1898年)秋田県脇本村(現男鹿市)に生まれ、昭和3年(1928年)南米に渡り、パナマ、ペルー、などで事業を行うと共に古代アンデス文明の遺跡を調査しました。昭和16年(1941年)第二次世界大戦勃発により、南米の財産を失い日本に帰国しますが、終戦後また南米に渡りペルーで事業を成功させると遺跡調査を行い、収集した遺物を展示する博物館を開きました。
- # 現代(35)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 冒険・チャレンジ(18)
- # 発明・発見(13)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 世界で活躍(31)
- # びっくり(38)
- # 熱血(61)
- # 面白い(48)
- # 坂田もち江(1)
- # 秋田県(2)
-
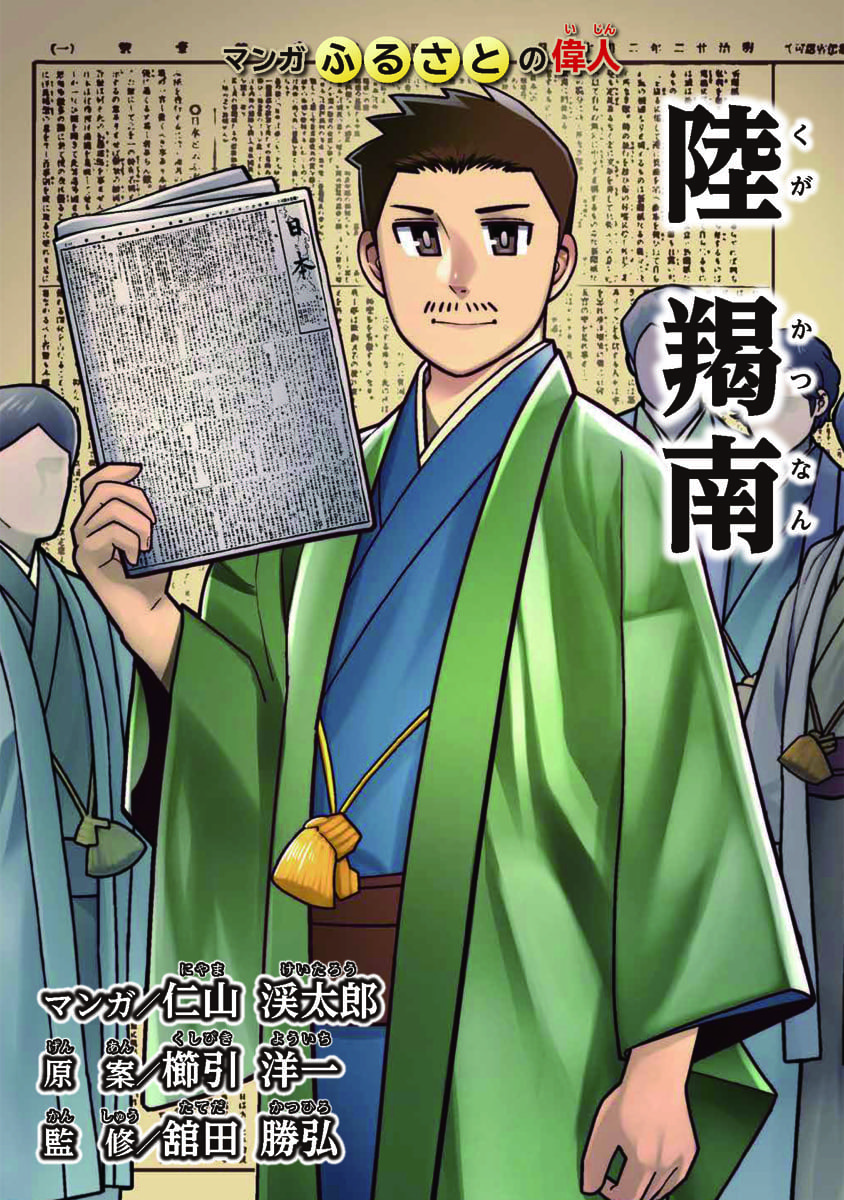
国民主義を唱えたジャーナリスト 陸羯南 くが かつなん
青森県弘前市マンガ家:マンガ 仁山渓太郎、原案 櫛引洋一、監修 舘田勝弘陸羯南(くが かつなん)は、幕末安政4年(1857年)陸奥国弘前在府町(現青森県弘前市在府町)に生まれ、官立宮城師範学校、司法省法学校に学び、青森新聞社や太政官文書局・内閣官報局編集課長などを経て、明治22年(1889年)大日本帝国憲法発布の日、新聞「日本」を創刊、硬骨のジャーナリストとして大きな足跡を残しました。また、正岡子規の文学活動を支援し、晩年闘病生活を送る子規を物心両面から支えました。
- # 近代(36)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 型破り(25)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # カッコイイ(40)
- # 熱血(61)
- # 仁山渓太郎(1)
- # 櫛引洋一(1)
- # 舘田勝弘(1)
- # 青森県(2)
-

マンガ家・画家・文化人として活躍 那須良輔 なす りょうすけ
熊本県湯前町マンガ家:原作 橋本博、作画 タネオマコト那須良輔さん(なす りょうすけ)は、大正2年(1913年)熊本県球磨郡湯前村(現湯前町)に生まれ、昭和7年(1932年)洋画家を目指して上京し太平洋美術学校に入学。内職のつもりで描いたマンガが採用されて、昭和8年児童マンガ家としてデビュー。人気マンガ家となり、そこから優れたデッサン力で政治家の特徴を捉えた似顔絵の政治風刺マンガ、釣りや自然を題材とした風景画・随筆などに活動範囲を広げ活躍しました。
-

中国で戦病死した早世の洋画家 靉光 あいみつ
広島県北広島町マンガ家:原案 石井誠治、作画 坪郷絵美靉光(あいみつ)は、明治40年(1907年)広島県北広島町に生まれ、大正13年(1924年)画家を志し上京。芸術家と交流しながら自らの画風を模索し「眼のある風景」で画壇に注目されます。自己を厳しく見つめた3枚の自画像を残し、昭和19年(1944年)で中国に出征。終戦を迎えますが、上海の陸軍病院で、わずか38歳で戦病死しました。独自性の強い作品で近代日本美術に大きな足跡を残した画家です。
-
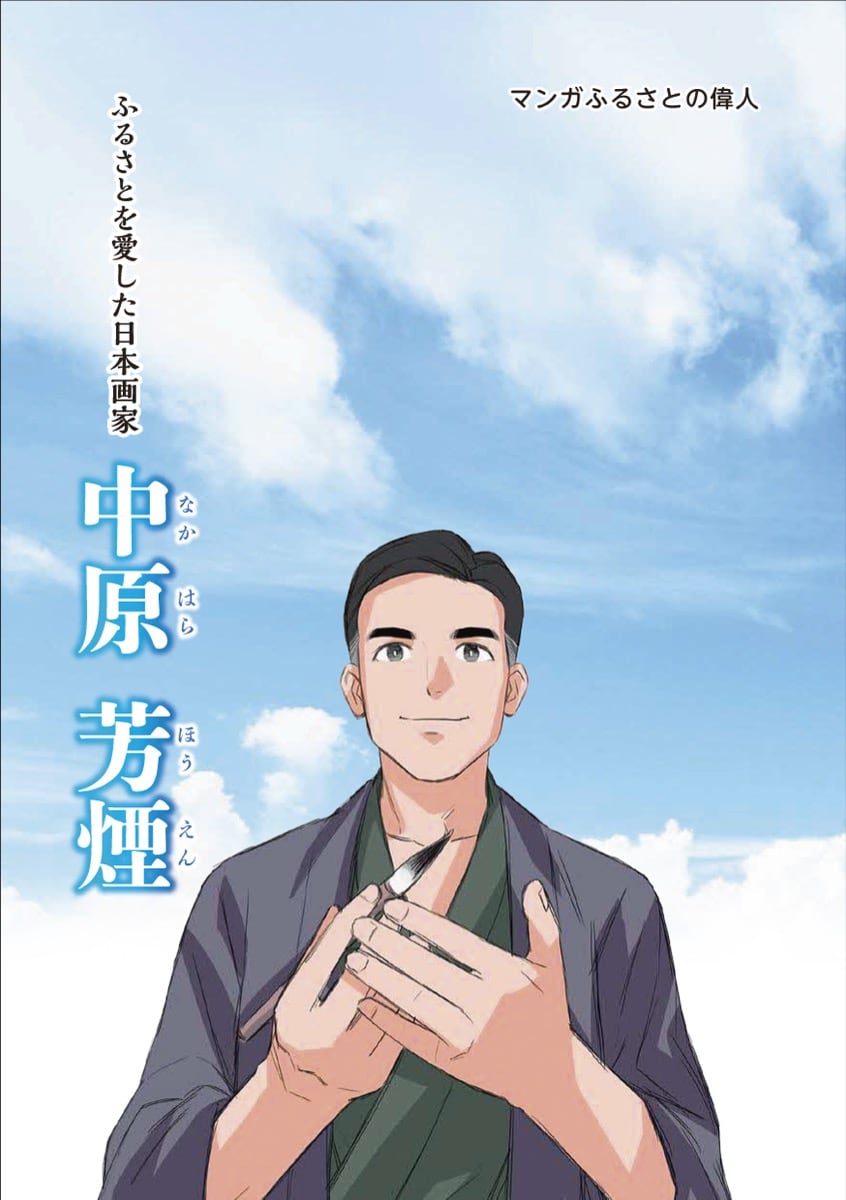
ふるさとを愛した日本画家 中原芳煙 なかはら ほうえん
島根県美郷町マンガ家:監修 神英雄、シナリオ 伊藤ユキ子、マンガ 小村博明中原芳煙(なかはら ほうえん)は、明治8年(1875年)島根県都賀行村(現美郷町)に生まれ、幼少期から身近な動植物の絵を描きながら育ち、東京美術学校(現東京藝術大学)に進みました。同校日本画科を首席で卒業した後、宮内省で正倉院の御物整理を担当したり、審美書院で古今諸派の技法を習得したりすることで画技を磨き、「鹿の絵」など故郷の風景をちりばめた写実的で優しいタッチの動植物画が高く評価されています。
-
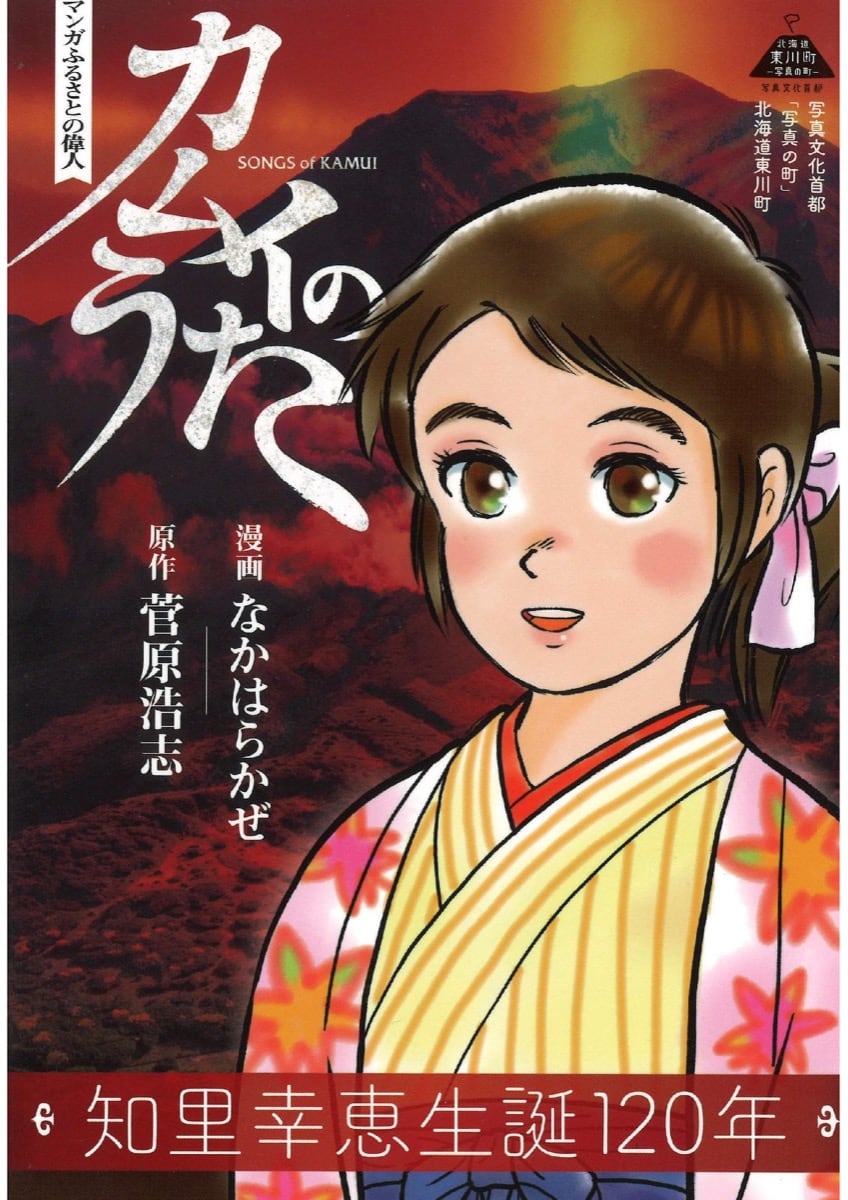
アイヌ叙事詩を文字で後世に伝えた 知里幸恵 ちり ゆきえ
北海道東川町マンガ家:原作 菅原浩志、作画 なかはらかぜ知里幸恵(ちり ゆきえ)は、明治36年(1903年)北海道ヌプルペッ(登別川)沿い(現登別市)に生まれ、言語学者金田一京助から「民族の歴史であると同時に文学でもあり、また宝典でもあり、聖書でもあった叙事詩 ユカㇻの価値」を聴き、同化政策で失われていく「ユカㇻ」を後世に伝えるため、文字のないアイヌ語をローマ字で表記し日本語訳を付した「アイヌ神謡集」を著し、大正12年(1923年)に刊行されました。
- # 近代(36)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 愛・献身(36)
- # 一般市民(16)
- # 女性(11)
- # 世界初(3)
- # 感動(33)
- # 泣ける(7)
- # なかはらかぜ(1)
- # 菅原浩志(1)
- # 北海道(4)
-
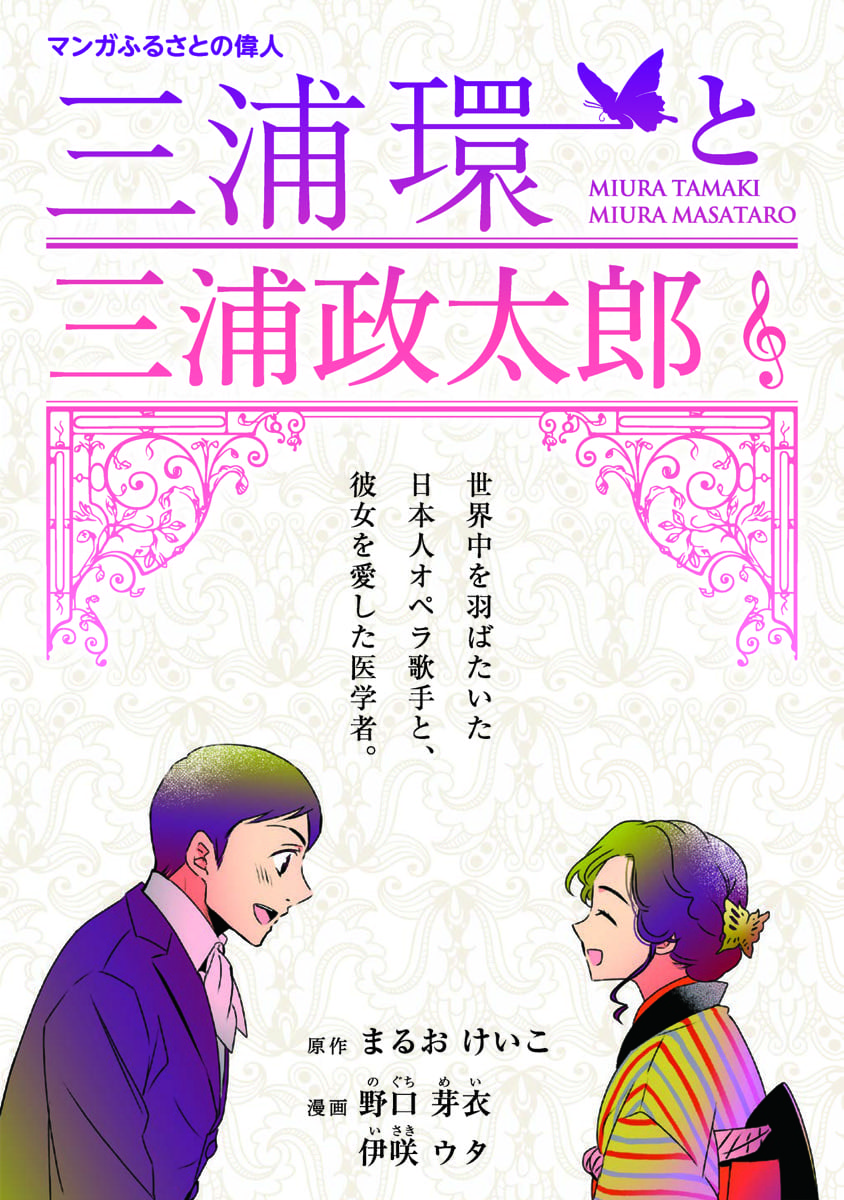
世界的オペラ歌手と医学者 三浦環、三浦政太郎 みうら たまき、みうら まさたろう
静岡県袋井市マンガ家:原作 まるおけいこ、マンガ 野口芽衣・伊咲ウタ、監修 田辺久之三浦環(みうら たまき)は、明治17年(1884年)東京府(現東京都)に生まれ、大正4年(1915年)アメリカで演じた「蝶々夫人」で、世界的なオペラ歌手となりました。
三浦政太郎(みうら まさたろう)は、明治12年(1879年)静岡県に生まれ、東京帝国大学医科を首席で卒業、大正2年(1913年)環と結婚し欧米で医学を研究、壊血病に効果のあるビタミンCが緑茶に多く含まれていることを発見しました。- # 近代(36)
- # 学者・医師(15)
- # 芸術・文化(26)
- # 先駆者(43)
- # 名人・巨匠(27)
- # 発明・発見(13)
- # 型破り(25)
- # 女性(11)
- # 世界で活躍(31)
- # 日本初(20)
- # カッコイイ(40)
- # 面白い(48)
- # まるおけいこ(1)
- # 伊咲ウタ(1)
- # 田辺久之(1)
- # 野口芽衣(1)
- # 静岡県(2)
-
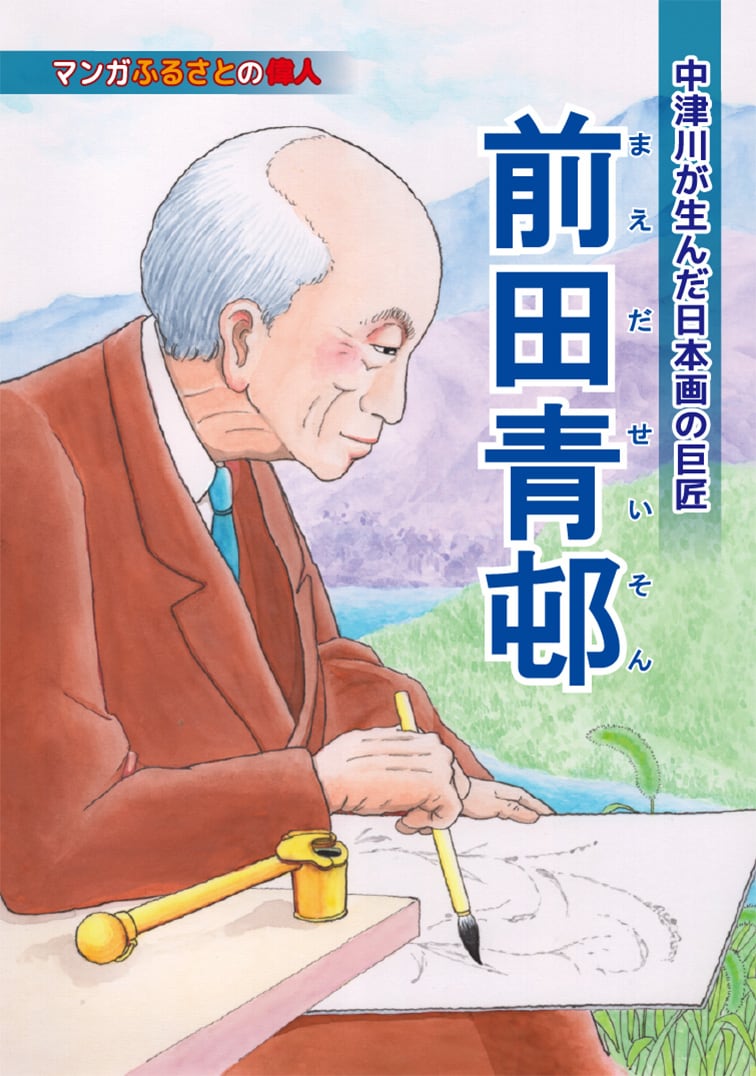
中津川が生んだ日本画の巨匠 前田青邨 まえだ せいそん
岐阜県中津川市マンガ家:島崎朝子前田青邨さん(まえだ せいそん)は、明治18年(1885年)中山道の宿場町中津川村(現中津川市)に生まれ、幼少期から絵の才能を現し16歳で上京して伝統的な日本絵画を学び、歴史画から肖像画・花鳥画など幅広く描き、広く海外にも知られました。また、晩年は法隆寺金堂壁画再現事業・高松塚古墳壁画模写事業など文化財保護にも貢献しました。92歳で亡くなるまで画を描き続け、文化勲章を受章した日本画の巨匠です。
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。



