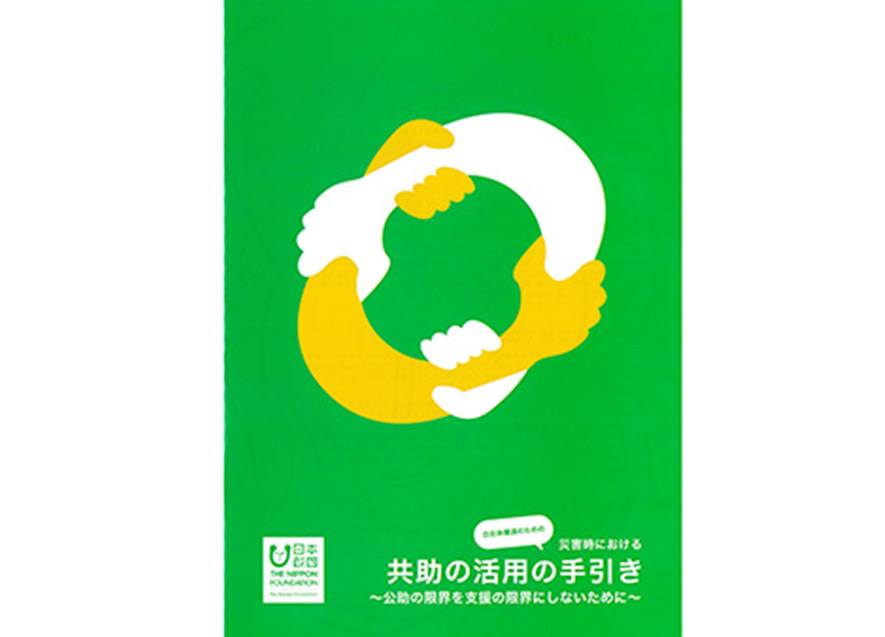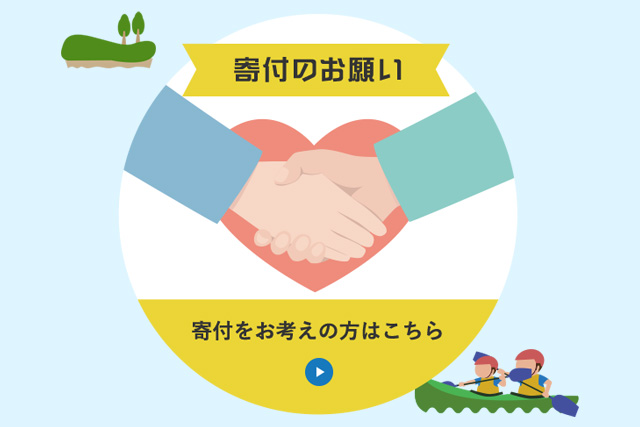2025年11月18日 更新
防災拠点事業
「広域座学研修」を開催
官民連携の強化 ~災害現場から読み解く連携の必要性~
防災拠点事業「広域座学研修」を11月11・12日の2日間、AP東京八重洲(東京都・中央区)で開催。全国57の防災拠点自治体の防災担当者および消防関係者114人が参加し、「官民連携の強化~災害現場から読み解く連携の必要性~」をテーマに、事例共有やワークショップを行い、官民連携の必要性について意見交換を行った。

ー目次ー
■主催者挨拶
■来賓挨拶
■特別基調講演
■ワークショップ
■分科会(防災部局担当者)
■分科会(消防関係者)
■ポスターセッション
■初動対処強化ワークショップ
■官民連携災害対応事例トークセッション
■閉会挨拶
■出展ブース
| 実施日 | 1日目:2025年11月11日(火)13:00~17:00 2日目:2025年11月12日(水) 9:00~12:00 |
|---|---|
| 場所 | AP東京八重洲 11階会議室 |
| 参加者 | <防災拠点設置57自治体> ・防災担当者および消防関係者 114人 <日本財団> ・理事長 笹川 順平 氏 <B&G財団> ・理事長 菅原 悟志 ・常務理事 朝日田 智昭 ・常務理事 岩井 正人 |
| 実施内容 | 〈1日目〉 一、開会 一、主催者挨拶 一、来賓挨拶 一、事業概要説明 一、特別基調講演 一、ワークショップ 一、分科会 一、ポスターセッション 〈2日目〉 一、初動対処強化ワークショップ 一、トークセッション 一、閉会 |
主催者挨拶
B&G財団理事長の菅原は、まず、研修出席のお礼と今年の豪雨災害や昨年の能登半島地震における重機の貸出協力の感謝を述べ、研修目的などについて説明した。
「日本は災害大国であり、今後もB&G財団と日本財団が連携して、防災拠点に配備した機材を迅速に現地へ届け、有効活用していく」と述べた。
その後、公助には限界があるため、各拠点での3年間の研修支援を通じて、「地域住民の皆さんに共助・自助の重要性を理解していただき、防災意識を高めていただきたい」と語った。
また、本研修で得た知識や経験を地元に持ち帰り、共有することで、万が一の災害時に役立ててほしいと話した。

菅原理事長
来賓挨拶
日本財団理事長の笹川順平氏は、日本財団が主にボートレースのファンと14万人の寄付者によって支えられている支援団体であるとしたうえで、寄付者の圧倒的多数が災害支援への活用を望んでいることから、その期待に応えるべく活動していると述べた。消防や自治体の担当者を中心に、人材育成・重機の提供・組織体制づくりの三本柱で支援を進めており、来年には100ヵ所という節目を迎える。「今後も優れた機械と志ある人材とともに、日本の安全を守るため支援を続けていきたいと考えている」と話した。

笹川理事長
特別基調講演
「災害時官民連携」を模索する ―能登半島復旧復興の舞台ウラ―
石川県 副知事 浅野 大介 氏
浅野氏は、災害対応を加速させるために「現場の声を拾う仕組み」「越境・対話・ロビイングの三位一体運用」「制度運用の公式化」の3点を挙げ、市町・県・国・民間が一体となって動くモデル構築の重要性を強調した。
奥能登地域の復旧では、初動の遅れや業者不足、手続きの煩雑さ、情報共有の不足など、多くの課題が明らかになった。これらを克服するため、組織や立場を超えた柔軟な協力(越境)、本音での議論(対話)、現場の声を直接制度に反映させる提案活動(ロビー)を推進。被災直後から毎朝オンライン会議を開き、多様な関係者が情報共有と対応を日単位で進めた。

浅野副知事
その成果として、災害NPOの提案をきっかけに国が土砂撤去の補助金要綱を改定したこと、また、輪島市町野地区で休校中の中学校をボランティアセンターとして活用したことを取り上げ、現場の知見を制度に反映させる対話の重要性を改めて強調。現場の声を丁寧に拾い上げ、制度に反映させることが、より実効性のある復旧・復興につながっていく。
一方、壊滅的な被害を受けた和倉温泉をはじめ能登地域の復旧・復興に向け、県は雇用維持と地域経済再生を両立させる独自の仕組みも構築した。雇用面では、雇用調整助成金の1年延長を実現し、在籍型出向(産業雇用安定助成金)と組み合わせることで、週3日以上の出向要件を柔軟化。被災事業者が復旧作業と出向支援を両立できる体制を整えた。さらに国の予備費を活用し、「創造的復興支援交付金」を創設。地方創生型で自由度の高い財源を確保することで、地域の再生に向けた多様な取り組みを後押しした。
政策形成の面では、県が主導して「土地境界再確定加速化プラン」を策定。国土交通省や法務省と連携し、地籍や境界の再確定作業を民間委託の活用や税軽減措置によって加速させることで、6~7年かかるといわれた期間を2年以内に短縮することを目指す。浅野氏は最後に、災害時の復興・復旧にあたっては国や民間の協力を遠慮なく求めるとともに、地方から国をリードしていく気概が重要だと述べた。
ワークショップ
官民連携推進講義型ワーク
B&G財団地方創生部 防災推進課
ワークショップではまず、災害支援団体の定義や災害中間支援組織の活動内容、技術系災害ボランティアについて説明が行われた。続いて、県外や周辺地域で発生した災害を想定し、技術系災害ボランティアに資機材を貸し出す場合の対応をテーマにワークショップを実施。
各グループは、被災状況の情報共有や所有している重機の保険補償内容の確認、貸出規程の整備など、被災地の要請に迅速に対応するための方法について議論した。
-

ワークショップの様子
-

グループごとに発表する様子
分科会(防災部局担当者)
九州豪雨災害派遣実績 事例紹介(湯前町)
熊本県湯前町の工藤氏は、災害支援団体との連携による災害支援の実績(福岡県久留米市、熊本県山都町ほか)やメリットなどについて説明した。
町のメリットは、信頼できる災害支援団体(九州テクニカルネットワーク)と連携し重機の貸出などを行うことで、「湯前町」の重機が被災地で活躍し、認知度向上につながること。また、情報共有により災害時の知見が広がり、被災時には迅速な支援を受けられる点である。
災害支援団体は被災地で不足しがちな重機の確保ができ、被災地では重機を扱える災害ボランティアが早期に現地入りすることで、行政が対応しきれない復旧作業を実施できるメリットがあると説明した。

工藤氏
分科会(防災部局担当者)
九州豪雨災害派遣実績 事例紹介(長島町)
鹿児島県長島町の大堂氏は、B&G財団から霧島市への資機材派遣依頼を受けての実務フローや確認事項などについて説明した。
8月25日午後、B&G財団から霧島市への資機材派遣依頼を受け、霧島市に必要機材を確認。総務課長と町長へ報告し、町長が即時対応を指示、承諾する旨をB&G財団に伝えた。
建設課と調整し、人員を確保したうえで8月27日に資機材を運搬することを決定。霧島市との受け渡し日時・場所を調整し、借用期間は1ヶ月(延長可)とした。
この内容をB&G財団に共有するとともに、町で付保している保険内容(対人・対物無制限、車両は取得価格)を確認。問題なくクリアしたため、建設課職員3名が予定通り資機材を運搬し、同日に受け渡しを完了した。大堂氏は最後に、「近隣で災害が発生した段階で、重機派遣の想定をしておけば、派遣までの時間をさらに短縮できたかもしれない」と語った。

大堂氏
分科会(消防関係者)
消防有志団体による災害支援活動 事例紹介(JFE韋駄天)
一般社団法人JapanForcibleEntry韋駄天の横田氏と渡辺氏は、消防士としての災害ボランティア活動、災害救援活動の現場での様子と、平時からの取り組みについて説明した。
日本で唯一の強制侵入の技術を学べる機関として、被災地で災害関連死を減らすための救援活動に取り組んでいる。普段は消防職員として火災や救急に対応しているが、大きな災害が起これば、緊急消防援助隊や広域応援として自然災害にも立ち向かわなくてはならない。
消防署の訓練で基礎は身につくが、実際の災害現場での判断や技術の使い方は、現場を経験しなければ理解できない。倒木や土砂の撤去、道路の確保、倒壊家屋の処理、貴重品捜索、家屋再生など、災害ボランティア活動には現場でしか学べない知識や技術が多くある。

横田氏
現場では思いどおりにいくこともあれば、うまくいかないこともある。失敗から学び、次の活動に生かすことが大切で、その積み重ねが、次の災害への備えになる。平時は、チェーンソーや重機の操作だけでなく、資機材のメンテナンスや建物構造についても専門家から学び、解体手順や家屋再生の知識を深めている。災害対応は、多様な知識と技術が組み合わさってこそ成果を生むものであり、人命と生活を守ることが被災者の未来につながると強調した。
ポスターセッション
各自治体が作成した拠点研修のポスターをもとに事例発表を行い、外国人や障がい者、子どもを対象とした訓練・教室など、各拠点の取り組みを共有しながら意見交換を行った。
-

ポスターセッションの様子①
-

ポスターセッションの様子②
初動対処強化ワークショップ
防災iwel 井村 浩之 氏
井村氏はまず、ワークショップの狙いや焦点について説明した。
今回のワークショップでは、自治体の災害対策本部が初動段階でしっかりと機能することが非常に重要であることを確認する。特に「初動の組織化」に焦点を当て、具体的に何をすべきかを各自治体で持ち帰り、実際に活かしてほしいと考えている。
災害対策本部は、ただ「早く開設する」ことが目的ではなく、「何をするか」を明確にし、限られた人員の中で優先順位をつけて迅速に行動することが求められる。そのためには、迅速な情報収集と連絡手段の確保、さらに事前に設置場所や運営体制を整えておく必要がある。
以上を踏まえ、「災害対策本部を開設するために何をするか」についてグルーワークを行った。
グループワーク終了後、各グループは15秒間で初動対処における具体的な行動を発表した。発表内容は、災害発生直後の情報収集、職員の参集、災害対策本部の立ち上げ、広報体制の整備、インフラ状況の確認、避難所の運用、休憩・交代体制の整備に重点が置かれており、全体として、「誰が何を行うか」を平時から明確にし、勤務シフトの運用を前提とした継続可能な体制づくりの必要性が強調された。
-

井村氏
-

ワークショップの様子
官民連携災害対応事例トークセッション
唐津市、唐津市社会福祉協議会、一般社団法人OPEN JAPAN、日本財団、B&G財団
はじめに、5人の登壇者がそれぞれの団体で行っている災害対応の取り組みや工夫について説明した。

5人の登壇者によるトークセッション
日本財団
災害対策事業部 寺田 歩 氏
寺田氏は、2023年8月から「共助の活用の手引き」の作成に取り組んだ。この手引きは、官民連携の進め方や災害対応ノウハウの不足、既存マニュアルの使いにくさ、過去の知見のマニュアル化不足という課題を踏まえ、関係者の意見をもとに分かりやすく整理した。公助の限界を補う共助の重要性を伝え、民間の力を活かすための手引きとなっていると述べた。
佐賀県唐津市
危機管理防災課 篠原 直人 氏
篠原氏は今回の題材となっている「令和5年7月大雨」災害について説明した。
令和5年7月、唐津市東部で集中豪雨により土砂災害が発生し、3人の方が亡くなった。6月末から大雨警報が数回発令・解除され、最後に短時間で80ミリの激しい雨が降り被害が拡大した。災害ボランティアセンターは発災から約1週間で立ち上げられ、迅速な復旧活動を開始した。発災当日に社会福祉協議会に災害ボランティアセンターの設置を連絡し、即座に準備に取りかかる返答があったことで円滑な連携が実現した。

篠原氏
佐賀県唐津市
社会福祉協議会 伊藤 雄司 氏
伊藤氏は、「令和5年7月大雨」での災害ボランティアセンターの活動について説明した。
令和5年7月の災害で初めて災害ボランティアセンターを設置した。佐賀県では以前から災害が多く、県の社会福祉協議会や災害中間支援組織(佐賀災害支援プラットフォーム)の準備ができていたため、スムーズに対応できた。災害発生後すぐに動き出し、被災者の生活支援のためボランティア活動を10月まで延長して実施。当初、大きな土砂災害が浜玉地区に加え、隣の永山地区も大きな被害を受けており、支援拠点を移設した。市の施設を借りて県外からのボランティアの宿泊場所にできたことも大きな助けとなった。

伊藤氏
一般社団法人OPEN JAPAN
肥田 浩 氏
肥田氏は、団体の活動内容やこれまでの災害支援活動の実績などについて説明した。
大規模災害が起こると、県外から災害支援団体が駆けつけるが、初めて会う行政や社会福祉協議会の方々には「どんな団体なのか」と警戒されることも少なくない。当法人は2011年の東日本大震災をきっかけに支援活動を始め、宮城県石巻市を拠点に、年間350日近く支援活動を行っている。
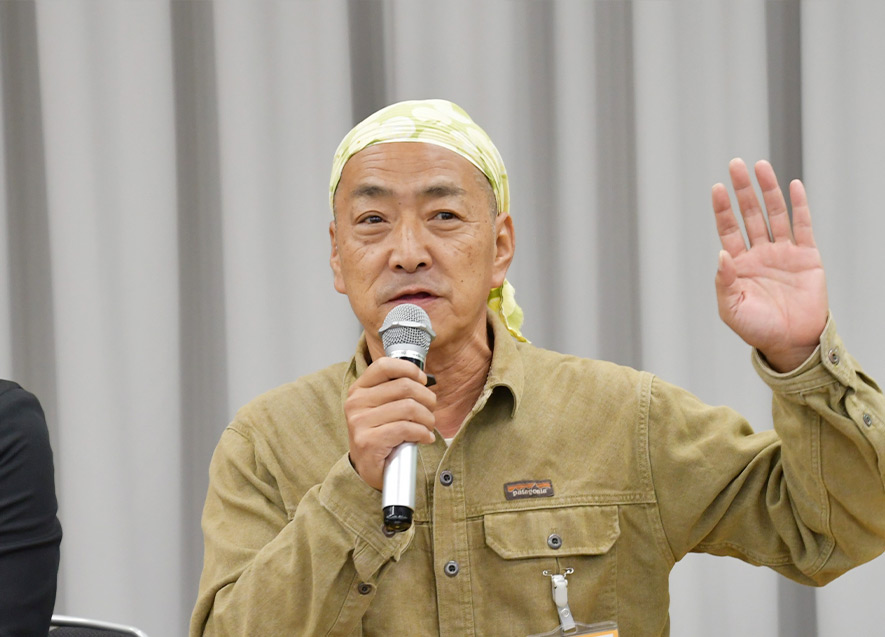
肥田氏
重機やダンプを使った土砂の撤去、炊き出し、家屋の修繕など、多岐にわたる支援を行っており、活動にあたっては必ず地元の建設業協会や行政の担当部署と調整し、必要とされる場所で適切に動けるよう連携を重視している。特に大規模災害では、行政の手が届かない宅地内の土砂撤去などもあり、そうした場面で私たちのような重機を扱えるNPOが重要な役割を果たす。
また、自治体や中間支援組織、社会福祉協議会の方々とも関係を築き、スムーズに現場に入れるよう努めている。阪神・淡路大震災をはじめ、東日本大震災、能登半島地震、静岡の竜巻災害、鹿児島の水害、佐賀県の油流出事故など、これまで全国各地で活動しており、それぞれの地域で連携を大切にしながら、すべては被災者の笑顔のために活動している。
B&G財団 地方創生部 防災推進課
藤江 嵐大
藤江は、防災拠点に関する取り組みについて次のように説明した。
今年8月には、日本財団災害対策事業部とともに九州豪雨の被災地である鹿児島を訪れ、資機材の稼働調整を行った。
続いて、B&G財団が防災拠点としてこれまで実施してきた支援活動について、青森県の豪雪災害(2025年1月)や九州豪雨、牧之原市の竜巻災害(同年9月)など、各地の災害現場で防災拠点と連携して重機派遣等の支援を行ってきたことを説明した。
また、海洋センター所在自治体同士による「ブロック別災害時相互応援協定」は、県域を越えた迅速な支援体制づくりを進めており、現在80%以上のB&G自治体が同意している。
さらに、B&G財団が介在しない自治体間の直接支援も進んでおり、今回の唐津市の事例では、南島原市の防災拠点が油圧ショベルとスライドダンプを派遣し、有効に活用された好事例である。
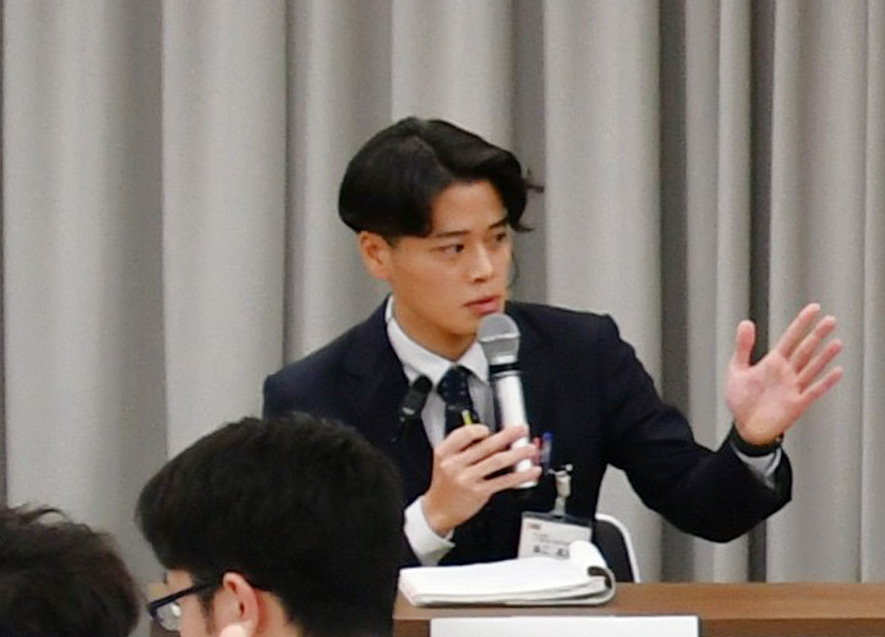
防災推進課:藤江
5人の登壇者がそれぞれの説明終了後、寺田氏をファシリテーターにディスカッションが行われた。
Q:唐津市の災害を契機に官民連携を始めるにあたり、民間の力が必要だと感じたきっかけをお聞かせください。
篠原氏:発災直後から土砂災害の多発が明らかで、公助だけでは対応が難しいと感じた。特に土砂被害の全容が見えにくく、迅速な現地確認や被災者支援が求められる中で、災害ボランティアセンターや中間支援組織と連携する必要性を強く実感した。実際、これらの団体の協力によって、行政だけでは手が届かない支援が可能となった。
Q:今回初めて開設された災害ボランティアセンターで、崖崩れの再発防止に重機が必要だと感じた経緯と、県の災害中間支援組織とどのように連携して課題解決を図ったのか教えてください。
伊藤氏:災害中間支援組織の存在は把握していたものの、当初は緊密な連携はなかった。県の社会福祉協議会の紹介で災害中間支援組織(佐賀災害支援プラットフォーム)と連携を開始し、被災地の現地調査やボランティア調整を共同で行った。重機については、操作できる人材は確保できたが、唐津市内での重機の数が不足しており、小型重機を用意できたものの依然として足りない状況だった。
Q:この災害中間支援組織の機能について、改めて藤江さんからご説明いただきたいと思います。
藤江:災害中間支援組織は、民間団体や企業をつなぐ仲介役を担っており、全国47都道府県のうち26都道府県に設置されている。佐賀災害支援プラットフォームはその一つで、今回の災害でも重要な役割を果たした。情報共有や団体間調整、ボランティア育成などを行い、県を越えた支援を支えている。
Q:篠原さん、肥田さんの協力がなければ技術支援はどうなっていたと思いますか。また、官民連携による支援のスピード感についても教えてください。
篠原氏:行政の支援には設計や入札に時間がかかるため、応急対策が必要な部分が残る。そこで技術系NPOなどボランティアの支援が重要となり、彼らの協力がなければ被災地の不満が高まり、支援は円滑に進まなかったと思う。
Q:肥田さん、オープンジャパンにも重機隊がありますが、行政と連携し、どのような支援活動を行っていたか教えてください。
肥田氏:この災害では福岡県の久留米市や東峰村も被災し、支援要請が多数寄せられた。佐賀県の技術系団体と連携して調整を行い、対応を分担した。唐津市には重機隊が常駐し、行政や社協と連携しながら、オペレーターが実際の支援活動の大部分を担った
Q:伊藤さん、重機のコーディネートを進める際の難しさやSPFの頼もしさなどについて、当時の経験を簡潔に教えてください。
伊藤氏:行政だけでは対応困難な部分を、民間やボランティアが補完し、技術系と一般ボランティアの連携も円滑に進んだ。ただし、生活支援の範囲やどこまで踏み込むべきかについては、今後さらに検討が必要な課題となる
Q:技術系支援のコーディネートや人材探しで、ヒントとなるポイントを教えてください。
肥田氏:災害時に動く技術系ボランティア団体の登録やリストがまだ全国的に整っておらず、現場で誰が何をできるか分からない状況。内閣府が進めるデータベース化への登録も少なく、連携が難しいため、地域の人脈や過去の被災地経験者との信頼関係を活かしながら対応している。行政や社会福祉協議会だけでは対応しきれず、地元の建設業者や消防団などのリソースを普段から把握し、平時からコーディネーターを確保することが重要になる。
また、牧之原の台風被害では、屋根の一部損壊が多く、ゴミ処理が課題になっていたが、牧之原市は重機やダンプで自力対応し、B&G財団の資機材が有効活用されていると感じた。
さらに今回、家屋屋根の復旧作業で画期的な事例が生まれたので、ここで牧之原市の曽根さんからも一言いただきたい。
続いて、研修に参加した牧之原市の曽根氏が発災直後の状況や民間団体・消防との連携について言及した。
曽根氏:Open
Japanが被災直後に災害対策本部に最初に来てくれた。このような時、まずは話を聞くことから始め、可能性を探ることが一番大事だと思う。そして、現場に来る団体の話を聞き、役割を見極めて関係部署へつなぐこと。今回は消防職員と一緒に家屋屋根の復旧活動などをすることができないか、という相談があったため、翌日には消防署長が来庁し、三者で協議を行った。その結果、消防職員が公務で民間の技術系ボランティア団体と協働するという初めての事例が実現した。
Q:最後に、篠原さんと伊藤さんからも一言ずつ、被災経験を踏まえた官民連携のアドバイスをお願いします。
篠原氏:唐津市からは二点。まず、大規模災害後の復旧・復興対応計画を自治体内で再確認し、防災部局が環境部局などと連携して学習機会を提供すること。次に、日頃からボランティアを防災事業に巻き込み、訓練や体験を通じて連絡体制を築くことが重要になる。
伊藤氏:この会議には消防や危機管理防災の方が出席しているが、社会福祉協議会との連携はあまりないと思う。日頃からボランティアも巻き込み、顔の見える関係を築くことが大切であり、そうした関係が災害時の円滑な対応につながる。
閉会
B&G財団常務理事の朝日田は、「本事業は拠点設置が目的ではなく、人材育成と災害支援体制の構築が本来の目的」と述べ、「平時からの備えや官民連携、顔の見える関係づくりが重要であり、自治体間を超えた連携が難しい場合はB&G財団を活用してほしい」と語った。
また、研修支援金を存分に活用し平時の研修や連携強化に役立ててほしいと呼びかけ、今回の研修を機に日頃から連携を深め、災害時に備えた協力体制を築いていきたいと話した。

朝日田常務理事
出展ブース
会場の一角には4社の出展ブースが設けられ、
・株式会社アルミファクトリーの「アルカラ」
・株式会社カナモトの「ポータブル蓄電池」や「ドローン」
・株式会社アンプラージュインターナショナルの「ポータブル浄水器Sawyer」
・株式会社エアドッグジャパンの「エアドッグXシリーズ」
など、多くの防災グッズが展示されていた。参加者は担当者の説明に熱心に耳を傾けていた。

出展ブースの様子
「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業は、災害発生時の緊急対応・避難所運営に必要な防災倉庫の整備、油圧ショベルやスライドダンプ、救助艇などの機材配備に加え、重機オペレーターなどの人材育成にかかる費用について支援を行うとともに、周辺自治体との災害時相互応援協定の締結など支援体制づくりを推進。本事業は2021年度から事業を開始し、これまでに39道府県84市町村への設置を決定している。
各種研修
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。