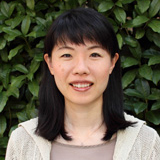「小1の壁」はなくなるか!?
こんにちは。経理課の日比野です。
今年4月に娘が小学校に入学して、早半年・・・「お昼寝ができる保育園は良かったな~」と言いながらも、娘は小学校生活を楽しんでいます。
もともと新しい環境に対しての子どもの適応力についてはあまり心配していませんでしたが、親が日常生活を回していけるかという不安は、入学1年前頃からありました。いわゆる「小1の壁」を乗り越えられるだろうか?という不安です。
「小1の壁」とは、子どもの小学校入学後、保護者が仕事をしながら子育てをするうえで、その両立が難しくなることをいい、それらが起こる理由は
①学校や学童保育の預かり時間が保育園に比べて短い
②学校行事やPTA活動など保護者の出番が多い
③夏休みなど長期の休暇がある
④宿題や翌日の準備など日常のフォローが必要になる などがあるそうです。

柔軟な勤務形態を
②~④は、基本的には夫婦が相談して対応できそうなことですが、①は自分達だけでは解決が難しい問題です。
保育園では7時に子どもを預けることができましたが、小学校は8時の開門前の登校不可のため、7時45分位までは家を空けられません。そして学童の預かり時間は19時までと保育園と比べて1時間前倒しされ・・・今の勤務形態のままでは、子どもの送迎対応が立ち行かなくなることは明らかでした。
そこで、私は、1時間単位で設定されている時差通勤制度を30分単位に変更してもらえないか職場に相談をし、了承いただきました。おかげさまで、朝は子どもと一緒に家を出て、帰りは学童の終了時間までにお迎えに行くことが可能になり、今も働き続けることができ大変感謝しています。
一方で、近所の家族ぐるみで仲良くしているファミリーは、「小1の壁」を乗り越えるために、お父さんが、子育てに理解があって柔軟な働き方ができる会社に転職をしました。このことがNHKの番組で取材&放送されて、とても反響が大きく、子ども家庭庁が調査に動き始めたとかなんとか・・・
多くの職場で柔軟な働き方が認められることを切に願うばかりです。

夏休みのお弁当問題
そして、勤務時間以外で最も心配だったことは、③の夏休みなどの長期休暇のお弁当作りです。子どもが高校生になれば、長期休暇だけでなく、毎日お弁当を作ることになるので、その予行練習と思ってやるしかないのかもしれませんが、なるべく負担は減らしたい・・・
試行錯誤の末、私は下記を実行することにしました。
・おにぎりは作らず、ごはんをそのまま詰める
・卵焼きは焼かず、電子レンジで作れるだし巻き卵にする
・冷凍食品(市販のもの&作り置き)を中心に入れる
・入れる場所を迷わない仕切りのあるお弁当箱を使う
・おかずの種類は少なくても、子どもが好きなものを4色構成で入れる
・ふりかけ&保冷剤がわりに入れるこんにゃくゼリーでバラエティ感を出す
以前は、食べやすいようにおにぎりを作ったり、卵焼きを焼いたり、どうやって詰めようか悩んだりして30分かかっていましたが、10分程度に短縮され、なんとか46日間の長~い夏休みを乗り切ることができました!
そのような中、近所の別の小学校の学童では、お弁当制度の試運転が行われていたとの話を聞き、来年度は是非とも全校に広がってほしいなと思いました。
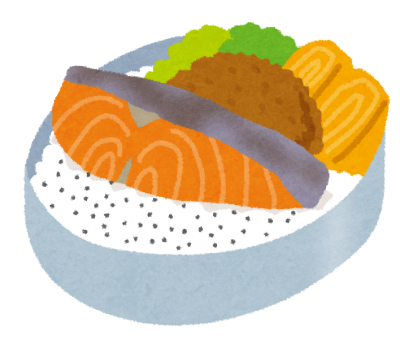
「小1の壁」の後には「小4の壁」があると聞きますし、その後もおそらく色々な壁が出現してくるのでしょう。自分達が工夫をして解決していくことが基本だとは思いますが、個人が頑張ってもどうにもならないことがあるのも事実。多くの人が子育てと働くことを両立させやすいように、国や職場等の子育支援制度がさらに進化して「小1の壁」がなくなるといいなと思います。