
今回の特集は、「学校を開く」をテーマに
1.女子教育・幼児教育の先駆者 タマシン・アレン(岩手県久慈市)
2.私塾を開き地域の人材を育てた 鈴木文台(新潟県燕市)
3.「地域で学び育つ」教育を実践 井上堰水(京都府南丹市)
4.私財を投じ教育に一生を捧げた 豊田太蔵(鳥取県北栄町)
の4作品をご紹介します。
-
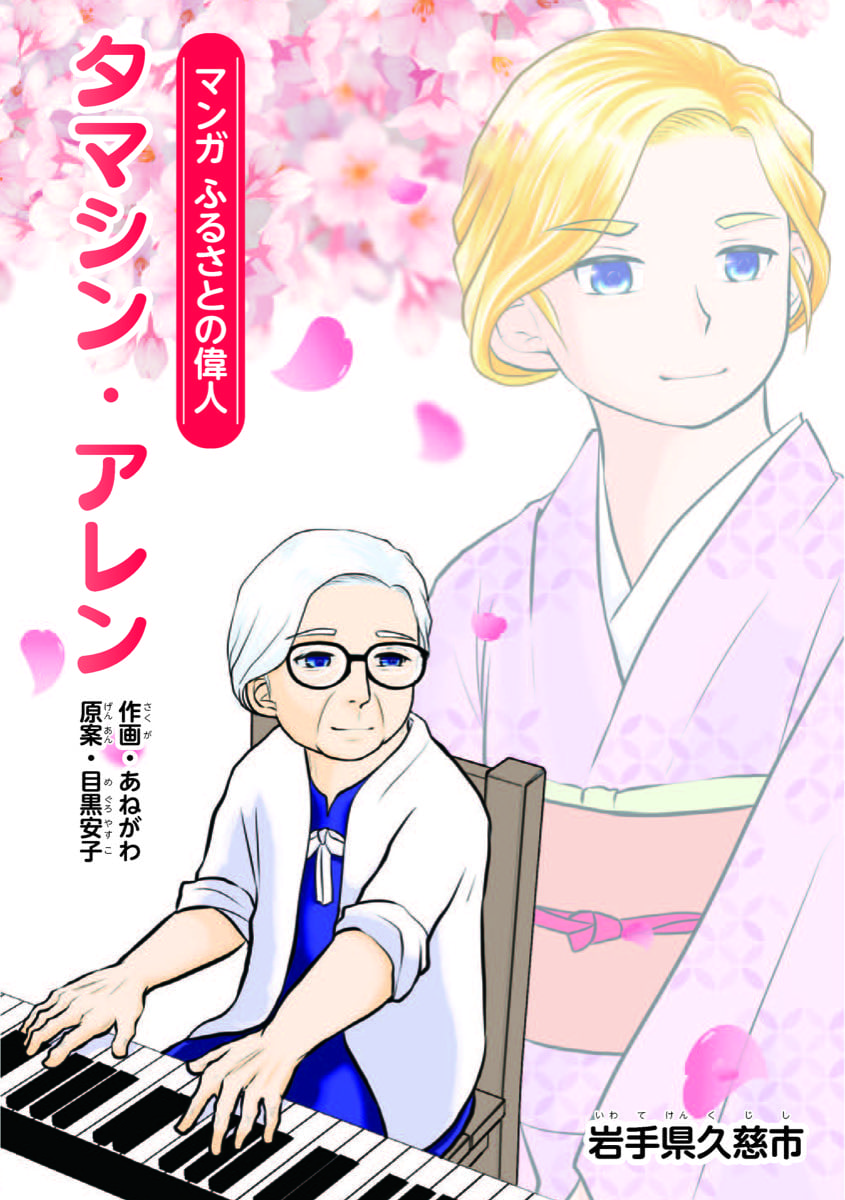
女子教育・幼児教育の先駆者 タマシン・アレン Thomasine Allen
岩手県久慈市マンガ家:作画 あねがわ、原案 目黒安子タマシン・アレンさんは、1890年米国に生まれ、大正4年(1915年)25歳で来日、東京・仙台・盛岡等で女子教育や乳母子の保健活動を行い、昭和13年(1938年)久慈市に久慈幼稚園を開園しますが、太平洋戦争開戦で米国に強制送還されました。アレンさんは、終戦後の昭和22年再来日して社会活動を再開、昭和27年学校法人頌美学園を設立し幼小中の一貫教育体制を作り、昭和45年アレン短期大学を設立しました。
- # 現代(35)
- # 社会貢献(14)
- # リーダー(39)
- # 先駆者(43)
- # 愛・献身(36)
- # 女性(11)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 世界で活躍(31)
- # びっくり(38)
- # 感動(33)
- # 熱血(61)
- # あねがわ(1)
- # 目黒安子(1)
- # 岩手県(3)
-
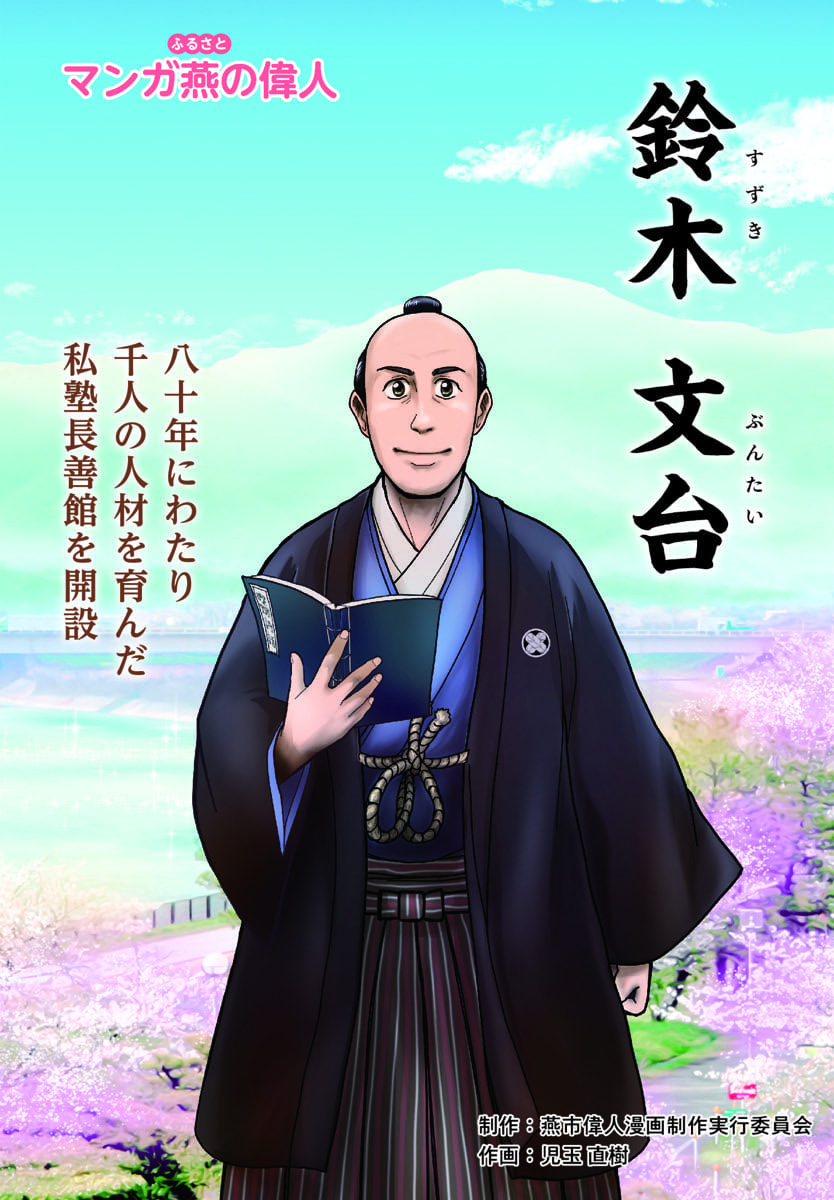
私塾を開き地域の人材を育てた 鈴木文台 すずき ぶんたい
新潟県燕市マンガ家:児玉直樹鈴木文台(すずき ぶんたい)は、江戸時代後期寛政8年(1796年)越後国粟生津村(現新潟県燕市)に生まれ、名僧良寛とも親交を持ちました。文台は、様々な学者の講義を聴き江戸にも遊学しますが、師事せずに多くの書物を読み自身で研究する「無師独学」を進め、天保4年(1833年)38歳で粟生津村に私塾「長善館」を開きました。長善館は、明治45年(1912年)まで3代79年間も続き、多くの人材を育てました。
-
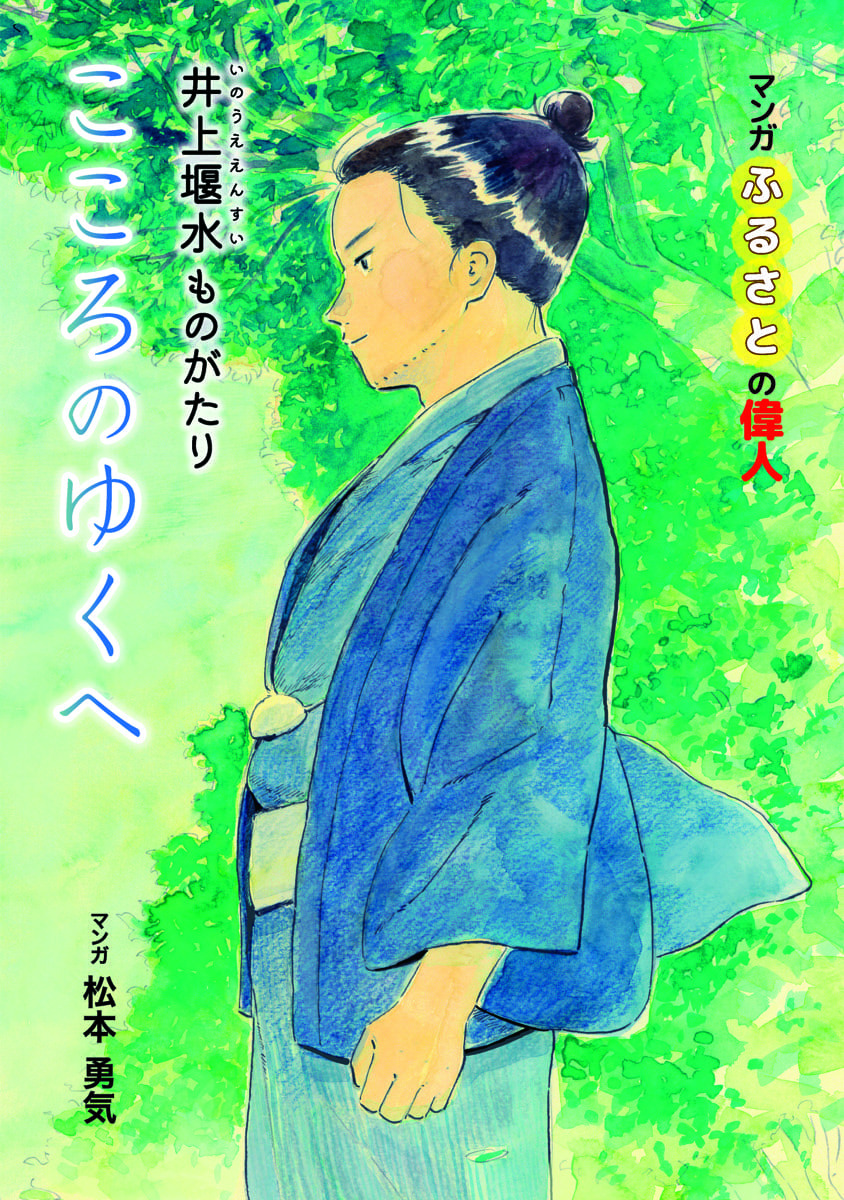
「地域で学び育つ」教育を実践 井上堰水 いのうえ えんすい
京都府南丹市マンガ家:監修 田中智子、マンガ 松本勇気井上堰水(いのうえ えんすい)は、幕末天保13年(1842年)丹波国船枝村(現京都府南丹市)に生まれ、元治元年(1864年)私塾発蒙館を開き、明治5年(1872)に新修校(旧新庄小学校)の初代校長となり、その後、船井郡立園部高等小学校・船井郡立高等女学校(現園部高等学校)の初代校長を歴任しました。学校田や学校林での授業など独自の「地域で学び育つ」教育方法を取り入れ、地域の人材育成に尽くしました。
-
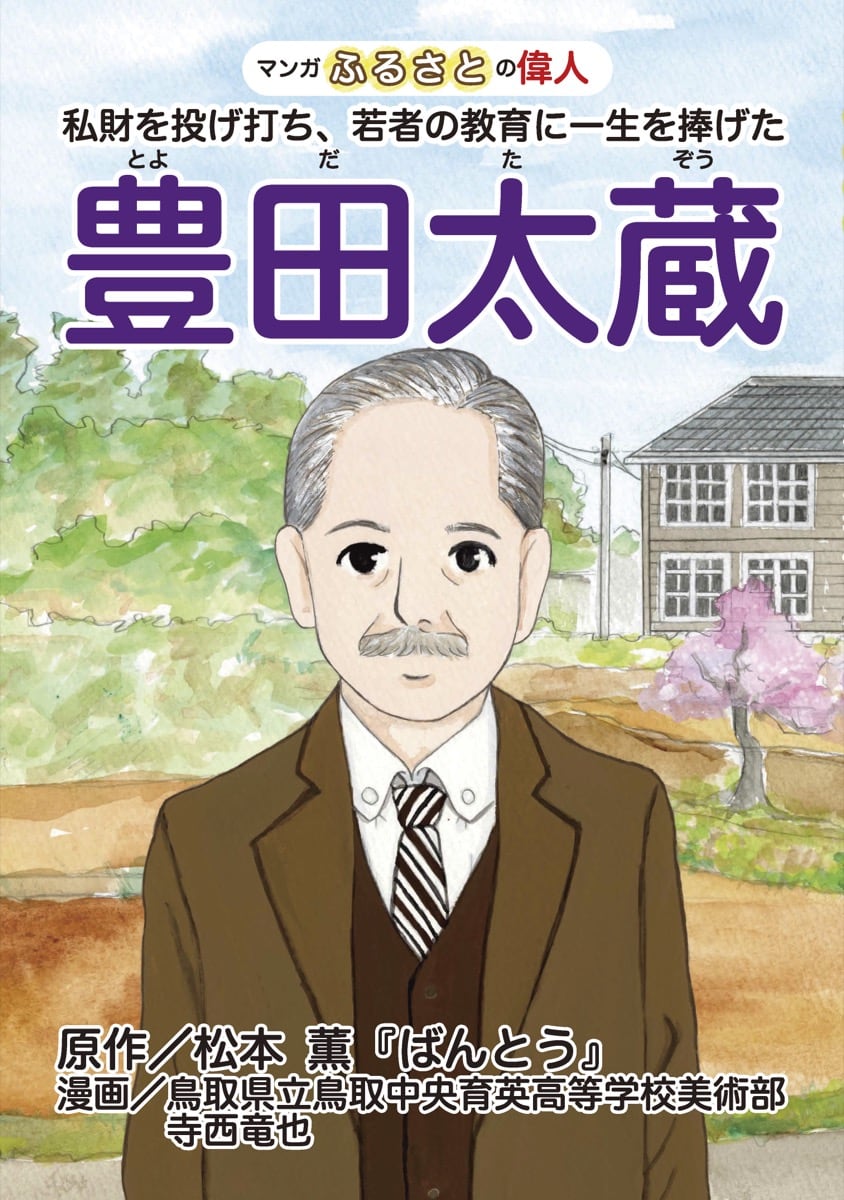
私財を投じ教育に一生を捧げた 豊田太蔵 とよだ たぞう
鳥取県北栄町マンガ家:原作 松本薫、マンガ 長谷川万桜・前美里・寺西竜也豊田太蔵(とよだ たぞう)は、幕末安政3年(1856年)伯耆国鳥取藩由良宿(現鳥取県北栄町)に生まれ、由良村議会議員・由良村長・県会議員などを務めながら、明治40年(1907年)私財を投じて私塾「育英黌」を開き、大正3年(1914年)山陰地方初の私立中学校「由良育英中学校」(現県立鳥取中央育英高等学校)を開校しました。郷土の教育に一生を捧げた太蔵の生涯は、松本薫の小説「ばんとう」に描かれました。
- # 近代(36)
- # 社会貢献(14)
- # リーダー(39)
- # 先駆者(43)
- # 起業家・ビジネスマン(30)
- # 熱血(61)
- # 前美里(1)
- # 寺西竜也(2)
- # 松本薫(1)
- # 長谷川万桜(1)
- # 鳥取県(2)
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。


