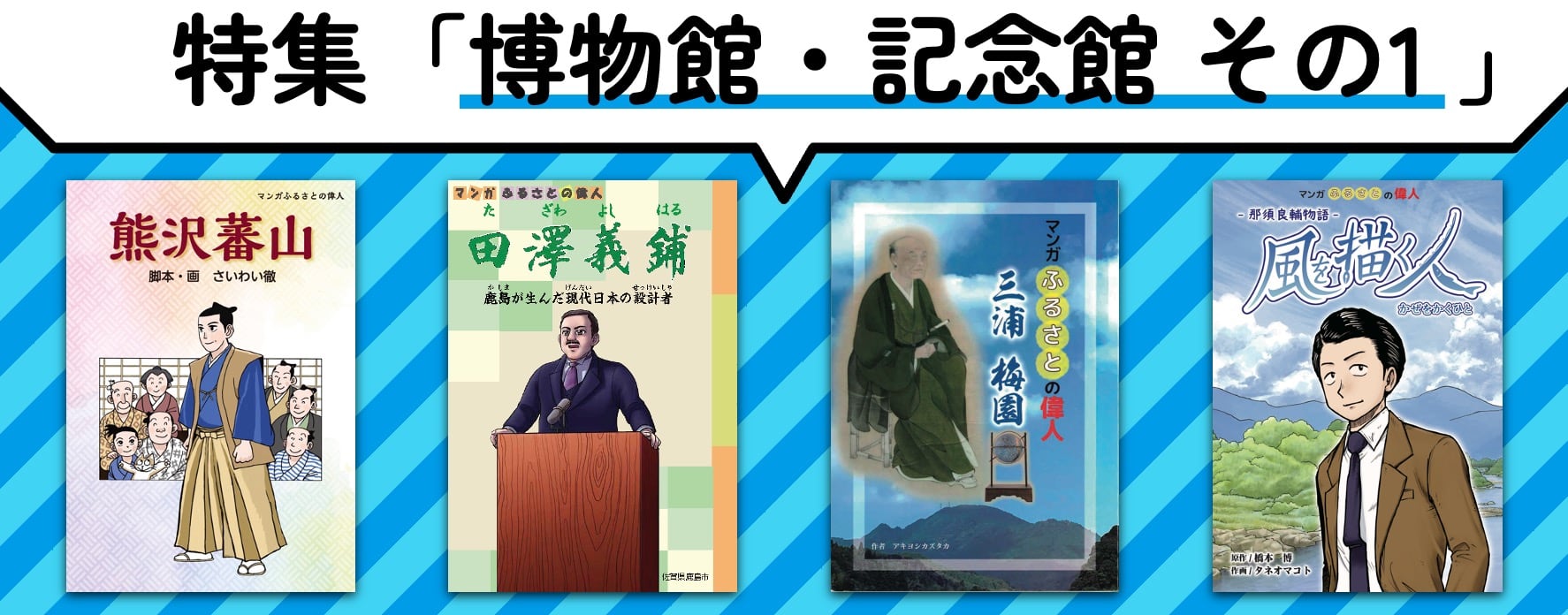
1.日本最古の庶民の学校閑谷学校につながる 熊沢蕃山(岡山県備前市)
2.青年団運動で地域社会の発展に貢献、日本青年館を建設した 田澤義鋪(佐賀県鹿島市)
3.独自の学問体系「条理学」を構築した思想家・自然哲学者 三浦梅園(大分県国東市)
4.マンガなどで活躍し、「湯前まんが美術館」の原点となった 那須良輔(熊本県湯前町)
の4作品をご紹介します。
-
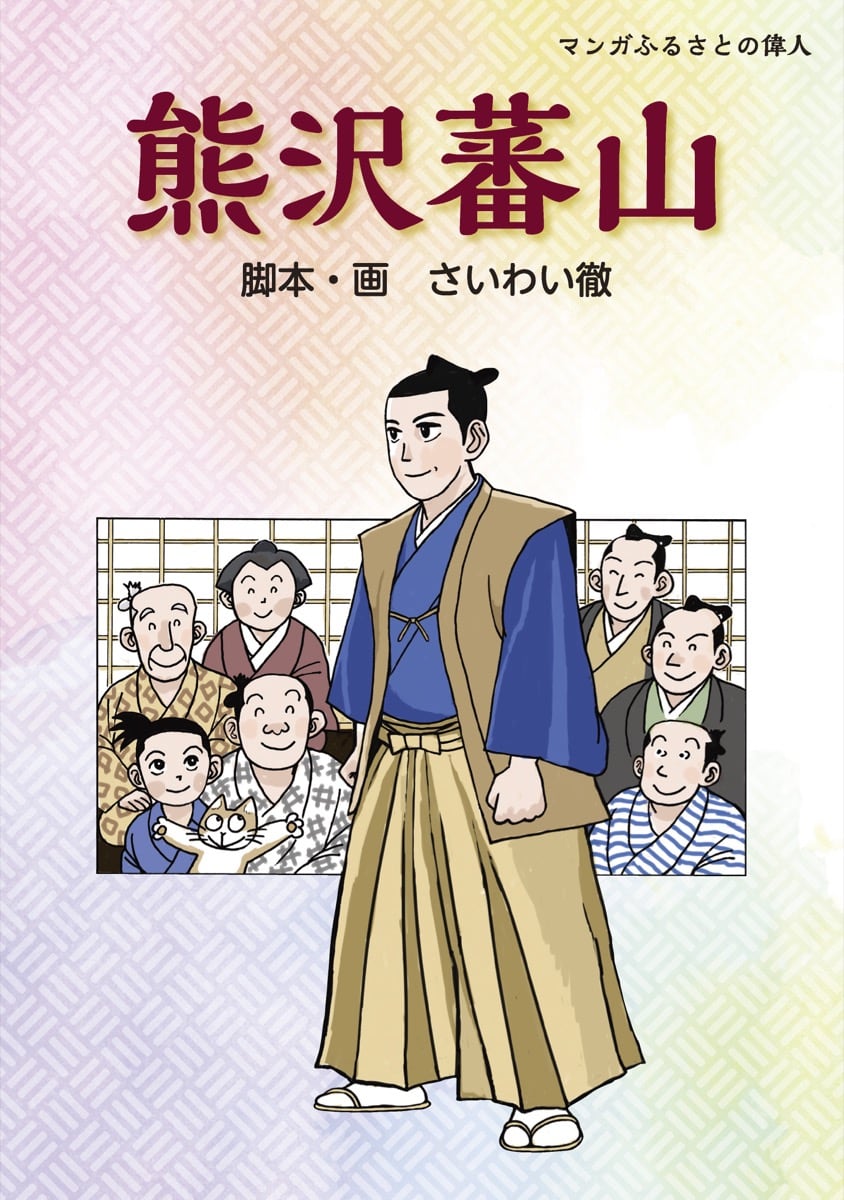
藩主を支え地域発展に尽くした 熊沢蕃山 くまざわ ばんざん
岡山県備前市マンガ家:短編マンガ監修 森熊男、マンガ さいわい徹熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)は、江戸時代初期元和5年(1619年)京都に生まれ、16歳から岡山藩主池田光政に仕えました。20歳で岡山藩を退き陽明学者中江藤樹の弟子として学問に励み、27歳で再び岡山藩に仕え、洪水復興・凶作対策として治山治水事業、飢饉の窮民対策事業で活躍しました。39歳で備前市(旧蕃山村)に隠居した後も、光政と閑谷学校創立に繋がる庶民教育事業や新田開発で地域の発展に貢献しました。
-
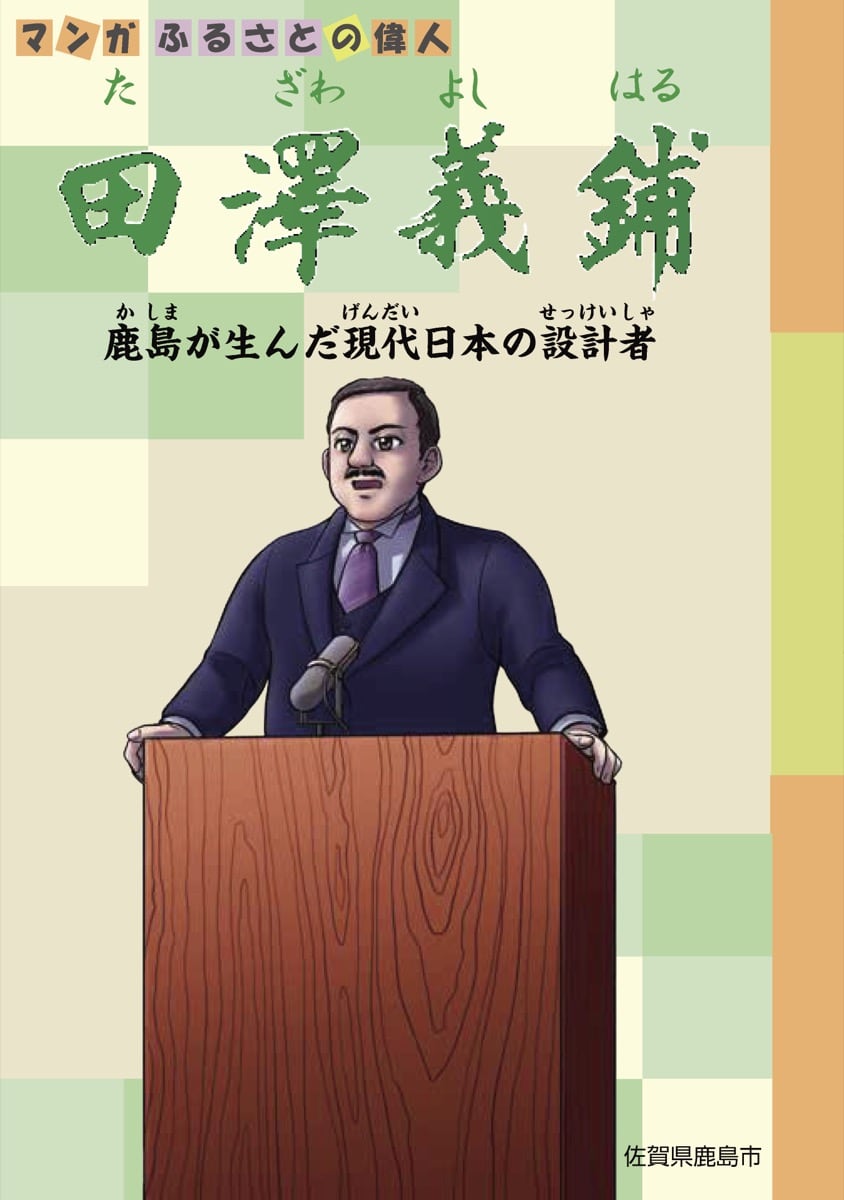
青年団運動で地域社会に貢献 田澤義鋪 たざわ よしはる
佐賀県鹿島市マンガ家:やまのたかし田澤義鋪(たざわ よしはる)は、明治18年(1885年)佐賀県藤津郡鹿島村(現鹿島市)に生まれ、明治42年(1909年)内務省に入省、日露戦争で疲弊した農村を立て直すため「青年団運動」に尽力しました。大正4年(1915年)明治神宮創建に際して、全国189団体1万人以上の青年団員が勤労奉仕に集まり、これを機に大日本連合青年団結成と日本青年館建設が行われ、田澤義鋪は「日本青年団の父」と呼ばれました。
-
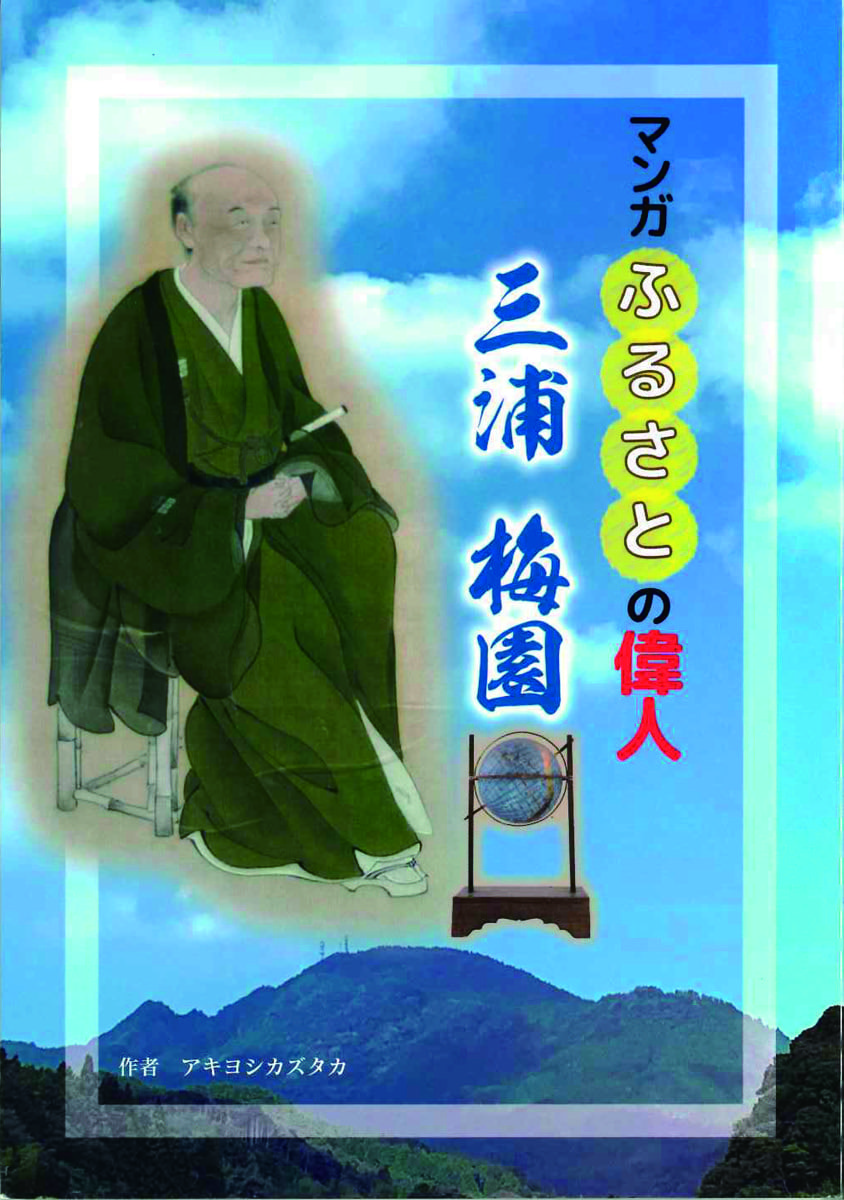
独自の哲学「条理学」を構築 三浦梅園 みうら ばいえん
大分県国東市マンガ家:アキヨシカズタカ三浦梅園(みうら ばいえん)は、江戸時代中期享保8年(1723年)豊後国杵築藩(現大分県国東市)に生まれ、富永村(現国東市)に「梅園塾」を開き、独自の学問体系「条理学」を打ち立て、玄語・贅語・敢語の「梅園三語」を著した、思想家・自然哲学者です。窮民救済制度「慈悲無尽」や村人を救った逸話から「豊後聖人」とも呼ばれました。明治30年代(1900年頃)、内藤湖南が再評価し、全国的に有名になりました。
-

マンガ家・画家・文化人として活躍 那須良輔 なす りょうすけ
熊本県湯前町マンガ家:原作 橋本博、作画 タネオマコト那須良輔さん(なす りょうすけ)は、大正2年(1913年)熊本県球磨郡湯前村(現湯前町)に生まれ、昭和7年(1932年)洋画家を目指して上京し太平洋美術学校に入学。内職のつもりで描いたマンガが採用されて、昭和8年児童マンガ家としてデビュー。人気マンガ家となり、そこから優れたデッサン力で政治家の特徴を捉えた似顔絵の政治風刺マンガ、釣りや自然を題材とした風景画・随筆などに活動範囲を広げ活躍しました。
©B&G財団
このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。



