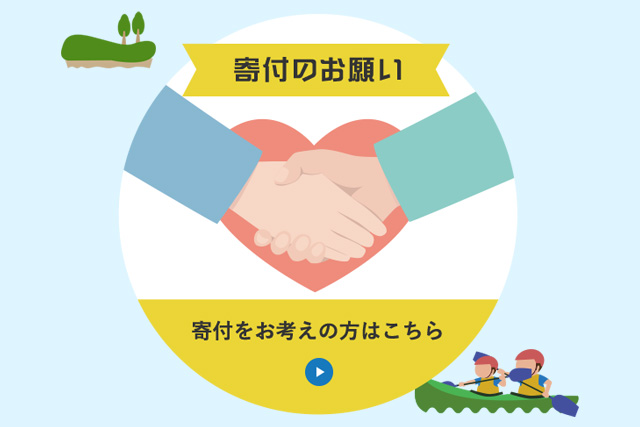2025.3.05 UP
東日本大震災から14年
二度の大災害を乗り越えた大船渡市
このたびの山林火災により、避難を余儀なくされた住民の皆さまをはじめ、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申しあげます。この記事は先月中旬に取材・作成したものです。
大船渡市は“夏は暖かく、冬は温暖”―三陸でも過ごし易いのは有名。陸中海岸南部最大の港湾を持つ臨海工業都市として知られている。
語り継がれる明治の大震災
未曽有の大惨事、東日本大震災から14年の月日が流れた。
日本周辺における観測史上最大規模のマグニチュード9.0。岩手県から茨城県沖まで南北500キロ、東西200キロ、面積は10万平方メートル。死者は東北を中心に12都道府県で2万2,325人。東日本大震災は筆舌に尽くしがたい大惨事だった。
だが大震災を語る上で変遷を語らないわけにはいかない。実に129年前の1896年(明治29年)。第1回アテネオリンピックが開催、日清戦争が終わった翌年。6月15日に「三陸大地震」が起き大船渡を直撃した。マグニチュード8.2、38.2メートルの津波が町を飲み込んだ。近県を含めて死者数は総数で2万数千人。この悪夢は語り継がれ、現在に至るまで脈々と受け継がれている。
約600人の命をつないだ海洋センター
2011年3月11日午後2時46分。不運にも再び巨大地震が発生。震度7、40.1メートルの大津波が容赦なく猛威を振るった。見慣れた街並みが一瞬にして崩壊。被害を受けた建物は5,556世帯(全壊2,789世帯)。死者は340人で行方不明は79人に上った。
震災直後、人命救助に大奮闘したのが大船渡市三陸B&G海洋センターの体育館。近くの綾里中学校の300人余は綾里駅まで移動し、ガレキと化した町を確認。直線距離で800メートルの海洋センターに避難を求めた。
道路はすべて寸断されており、引率した教員、消防士は明治の大震災が脳裏をかすめたという。怒号と悲鳴が飛び交う中、素手で崖をよじ登り、幸いにも無事全員が体育館に到着。綾里小学校、近隣の避難者を含め約600人が肩を寄せ合った。さらに海洋センターの駐車場には車で避難してきた約100台が集まり、館内に入れなかった人は車中泊を余儀なくされた。

綾里地域には津波で漁船が打ち上げられた
「当日、支援物資は届かなかった。寒かったので館内は反射式ストーブ、外にいる人はバーベキューコンロで暖を取った」と当日勤務していた菅生さん(大船渡市スポーツ協会)は振り返った。翌日に自衛隊が到着、食料が配られ命をつないだ。
3日後には全員、避難所となった小学校、中学校などに移った。校庭には最短1ヵ月余りで仮設住宅が建設され、被災者は出来次第、随時入居していった。余談だが、今年ロサンゼルスドジャースに入団した佐々木朗希選手(陸前高田市から実母の親戚がいる大船渡市に移住)もこの仮設住宅で暮らしていた。
菅生さんは「仮設住宅に移ってからも『あの時はありがとう』と皆が笑顔で声をかけてくれた」と語った。約600人の命をつないだ海洋センターへの感謝の念は市民の心に深く刻まれたことだろう。
大船渡市では、震災の影響で水への恐怖心を子どもから取り去る活動が現在も行われている。海洋センター指定管理者である大船渡市スポーツ協会と水難学会が協力し、市内11の小学校のプールで「水辺の安全教室」の出張授業を実施。
着衣泳、背浮き、ライフジャケット体験、ペットボトル浮きを中心に、自分の命は自分で守るための落水時の対処法の実技授業を行う。保護者からも好評で笑顔をのぞかせる子どもも多く、楽しく学べる授業になっている。
また、毎年7月には「ヨット教室」を実施。ヨット体験を通じてジオパークに関する環境学習を行うと同時に、海や海辺の清掃活動を行っている。
-

水辺の安全教室(出前授業)
-

ヨット教室
未来に向け歩み続ける大船渡市
大船渡市では、湾口防波堤や住宅の高台移転、災害公営住宅など着々と整備され、基幹産業の漁業やセメント産業も堅調。複合型商業施設(キャッセン大船渡)などの復興事業も芽生えてきた。
さらに創業の機運も高まってきている。中でも注目したいのは、株式会社スリーピークスだ。「三陸で100年続く文化を創造する」「地元で人を呼べるワイン文化を作りたい」。この信念を貫いているのが代表の及川武宏さん。
震災から2年後の2013年に埼玉県から故郷の同市にUターン。5月からワイン造りを始めた。何もない海辺の荒れ地を50坪と廃業を予定していたリンゴ園も購入。ブドウが実るまではリンゴジュースを販売した。2018年にワイナリー(醸造所)が完成し、ワインやアップルワイン、シードルの販売を開始。現在はブドウ畑を拡大し、年間に白ワイン約3,000本、赤ワイン約700本を製造販売している。

また及川さんは、三陸といえばリアス海岸、世界に数多くあるリアス海岸を有する地域とネットワークを作り、ワインだけでなく、食や養殖技術の連携、交換留学など人材交流ができるようにしていきたいと語る。スリーピークスが大船渡市の復興の象徴として、牽引役になってくれることを期待したい。
東日本大震災から14年。復興に向けた市民一人一人の努力と絆が大船渡市の「今」を創り出した。大船渡市は未来へ力強い歩みを進めている。
関連ページ
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。