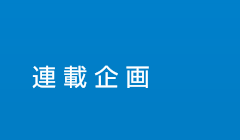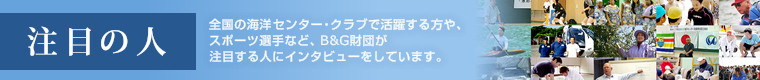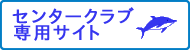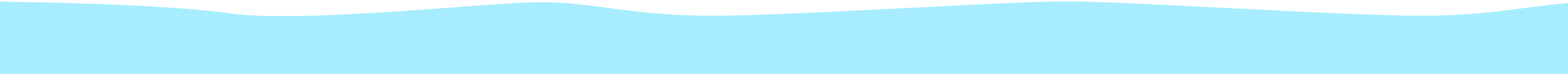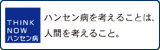No. 78
島の子どもたちに、美しい海の大切さを伝えたい!


上:与論町B&G海洋クラブの活動
下:与論町B&G海洋センター
~海の環境を守りながら島の活性化をめざす~
与論町B&G海洋センター・クラブ(鹿児島県)
沖縄本島を沖に臨む鹿児島県の与論島。さんご礁で囲まれた島の沿岸は風が吹いても大きな波が立たないため、ウインドサーフィンのメッカとして知られ、プロの選手たちがトレーニングに訪れます。
地元の与論町B&G海洋センター・クラブでもウインドサーフィンに力を入れ、練習を重ねた不登校の高校生たちが大会で活躍するなどの成果を上げました。
「少子化の波は与論島にも押し寄せています。ですから、これからは島の伝統を継承していく文化的な活動にも力を入れていきたいと思います」と語る海洋センターの柳田所長。
プロフィール
- ●与論町B&G海洋センター・クラブ
-
昭和56年、島在住のマリンスポーツ愛好家が集まって与論町B&G海洋クラブを設立し、地元の子どもたちにウインドサーフィンやカヌー、水上スキーなどを指導。平成4年には艇庫・プールによる海洋センターが開設され、活動が拡大した。
なお、海洋センターの運営は平成24年度から指定管理制度を導入。現在は、NPO法人「ヨロン島スポーツクラブ」が指定管理者として業務を担っている。

第2話広がりを見せた、海とプールの活動
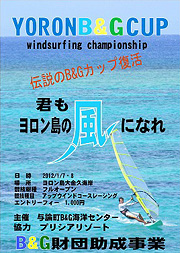
14年ぶりに復活した"YORON B&G CUP"のポスター。美しい海に「伝説のB&G CUP復活」の文字が彩られています
プロも虜にした伝説のレース
海洋クラブ、海洋センターの活動を中心に、マリンスポーツが根付いていった与論島。なかでも、ウインドサーフィンはB&Gの冠をつけた大会が大いに盛り上がっていきました。
「海洋センターができた平成4年から、“YORON B&G CUP”という名でウインドサーフィンの大会を毎年、開催していきました。良い風が吹く冬場に日程を組んだところ、シーズンオフの合宿練習を島で行うプロの選手や上級者の皆さんも参加してくれるようになって、大盛況となりました」
冬でも暖かい与論島で合宿をしながら調整に励んでいた、トップレベルの選手たち。現地で大会があると聞いて、最初は腕慣らしの気持ちで参加したケースも多かったそうですが、いつしか誰もが真剣に競い合うようになっていきました。
「他と同じ内容の大会では面白くありません。一般的なコースで走るレースはシーズン中にたくさんあるわけですから、“YORON B&G CUP”では直線でトップスピードを競う種目や、ジャイビング(風下航での方向転換)の技を競う種目などを取り入れて趣向を凝らしていきました」
他の大会にはない趣向を凝らしたレースにしたことで、勝つためにさまざまなテクニックが求められた“YORON B&G CUP”。その結果、「“YORON B&G CUP”を制したら一流の選手だ」とまで言われるようになって、プロ・アマ問わず多くのウインドサーファーを虜にしていきました。

絶好の風が吹いて大成功に終わった新生"YORON B&G CUP"。大会後の親睦会では「ワールドカップを誘致しよう」という声も上がりました(写真提供:B&G特派員 平成22・23年度 南九州ブロック担当 大平 淳一さん)
"YORON B&G CUP"の盛り上がりを受けて、ウインドサーフィンのメッカとして知られるようになっていった与論島。ところが、ブームに沸いた1980年代と異なり、1990年代に入ると徐々にウインドサーファーの数が減少していきました。
「参加者の数が減ってしまったため、残念ながらこの大会は1998年を最後に休止となりましたが、さんご礁に囲まれた与論島の海が最高のゲレンデであることに変わりはありません。そのため、ここにきてまた"YORON B&G CUP"を復活させようという声がウインドサーフィン愛好家の間で高まりました」
こうして、島内外の熱心なウインドサーファーが中心になって大会が再興。今年1月、風速6~8メーターの絶好の風が吹くコンディションのなかで25名の選手が熱戦を繰り広げました。
海があってもプールは必要!

夜の磯場でタコなどを捕る、夜のいざり漁体験に参加する皆さん。島の自然や環境を学ぶイベント活動が続けられています

海洋センターの敷地内には、さんご礁の海を臨むテラスがあり、バーベキューなども爽快に楽しめます
海洋センターの開設とともに、“YORON B&G CUP”で盛り上がっていった与論島。所長の池田さんほかスタッフの皆さんは、ウインドサーフィン以外にもさまざまな活動を展開して施設の利用率アップに努めていきました。
「かつて、島の漁師さんたちは帆のついた船で漁をしていたため、ヨットやウインドサーフィンに理解があり、風向きが悪くてぶつかりそうになると、早々に自ら避けてくれます。
また、そんな漁師さんたちに協力してもらいないながら、一時期は海洋センターで追い込み漁の体験イベントなどもしていました。親子で参加してもらい、取れた魚でバーベキューを楽しんだものです」
海の恵みを最大限に活かしながら海洋センター・クラブの事業を進めた池田さんほかスタッフの皆さん。その一方、海から離れた丘に建設されたプールも大いに有効利用されていきました。
「海洋センターができる前は、町内1カ所の小学校にプールがあるだけでした。しかも、それは海洋センター設立2年前にできたプールでしたから、島の人たちのほとんどがプールで泳いだ体験がありませんでした。私も、アクアインストラクターの指導者養成研修に行った際、体が浮かびにくいプールの真水に苦労したものです」
そう池田さんが振り返ると、現在、海洋センターの指定管理委託業務を行っているヨロン島スポーツクラブの高井克彦会長は次のように述べました。
「兄弟が大勢いた昔は、子どもたち同士で海に行っても年長者が年下の面倒をみてくれたものでした。しかし、兄弟が減ってそれが期待できなくなった昨今、親たちは『海は危ない』といって子どもを海から遠ざけるようになりました。そのため、子どもたちは海での泳ぎさえも覚えなくなっていきました」
島の小学校に初めてプールができた際、25メートルを泳ぎ切る子は数えるほどしかいなかったと語る高井さん。これでは良くないと考えて、水泳スポーツ少年団を結成。海洋センターのプールができたことを励みに活動を進めた結果、県大会で優勝する子も出るようになりました。(※続きます)

島の水泳環境を大きく変えた海洋センターのプール。
開設以来、泳げる子どもたちを大勢育てています
写真提供:与論町B&G海洋センター・クラブ