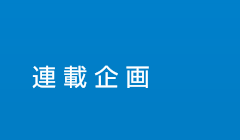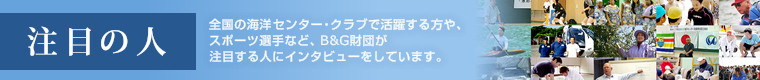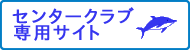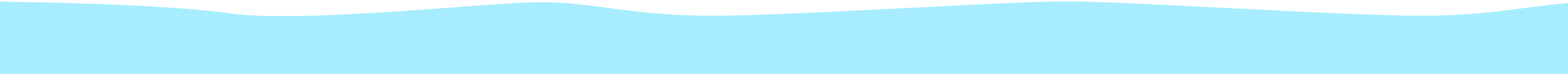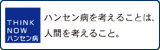No. 89
いのちのバトンは、つかんだら離さない!

2013.06.26 UP
ライフセービングの普及・指導に努める、泉田昌美さん
B&G「体験クルーズ」小笠原の寄港地活動では、メンバーの子どもたちがレスキュー用具を実際に使いながらライフセービングを体験しました。
その際、いつも講師を務めてくださったライフセーバーが、泉田昌美さんでした。普段、泉田さんは警備会社に勤めていますが、大学時代から始めたライフセービング活動に力を入れており、現在、NPO法人 日本ライフセービング協会(JLA)の競技力強化委員会委員長、ならびにライフセービングスポーツ推進副本部長を務めています。
「いのちを守る活動を通じて、あきらめない気持ちが大切であることを知りました」と語る泉田さんに、ライフセービングの魅力を語っていただきました。
プロフィール
- ● 泉田 昌美(いずみだ まさみ)さん
-
昭和44年(1969年)生まれ、東京都練馬区出身。小学2年生のときから水泳を始め、体育の先生をめざして日本体育大学に進学。在学中はライフセービングクラブに所属し、現在、日本ライフセービング協会理事長を務める小峯 力氏(B&G財団評議員)に師事。社会人になってからもボランティアで協会活動に励み、平成18年以降は、B&G「体験クルーズ」小笠原で、子どもたちにライフセービング体験プログラムを指導した。

第4話(最終話)「普通に見えて実は強い人」を育てたい
B&G財団との出合い

「第2回 水とのふれあい in 浜名湖」で、仲間が行うライフセービングのデモンストレーションを解説する泉田さん。このイベント参加をきっかけに、B&G「体験クルーズ」小笠原で講師を務めるようになっていきました
大学を出てからも、後輩の指導やJLA(日本ライフセービング協会)の活動を熱心に続けた泉田さん。こうしたなかで、B&G財団の事業を手伝う機会も生まれていきました。
「B&G財団との出合いは、2004年に開催された「第2回 水とのふれあい in 浜名湖」というイベントだったと思います。私を含めて何人かのインストラクターがJLAから派遣され、会場になった浜名湖競艇場で救急法のデモンストレーションを行いました」
その後、2006年にはB&G「体験クルーズ」小笠原(以後、小笠原クルーズ)に講師として乗船。寄港地の父島で、メンバーの子どもたちにレスキューチューブの使い方や心肺蘇生法を紹介するライフセービング体験プログラムを指導しました。
「B&G財団からライフセービング活動の講師を派遣してほしいとJLAに依頼があって、私ともう1人のインストラクターが行くことになりました。小笠原クルーズに参加するには3月の年度末に一週間の休暇を取らねばなりませんから、会社員や学校の先生はなかなか休みが取れませんが、ありがたいことに私の場合は職場に理解があって休暇が取れました」
 ふじ丸の船上でメンバーの子どもたちと写真に納まる泉田さん。小笠原クルーズには2006年から2013年まで、毎年欠かさず講師として参加し続けました
ふじ丸の船上でメンバーの子どもたちと写真に納まる泉田さん。小笠原クルーズには2006年から2013年まで、毎年欠かさず講師として参加し続けました
JLAの活動でも、ジュニア向けの教育プログラムを受け持っていた泉田さん。子ども相手の活動は楽しいそうで、手を焼く子ほど、教え甲斐を感じるそうです。
「日体大ライフセービング部では、冬場の2カ月は活動を休止して部員それぞれが普段できない活動を体験する方針を取っていました。そこで私は、冬になると子どもの頃に水泳を習った「大泉スワロー体育クラブ」に通って、幼稚園児や小中学生に水泳を教えていました。ですから、子どもたちと向き合うことには慣れていました」
とはいえ、クルーズでは500人近い子どもを対象に、2日間にわたってプログラムを行わなければなりません。JLAの活動で泉田さんが一度に接したことのある子どもの数は、多いときでも50人程度だったため、講師を受け持った責任の重さを感じたそうです。
「いくら子どもたちと接する経験を重ねていたとはいえ、こんなにたくさんの子どもたちにライフセービングを教える機会は初めてでした。言い換えれば、これほど普及に弾みのつく活動はないわけですから、気持ちが引き締まりました」
一生懸命はカッコいい!

バトンに向かってビーチを走る子どもたち。泉田さんは、ビーチフラッグス競技を通じて命の大切さ、あきらめない精神を伝えていきました

小笠原クルーズではワークショップの審査員も務めた泉田さん。船の上でも子どもたちとの交流を楽しみました
このときの寄港地活動は天気に恵まれず、寒くて海にもあまり入ることができなかったので、泉田さんは機転を利かせて陸上でできるビーチフラッグス競技に時間を割きました。
「ライフセービングの意味を知ってもらうためにも、ビーチフラッグスを教えたいと思っていました。これは、『ヨーイ・ドン』で走って、浜に立てたバトン(フラッグ)を取り合う単純な競技ですが、私たちは、このバトンを家族や友だちの命に例えます。つまり、『より速く走ってバトンをつかみ(命を助け)、つかんだバトン(命)は絶対に離さない』と、子どもたちに説明するわけです」
バトンに向かって懸命に走る子どもたち。なかには砂に足を絡めて転ぶ子も出ますが、泉田さんは、「バトンは大切な人の命なのだから、転んだくらいであきらめないで!」と声を掛けました。
「この競技を通じて、あきらめない気持ちが大切であることが分かってもらえるのではないかと思います。また、ビーチで行うので思うように走ることができなかったり転んだりすることもよくあります。
ですから、このときも、『転んだりして、ふてくされたり恥ずかしがったりしたら、とってもカッコ悪いよ』、『転んでカッコ悪いと思うのは自分だけで、一生懸命に走る姿はとてもカッコいいよ』と言って子どもたちを励ましました」
スーパーマンをめざせ!
2日間にわたって、500人あまりの子どもたちにライフセービングの心を伝えた泉田さん。これは大切な普及活動だと考え、2006年以降、休止を迎えた今年まで、毎年、小笠原クルーズに講師として参加し続けました。
「毎年、小笠原クルーズに参加させていただいた結果、JLAに子どもたちから問い合わせが来るようになり、やがて『子どもの頃に小笠原クルーズに参加したことがある』という大学生のライフセーバーと出会うようにもなりました」
インストラクターとして、さまざまな年齢層にライフセービングを教える役目を担っている泉田さん。これからも、機会さえあればB&G財団の事業に協力していきたいと語ります。
「ライフセービングを教える立場で言えば、子どもたちには、とにかく水の事故を起こさない人になってもらいたいと願うばかりです。そして、何事に対してもあきらめない気持ちを持って、精一杯生きてほしいと思います。
また、将来、ライフセーバーになる子どもたちもいると思いますが、誰に対してもやさしい人になってもらいたいですね。一見すると普通の人でも、いざとなったら強い人に変身する、スーパーマンのようなライフセーバーをめざしてくれたら、頼もしいですね」
普通に見えて実は強い人。それがまさにカッコいいライフセーバーだと語る泉田さん。将来、小笠原クルーズの思い出を語り合えるたくさんのスーパーマン、ウーマンと再会したいと期待を寄せていました。(※完了)

泉田さんの指導を受けながら、慣れない手つきでレスキューチューブを使う子どもたち。将来、たくさんのスーパーマン、ウーマンが生まれることを期待しています

レスキューボードに刻まれたSURF RESCUEの赤い文字。海の安全を守るため、今日も大勢のライフセーバーが活動に励んでいます