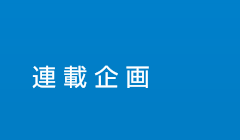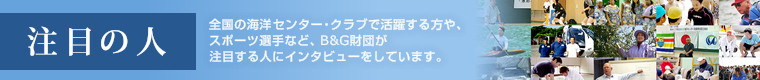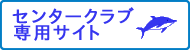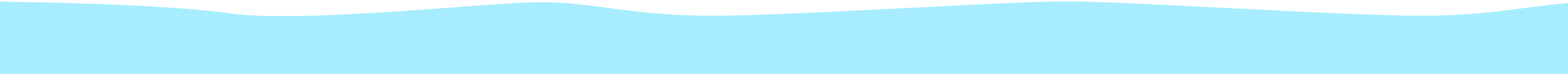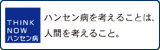No. 89
いのちのバトンは、つかんだら離さない!

2013.06.05 UP
ライフセービングの普及・指導に努める、泉田昌美さん
B&G「体験クルーズ」小笠原の寄港地活動では、メンバーの子どもたちがレスキュー用具を実際に使いながらライフセービングを体験しました。
その際、いつも講師を務めてくださったライフセーバーが、泉田昌美さんでした。普段、泉田さんは警備会社に勤めていますが、大学時代から始めたライフセービング活動に力を入れており、現在、NPO法人 日本ライフセービング協会(JLA)の競技力強化委員会委員長、ならびにライフセービングスポーツ推進副本部長を務めています。
「いのちを守る活動を通じて、あきらめない気持ちが大切であることを知りました」と語る泉田さんに、ライフセービングの魅力を語っていただきました。
プロフィール
- ● 泉田 昌美(いずみだ まさみ)さん
-
昭和44年(1969年)生まれ、東京都練馬区出身。小学2年生のときから水泳を始め、体育の先生をめざして日本体育大学に進学。在学中はライフセービングクラブに所属し、現在、日本ライフセービング協会理事長を務める小峯 力氏(B&G財団評議員)に師事。社会人になってからもボランティアで協会活動に励み、平成18年以降は、B&G「体験クルーズ」小笠原で、子どもたちにライフセービング体験プログラムを指導した。

第1話用意されていたステージ
濡らし忘れたタオル
小学校に上がって水泳の授業が始まると、きまってお腹が痛くなってしまった泉田さん。家に帰って授業に出なかったことが分かると叱られるので、いつも水着とタオルを濡らしてから下校していました。
「大人は皆、私が仮病をしているのではないかと疑っていたようでしたが、本当にお腹が痛くなってしまうのでした。それでも授業に出ないと母に叱れるので、授業に出たフリをして水着とタオルを濡らして帰っていたのですが、ある日、うっかりしてタオルを濡らし忘れてしまいました(笑)」

学校で泳ぐのが苦手なので、地元の「大泉スワロー体育クラブ」に入って水泳を覚えた泉田さん(後列右から3番目)。小学5年生になってタイムを縮めるのが楽しくなってきた頃の写真です
濡れた水着と乾いたタオルによってバレてしまった苦肉の策。当然、泉田さんは叱られてしまいましたが、後になってお母さんから、「どうしても学校がダメなら、スイミングクラブに行ってみましょう」と励まされました。
「最初はスイミングクラブも抵抗がありましたが、不思議なことにお腹は痛くなりませんでした。先生が楽しく教えてくれたので、自然についていくことができたのです。また、学校では水泳が得意な子も苦手な子も一緒になって授業を受けますが、スイミングクラブでは同じレベルの子どもたちが集まってレッスンを受けるので気分的にも楽でした」
プールに入ってもお腹をこわさなくなったことで、泉田さんはどんどん水泳が好きになっていき、中学に入るまでには大会で活躍するほどに腕を上げました。
ボートレーサーへの憧れ

B&G「体験クルーズ」小笠原でメンバーの子どもたちと出航を待つ泉田さん(奥左)。子どもの頃、泉田さんはプロレスラーかボートレーサーになりたかったそうです
小学生の頃、泉田さんが将来してみたかった職業は、幼稚園の先生や医師などいろいろありましたが、特に憧れたのはプロレスラーとボートレーサーでした。
「プロレスラーに関しては、ビューティー・ペア(人気のあった2人組の女子プロレス選手)全盛期だったので、近所の男の子たちとプロレスごっこをしながら、ごく単純に憧れました。
また、ボートレーサーについては、ある選手がテレビに出て『女子のレーサーが少ない』と言ったことがきっかけでした。機械をいじることにも興味があったし、同じ条件で男子に勝てる唯一の競技ですから、男女の差がない真剣勝負に魅力を感じました」
子どもながらにボートレーサーのことをいろいろ調べたという泉田さん。実際には、高校時代に体育の先生を志すようになって、日本体育大学に進学しました。
知らない世界との出合い
小学生時代、スイミングクラブに通って水泳が得意になった泉田さんでしたが、中学、高校時代はバスケットボールに明け暮れました。
「私が入った中学、高校には水泳部がありませんでした。スイミングクラブを続けることも考えましたが、部活がしたかったので水泳をやめて同じクラスの仲良しと一緒にバスケットボール部に入りました」
中学、高校時代はほとんど泳がなかったと語る泉田さん。屋内競技のバスケットボール部に入ったため、海やプールに行って日焼けをすると部内で目立ってしまうからでした。
その後、大学に入ったときも最初にバスケットボール部の門を叩いた泉田さん。ところが、部内の選手層の厚さに圧倒されてしまいました。
「日体大の場合、おそらく他の運動部に行っても同じだったと思いますが、まず書類による一次選考があって、それをパスしても一軍二軍ばかりか、何軍にも分かれた階層のどこかに振り分けられます。ですから、自分のレベルでゲームができる世界ではないことを、すぐに悟りました」
そこで思い出したのが小学生時代に励んだ水泳でしたが、ここでもトップレベルの選手がしのぎを削っていました。
「それなら水球もあるかなと思いましたが、体格の良い選手がパワフルに練習している姿を見て、とてもついていけないと思いました」

大学4年生のとき大会に遠征した際の泉田さん(右端)。一緒に写っている5人は同期の仲間です
中学、高校と水泳を続けていなかったギャップの大きさは計り知れませんでした。泉田さんはどうしたらいいのか迷ってしまいましたが、ある日、ライフセービングクラブの勧誘を受けて、進む道が目の前に広がりました。
「当時、ライフセービングなんて聞いたこともなく、競技があることも知りませんでした。ですから部室でビデオを見せられて、こんな世界もあるんだと思って驚きました」
泉田さんが見たビデオは、1988年に開催された「レスキュー88」という世界大会の様子でした。初めて見るライフセービング競技に興味を抱いた泉田さん。幸いにも、同クラブはサークルとして発足したばかりで部員も少なく、バスケットボール部のような書類選考もなければ一軍も二軍もありませんでした。
「私は、1年生で入る初めての女子部員だったので、とても大切にされました。いま思えば、私がライフセービングの道を歩むために、最初からステージが用意されていたようなものでした」(※続きます)