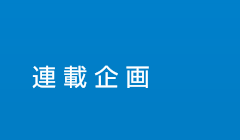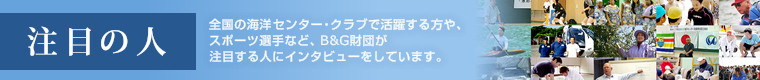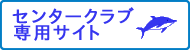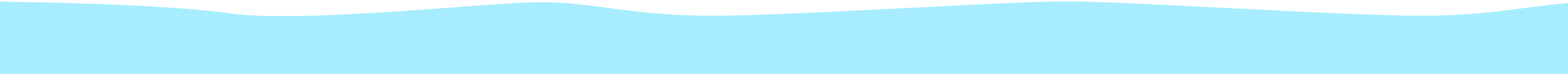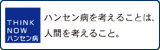No. 69
沖縄の海に学び親しんだ、我が指導者人生


沖縄海洋センター指導者として、35年にわたって海に出続けた
小橋川朝功さん
プロフィール
- 小橋川朝功(こばしかわ ちょうこう)さん:
- 昭和27年(1952年)1月生まれ、沖縄県那覇市出身。小学時代まで沖縄で育ち、中学以降は東京で生活。スポーツが大好きで、強いイメージに引かれて陸上自衛隊少年工科学校に入学し、卒業後は器械体操を極めるため日本体育大学に進学。その後、沖縄の企業にUターン就職し、翌年(昭和52年)、沖縄海洋センターに転職。平成14年、海洋センター施設が本部町に譲渡されたのを受けて新しい運営団体である健康科学財団に転籍し、今日に至る。
- 沖縄海洋センター
- 昭和51年(1976年)、設立。平成10年( 1998年 )、施設を一新し、マリンピアザオキナワとしてリニューアルオープン。平成14年( 2002年 )、沖縄県本部町に譲渡、健康科学財団が運営母体となって今日に至る。
B&G財団は、設立3年後の昭和51年(1976年)から海洋性レクリエーション指導者養成事業を開始し、その拠点となる沖縄海洋センターを同年に開設しました。
小橋川さんは、翌、昭和52年に同海洋センターの指導部門に採用され、数々のマリンスポーツ指導事業に着手。平成14年(2002年)に施設が地元の本部町に譲渡された後も、新しい運営団体に移籍して施設を守り続けています。



第2話安全に神話なし

開設して間もない沖縄海洋センターで、水泳大会のスターターを務める小橋川さん。少年工科学校で学んだ安全知識は、さまざまな事業に活かされていきました
渡河訓練での出来事
大学卒業後、沖縄に戻って電力系の企業に就職したものの、デスクワークに馴染めず沖縄海洋センターに転職した小橋川さん。第2期育成士研修の終了後、マリンスポーツの指導に励むことになりましたが、水に対する安全意識については人一倍高いものがありました。
「陸上自衛隊少年工科学校(以下、少年工科学校)に入った1年目に、私の2期上の先輩たちが水難事故に遭遇しました。それは、銃などの実戦装備を身に着けた格好で深さ10メートルの水場を泳いで渡る、渡河訓練のときに起きました。
皆、プールで事前練習を何度もしており、泳ぐことに関しては誰一人不安はありませんでしたが、いざ本番となったときにパニックが起きてしまったのです」
装備の重さは4.5キロ。これは、比較的軽い装備なのだそうです。しかし、戦闘服を身にまとい、足には戦闘靴、頭には鉄製のヘルメットを着用しているので、とても泳ぎにくい格好です。そのため、隊列を組んで泳いでいるなかの1人が少し姿勢を崩して、本能的に立とうとしてしまいました。
「戦闘服を着ていても、姿勢を水平に保っていれば呼吸を確保しながら泳ぐことができます。しかし、何かにあわてて立った姿勢になってしまうと浮力を失い、水を含んだ戦闘服や戦闘靴、装備などが重りになって、一気に体が沈んでしまいます。1人が沈んだことで、連鎖的に皆が立ってパニックが発生し、事故につながってしまいました」
先を読め

率先して現場仕事に臨んできた小橋川さん。沖縄海洋センターに配備されることになった航海訓練用のセーリングクルーザーも、自ら乗り込んで台湾から回航しました
渡河訓練の事故に衝撃を受けた小橋川さん。この世に100%安全なものはない。だから、常に危険に備えるべきだと考えるようになりました。
「先輩の方々は、後に続く私たちに貴重な教訓を残してくださいました。つまり、『たとえ泳げても、沈むこともある』ということです。言い換えれば、慣れたことをする場合でも用心に徹し、安全に気を配ることが大切だということです」
少年工科学校は、さまざまな授業や訓練を行っていましたが、この事故の影響もあって安全教育に関しては特に力が入れられました。
「少年工科学校の教育では、どんな事態になったらどう対処すべきか、事前の予測と、それに対する準備の想定、いわゆるシミュレーションの組み立てが徹底されました。たとえば、毒ガスのなかで活動する訓練では、しっかりつけたはずの防毒マスクが外れたらどうするかといった最悪のことまで想定したうえで、実際に煙幕を張った部屋のなかに入っていきます。もちろん煙幕は無毒ですけどね(笑)」
何をするにも、事前の準備が鍵を握ることを学んだという小橋川さん。特に危険が絡む活動をする際には、どんな場合にどんなことが起きるか、先を読んでそれに対する準備を行う努力が大切になると語ります。
究極の合言葉
「たとえ泳げても、沈むことがある」、「あらゆる事態を想定し、先を読む努力を怠るな」。少年工科学校で小橋川さんが学んだこの2つの言葉は、海洋センターの仕事に活かされていきました。
「海洋センターに就職する際、正直言って海は怖い場所にもなり得ると思いました。だからこそ、絶えず安全には気を配り、常に先を読んで行動していこうと自分に言い聞かせました」
小橋川さんが実践したもう1つのことは、徹底的に海に出てマリンスポーツの腕を上げることでした。就職してしばらくの間は、休みの日でも海洋センターに来て納得のいくまでカヌーやヨットに乗り続けたそうです。

台風が接近するなか、ディンギーヨットに乗って海に出たときの貴重なスナップ。この後、沖に出たところで豪快に沈をしたそうです
「海は怖い場所にもなり得る。だから、できるだけいろいろな事態に対応できるよう、カヌーやヨットの腕を上げていかねばならないと思ったからでした」
「海に出たら、必ず戻る」。それが、マリンスポーツを行う際の小橋川さんの鉄則であり、とても明快に海の安全意識を表現しています。
「子どもが海に出るときはレスキュー体制をしっかり整えますが、どんな場合にどんな救いの手が必要になるのかを知るためには、自分が1人で海に出てみるとよく分かります。
1人で海に出たら、レスキューはいません。そのため、自分で自分を守るための五感が鍛えられ、それが子どもたちを海に送る際の心構え、レスキューを組む際の知恵になっていきます。『海に出たら、必ず戻る』という言葉は、1人で海に出たときに誓う、自分自身に対する究極の合言葉です」
強風が吹いたとき、どのようにしてヨットが危険な状態になっていくのか、実際に台風が接近したときに自ら舵を握って荒海に出航。その様子を部下たちに陸から観察させたこともあるという小橋川さん。こうして、いつも全力で現場仕事に励む小橋川さんのもとで、次世代を担う若者たちが次々と育っていきました。(※続きます)