

 |
|||
 |
|||


特定非営利活動法人
気象キャスターネットワーク
特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク:
●沿革:2004年2月、10数名の気象キャスターによって設立。初年度から約100校の小学校で環境教育の出前授業を展開。2005年、ウェザーワールド「気象報道フェスティバル」開催。2010年、「海を知り、海を楽しむ」講座を実施(日本財団助成事業)、「お台場 水辺の安全教室」に出展(主催:船の科学館、B&G財団)、出前授業累計2500校を突破。現会員数は181名。
●賞:2004年、地球温暖化防止活動環境大臣賞。2006年、東京都環境賞知事賞。2007年、資源エネルギー庁長官賞。2009年、気象庁長官賞。2010年、地球環境大賞「文部科学大臣賞」。
藤森涼子さん:
日本テレビキャスター・気象予報士。気象キャスターネットワーク発起人のメンバーで、現代表。
テレビやラジオの天気予報で活躍する気象キャスターの仲間によって結成された、NPO法人 気象キャスターネットワーク。地球温暖化の問題をはじめとする環境教育を小学校の出前授業で行いながら、後輩を育てる気象予報士講座を開くなど、積極的な活動を展開。現在は、ウォーターセーフティー ニッポン(水の事故ゼロ運動推進協議会)のパートナーとして、水辺の安全を含む防災啓発事業にも力を注いでいます。
今回は、「地球環境を語るうえで海や水の存在は欠かせません。ですから、安全を心がけながら海や水辺の自然を理解することが大切です」と語る藤森涼子代表に、同法人の活動の様子をお聞きしました。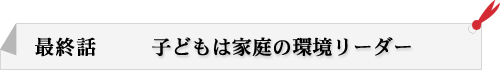
![]()

WSN(ウォーターセーフティー ニッポン)の活動に賛同する傍ら、藤森さんは海上保安庁のプール施設でライフジャケットを着て波にもまれる実験にも参加しています。この体験を通じてどのようなことを得ましたか。
海の事故に関しては、突発的に落水するようなケースが多いと思います。そのため、以前から着衣した状態で水に落ちたらどうなるのか、本当にペットボトルで体を浮かせることができるのかといった実験をしてみたいと思っていました。
実際に体験した感想を言えば、着衣したまま水に落ちたときの不自由さを痛感したほか、ライフジャケットは大きければ大きいほど浮力が得られるのかと思っていましたが、大き過ぎるとジャケットが動いて頭が沈み込んでしまう場合もあることを知りました。ペットボトルについても、頭を浮かせて呼吸できる体勢を整えるためにアゴの下にしっかり入れることが大切であることを知りました。

このようなことは、体験して初めて理解できたことなので、自分自身のためにとてもためになりました。また同時に、海は防災教育の場として子どもたちに伝えることがたくさんあると思いました。WSNやB&G財団の事業でも子どもたちを対象に着衣泳やペットボトル浮遊体験を実施していると聞いて、心強く感じました。
また、昨年の夏に出展させていただいた「お台場 水辺の安全教室」(主催:船の科学館、B&G財団)では、主催者の皆さんが子どもたちに海の安全を説きながら貝殻を拾ってネックレスを作るなど、真剣に学ぶことと楽しい遊びを上手に織り交ぜながら子どもたちをリードしている姿が勉強になりました。
当日はとても暑かったので、浜辺の温度を子どもたちに測ってもらっていましたが、状況を理解しているつもりでも高い温度に驚きました。自然のパワーを侮ってはいけませんね。感覚だけでなく、実際に温度を測るといった科学的なアプローチをもとに、熱中症対策や日焼け対策なども広めていきたいと思いました。

![]()
前回でも少し触れていただきましたが、今年は東日本が大震災に見舞われました。この未曾有の災害を通じてどのよう教訓を得ることができましたか。
気象キャスターは、より正確な情報を入手したうえで、どれだけの危険度があるのか、より分かりやすく多くの人に伝えていかねばならないと思いました。
特に、災害時に発せられる警戒情報の数々は専門用語なので一般の人には分かりにくい面もあると思います。それらの情報をしっかりかみくだいて伝えていくことが、私たち気象キャスターに求められています。
その一方、どこに暮らす人でも自分の住んでいる場所の地理的な特徴を知ってもらい、どんな危険がどんなところに潜んでいるのかを頭に入れておいてほしいと思いました。
そのためには、過去にどんな自然災害が地域で起きたのか調べてみることが大切だと思います。今回も、過去の教訓に習って裏山などに上がって助かった人が出ています。ですから一度、子どもたちと一緒に地域を歩き、お年寄りの話を聞くなどして調べてほしいと思います。
なぜ子どもと一緒が良いのかと言えば、こうした活動で得た知恵は代々受け継がれていかねばならないものだと思うからです。災害は忘れた頃にやってくるものですからね。

また、環境問題や省エネの話をすると、子どもたちはとても純粋な気持ちで受け止め、実に熱心にリサイクル活動や節電などに励みます。子どもに促されて無駄な電気を消したお父さんも多いと思いますが、防災に関しても同じことが言えると思います。
ですから、防災対策を含めた家庭の環境リーダーは大人ではなく子どもなのではないかと思います。子どもが動けば大人も変わることでしょう。
私たち気象キャスターネットワークにしても、さまざまな事業を行うなかで子どもたちに大きな期待を寄せています。出前授業やイベントを通じていろいろな気象の知識を身につけた子どもたちがたくさんいれば、テレビなどでお伝えする天気予報もより広がりをもった価値ある情報に生まれ変わっていくからです。これからも、子どもたちに背中を押されながら活動の輪をどんどん広げていきたいと思います。(※完)