

 |
|||
 |
|||


瀬戸内市B&G海洋センター指導者会
活動年数:19年、会の登録:平成18年9月6日、登録人数:38人、年間活動日数:59日、活動人数1,300人。
褒賞理由:19年にわたり青少年の健全育成に貢献。B&Gスポーツ大会、中国ブロック大会、OPヨット大会において優秀な選手を輩出。クリーンキャンペーンの継続によって海の環境保全活動に尽力。民間ボランティア団体として、平成10年度県民局長表彰、平成21年岡山県知事賞受賞。
山本博文さん:1998年度インストラクター資格取得。職業:会社員
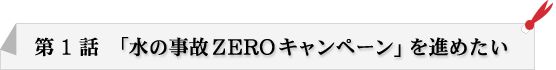
![]()

山本さんは、会社勤めをしながらボランティアで海洋クラブを指導されているそうですが、いつごろどのようなきっかけで始めたのですか。
平成2年に海洋センター艇庫が建てられましたが、その場所が幼い頃から遊んでいた浜辺だったので、オープン当初から親近感がありました。そして、これは何かの縁だったのでしょうか、いまから10年ほど前に義兄が育成士として海洋センターに勤務することになり、その際、「一緒に海洋クラブの子どもたちの世話をしてみないか」と誘われたので、B&Gのインストラクター資格を取りました。
当時から指導者会のような組織が作られていたのですか。
海洋センターができたときに、海洋クラブが同時に立ち上げられ、その際、クラブの子どもたちの世話をする、「育成会」という保護者の集まりができました。私も、そのなかでお手伝いしてきました。
そこから指導者会ができたのですか。
育成会の活動をするなかで自主的にB&Gの指導者資格を取る親もいましたが、我が子が中学を卒業して海洋クラブを出てしまうと、一緒に育成会を辞めてしまうケースがほとんどでした。
これは残念なことですから、私と義兄で相談して指導者会を別に立ち上げ(平成18年登録)、資格を持っている人の継続的な活動を呼びかけていくことにしました。我が子が海洋クラブを出た後も、引き続きボランティアで新たな子どもたちを指導してくれる人が増えていくことを期待しています。
![]()

現在は、どのような活動に力を入れていますか。
冬場に育成会と指導者会が協議をして夏場の活動予定を組んでおり、ここ2年は岡山市建部町B&G海洋センター・クラブとの交流事業を進めています。私たちは海辺のクラブですが、建部町の艇庫は川辺に建てられています。ですから、建部町に出向いて交流することで、普段はできない川下りを子どもと大人が一緒になって楽しんでいます。今後は、建部町の親子に海のカヌーを体験してもらいたいと考えています。
昨年、艇庫を「岡山県牛窓ヨットハーバー」内に移転したそうですが、このことで活動に変化が現れましたか。
ヨットハーバー内には地元高校ヨット部の艇庫もあり、学連の選手と同じ水面を使って練習するようになりました。先輩選手たちの練習を目にすることもあるので、OPヨットに乗る子どもたちにとっては、とても良い刺激になっているようです。
また、カヌーでは昨年、B&Gの県大会や中国大会で優秀な成績を収める子が出て、クラブの活動が盛り上がってきました。艇庫の移転と合わせ、この機に乗じてクラブのメンバーを増やしたいと思っています。
![]()

育成会の発足から数えて19年間の活動実績があるわけですが、ここまで続いている秘訣はどんなところにあると考えますか。
現在、指導者会の1/3ほどは私のような完全な民間ボランティアで、海洋センターから他の部署に異動した後も、引き続き手弁当で指導に来てくれる市職員が多いので助かっています。こうしたボランティアの力が活動を継続するための大きな力になっていると思います。
自主的に動くことが大切で、何でも行政に頼っていたらクラブの活動は長続きしないと思います。保護者とボランティア指導員、そして行政による三位一体の活動が必要です。
今後は、どのような面に力を入れていきたいと思いますか。
今回の設立総会でも紹介された「水の事故ZEROキャンペーン」に、とても関心があります。なぜながら、こうした活動は、これまで気にはしていたものの、なかなか取り組めなかったテーマだからです。
これからは、私たち指導者会でもライフセーバーなどの専門家をお招きして、しっかりとした対策を学ぶ機会を作っていきたいと思います。私たち指導者は、子どもたちにマリンスポーツを教えるだけでなく、自分で自分の命を守る知識と技術も伝えなければならないと思います。
今後の活躍に期待しています。インタビューありがとうございました。
次週は「周防大島町B&G海洋センター指導者会」の皆さんをご紹介します。