

 |
|||
 |
|||


昭和17年(1942年)生まれ。滝川市役所に就職後、水道事業を経てスポーツセンター(市営体育館)に勤務。平成6年に海洋センター(艇庫)が設立されて間もなく、同センターへ異動。以後、カヌーを中心に各種マリンスポーツの普及事業に力を入れ、艇庫利用では全国1、2位を競う動員数を常に記録。平成21年3月をもって退職し、現在は後輩の指導に努めている。
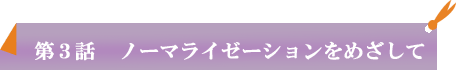
 養護学校の児童にカヌーの乗り方を教える海洋センターのスタッフ。車椅子の子も参加しています
養護学校の児童にカヌーの乗り方を教える海洋センターのスタッフ。車椅子の子も参加しています「テレビのローカル局で海洋センターのカヌー体験教室が紹介された際、その番組を見ていた養護学校の先生が関心を寄せて電話を掛けてきてくれました。障害を持つ子や慢性疾患の治療を受けている子たちにも、カヌーで川の自然を満喫させてあげたいというのです」
この養護学校では、以前に旅先で大きく体調を崩してしまった児童が出たため、長い間、修学旅行が取りやめになっていましたが、ようやく2年前から再開されたところでした。ただし、児童の健康管理を考慮して、再開後の過去2回は見学中心の旅行にとどめられていました。
しかし、電話を掛けてきた先生は、3回目になるこの年からはなにかを体験できる旅行にしたいと考えていました。そんな相談を受けた山田さんや長瀬さんは、ただちに札幌に出向いて事情を詳しく聞きました。 養護学校の体験授業では、その子の体力に応じて乗り物を選びました
養護学校の体験授業では、その子の体力に応じて乗り物を選びましたすでに山田さんたちは、平成9年に視聴覚障害者のグループを受け入れたことをきっかけに、どうしたら多くの人にカヌーを楽しんでもらえるか、いろいろな工夫を考えるようになっていました。
「細かいルールのもとで行う他のスポーツと異なり、自然に親しむことから入るマリンスポーツは、個々の事情に合わせて楽しめる要素が多いのです。障害といっても知的障害もあれば身体障害もあり、人によってさまざまな事情を抱えていますが、カヌーのようなマリンスポーツには、そうした個々のケースに対応できる力が秘められています」
児童が川に出ることを心配する先生もいましたが、山田さんたちはこのような説明をしながら勇気付け、さらに次のステップで先生方の不安を自信に変えていきました。 カヌーを2つ並べた双胴船には座椅子を設けて車椅子の子に対応。下半身が水に濡れないよう、座椅子の周囲はビニールで覆いました
カヌーを2つ並べた双胴船には座椅子を設けて車椅子の子に対応。下半身が水に濡れないよう、座椅子の周囲はビニールで覆いました「一度だけでなく、何度も下見に来てカヌーに慣れてもらっていきました。5回ぐらい来た先生もいましたが、こうすることで次第に、『水に落ちても、ライフジャケットを着ていたら大丈夫』とか、『これぐらいの川の流れなら、子どもたちでも十分に漕げる』と言って安心する先生が増えていきました」
先生の次は、子どもたちの番でした。山田さんたちはカヌーを学校の体育館に持ち込み、実際に乗り込むことができるか1人1人に試してもらい、そのうえで個々の体力に応じた活動メニューを作成していきました。
「とにかく、できそうなものからはじめるという発想で、力のある子はシングルカヌー、ある程度漕げる子はペアカヌー、水を怖がる子や自信のない子はゴムボードに乗せてあげるといった具合に活動内容を分けました」
もっとも、どのようにして車椅子の子を乗せてあげるかという課題については、かなり頭を悩ませました。試行錯誤の末、山田さんたちはカヌーを2つ並べた双胴船をつくって十分な安定性を確保し、コクピットには背中を固定する座椅子を設置。さらに下半身に水がかぶらないよう、座椅子の周囲をビニールで覆いました。 双胴カヌーに乗る養護学校の児童たち。中央両脇には車椅子の子が乗っています
双胴カヌーに乗る養護学校の児童たち。中央両脇には車椅子の子が乗っています「体力面のことを考えて、どうしても見学になってしまった子が1人いたのですが、なんとかしてあげたいと思い、乗り方を何度も練習してから、抱きかかえるようにして水上バイクに乗せてあげました。すると、たちまち笑顔になって元気を出してくれました。
『危ないから乗せるな』では、なにも生まれません。そうではなく、知恵を出せばなんらかの体験ができるはずなのです。帰り際、その子は『ほかの子と同じように川に出ることができたと』言って、とても喜んでいました」
後日、その子は「14年間生きてきて、一番楽しい時間を過ごすことができました。体が弱い私でも、皆と同じように川に出て遊ぶことができたので、とてもうれしかったです。生きる自信を持つことができました」と語ってくれました。
そんなコメントが口コミで広がり、その後、さまざまな養護学校が体験学習で海洋センターを利用するようになっていきました。山田さんは、この子と一緒に水上バイクに乗ったことを、いまでも昨日のことのように覚えているそうです。(※続きます)