

 |
|||
 |
|||


昭和17年(1942年)生まれ。滝川市役所に就職後、水道事業を経てスポーツセンター(市営体育館)に勤務。平成6年に海洋センター(艇庫)が設立されて間もなく、同センターへ異動。以後、カヌーを中心に各種マリンスポーツの普及事業に力を入れ、艇庫利用では全国1、2位を競う動員数を常に記録。平成21年3月をもって退職し、現在は後輩の指導に努めている。
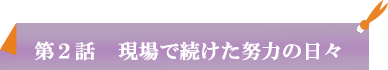
 早朝から器材の手入れに励むスタッフの皆さん。団体利用が入っている日は、いまでも朝7時半頃から仕事に取り掛かっています
早朝から器材の手入れに励むスタッフの皆さん。団体利用が入っている日は、いまでも朝7時半頃から仕事に取り掛かっています山田さんが赴任した当時のスタッフには、B&G指導者資格を持つ山田さんや長瀬さんといった市の職員に加え、シーズンごとの契約で採用される臨時職員が2〜3名配置されました。
「臨時職員の皆さんは現役を引退した年配の方々だったので、カヌー体験にやってくる子どもたちを孫のような感覚で迎え入れてくれました。そのため、アットホームな雰囲気になって、とても助かりました」
臨時職員の多くは、冬になると市営スキー場の運営管理を行っていた人たちでした。そのため、さまざまな道具の扱いに慣れており、カヌーやヨットの整備や修理も難なくこなしてくれました。
「特に決まりはありませんでしたが、毎朝7時半には全員が自主的に出勤して、艇庫や水面の整備に取りかかっていました。多いときで年間1万8千人もの利用者が詰めかけていましたから、常に準備を整えておく必要があり、そのことをスタッフの皆が自覚してくれました」 水面から帰ってきた子どもたちを桟橋で迎えるスタッフ。平成6年に海洋センターが開設されて以来、毎日のように続けられている光景です
水面から帰ってきた子どもたちを桟橋で迎えるスタッフ。平成6年に海洋センターが開設されて以来、毎日のように続けられている光景です「海洋センターのように現場が常に動く仕事においては、事務仕事のようにペーパーの指示だけで人を動かすことはできません。管理職といえども、現場のあらゆる仕事をこなす必要があり、それができなければスタッフに適正な指示を出すことができません。
一方、スタッフの側にしても現場を担う自覚がなければ、海洋センターの事業そのものが開花していきません。ですから、たとえ臨時職員ではあっても、積極的にB&Gのリーダー資格を取ってもらって、子どもたちを指導するノウハウを学んでもらいました。また、こうすることで自然に彼らの仕事に対する意識も高まっていきました」
山田さんは、毎朝5時に起きて艇庫や川の様子をチェックして家に戻り、それから朝食を済ませて、皆と同じ7時半に出勤していました。自分が率先して動くことが、なによりも大事であると考えていたからだそうです。 OPヨットの陸上シミュレーション。活動場所が川なので水面に限りがありますが、ヨットの普及にも力を入れています
OPヨットの陸上シミュレーション。活動場所が川なので水面に限りがありますが、ヨットの普及にも力を入れています「大勢の子を前にカヌーの乗り方や、水面に出たときの注意点などを説明していると、大事な話を聞き逃してしまう子が必ず出るものです。ですから、まず1から10までの細かい説明は避け、要点だけを分かりやすくまとめるように心掛けました。
そして、必ず話の所々に冗談やユーモアのある話題を織り込むようにしました。皆がドッと笑えば、うわの空だった子も話についていこうと耳を傾けるようになるからです。どのような話題で子どもたちを笑わせるかについてはスタッフそれぞれに任せたので、皆がお互いの話を参考にしながら、さまざまに工夫していきました」
ユーモアのある話で十分に説明を受けたとしても、水面に出れば必ず沈をして水に落ちてしまう子が現れます。すると、山田さんたちは、すかさずその子の顔と名前をチェックしておきました。
 活動前のレクチャーを受ける子どもたち。ユーモアたっぷりに話すため、誰もが説明に立つスタッフに注目します
活動前のレクチャーを受ける子どもたち。ユーモアたっぷりに話すため、誰もが説明に立つスタッフに注目します案の定、なぜ沈をしてしまったのか、スタッフに尋ねられて子どもたちは重い口を開きますが、スタッフの言う次の言葉で状況は一変します。
スタッフは、『○○君は、こうして沈をしてしまいましたが、ライフジャケットを着ていたおかげで無事でした。つまり、○○君は皆にライフジャケットの安全性を実証してくれたのです。身を持ってライフジャケットの大切さを示してくれた○○君に、皆さん感謝しましょう』といって拍手されるからです」
前に立った子どもたちは、拍手を受けながらB&Gのロゴが入ったキャップやタオルをプレゼントされて大喜び。泣きながら前に立った子も、最後には笑顔であいさつするそうです。
このような現場の努力によって、全国トップクラスの艇庫利用率を記録するようになっていった滝川市B&G海洋センター。開設から7年が過ぎた平成13年には、慢性疾患の治療を受けながら勉強に励む札幌の養護学校の子どもたちも、カヌー体験にチャレンジすることになりました。(※続きます)