

 |
|||
 |
|||


昭和17年(1942年)生まれ。滝川市役所に就職後、水道事業を経てスポーツセンター(市営体育館)に勤務。平成6年に海洋センター(艇庫)が設立されて間もなく、同センターへ異動。以後、カヌーを中心に各種マリンスポーツの普及事業に力を入れ、艇庫利用では全国1、2位を競う動員数を常に記録。平成21年3月をもって退職し、現在は後輩の指導に努めている。
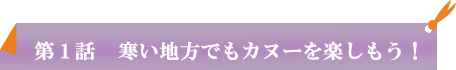
 平成6年に開設された滝川市B&G海洋センター。水のシーズンは5月初頭から9月末までと短いですが、多い年で年間1万8千人ほどの利用者で賑わいます
平成6年に開設された滝川市B&G海洋センター。水のシーズンは5月初頭から9月末までと短いですが、多い年で年間1万8千人ほどの利用者で賑わいます「最初はスポーツセンター(市営体育館)に勤務しましたが、平成6年に海洋センターが開設されて間もなく、そちらへ異動しました。興味津々、50歳の手習いでボート免許を取ったら、『救難艇が運転できてちょうどいいから、海洋センターに行ってくれ』となったのです(笑)」
海洋センター(艇庫のみ)の誘致は、日本で3番目に長い石狩川を利用して、寒い北海道でも何とかマリンスポーツを普及したいという、市民有志の強い要望によって実現したものでした。
「マリンスポーツの普及に関しては市議会も大いに賛同してくれたので、海洋センター事業を何とか軌道に乗せたいと思いました。そこで、すでに海洋センターに赴任していたセンター育成士(現:アドバンストインストラクター)の長瀬文敬職員と知恵を出し合いながら、利用者の増大に着手していきました」
当時の北海道では、寒い土地柄もあってマリンスポーツはさほど普及していませんでした。そのため、山田さんも長瀬さんも自ら足を使って営業を掛けなければ海洋センターに人は集まらないと考えました。
「いくら立派な艇庫ができても、黙っていたら利用者は増えません。まず、パンフレットを作って周辺の学校を回りましたが、それだけでは説得力に欠きました。寒くて水辺で遊ぶ習慣の少ないことから、どの先生も『体験授業はいいが、水辺の活動は危険が多い』といって敬遠してしまうのです。なかには、生徒が乗る1艇ずつに救難スタッフを乗せて欲しいと言う先生もいました」 常時、きれいに整備されている艇庫。寒さが厳しい土地柄ですが、市内を流れる石狩川を利用してマリンスポーツを楽しみたいという市民の願いによって建設されました
常時、きれいに整備されている艇庫。寒さが厳しい土地柄ですが、市内を流れる石狩川を利用してマリンスポーツを楽しみたいという市民の願いによって建設されました「どの先生も、単なるイメージでカヌーやヨットを危険に思っていただけでした。ですから、実際に自分で乗ってみて初めて、それが誤解であったことを理解してくれました。ただし、こちらにもそれなりの努力が必要でした。
その1つが、手作りでまとめた安全マニュアルでした。体験乗船に訪れる先生たちに読んでもらい、その質問に答えながらコミュニケーションを取るようにしたのです。人間相手の仕事ですから、危険や不安を払拭するためには会話を重ねることが大切だと思いました」
このような努力が実って、カヌーを体験授業などに使う学校が徐々に増えていきましたが、そんな矢先、ある中学校が体験授業でカヌーに乗りに来た際、ちょっとした事件が起きてしまいました。
生徒に同行していた校長先生がカヌーに乗って川に出て、沈をして流されてしまったのです。あわてて現場に急行するスタッフたち。さすがの山田さんも少々不安に駆られたそうですが、当の校長先生は全身ずぶ濡れになりながら笑顔を見せてくれました。
「あまりにも楽しそうに生徒たちがカヌーに乗っているで、校長先生も思わず川に出たそうです。沈をしましたが、『水に落ちてもライフジャケットを着ていれば大丈夫なんですね。それより、自分の力で水面を走る爽快感が忘れられません』という感想を述べてくださいました」 取材当日も午後から団体利用の予約が入っており、桟橋には多数のカヌーが用意されていました。ゆっくり流れる石狩川がゲレンデなので、初心者でも安心してマリンスポーツを楽しむことができます
取材当日も午後から団体利用の予約が入っており、桟橋には多数のカヌーが用意されていました。ゆっくり流れる石狩川がゲレンデなので、初心者でも安心してマリンスポーツを楽しむことができます「体験談に勝る説明はありません。このときの校長先生は、まさにカヌーの伝道師でした。これを機に、校長会に出席していた多くの校長先生がカヌーの体験授業を自分たちの学校に導入してくれるようになり、しだいに『カヌーは危険だ』というイメージが払拭されていきました」
体験授業に出た引率の先生たちも、カヌーの普及に一役買ってくれるようになっていきました。カヌーに乗って喜ぶ生徒の顔を見た先生、自ら乗って爽快さを体験した先生などが別の学校に異動するたびに、今度はその学校の生徒を連れて来るようになったのです。
「口コミの力は想像以上に大きく、しだいに海洋センターのスケジュールが学校の団体利用で埋まるようになっていきました。また、その一方で、一般の飛び込み客も積極的に受け入れていきました」
 海洋センターの入口には手作りの案内標識が立てられており、飛び込みの一般利用者も常時、歓迎しています
海洋センターの入口には手作りの案内標識が立てられており、飛び込みの一般利用者も常時、歓迎しています「本来は30分単位ぐらいで対応しますが、忙しいときは理解を求めたうえで10分でもいいから乗せてあげるようにしています。ちょっと体験してみたいという人なら、10分でも乗れば満足してくれます。
逆に、忙しいことを理由に飛び込みの利用者を断ったら、けっして良い評判は生まれません」
団体利用が先生たちの口コミで広まっていったことを思えば、飛び込みの利用者もおろそかにはできませんでした。ただし、こうして利用者の数が増えるにつれ、仕事の現場ではいろいろな工夫が求められるようになっていきました。(※続きます)