

 |
|||
 |
|||


海洋センター:兵庫県旧南淡町に、昭和53年11月設立(体育館、武道館、艇庫)。昭和59年5月、同町に無償譲渡。開設以来、地域のさまざまなスポーツ拠点として利用され、平成17年1月に周辺4町が合併して南あわじ市になってからも積極的な活動を続けている。
指導者会:海洋センター施設の高い利用率を受け、南淡町の時代から海洋センター職員経験者が中心になって施設の活動を支援。こうした経緯を踏まえ、合併後の平成18年に指導者会を発足(近畿ブロック登録第1号)。以来、市長、教育長の理解を得ながら海洋センターのあらゆる事業を支え続けている。
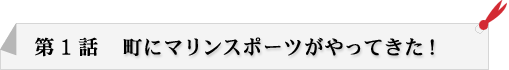
![]()


旧南淡町の時代を含めて30年以上の歴史を数える、南あわじ市南淡B&G海洋センター。施設ができた当時、町で初めてのセンター育成士(現:アドバンスト・インストラクター)として事業に励んだ職員が、現在、南あわじ市総務部に勤務しながら指導者会の会長を務めている松下良卓さんでした。
「海洋センターができる前から、旧南淡町の周辺地域ではバレーボールや卓球、剣道など、さまざまなスポーツが盛んに行われていましたが、社会人の団体は小学校の体育館を借りるなどして場所の確保に苦労していました。
ですから、海洋センターができて皆たいへん喜び、開設当初から施設はフル稼働していきました」と振り返る松下さん。
こうした状況を踏まえ、町では社会体育課を海洋センター体育館内に設置。以後、海洋センターが町の社会体育事業の拠点として機能していきました。
「スポーツが盛んな町でしたが、艇庫ができたおかげでマリンスポーツという、当時の住民にとっては目新しい種目が身近な存在になりました。ただ、艇庫に支給されたカヌーが合板キットによる自作艇だったので、組み立てて配備するのには苦労しました」
最初は松下さんと同僚の職員2人で組み立てましたが、全てを作るには時間が掛かり過ぎるため、中学校の技術科の先生を集めて組み立ての説明会を実施。各中学校にキットを配分し、技術科の先生に指導をお願いして生徒たちに組み立ててもらいました。
![]()

地元の中学生が手伝ってくれたおかげで、カヌーはただちに使用することができました。また、中学校でカヌーを作ることが話題になって雑誌も取材に訪れたため、大いに海洋センターをPRすることができました。
「雑誌に紹介されたことで、大勢のビジターがカヌーを目当てにやってくるようになりました。もちろん、地元の中学生たちも入れ替わり訪れては、カヌーに乗ったり手入れをしたりしてくれました。自分たちが作った作品ですから、愛着が湧いたのだと思います」
こうして、カヌーという新しいスポーツが徐々に定着。そのなかで、松下さんたち職員は海洋クラブづくりにも励んでいきました。
「当時、男子は野球、女子はバレーボールに高い人気がありました。ですから、どうしても子どもたちはこれらの種目に目が向きがちでした。しかし、野球やバレーボールが水に合わない子もいるわけですから、海洋クラブを立ち上げて本当に良かったと思います。
なぜなら、このようなメジャーな種目が苦手な子どもたちに声をかけて集まってもらい、そして大いにカヌーやヨットの活動に励んでもらうことができたからです。陸が苦手なら、海があるというわけでした」


海洋クラブもできて、どんどん事業が拡大していった海洋センター。いつしか松下さんのような常勤職員だけでは仕事をこなしていくことが難しくなっていきました。
![]()
「2人ほどの常勤職員だけでは施設の運営が難しいことは、あらかじめ分かっていました。そのため、海洋センターができた当初から町役場の職員を対象に年に2回ほど研修会を開き、有志を募って2級育成士(現:リーダー)の数を増やしていきました」
その数が10人以上になったときから、海洋センターでは年間計画表を作成し、忙しいと思われる日には部署の垣根を越えて資格を持つ職員に手伝ってもらうことにしていきました。
「忙しくなって急に頼むのではなく、年間計画の上で誰がどの日に手伝うのかを年度始めに決めていたので、特に大きな混乱はありませんでした。部署によってはなかなか理解してもらえないケースもありましたが、指導者同士で協力の輪を作ってやり繰りしていきました」
部署によって温度差はあったものの、業務の応援体制がしだいに定着していった海洋センター。合併によって施設の所管が南あわじ市に移ってからも、そのシステムの役割はしっかりと受け継がれていきました。(※続きます)