

 |
|||
 |
|||


B&Gなごや海洋クラブ:
昭和62年設立の、なごやジュニアヨットクラブを母体に、平成9年開設。活動拠点は、名古屋港少年少女ヨットトレーニングセンター。二村種義名誉会長ほか複数のベテランセーラーが指導にあたり、現在の会員は親子合わせて約30人。B&G OP級ヨット大会 東日本大会のホストクラブとしても知られている。
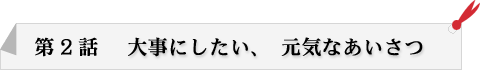
![]()


長年培ったジュニアヨットクラブの活動をベースに、平成9年から活動を開始したB&Gなごや海洋クラブ。親子が共にヨットを楽しむことをモットーに、さまざまな活動を展開し、平成18年からはB&G OP級ヨット大会 東日本大会の運営を担うようになりました。
「私たちには、昭和62年から始めたジュニアヨットクラブの活動ノウハウがあり、すでに日本ジュニアヨットクラブ連盟の全国大会で200隻を超える参加の大会運営を行った経験もありました。ですから、全国から子どもが集まるB&G OP級ヨット大会東日本大会を引き受ける自信はありました」
そう当時を振り返った、現クラブ会長の柴沼克己さん。柴沼さんは、初代会長の二村さんとともとにジュニアヨットクラブの設立に努めたメンバーの1人で、2人の息子さんをジュニアヨットクラブで育ててきました。
「それまで、B&Gの冠をつけたヨット大会は九州のみでの開催でした。そのため、東日本でも同様の大会をしようという声を受けて、大きな大会の運営経験を持つ私たちがホストクラブになりましたが、そんな私たちでもこの大会には未経験の仕事がありました。
それは、ビギナーの子どもたちを対象にしたCクラスの運営でした。上級者や中級者を対象にしたA、Bクラスは、一般的なヨットレースの運営なので問題はありませんでしたが、初心者の子どもたちを集めてどのようにレースを行ったら良いのか不安がありました」
Cクラスに関しては手探りの運営だったと語る、柴沼さんや現副会長の水谷さん。皆でいろいろ知恵を出し合った結果、陸から見守ることのできるマリーナ内の静かな水面を使用。スロープの浅瀬でスタッフに艇を支えてもらいながらスタートし、数十メートル先のブイを回って戻ってくる短いコースを設定しました。
「波の入らない港内の水面を使って、多くの子どもたちが安心してヨットを楽しむことができました。参加した子どもたちが喜んだのを見て、ヨット初体験の子も挑戦してくれましたし、『それなら私たちも』と、急遽、親御さんたちによる余興のレースも実施されました」
![]()

当初の心配をよそに、盛り上がったCクラスのレース。この成功を誰よりも喜んだのが、クラブ名誉会長の二村さんでした。
「トップレベルの選手に育っていく子を見るのもうれしいのですが、まずは水を怖がらない子を育て、それからヨットで元気に遊ぶ子を育てようという方針で、これまでクラブ活動を続けてきました。
こうした考え方は、子どもたちの健全育成や海洋性スポーツの普及をめざすB&Gの理念に共鳴します。ですから、そのような発想で設けられたCクラスの成功は、何よりうれしいものでした」
ヨットのおもしろさを知って、元気よく海に出て行く子どもたちを大勢育ててきた二村さん。しかし、そのような活動のなかで、レースに勝つことばかりを追い求める親子の姿も見てきました。
「子どもがレースに出るようになると、親のほうが熱心になり過ぎてしまうケースがあります。ジュニアクラスを卒業した後、越境入学までしてヨットのエリート高校へ我が子を進学させる親もいますし、高校時代に良いレース成績を収めてヨットの強豪大学に推薦してもらう道を追いかける親もいます。


しかし、皆がそれをしたら地元には何も残りません。できることなら地元の高校や大学に入ってもらい、子どもの頃から慣れ親しんだ海を盛り上げてほしいと思います。こうした考えもまた、地域スポーツの大切さを唱えるB&Gの理念に通じているのではないかと思います」
![]()
他県に進学した子どもたちは、なかなかクラブに遊び来ることができませんが、地元の学校に進学した子どもたちは時々、遊びに来てくれます。二村さんは、そんなひと時をとても大事にしているそうです。
「高校に行ってからヨット以外のスポーツを始めた子どもたちでも、海に愛着を持ってクラブに遊びに来てくれます。そんなつながりが続くことがうれしいですね」
遊びに来るクラブのOB、OGたちは、きまって元気よくあいさつしてくれます。二村さんが、常に子どもたちにあいさつの大切さを伝えてきたからです。
「私が子どもたちに『おはよう』と言うときは、子どもから『おはようございます』という返事をもらうまで、何度でも大きな声で言い続けます。人づきあいのなかで、あいさつはとても大事ですから、クラブのどんな子どもたちにも、あいさつを習慣づけています」
大きな声であいさつができるようになった子は、自発的に言葉を交わすようになって指導者に歩み寄ってくるそうです。人間教育の基本が、そこにあると二村さんは語っていました。(※続きます)