

 |
|||
 |
|||


愛南町御荘B&G海洋センター・クラブ:
平成5年(1993年)、上屋温水プール、および体育館を開設。その後、宝くじ助成によって艇庫を設置して海洋クラブの活動も開始。高齢者の健康対策に力を入れ、転プロをベースにした“オタッシャ教室”を展開。教室を卒業した多くの高齢者は、自主的にラケットテニスクラブやシニアシークラブ(ヨット、カヌー)などを通じてスポーツ活動を継続している。
注)高齢者を対象にした転倒・寝たきり予防のための運動プログラム。B&G財団の運動ノウハウと、身体教育医学研究所(運営委員長:武藤芳照東京大学大学院教授)を中心とする研究グループが開発した「健脚度(R)」測定(商標登録第4752854)が活用されている。
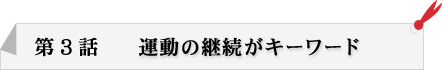
![]()

“転倒・寝たきり予防プログラム”(転プロ:冒頭の注を参照)をベースに、登山やマリンスポーツ体験などの独自メニューを加えて考案された「オタッシャ教室」。保健師の協力を得ながら大勢の参加者を集め、事業は順調な滑り出しを見せました。
「初年度は計3回の教室を実施しましたが、いずれも満員となりました。保健師が高齢者に教室を勧めてくれたことが大きかったと思います。
また、翌年度には町村合併が実施されましたが、新しい町政に移った後もオタッシャ教室は継続されました。初年度の事業が順調に推移し、口コミによって参加者が増える勢いにあったうえ、教室に参加した町の職員もいたため、役場内でも事業の良さが知られていました」
町政が変わっても、多くの賛同を得て継続されていったオタッシャ教室。今年1月に開催された第3回B&G全国サミット・海洋センター首長会議においては、現職の清水雅文町長がオタッシャ教室の導入経緯を報告するとともに、高齢者の健康増進につながる事業効果についても詳しく述べました。
![]()

前回で紹介したように、オタッシャ教室にはミニ四国巡りや町内最高峰の篠山登山、マリンスポーツ体験など、楽しく体を動かすメニューも組み込まれています。
「これは、ひとえに運動の継続を願って考えた結果です。教室に通う3ヵ月の間に、いろいろな活動を体験することで、体を動かすことの楽しさを身に付けてもらいたいと思いました」
運動の継続が最大のテーマであると語る稲住さん。初年度の教室が終わった段階で卒業者を対象にアンケート調査を行い、継続してみたい運動メニューを聞いてみると、ラケットテニスに人気が集中していました。
「卒業者同士で仲良くなって、一緒にお茶や食事を楽しむ高齢者のグループができていたので、アンケートからヒントを得て『皆でラケットテニスも楽しんでみたらどうですか』と声を掛けました。
すると、海洋センターの体育館に通ってラケットテニスを楽しむ高齢者のグループが現れるようになり、やがていろいろな人たちのグループで賑わうようになっていきました」
こうしたグループに、後から教室を卒業した人たちが加わっていき、いつしか体育館は予約で満杯の状態が続くようになりました。


「利用者が増えるのは喜ばしいのですが、予約の調整が難しくなっていったため、各グループの代表を集めて会合を開き、統一した組織を作って円滑な活動をめざしました」
海洋センターの呼びかけを受けて、愛南町ラケットテニス協会が発足。各グループの代表が役員になってミーティングが開かれるようになり、体育館利用の調整が進められていきました。
![]()
オタッシャ教室をきっかけに、グループ交流をしながらラケットテニスを楽しむようになっていった高齢者の皆さん。同じような動きがマリンスポーツにも見られるようになっていきました。
「カヌーやヨットに関心を示す高齢者は少なくありませんでした。なかには、『まさか自分の人生のなかでヨットに乗ることがあるとは思わなかった』と感激する人もいて、皆で四万十川を下るカヌーツーリングも人気を集めていきました」
このような展開のなかから、やがてヨットやカヌーを楽しむ高齢者の人たちによって「愛南シニア・シークラブ」が発足。B&Gリーダー研修を受けて自己啓発に励むメンバーも大勢いて、海洋センター・クラブでイベントがあるときには、ボランティアスタッフとして活躍しています。
オタッシャ教室をきっかけに、ラケットテニスの愛好者グループがたくさん生まれ、シニア・シークラブの活動も盛んになっていった愛南町。元気な高齢者の輪が、町内にどんどん広がっていきました。(※最終回に続きます)