

 |
|||
 |
|||


愛南町御荘B&G海洋センター・クラブ:
平成5年(1993年)、上屋温水プール、および体育館を開設。その後、宝くじ助成によって艇庫を設置して海洋クラブの活動も開始。高齢者の健康対策に力を入れ、転プロをベースにした“オタッシャ教室”を展開。教室を卒業した多くの高齢者は、自主的にラケットテニスクラブやシニアシークラブ(ヨット、カヌー)などを通じてスポーツ活動を継続している。
注)高齢者を対象にした転倒・寝たきり予防のための運動プログラム。B&G財団の運動ノウハウと、身体教育医学研究所(運営委員長:武藤芳照東京大学大学院教授)を中心とする研究グループが開発した「健脚度(R)」測定(商標登録第4752854)が活用されている。
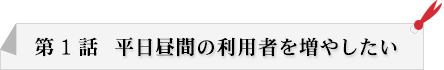
![]()

海洋センターが開設した翌年の平成6年から、海洋センター勤務になった町職員の稲住好秋さん。赴任して間もなく、他のスタッフと意見を出し合いながら、一般利用の少ない平日昼間の施設運用について考えました。
「休日の利用は多いものの、平日の昼間はかなり空いていました。この時間帯に来てもらえる人たちは誰かといえば、真っ先に思い当たるのは地域で暮らす高齢者の皆さんです」
そこで、ふと頭に浮かんだのが、海洋センターができて以来、足繁くプールに通っていた1人の女性高齢者の姿でした。
「尾崎さんというその方は膝痛に悩まされていて、毎日のように病院に通っては電気治療を受けていましたが、一向に良くなりませんでした。そのため、藁をつかむ思いで海洋センターを訪れ、膝が良くなる運動を指導してほしいと懇願されたので、私たちが独自に水中運動やフロア体操などのメニューを考えて、地道に指導していきました。

すると徐々に膝の状態が良くなっていき、最初の頃は手すりに頼って辛そうに階段を上がっていたのに、スイスイと軽快に上がるようになったので、指導していたこちらが驚いてしまいました」
こうした経験が、稲住さんたちスタッフを勇気づけました。尾崎さんのように、地域の高齢者の皆さんに足繁くプールや体育館に通ってもらえれば、平日昼間の利用率が上がるうえ、地域に住む高齢者の健康対策にもつながります。
稲住さんたちは、さっそく尾崎さんの指導で得たノウハウを基に独自の運動メニューを考案。高齢者をはじめとする地域住民を対象にした「健康体操コース」を週3回、2時間程度の内容で実施していくことになりました。
![]()

尾崎さんを指導した実績から、適度な運動が高齢者を元気にしていくことを確信した稲住さんたち海洋センターのスタッフ。町内を回って大勢の住民、特に高齢者に声をかけ、健康体操コースへの参加を勧めていきました。
「最初は4〜5人ほどの参加で始まりましたが、回を重ねるごとに口コミで話題になっていき、最終的には20人の定員を上回る数が集まるようになりました。
多くの人が自分にとってどんな運動が良いのか、なかなか判断できません。ですから、こちらからアプローチしてあげることが大切です。皆さんが楽しく参加できるよう、1人1人の体力や運動能力に応じたメニューを考えていきました」
最初は熱心に体を動かす人でも、同じメニューの繰り返しでは飽きてしまいます。そのため、稲住さんたちはスタッフごとに異なるメニューを考え、担当が代わるたびに参加者が新しいメニューを楽しめるように配慮しました。
「体を動かすことの継続性が最も大切ですから、スタッフそれぞれにオリジナルのメニューを考えて、参加者が飽きないように対応しました。
また、メニューを行う際には、なぜこの運動が良いのか、この運動が体や健康のどんな面に効果があるのか説明するようにしたので、参加者の皆さんもメニューをこなすなかで自然に健康意識が高まっていったのではないかと思います」
![]()

海洋センターが始めた、こうした積極的な事業展開に町役場も注目。やがて、足腰の弱い人でも利用できるように公民館の車を使って参加者を送迎するようになり、海洋センターから15キロも離れた地区に住む高齢者の参加も見られるようになりました。
「公民館の車を使うことから、公民館でもフロア体操を行うようになっていきました。知らないうちに、町全体で健康づくりに励むようになっていたという感じです」
町の応援を受けながら、健康体操コースは毎年、順調に推移。平日の昼間でもプールや体育館で元気な声が飛び交うようになっていきましたが、やがて更なる事業に着手するときが訪れました。
“転倒・寝たきり予防プログラム”(転プロ:冒頭の注を参照)の第1回研修会が、平成15年に長野県で開催されることになり、稲住さんたち海洋センターのスタッフも参加することになったのです。(※続きます)