

 |
|||
 |
|||

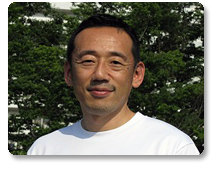

昭和37年生まれ、東京都出身。
東海大学医学部卒業後、救命救急医の道を選択。
現在、東海大学医学部付属病院高度救命救急センター次長、ならびに同大医学部専門診療学系救命救急医学准教授。医学博士。
日本ライフセービング協会理事、国際ライフセービング連盟メディカルコミッティ。
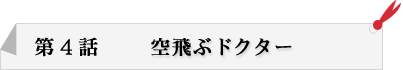
![]()


試行的事業を経て、平成13年度から正式にスタートした日本のドクターヘリ事業。翌、平成14年度からは、東海大学付属病院高度救命救急センター(以下、東海大病院)でも事業が開始され、中川先生も頻繁に空を飛ぶことになりました。
「よく、空を飛ぶのは怖くありませんかと質問されることがありますが、ヘリに乗り込んだら全面的に機長を信頼しています。また、機内では患者さんの対応に追われますから、怖いなどと思っている暇はありません」
ちなみに、遭難した人を吊り上げて救助する仕事は防災ヘリや警察のヘリなどが行います。ドクターヘリが人を吊り上げて救助することはなく、各地域に設定されている救急用ヘリポートか、状況によっては救急現場付近に着陸して急患を収容します。
そのため、機体後部に大きな開閉口があって、患者さんを寝かせたストレッチャーを搬出入できるようになっています。こうしたことから、ドクターヘリのテールブーム(後方に伸びた尾の部分)は、着陸時の姿勢で人の頭にぶつからない高さに設計されています。
また、機長や整備士が乗るコクピットは必要最小限のスペースに抑えられており、機内の大半がストレッチャーをはじめとする医療用機器の設置スペースに使われています。
それでもストレッチャーを入れたら機内にほとんど余裕はなく、限られたスペースのなかにさまざまな医療機器が並んでいます。
![]()

東海大学病院の場合、ドクターヘリの医療スタッフは3チームに分かれており、交代で356日の昼間(基本的には午前8時30分から午後6時30分)、常に待機しています。
また、ドクターヘリの機体運用については民間の航空会社に委託されており、こちらも機長、整備士、管制官の3名が一組になって、医療チームとともに356日の昼間、常に待機しています。
ちなみに、管制官は医療チームと同じ部屋にいて、常にオンラインで地域の気象状況を把握しています。
そして、出動要請を受けると現場へ向かうフライトや着陸に支障がないか天候を確認。問題がなければゴーサインを出し、ただちに医療チームが病院の敷地内にあるヘリポートに出向いて機長、整備士と合流します。

「医療チームは、医師や看護士などによって構成されており、必要に応じて5名ぐらいがヘリに乗る場合もあります。また、県下には200カ所ぐらいの救急用ヘリポートが確保されおり、現場の天候次第では管制官が着陸場所を変更することもあります」
![]()
ドクターヘリの運用効果は地域によって異なります。受け持つエリアが広すぎたり、対象人口があまりにも少ない地域だったりすると費用対効果が薄れてしまいます。
一方、人口の多い大都会ではヘリポートの用地確保が難しい反面、病院がたくさんあって救急車でも比較的短時間で到着できるエリアが少なくありません。そのため、都会にドクターヘリを配備する例は、郊外に比べてそう多くありません。
「1機のヘリコプターが受け持つ理想のエリアは、救急ヘリポートの確保が比較的しやすい、都市郊外の半径50キロぐらいだと言われています。ドイツでは、半径50キロで全土を網羅しており、日本でも北海道では4つの円でほぼ全域を網羅しています」
現在、日本では20カ所でドクターヘリが運用されており、関東では東京都を除くほぼ全域がカバーされているそうですが、中川先生は、「最低でも一県に1機、計50機は欲しいですね」と語ります。
実際、東海大病院が受け持つ神奈川県西部エリアだけでも、対象人口200万人に対して年間300〜400件もの出動要請を受けているいのが現状で、場合によっては山梨県まで足を伸ばして救命救急に当たっています。
「2年後には山梨県にもヘリが導入されることになっているので、そうなれば少し数が減るとは思いますが、それにしても相当な出動回数をこなしています」
試行的事業だったときよりも、さらに多くの出動要請をこなしている東海大病院のドクターヘリ。資料によれば、本格的な運用が始まった平成14年度から平成18年度までの4年間で、実に1800名もの急患を搬送しています。
「法律が整備されたことをうけて、ドクターヘリ自体の数はしだいに増えています。問題は、この事業をしっかり運用していく人材の養成です」
いくらハード面の環境が整っても、それを使いこなすソフト面の充実が必要です。「これからは、自分の経験を活かして若手の救急医を数多く育てていきたい」と、中川先生は語っていました。(※続きます)