

 |
|||
 |
|||

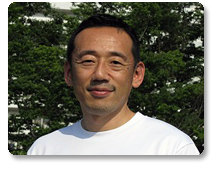

昭和37年生まれ、東京都出身。
東海大学医学部卒業後、救命救急医の道を選択。
現在、東海大学医学部付属病院高度救命救急センター次長、ならびに同大医学部専門診療学系救命救急医学准教授。医学博士。
日本ライフセービング協会理事、国際ライフセービング連盟メディカルコミッティ。
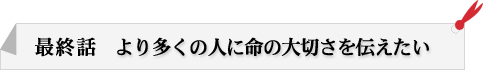
![]()


法律が整備されたことをうけてドクターヘリの数がしだいに増えている昨今、この事業をしっかり運用していく人材の育成も必要で、「これからは自分の経験を活かして若手の救急医を数多く育てていきたい」と中川先生は語ります。
「幸いなことに、私は大学にも籍があって学生や研修医に救命救急医学を教えています。そのため、教育の立場からもより多くの後進を育てていきたいと思っています。
また、どんな専門医になっても救命救急の素養は必要です。救命救急医をめざす、めざさないに関わらず、あらゆる医師の卵たちにいざというとき医師として何をすべきなのかを広く伝えていきたいと思います。
たとえば、白内障や緑内障の手術で入院した患者さんでも、心筋梗塞などを併発する場合があります。その際、『私は眼科医なので対処できません』などと言うことはできません。
ですから、たとえ眼科をめざす医師の卵であっても、いざというときに必要な救命救急のありかたをしっかり学んでおいて欲しいのです」
救命救急センターで働く傍ら、大学医学部で准教授の職に就いている中川先生。日々、学生や研修医と向き合いながら、教育者としても忙しい日々を送っています。
![]()

いかなる専門医でも、救命救急の素養はしっかりと身に付けて欲しいと語る中川先生。その言葉の奥には、ご自身がライフセーバーであることも大きく影響しています。
「私がライフセービングと出合ったのは、大学を出て救命救急センターに入局した頃でした。大学陸上部の仲間のなかでライフセーバーの資格を取った部員がいたので、仕事柄、話を聞いて関心が高まり、自分も研修を受けてみたいと思いました。
研修は1週間で、医学の基本や海の生物に関する知識を学ぶほか、水泳の実技や蘇生法の習得などがあり、最終日に総合的な試験がありました」
そのとき試験官を務めた協会のスタッフが、現:日本ライフセービング協会の小峯 力理事長(B&G財団評議員)でした。
「試験後の懇談会で私が救命救急医であることが紹介されると、小峯さんが声を掛けてくださり、『いつか一緒に仕事をしたいですね』などと言って、すっかり意気投合しました。
その後、しばらく年賀状のやり取りが続きましたが、協会が新体制になって小峯さんが理事長に就任されたときに、あらためて仕事を手伝って欲しい旨の話をいただきました」
小峰理事長の依頼を快諾した中川先生。協会内ではメディカルディレクターの役割を担うことになり、心肺蘇生法のテキストづくりやガイドラインの作成、各種講習会の内容の検討や溺水事故の統計・分析など、さまざまな仕事に着手していきました。
![]()

日々の仕事をこなしながら、ライフセービングの仕事に力を入れている中川先生。今年からはじまった“水の事故ゼロ運動”にも大きな関心を示しています。
「医学的な立場で言えば、溺水事故が起きた際に何からすべきなのか、さほど研究が進んでいません。ですから、これまで行われてきた通り一遍の方法ではなく、溺水に特化した蘇生方法もあるのではないかと関心を寄せています。
しかし、いずれにしても溺水に至らないことが一番大切なのであり、人が溺水しない環境作りから始めることが大事です。そのためには、さまざまな安全啓蒙活動が求められます。事故に遭った人を助けることも大切ですが、事故を起こさない努力も大切です。
小峯理事長がよく使う言葉をお借りするなら、『私たちライフセーバーが不要になる世界をめざしたい』のです」
そのときが来るまで、ライフセービング活動はおろそかにできません。中川先生は、いまでも休日になると地元の浜に出て、若手のライフセーバーたちを見守っています。
「もう現場は若手に委ねており、私といえば差し入れを持っていくことが何よりの楽しみになっています(笑)」
浜に出てライフセービング活動に関わると、気持ちがリフレッシュするという中川先生。特に、夏の終わりに皆で浜に集まって、夕焼けを浴びながら「今年も終わったね」と言いながら飲むビールは最高で、このときばかりは時間に追わる日々の仕事を忘れるそうです。(※完了)