

 |
|||
 |
|||

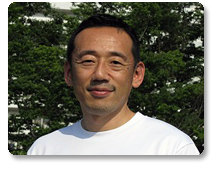

昭和37年生まれ、東京都出身。
東海大学医学部卒業後、救命救急医の道を選択。
現在、東海大学医学部付属病院高度救命救急センター次長、ならびに同大医学部専門診療学系救命救急医学准教授。医学博士。
日本ライフセービング協会理事、国際ライフセービング連盟メディカルコミッティ。
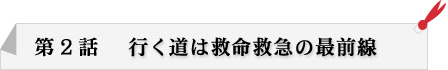
![]()

大学に入った当初は、おぼろげながら父親と同じ循環器系の医師になることを考えていたという中川先生。ところが、5年生のときに交通事故の現場に遭遇し、さらに臨床実習によって救命救急医療を実際に体験したことで、本当に自分がめざしたい道が見てきました。
「脳の手術を専門の外科医に委ねるように、さまざまな分野で医療のスペシャリストは必要です。しかし、どんな容態の患者さんでも受け入れて命を救うためにあらゆる手を尽くす、ジェネラリストというべき間口の広い救命救急医の存在も大事です」
問題は間口の広さと質で、間口が広くても経験や知識の奥行きが浅ければ役に立ちません。いくら間口を広げても、その奥行きは自分の努力で深めていかねばなりません。
「一刻を争う患者さんの場合、傷や病気の専門的な処置はさておき、とにかく命を救うための初期治療を施します。たとえば血圧が極端に下がって、放っておいたら死んでしまうような場合は、傷や病気の診断を進めつつも、血圧を上げる特殊な治療を行って目の前の危機を乗り越えます」
ジェネラリストが危うい命を持ち上げなければ、脳や心臓などのスペシャリストに後を託すことができません。血圧を上げるような特殊な治療ができるかどうかは、ジェネラリストとしての奥行きの深さにかかっており、まさに経験と技能が問われます。ですから、救命救急医とは間口の広いジェネラリストではあるものの、あらゆる命を救うスペシャリストでもあるわけです。
![]()


大学を卒業して晴れて医師になった中川先生は、研修医を経て高度救命救急センターに入局し、救命救急医の道を歩むことになりました。
「私が医師になった昭和62年当時といえば、外科や内科などを選ぶのが一般的で、救命救急に手を上げる仲間は誰もいませんでした。ですから、私が『救命救急に行く』と言ったら周囲がとても驚きました」
人が何を言おうが我が道を進んだ中川先生。勤務が始まると、救命救急センターで待機しているだけでは物足らず、現場に急行する消防の当直も経験したいと申し出ました。
「いまでこそ状況は変わりましたが、当時の消防は法的に患者さんを搬送することしかできず、救命救急センターは運ばれてくる患者さんを待つだけでした。つまり、救急隊と医師との連携が十分に構築されていなかったのです」
そのような時代であったため、中川先生の申し出はまた周囲を驚かすことになりましたが、地元の医師会の協力を得て、週に一度は地域の消防署に当直できるようになりました。
「それまで医師が消防署に当直する例はほとんどなかったので、消防署も驚いたようでしたが、泊りがけで消防に詰めることで救急隊員との連帯意識が次第に高まっていきました」
![]()

当直することで、救急隊員とは同じ釜の飯を食べる仲間になっていったと語る中川先生。仕事の面でも救急隊員の立場で現場を考えることができるようになっていきました。
「相手を知っていれば無駄な動きを省けます。従来、救命救急センターに救急車から連絡が入ると、状況を詳細に知ろうとして根掘り葉掘り聞いていましたが、お互いに顔が見えるようになってからは必要最小限のやり取りでコミュニケーションが取れるようになり、より迅速に行動できるようになりました」
救急隊の働く環境を知ることができたのは、大きな成果だったと語る中川先生。平成3年には救急救命士法が制定され、さらに病院と消防の連携が深まっていきました。
「この法律によって、救急救命士の資格を持つ救急隊員であれば、指導医の指示を受けながら一定の医療行為(救急救命処置)ができるようになりました。その技能は医師が教えるしかありませんから、救急隊員が病院に来て実習するようになったのです」
また、時を同じにして国の外郭団体がドクターヘリの有効性に関する研究に着手。数年かけてさまざまな検討を重ねた結果、平成11年から旧厚生省が試行的事業を行うことになり、東海大学付属病院もその一役を担うことになりました。(※続きます)
写真提供:東海大学付属病院高度救命救急センター