

 |
|||
 |
|||


府中市B&G海洋センター:昭和52年(1977年)、第1期海洋センターとして市内を流れる芦田川沿いに艇庫と屋内温水プールを開設。
おもに水泳教室事業に力を注ぎ、FSC(府中スイミングクラブ)の名で数々の大会に出場。これまでに、JOCジュニアオリンピック10回出場、B&G財団の「ウォーターマラソン」に5年連続参加。
水泳のほかにも、指導者会が中心になってカヌーの普及活動にも励んでおり、平成17年度にはプールの一部バリアフリー化を含む大規模改修を実施した。
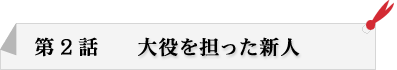
![]()

小学1年生のときから海洋センターに通って水泳に親しみ、高校時代には指導員のアルバイトで子どもたちの世話をした大越さん。その後は大阪の専門学校に進学しましたが、卒業すると再び郷里の海洋センターに戻ってきました。
「専門学校を出た後は、スポーツとは関係のない一般的な会社に就職するつもりでいましたが、いざ卒業を迎えると、どうしても大好きな水泳で生計を立てていきたいと思うようになりました」
そこで、真っ先に思い浮かんだのが、子どもの頃から慣れ親しんだ郷里の海洋センターでした。大越さんは、迷うことなく海洋センターに出向き、あいさつもそこそに「掃除でもなんでもしますから、とにかくここで働かせてください」と懇願しました。
「本当に偶然だったのですが、このときたまたま職員を1人募集していました。ですから、海洋センターにとってもアルバイトの経験がある大越君が来てくれて、とても助かりました。彼の誕生日は7月20日なので、海の日の申し子が来てくれたと感じましたね(笑)」
そう当時を振り返る石山所長。就職が決まった大越さんは、さっそく沖縄のB&G指導者養成研修に派遣されました。
![]()
府中市B&G海洋センターにとって、指導者養成研修への職員派遣は実に10年ぶりのことでした。大越さんが就職した平成8年といえば、B&G財団と話し合いを重ねて修繕助成を実現した年でした。そのため、海洋センターとしては将来に向けた事業への期待を新人の大越さんに託したかったのです。
「修繕助成の話を詰めるなかで、私たちは常にB&G財団と意識を共有し連携を図っていかねばならないと考えました。そのなかで決めた10年ぶりの沖縄派遣でしたから、なんとか市にお願いして派遣の予算を組んでもらいました」と石山所長。
一方、新人ながら大役を担った大越さんには戸惑いもありました。

「10年ぶりのことなので研修の様子を教えてくれる先輩職員がいなくて、とても不安を感じました。特にヨットは未経験だったので、どうなるものかと思いました。
しかし、実際に研修を終えてみると、マリンスポーツの実習もさることながら、大勢の研修生仲間と交流できたことが貴重な財産になりました。それぞれが地元に戻った後も、絶えず情報を交換しながらお互いの仕事を支えあうことができたからです」
指導者養成研修は、マリンスポーツのスキルを磨く場というよりも人の輪の大切さを知るところであると語る大越さん。40日間の研修を終えて地元に戻った大越さんは、さっそく海洋センターで忙しい日々を送るようになりました。
![]()


B&Gの指導者資格を取得した大越さんは、地元に戻ると屋内温水プールという利点を活かして、幼児から高齢者までを対象に、さまざまな年間型の水泳教室を展開していきました。
前回紹介したように、水泳教室の子どもたちはFSC(府中スイミングクラブ)の名で数々の大会に出場しています。冬場も利用できるプールのため、年間の活動を通じてクラブ仲間の意識が芽生えていくそうです。
「沖縄の指導者養成研修で学んだことを基本にしながら、子どもたちにはあいさつの大切さ、礼儀正しく振舞うことの大切さを教えており、年上の子どもたちには下の子の面倒を怠らないように指導しています」
技術的な指導はもとより、あいさつの大切さを教えることが先決だと語る大越さん。あいさつができるようなると、指導者の説明にしっかり耳を向けるようになっていくそうです。
「あいさつができるようになると、人の話を聞く態度もしっかりしてきます。そうなれば、技術面の飲み込みも早くなり、練習するほどにどんどん上達していきます」
あいさつの大切さを掲げ、年上の子が年下の子の面倒を見ながら力をつけていった水泳教室の子どもたち。FSCはJOCジュニアオリンピックカップに10回出場するなど、さまざまな大会で実力を発揮するようになっていきました。(※続きます)