

 |
|||
 |
|||


香取市小見川B&G海洋センター・クラブ:旧小見川町時代に、町内を流れる黒部川流域に建設され、1983年(昭和58年)に開設。近隣の水辺にはスポーツコミュニティセンター(市営体育館)や少年自然の家(県営研修施設)も建てられ、周囲一帯で盛んにカヌーやボート、自然体験活動などが行われている。
また、同海洋クラブは小学生から中高年者まで幅広い年齢層で構成されており、現在は約100人の会員が在籍。一般的なレクリエーション活動に加えて選手の育成にも力を入れており、今年度はクラブから5人の日本代表選手を輩出している。
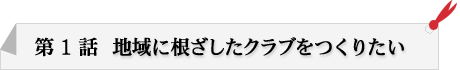

![]()
1983年(昭和58年)、香取市小見川B&G海洋センターの開設が決まると、民間企業で働きながら旧小見川町の体育協会役員を務めていた真田行康さんが、初代センター所長に抜擢されました。
「スポーツが好きで体育指導員をしていた関係で町役場から声を掛けていただき、役場の職員としてセンター所長に就任しました。それまでサーフィンは好きで楽しんでいましたが、カヌーやヨットなどは沖縄の指導者養成研修で初めて乗ることになり、とても新鮮な感動を覚えました。
また、指導者養成研修でB&Gプランを学び、地域に根ざしたスポーツ活動の大切さを知ったことが、海洋センター事業を進めるうえでの大きな原動力になりました」
沖縄から戻った真田さんは、海洋センター事業の特色を打ち出したいと考え、地域ぐるみで参加する海洋クラブづくりに着手しました。
「クラブをつくろうと努力しましたが、最初の頃はいくら声をかけてもなかなか人が集まりませんでした。それまで、住民の大多数がカヌーなんて見たこともなかったのですから無理もありません。子どもたちにしても、スポーツが好きな子はすでに野球やミニバスケなど他の競技をしていて、これまで接したことのないカヌーには興味を示しませんでした」
![]()



子どもたちがカヌーを知らなければ、いくらクラブづくりを呼びかけても成果は上がりません。そこで真田さんは、現在、多くの海洋センターが実施している出前カヌーを試みました。
「町内に5ヵ所あったすべての小学校と相談し、プールにカヌーを持ち込んで子どもたちに体験してもらうことを考えました。学校側に話を持ちかけた際には、あまり快い返事をいただけませんでしたが、『運営責任や準備の手間などはすべてこちらが負いますので、ぜひお願いします』と説得しました」
小学校での出前カヌーを続けて3年、ようやく興味を持った子どもたちが集まるようになってクラブ組織の骨格ができました。
「何事にしても、体験の場を与えれば子どもたちはそれなりに関心を寄せるものです。カヌーにしても、説明を受けた多くの子どもたちが珍しいあまりに興味を示し、乗り始めると今度は楽しくなってクラブに足を運ぶようになっていきました」
しかし、海洋センターができた当初はカヌーを川に下ろす設備が整っていませんでした。そのため、艇庫から出したカヌーを人力で川原まで運ばなければならず、出艇までに1時間も掛かってしまいました。
「カヌーの出し入れは重労働だったので、ボランティアで手伝ってくれる人を募集しました。最初は口コミで集めるしかありませんでしたが、そんな私たちの姿見て、いつしか海洋クラブで活動する高校生や、高校を出たOB、OGなどが率先して子どもたちの面倒を見てくれるようになっていきました」
こうして一歩ずつ前に進んでいった、香取市小見川B&G海洋センター・クラブ。その活動の輪は、やがて町が打ち出したアクアポリス構想によって、さらに拡大していきました。

「アクアポリス構想とは、水郷という土地を活かして地域を活性化していこうという取り組みで、海洋センター・クラブが行う水辺のスポーツ活動もアクアポリス構想の後押しを受けました」
アクアポリス構想に則って、さまざまなマリンスポーツの大会誘致に力を入れていきたいと考えた真田さん。すると、そんな願いが伝わったのか、とても頼もしいパートーナーが現れました。町の社会体育事業を担っていた志村一実さんが、海洋センターに配属されたのです。志村さんは、さっそく所長の真田さんとともに新たな事業を展開していきました。(※続きます)