

 |
|||
 |
|||


WSNZ(ウォーターセーフティー ニュージーランド):国内の溺死事故をなくす目的に、行政・海事団体、企業など官民36団体によって、1949年に設立された共同事業体。運営資金はカジノやトトの売上げ、企業協賛金などから出資されており、警察や病院、サーフライフガードなどと連携しながら、溺死事故を防ぐ教育、啓蒙、調査研究活動を続けている。
アラン・ミューラー専務理事:1988年からWSNZに従事。構成諸団体の意見をまとめながら政府、教育機関等への働きかけに努めている。11歳でジュニア・サーフライフガードの活動を始め、サーファーとしても活躍。ラグビーにも精通しており、福岡市のラグビーチーム“SANIX”の指導も行っている。
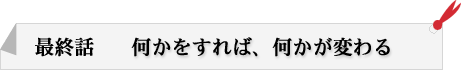
![]()
溺死事故のデータベース化を始めて30年ほどが過ぎたいま、65歳以上のリタイア世代の動向に大きな変化が現れてきているそうですが、具体的にそれはどのような事なのででしょうか。


簡単に言えば、65歳以上の人たちの事故が増えてきているということです。この年齢層は、昔なら静かに余生を送っていた世代ですが、現在は65歳以上でも元気で体力に自信のある人が少なくありません。
そのため、カヤックやラフティングなどチャレンジングな遊びに興味を示す人が多く、準備不足や勉強不足、体力の過信といったことで事故を起こしてしまうケースが増えてきました。
ですから、どのようにこの世代と向き合っていったら良いのかということが、いまWSNZに問われていますが、こうした課題が分かったのもデータベースのおかげです。
データベースは、ほかにどのような面で効果を上げていますか。
基本的にWSNZは水に関係する団体で構成されていますが、たとえば0歳から5歳までの溺死事故が多いことが把握されてからは、母子や新生児に関係する団体との連携も取るようになりました。水に関係する団体以外の意見や情報を集めることの必要性が分かっただけでも大きな成果です。
その一方、私が話を聞いているところによると、日本ではニュージーランドで最も事故率の低い5歳から15歳までの年齢層で多くの悲劇が生まれているようです。ですから、WSNが最初に取り組むべき最大の課題は、この年齢層への安全教育、啓蒙活動なのではないかと思います。そのために、私たちWSNZは協力を惜しみません。
![]()
データベースの構築をはじめとするWSNZの事業は、各種団体、企業の助成を受けているそうですが、その仕組みを簡単に説明してください。
WSNZの運営資金は、おもに公営カジノやトトの売り上げの一部によって賄われています。こうした公的な資金が、年度始めにスポーツ機関、芸術機関、学術機関の3つの分野に分配された後、それぞれの傘下に入る12の大きな団体に分けられていきます。そのなかで、WSNZはスポーツ機関傘下のアウトドアセーフティ協会を経て資金を得ています。
ただし、このような資金は自動的に傘下の各団体に流れていくわけではありません。それぞれの団体が事業の必要性を訴えて資金確保に動きます。その交渉はたいへんで、毎年、思った通りの資金が得られる保障はありません。
また、10年ほど前からは、カジノやトトに頼りすぎているのではないかという見解が出て、現在では一般企業の協賛も含め、政府系保険機関や銀行協会などの支援も受けています。
![]()

交渉で得た運営資金は、WSNZの事業のなかでどのように配分されていくのですか。
インタビューの最初に述べたように、我が国ではサーフライフガードとコーストガードがレスキューに特化した活動を展開しており、WSNZは水辺の安全教育、安全啓蒙活動、そしてそのための調査研究活動を事業の柱にしています。
ですから予算を組む優先順位としては、
●泳げる子を育てる教育
●プレジャーボートの事故を防ぐための安全教育、啓蒙活動
●浜や家庭など各現場に即した安全確保のための環境教育
●スポーツ事故対策
という教育、啓蒙活動に関する4つの柱が掲げられています。
そのような活動の具体的な成果として、一番先にどのようなことが挙げられますか。
データベース化が始まって間もなくの1985年には、全国で年間215人の溺死者を数えましたが、それが2008年には96人に大幅に減少しています。また、1980年代の年間平均溺死者数が180人だったのに対し、1990年代には140人に下がり、2000年代には110人になりました。これは、明らかに安全教育、啓蒙活動の成果だったと評価されています。
教育や啓蒙活動の事業が柱になっているということですが、学校の授業などにも関わっているのですか。
小中学校の保健体育のカリキュラムにウォーターセーフティの課目が取り入れてられていて、どの学校でも授業のなかで水辺の安全教育を行っています。また、自治体などの助成金を使ってプール施設を改善した学校については、新しい施設をどのように活用していくべきかをアドバイスしています。放っておいたら、プールがきれいになっただけで安心してしまう学校もあるわけです。

日本では、これからWSNの事業が始まろうとしています。活動を展開するなかで、特に注意すべき点があったら教えてください。
まずは、これまで述べてきたように確固たるデータベースを作り上げていくことが大切です。また、安全教育、啓蒙活動を行う事業計画や、その際に使用するプログラムなどについて、それが本当に良かったものなのかどうか常に過去を振り返って評価するシステムを取り入れるべきだと思います。
また、WSNZ にしてもWSNにしても、さまざまな加盟団体によって活動が支えられているわけですから、どのようにして各団体と情報を共有していくかを十分に考える必要があります。
このような安全教育、啓蒙活動は、何もしなければ何も起きません。逆に、何かをすれば何かが必ず変わります。ですから、そのことを信じて、ぜひともこの事業を推し進めていただきたいと思います。(※完)