

 |
|||
 |
|||


WSNZ(ウォーターセーフティー ニュージーランド):国内の溺死事故をなくす目的に、行政・海事団体、企業など官民36団体によって、1949年に設立された共同事業体。運営資金はカジノやトトの売上げ、企業協賛金などから出資されており、警察や病院、サーフライフガードなどと連携しながら、溺死事故を防ぐ教育、啓蒙、調査研究活動を続けている。
アラン・ミューラー専務理事:1988年からWSNZに従事。構成諸団体の意見をまとめながら政府、教育機関等への働きかけに努めている。11歳でジュニア・サーフライフガードの活動を始め、サーファーとしても活躍。ラグビーにも精通しており、福岡市のラグビーチーム“SANIX”の指導も行っている。
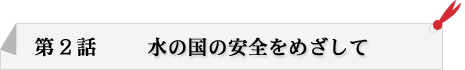

![]()
ミューラーさんは、11歳で地元のジュニア・サーフライフガードクラブに入り、ラグビーにも夢中になったそうですが、スポーツやアウトドア関連の仕事を探して現在の職に就いたのですか。
若い頃からラグビーに情熱を燃やしていましたが、いくらスポーツが好きでも、それだけでは食べていけませんから、最初は一般的な会社に勤めました。その後、機会があって現在の仕事に就きました。
WSNZという団体は、ニュージーランドという国と、そこに暮す人たちにとても深い関わりのある仕事をしています。ですから、より良い方向をめざして仕事をこなしてきたら、あっという間に22年の月日が過ぎてしまいました。
その“深い関わり”の意味を含め、WSNZが設立された経緯をお聞かせください。
最初に、ニュージーランドという国の地理的な条件や歴史的な背景を説明する必要があるでしょう。ご承知のように我が国は長細い小さな島国ですが、海岸線の総延長距離だけを見ればアメリカ合衆国のそれに肩を並べます。
また、湾岸地域に町が多く、こうした町とアクセスしやすいように、内陸の町でもその多くは川沿いに位置しています。つまり、水に接していない町はほとんどなく、多くの人が水に関わる国民性を備えています。このように、地理的な話をしただけでも、いかに海や川がニュージーランド人の生活に関わっているかが理解できると思います。
![]()
地理的な条件はよく分かりましたが、歴史的な背景としてはどのようなことが挙げられますか。
ニュージーランドは移民の国です。19世紀の終わりから20世紀初頭にかけて多くの人がここの国にやってきましたが、その目的の大半は金の発掘でした。大勢の人が川に入って砂金を掘ったのです。
当時は、十分に道路や橋が整備されていませんから、金のある場所をめざして無理に馬車で川を渡ったり、体ひとつで泳いで渡ろうとしたりして、溺死事故が頻繁に起きました。しかも国の至るところで川底を掘りあさったため、各地で洪水も起きやすくなりました。
資料を見ると、1900年には1000人ほどの人が水の事故で亡くなっています。国の人口が100万人足らずの時代ですから、これは深刻な数字だと言えるでしょう。当時、溺死は“ニュージーランドの死”とも呼ばれていたほどです。
![]()

道路や橋は時代とともに整備されていったと思いますが、どのような経緯があって1949年にWSNZが設立されたのですか。
1949年頃にはインフラ整備も進んで洪水も減少していましたが、ニュージーランドが島国で長い海岸線を持ち、川沿いに町があることに昔も今も変わりはありません。1949年当時といえば世界大戦も終わって社会が落ち着きを取り戻しつつありましたから、それに伴って今度は水で遊ぶなかでの事故や家庭内での浴槽の事故などが、以前に比べて増える傾向が見え始めていました。
そこで、サーフライフガードやコーストガード(沿岸警備隊)といった水に関わる諸団体が危機感を覚えて一堂に介し、WSNZが組織されました。30以上もの団体が共通の意識を持って1つにまとまることができたのはセンセーショナルなことでした。

おもに、どのような活動に力を入れていったのですか。
サーフライフガードとコーストガードがレスキューに特化した活動を展開しますが、WSNZは水辺の安全教育、安全啓発活動、そしてそのための調査研究活動を事業の柱にしています。3つの団体がはっきりと仕事のすみ分けをしています。
ミューラーさんは、どのような仕事を担当してきましたか。
加盟団体との意見調整をはじめ、事業の財源を確保するための役所との交渉や、ライフジャケットなど安全備品の基準づくりなどに日々追われてきましたが、1979年から始められた事故例のデータベース化にもスタッフ総出で取り組みました。
水の事故が起きた場合、それまではサーフライフガードや警察、病院といった事故に関わった当該団体が個々に記録を取っていましたが、他の団体、組織と情報を共有できるような一括的な管理がされていませんでした。
そこで、私たちWSNZが共通フォーマットを作って一括管理しながら、各加盟団との情報の共有化を進めたのです。
また、寄せられた情報を基に事故事例のデータベース化に力を入れたところ、さまざまな年齢層における水辺の活動事情を把握することができるようになっていきました。
※続きます。