

 |
|||
 |
|||


八百津町B&G海洋センター指導者会
活動年数:26年、会の登録:平成18年4月1日、登録人数:73人、年間活動日数:78日、活動人数337人。
褒賞理由:26年にわたり海洋性レクリエーションの普及に努め、青少年の健全育成に貢献。多くの指導員が海洋センター運営の補助に携わり、安全管理の充実を図っているほか、岐阜県連絡協議会での研修会やイベントに指導員を派遣し、県連絡協議会の活性化に努めている。
飯田孝仁さん:八百津町教育委員会 教育課長・海洋センター所長
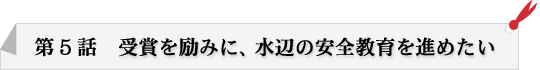
![]()
まず、海洋センターが活動をはじめた頃の状況についてお聞かせください。
昭和59年、海洋センターのオープンにあわせて8人の指導員体制を整えましたが(現アドバンスト・インストラクター2人、現アクア・インストラクター1人、現リーダー5人)、すぐに人手不足の問題が出てしまいました。
積極的な運営をめざして、町内はもちろん町外利用者の呼び込みにも力を入れたところ、予想以上の集客で賑わうようになったことが大きな理由でしたが、施設が分散していることも人手不足に拍車をかけました。
町を流れる木曽川の下流に艇庫があって、プールは上流のダム湖付近、そして体育館が町中にあったので、8人程度の指導員体制では効率の良い仕事ができなかったのです。施設間の移動に時間がかかるため、食事の時間も満足に取れませんでした。
そこで、海洋センターを管轄する教育委員会が町役場の課長会で現状を訴え、さらには町長にも直談判して指導員体制の充実を求めたところ、「町の職員が一丸となって海洋センターを支えよう」と、町長が声を上げてくれました。

オープン2年後の昭和61年以降、年を追うごとに指導員の数が増えています。このときを境に何か方策を打たれたのですか。
町長が声を上げてくれた後、タイミングよく岐阜県B&G連絡協議会が近隣の川辺町B&G海洋センターで2級育成士(現リーダー)の研修会を実施するようになったのです。
さっそく新人研修の一環として町の新人職員10人を派遣して資格を取ってもらい、忙しいときに手伝ってもらうようになりました。そして、以後、町役場に就職した新人職員は必ずこの研修を受けるようになったため、年を追うごとに指導員体制が充実していきました。
町の職員には担当部署の仕事があると思います。どのようにして海洋センターの応援に回るのですか。
これも町長の英断でしたが、資格を取った職員には必ず海洋センター兼務の辞令が出ました。ですから、担当部署の仕事に支障がない限り、誰もが納得の上で海洋センターの要請に応えてくれました。いま思えば、よくこのような仕組みができたものだと感心します。それだけ、町としても海洋センターに期待を寄せていたのだと思います。
![]()

海洋センターを手伝う際、担当部署の仕事を離れることを気にする人はいませんか。
最初の頃は、上司から「忙しいのは海洋センターだけじゃない」と言われる指導員もいましたが、毎年確実に指導員の数が増えていったので、それにつれて各部署の上司の理解も深まっていきました。
また、指導員の数が増えれば、それだけ海洋センターを手伝う1人あたりの機会も少なくなります。最初の頃は、夏場の2ヵ月たらずの間に1人4、5回ほどの要請が出たものですが、73人も指導員がいる現在は、1人あたり年に1、2回手伝う程度で済んでいます。
リーダー研修に参加することを嫌がる職員はいませんか。
一般職はもちろん、保育士や栄養士などにも参加してもらっていますが、おかげさまで「どうしてもできない」という声は聞いたことがありません。なかには、仕事の手伝いをするときに日焼けを気にする女性職員もいますが、そのような場合にはテント内の作業を手伝ってもらうなどの配慮をしています。
振り返れば、これまで25年にわたりリーダー研修を続けてきたおかげで、50歳以下の町職員は、ほぼ全員が指導員です。海洋センターを手伝う際、昔なら若手職員が担当部署の上司に手伝う内容をいろいろ説明したものですが、いまでは管理職も指導員を経験していますから、職場を離れる許可も阿吽の呼吸で行われています。
![]()

歴史ある組織ですが、これからはどのような活動をめざしていきたいと思いますか。
歴史があるだけに会員の高齢化が目立つようになってきました。最近は新人採用の数も限られてきているので、今後はボランティア指導員の確保が求められていくと思います。地域スポーツクラブの指導者などに呼びかけて、いまある充実した指導員体制を維持していきたいと思います。
もっとも、町職員の場合は活動中にケガをしても勤務扱いとなって労災を使えるので安心できますが、ボランティア指導員の身をどのように保障したらいいのか、方策をいろいろ考える必要があると思います。
ただ、今回の受賞は指導者会にとって大きな励みになりました。これを機に活動域を広めていきたいと思い、総会で取り上げられた水の事故ゼロ運動に大きな関心を寄せています。
現在、私たちも町内2カ所の小学校で出前カヌー教室を実施しており、そのなかで安全指導も行っていますが、これを5校ある町内すべての小学校に広めたいと思います。
そして、ここに全国指導者会が誕生したわけですから、地域の活動情報を交換しあいながら、水の事故ゼロをめざす運動を日本中に展開していけたらいいなと思います。
今後の活躍に期待しています。インタビューありがとうございました。