

 |
|||
 |
|||


平成6年(1994年)開設。保有施設は温水プール。児童公園やテニスコートなどを設けた「ふるさと公園」内に位置し、年間利用は少ない年で7万人弱、多い年で9万人以上を記録。平成9年にアクアリズムのモデルセンター指定を受け、以後、積極的に同プロラムを推進。平成17年にはプール外壁、館内塗装の修繕を実施した。
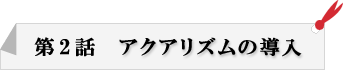
![]()

海洋センターの水泳教室を通じて、町内のほぼ100%の小学生が泳げるようになった明和町。かつては、町内の用水路で年に1、2回は子どもの水難事故が発生していましたが、おかげでそんな心配もしだいに解消されていきました。
こうした水泳の普及を底辺で支えたのが、町内の幼児を対象に海洋センターで始められた、B&G幼児運動プログラム・アクアリズム(以下、アクアリズム)でした。
「アクアリズムは、B&G財団で研究・開発された後、私どもの海洋センターが導入モデルの1つに選ばれて開始されました。海洋センターができて3年目の平成8年度に、まず実験的に始められ、その成果を確認したうえで翌9年度から正式な事業になりました」(海洋センター職員の石川春男さん)
小学生の水泳教室につながる、5歳児の年齢に合ったアクアリズムの指導内容に魅力を感じたという石川さん。すでに、同海洋センターでは小学生低学年児を対象にした水泳教室に力を入れていたため、アクアリズムを導入することで幼児から小学生につながる指導の流れができました。
「水泳を覚えるには、最初に水と触れ合うステップが大切です。アクアリズムは、水泳のスキルだけでなく遊びを通じて体を動かすことに重点が置かれているので、幼児の成長過程に応じた体力づくりをしながら、水に慣れ親しむことを覚えていきます。そのため、アクアリズム教室を終えた子のほぼすべてが、小学校に上がって以降、ごく自然に水泳ができるようになっていきました」
![]()

アクアリズムの導入に関しては、当時のセンター所長、金子春江さんも熱心でした。
「以前、保母をしていたので分かりましたが、アクアリズムのカリキュラムは保母のカリキュラムとよく似た作り方をしており、幼児の仕事に関わる人にとっては、とても理解しやすい内容でした。
とはいえ、私どもの海洋センターが全国で初めて実験的に試みた事業ですから、導入するにあたっては、地域の人たちからどれだけ関心が得られるかは未知数でした」
金子さん曰く、「暗中模索で始めた新事業」だったそうですが、教室の定員30人は、あっという間に集まってしまいました。住民の熱い要望によって誘致され、すでに小学生の対象だけでも4つの教室が稼動していた海洋センターゆえ、幼児対象のプログラムにも高い関心が寄せられたのでした。
![]()

海洋センターのアクアリズム事業は順調に推移し、地域の要望を受けて当初30人だった定員も10年目の平成17年度からは40名に増大。現在、海洋センターには正職員、臨時職員合わせて15人の指導員体制が整えられており、アクアリズムの時間には必ず6人が配置されることになっています。
また、同海洋センターでは60分単位で各教室の予定が組まれるため、本来は90分のプログラムであるアクアリズムを、導入4年目からは60分の教室に変える工夫も行いました。
「アクアリズムの基本部分はまったく同じですが、時間が短くなったり定員が増えたりするなかで少しずつ工夫しています。内容の一部を減らす代わりに、楽しい要素の多いプログラムの時間を長めに取るなどしてメリハリをつけ、飽きさせないようにしています。

また、水への顔入れ、潜る、といったプログラムの鍵になるアクアプレーにも長めの時間を用意して、十分に慣れてもらう工夫をしています。簡単に言えば、“楽しく、ちょっとがんばる”が、教室のモットーです」現、指導員:富塚かず子さん)
このほか、保護者に読んでもらうアクアリズムの説明書には、なるべく専門的な用語を避けながら読みやすい文面に工夫しているという同海洋センター。こうしたスタッフの努力によって、“泳げない子のいない町”づくりが着々と進められていきました。
(※続きます)