

 |
|||
 |
|||


平成6年(1994年)開設。保有施設は温水プール。児童公園やテニスコートなどを設けた「ふるさと公園」内に位置し、年間利用は少ない年で7万人弱、多い年で9万人以上を記録。平成9年にアクアリズムのモデルセンター指定を受け、以後、積極的に同プロラムを推進。平成17年にはプール外壁、館内塗装の修繕を実施した。
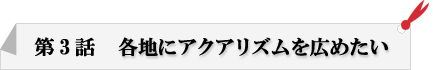
![]()

導入モデル・センターとして平成8年度に試験事業を行い、翌9年度から全国にさきがけてB&G幼児運動プログラム・アクアリズム(以下、アクアリズム)教室を本格的に開始した明和町B&G海洋センター。
最初の3年間は、当時のセンター所長、金子春江さんが陣頭に立って教室事業の定着に力を入れ、その後は富塚かず子さん(アクアインストラクター)が中心になって幼児たちの指導に励みました。
「以前、私は民間のスイミングスクールで働き、そのときも幼児を対象にした教室の担当をしていました。ところがその後、海洋センターに転職してアクアリズムを学び、とても大きな驚きを感じました。スイミングスクールとはまったく異なる発想のプログラムで構成されていたからです。
![]()

私が勤めていた民間のスイミングスクールでは、泳力を身につけ、それをさらにアップさせていく内容のプログラムが中心でした。しかし、アクアリズムは“幼児期からのこころとからだの健康づくり”という基本理念が根本にあって、水中での遊びを取り入れながら“水に慣れる”ことから入っていきます。
ですから、同じ幼児向けの教室でも内容が完全に違います。私は、泳力だけでなく、B&Gプランに則って、こころとからだを育てていくアクアリズムに共感を覚えました。また、一度に大勢の子どもたちを扱いながら、皆が一緒になって同じプログラムを進めていくことも、スイミングスクールにはない発想でしたので、とても新鮮に感じました」
アクアリズムと出合って、「自分の子も、このプログラムから入れば、きっと水が好きになるだろうな」と思ったという富塚さん。さっそく、海洋センターという新たな職場でアクアリズムの事業に取り組んでいきました。
![]()

仲間のスタッフとともに、今日まで明和町B&G海洋センターのアクアリズム事業を支え続けてきた富塚さん。そこで培われた貴重な指導ノウハウは、他の地方にも伝えられていくことになりました。
「一昨年に、B&G財団の指導者人材バンクに登録させていただきました。そのため、これまでに九州や四国の海洋センターに出向いて、アクアリズム事業推進のお手伝いをさせていただいています」
九州の福岡県朝倉市に行ったときは、「アクアリズム運動指導者実践セミナー」に参加して、県内の海洋センターから集まった大勢の受講者に向けて、アクアリズムの「事例発表」と「実技講習」を受け持った富塚さん。地元で培った10年間の経験を活かしながら、参加者の質疑応答にも熱心に答えました。
「機会があれば、どんどん他の海洋センターに出向いて、アクアリズムの普及に向けてお手伝いしたいと思っています。また、他の地方に行って、いろいろな人と出会うことは、自分自身の勉強にもなります」
![]()
他の海洋センターに出向くことは、自分のためにもなると語る富塚さん。実際、四国に出向いたときは、基本に戻ってアクアリズムを考えることができたそうです。
「四国での実践セミナーには、幼稚園の先生も参加していたので、『いつも砂場で遊んでいることをプールに入ってするだけです。ただ、水には注意してください』と、シンプルな話にとどめて、普段、幼稚園でしていることの延長で考えれば大丈夫ですと説明しました。
そのため、先生方もどんなことをしたらいいのかイメージできたようで、『それなら、私たちにでもできます』と言って行動してくれました。

子どもを指導する側がプログラムの枠にはまってしまうと、身動きができなくなってしまいます。また、細かく考えてしまうと、『道具がないから、これはできない』、とか『スタッフの数が足りないから無理』などという発想になってしまいます。
しかし、アクアリズムが持つ“幼児期からのこころとからだの健康づくり”という基本理念をしっかり頭に入れておけば、たとえ道具が何もなくても、水遊びを通じたスキンシップだけで、かなりの目的を達せられます。その風呂敷の広さが、アクアリズムの大きな魅力の1つだと思います。四国では、そのことを私自身も再認識することができました」
アクアリズムの本質を知っていれば、場所やスタッフの人数を問わずに、使えるものだけを使って活動メニューを考えることができると語る富塚さん。指導者人材バンクを通じて、これから先も、いろいろなところで富塚さんの活躍が見られることでしょう。
(※続きます)