

 |
|||
 |
|||
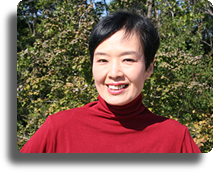

兵庫県芦屋市出身。神戸松蔭女子学院短期大学卒。西野バレエ団に所属しながら関西地区のテレビ、ラジオ出演を経て、21歳で女優デビュー。絵画活動にも励み、二科展入選のほか、2009年度「政経文化画人展」内閣総理大臣賞受賞。農林水産省、国土交通省関係を中心に公職も多数経験。現在、B&G財団理事。農業に関心が高く、休日には山梨県韮崎市郊外の農地で作物づくりに励んでいる。
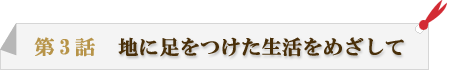
![]()

仕事を通じて再発見した、美しく豊かな国、日本。この恵まれた地にしっかりと足を下ろし、少しでも自然に感謝をしながら暮したいと、岸さんは願うようになっていきました。
そんな思いが形になったのは、いまから22年ほど前のことでした。山梨県に住む友人に、「休日には、父が好きだった富士山が見えるところで農作業をしてみたい」と話してみたところ、その友人が人を介して現在の場所を探してくれたのでした。
「現在の場所を紹介してくれた方をはじめ、地元の方々がとても親身にお付き合いをしてくださったので、すっかり気に入ってしまいました」
宅地申請が下りるまでに4年もかかりましたが、その間、地元の人達との交流が広がり、触れ合いの時間を大いに楽しみました。
「ここは単なる別荘ではありません。宅地申請が下りた後は、地元の棟梁に頼んでこの地に伝わる様式で家を建ててもらい、地元の神社の氏子になって地区会費も払っています。毎日は暮していませんが、家に来た際には近所の人たちと顔を合わせて、仲間としておしゃべりを楽しんでいます」
胸襟を開いて暮すことをモットーにしているという岸さん。東京でも、韮崎の家と同じように近所づきあいを心掛けて暮してきました。
「東京も地方も同じで、その土地に溶け込もうとしたら、それなりの努力が大切です。東京に家を構えたときも、その土地の人に受け入れてもらえるよう近所づきあいを大切にしてきました」
こうした人との触れ合いが、日々の生活のなかで楽しさを生むと語る岸さん。韮崎の家が完成したときには、地元の人たちが45名も集まって祝ってくれました。
![]()

念願の家ができたことで、地元の人たちとの交流がさらに深まっていきましたが、庭を耕して作物を育てる作業には厳しいものがありました。
「カチカチに固まっていた土地を夫婦2人で開墾していきましたが、それは尋常な作業ではありませんでした。でも、本当にそれが辛い仕事だったら、1、2年でこの暮しを止めていたはずです。
つまり、ここでの農作業は、たいへんだけれど遣り甲斐があって心地良いのです。クタクタになって寝転がれば快眠できますし、仕事の後の食事やお酒は格別です。


また、農作業をやりすぎると手がしびれて顔も洗えなくなりますから、自分の力の限界を知ることができます。言い換えれば、『もうこれが私の限界だ』などと言いながら土をいじることで、自然と対話をすることができるわけです。そんなときは、自分が地球に暮す小さな生き物の1つであることを知り、命の元ととなるエネルギーを大地からもらっている事を思うのです」
![]()
家の庭には実にさまざまな作物が植えられていますが、「自給自足をめざしているわけでも、憧れているわけでもありません」と、岸さん夫妻は口を揃えます。
「もし自給自足をめざすのであれば、定住する必要がありますし、もっと広い農地に牛や鶏なども飼わねばなりません。私たちが行っているのは週末だけの素人農業であり、自分たちで作ったものを皆で分かち合って喜ぶという、人づきあいの輪のなかにある農業です」
自分たちの農業は、あくまでも生活のなかの一部であると語る岸さん夫妻ですが、1つだけ大切に思うことがあります。
「私たちが農業に関心を寄せたのは、農業のテレビ番組を通じて『山の雪解け水が大地を潤し、そのおかげで米が育つ』ということを改めて知ったからです。スイッチ1つでなんでもできる便利な世の中になりましたが、人間として、もう少し汗をかき、地に足をつけて生きたいと思ったわけです。

ですから、私も主人も動力機械に頼らず、鍬を使って耕します。自分たちの力、自分たちの知恵だけを頼りに作業することで、少しでも人間としての生きる力を養いたいのです」
こうして育った作物は、とても愛しいと語る岸さん。日頃から、いろいろな作物を料理して楽しむそうですが、特に年末を迎える頃になると、1年の思いを込めながら自前の作物を使って、おせち料理作りに励むそうです。(※最終回に続きます)