

 |
|||
 |
|||


昭和27年(1952年)生まれ、北海道留萌郡出身。小平町教育委員会に就職後、旧センター育成士として地元海洋センターの運営に励み、カヌー、カッターの全国大会で何度も優勝を遂げるなど、海洋クラブの指導者としても活躍。現在は町の教育長を務めながら、海洋センター事業の発展に期待を寄せている。
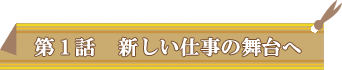
 日本海に面する小平しべ川の河口に艇庫(手前左下)と体育館(左中央)を備えた小平町B&G海洋センター。昭和53年に建設され、北海道では2番目に古い施設として知られています
日本海に面する小平しべ川の河口に艇庫(手前左下)と体育館(左中央)を備えた小平町B&G海洋センター。昭和53年に建設され、北海道では2番目に古い施設として知られています「右も左も分からないまま海洋センターへの配置が決まり、どのような研修を沖縄で受けるのかもまったく分かりませんでした。ただ、幸いにもすでにセンター育成士になっていた職場の先輩がいたため、いろいろ話を聞くことができ、沖縄に向かう前にカヌーの手ほどきを受けることもできました」
海洋センターに配置されていた木製のカヌーで乗り方の基礎を学び、安心した板垣さん。しかし沖縄に行ってからは、その苦労はあまり役に立ちませんでした。
「沖縄には最新式のFRP製カヌーが配備されていました。重くて船底が広い木製のカヌーと異なり、軽くて機敏な動きをするFRP製カヌーでは思うようにバランスを取れず、なかなか直進することができませんでした」 艇庫には建設当初からクレーンが設置され、浮き桟橋も確保されています
艇庫には建設当初からクレーンが設置され、浮き桟橋も確保されています「実習プログラムがしっかり組まれていたので、研修の間に自信を持って乗れるようになりました。カヌーもヨットも、自分の力で思ったところに走っていける楽しさがあります。自然と対話をしながら、自己を磨くことができる点が大きな魅力です」
沖縄で学んだのはマリンスポーツだけではありませんでした。同期の仲間と一緒に生活を送りながら深い友情を育むことができ、ともに助け合うことの大切さを知ることができました。
「研修の同期は26名いて、13名ずつ2の班に分かれて行動しました。そのため、いつもお互いの班が意識し合って切磋琢磨していきました。いまでも忘れないのは、水泳の練習です。毎日、夕飯前の自由時間を使って班の全員でプールに集まり、相手の班に負けないよう、水泳に自信のない仲間を皆で応援しながら自主練習に励みました。
この連体意識がなかったら、班の全員が水泳の修了試験に合格できなかったのではないかと思います。プールでの自主練習は、普段の生活では得ることができない、貴重な体験でした。班の仲間の多くとは、いまでも年賀状のやり取りをしています」 川に面した広い敷地に建設された体育館。現在、B&G財団の修繕助成を受けて外装の改修が進められています
川に面した広い敷地に建設された体育館。現在、B&G財団の修繕助成を受けて外装の改修が進められています沖縄から戻った板垣さんを待っていたのは、想像以上に忙しい日々でした。北海道で2番目にできた海洋センターということもあり、話題を呼んで町外からも利用者が殺到していたのです。
「当時の北海道では、あまりマリンスポーツは普及していませんでした。ですから、ここに来ればカヌーやカッターに乗れるということもあって、広く道内から利用者が集まりました。多いときには、1日で240名に対応したこともありました」
特に夏場は多忙を極め、自分の休みもなかなか取ることができませんでした。海洋センターに勤めていた間は、夏休みに我が子をどこかに連れていった記憶がないそうです。
 写真は今年実施された指導者養成研修の様子。いまから30年近く前、板垣さんも同じようにカヌーの実習に励みました。板垣さんが参加した昭和55年当時、センター育成士の研修には3ヵ月の期間が設けられていました
写真は今年実施された指導者養成研修の様子。いまから30年近く前、板垣さんも同じようにカヌーの実習に励みました。板垣さんが参加した昭和55年当時、センター育成士の研修には3ヵ月の期間が設けられていました「沖縄での研修後、人を指導することに自信がついて、地元の中学校でバレーボールの指導もするようになりました。ですから、いっそうプライベートの時間が少なくなってしまいましたが、センター育成士になった以上、指導者としてこれはやむを得ないことだと思いました」
沖縄から戻った板垣さんは、人前に出てなにかを話すことが得意になっていきました。研修を通じて、物事を相手にはっきり伝えることの大切さを学ぶことができたからだそうです。
完成したばかりの海洋センターを舞台に、研修で学んだことを励みに板垣さんは次々に新しい事業にチャレンジしていきます。(※続きます)