

 |
|||
 |
|||

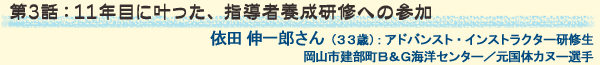

―高校まで水泳をしていたので、大学でも続けようと思いましたが、入った大学に水泳部がありませんでした。そこで、何をしようか考えていると、母の友人からカヌーを勧められました。
実は、母とその友人は学生時代にペアを組んでカヌーの選手をしていたそうで、この時点まで私はそのことをまったく知りませんでした。そして、母の友人から指導者を紹介してもらうことができました。
■ カヌーに乗った最初の印象は、どのようなものでしたか。―泳ぎに自信があったので、水面に出ることに関して不安はありませんでしたが、いきなり細長いレーシングカヌーに乗せられたので思うようにバランスを取ることができず、やきもきしました。しかし、練習を重ねて乗れるようになっていくにつれ、カヌーがおもしろくなっていきました。
■ 大学時代には、どのような目標を持って練習に励みましたか。 指導養成研修でカヌーに乗る依田さん。学生時代から競技で活躍したものの、海洋センターに勤務してからは自然に親しむレクリエーション活動のカヌーにも関心を寄せるようになりました
指導養成研修でカヌーに乗る依田さん。学生時代から競技で活躍したものの、海洋センターに勤務してからは自然に親しむレクリエーション活動のカヌーにも関心を寄せるようになりました―神戸の大学に通っていたのですが、両親の意向もあって郷里の岡山県で仕事を探すことになりました。その際、おかやま国体でカヌー競技の誘致を考えていた旧建部町から声を掛けていただき、国体選手を育成する仕事を兼ねながら海洋センターで働くようになりました。
■ 指導者としての腕を見込まれた依田さんですが、実際には選手としても国体に出場しました。その経緯を聞かせてください。―学生時代の私はフラットウォーター(平水面)の選手でしたが、国体選手の育成ということでワイルドウォーター(急流下り)も学ぶ必要がありました。そのため、自らワイルドウォーターの練習をしたところ、そのおもしろさに魅せられてしまったというわけです。
■ おかやま国体では、ご夫婦それぞれで出場し、ともに優勝しています。妻の聡子さんとはどのような出会いがあったのですか。―家内は、中学時代までB&G建部町海洋クラブでカヌーに乗り、いろいろなジュニアの大会に出ていました。しかし、高校に入った時点で海洋クラブは卒業ですから、高校生になった家内が新たな活動の場を求めて私のところにやってきたのです。
そのため、一緒に練習しながら地元の国体を目指していきました。平成10年に就職し、平成14年に結婚、平成17年に地元国体が開催された順になります。
■ 選手としては、夫婦でどのように意識し合いましたか。
―カヌー教室や海洋クラブの活動などで、子どもたちを連れて川下りをするようになってから、競技とはまた違ったカヌーの楽しさを見出すことができました。カヌーに乗れば歩いていけない対岸の岩場にもアプローチすることができるし、人の近寄らない岸辺で亀が甲羅干ししていたり、蛇が泳いでいたりといった自然の姿を垣間見ることができます。
これはとても貴重な環境教育だと思います。大人の私でさえ、自然のなかに包まれた自分に感動しますからね。こうしたことの積み重ねによって、海洋センターに勤めるようになってから、レクリエーション活動の大切さを痛感するようになりました。自然体験活動は、人間としての視野を大きく広げてくれます。 高校時代までは水泳の選手だったため、シュノーケリングで海に入ったときは仲間が自然に依田さんを頼って集まってきました(中央が依田さん)
高校時代までは水泳の選手だったため、シュノーケリングで海に入ったときは仲間が自然に依田さんを頼って集まってきました(中央が依田さん)―就職した当初は、地元国体を控えていたため参加する機会がありませんでした。その間は、町役場にセンター育成士の資格を持つ職員が複数いたので、いろいろ協力してもらいながら業務をこなしました。
また、2年前にも研修に参加するつもりで健康診断を受けたのですが、その結果、心臓に問題があることが分かって参加できませんでした。その後、治療をしてペースメーカーを入れるなどの処置を済ませたため、やっと今回参加することができました。活動の一部に制限があったものの、教官に配慮していただきながら晴れて研修を終えることができました。

―ビート板なんて単なる練習器具だと思っていましたが、これを使って子どもたちに速く泳げる気分を体験させるといった指導方法を教えていただき、とても感激しました。ただ練習するのではなく、気持ちの面で子どもたちをリードしていくことの大切さを知りました。
また、日々の生活が楽しくて仕方がありませんでした。異年齢同士で共に暮らす部屋割りによって、普段体験できないさまざまな年齢層の人たちと情報交換することができて、とても有意義でした。
また、県内各海洋センターとの交流は事あるごとに行っていますが、この研修を通じて全国規模の交流ができました。ここで知り合った仲間とは、末永く交流が続いていくと思います。これは同じ海洋センターで働く者としての大きな財産になっていくはずです。