

 |
|||
 |
|||


B&G YASU海洋クラブ:高知県香南市から旧国体施設の指定管理委託を受けているNPO法人YASU海の駅クラブを拠点に、平成18年に誕生。現在10名のメンバーがOPヨットやカヌーの練習に励んでおり、四国ブロック内の交流を深めるキャンプ活動も盛ん。
B&G YASU海洋クラブ代表 丸岡 克典さん:昭和28年(1953年)高知市生まれ。3歳で香南市夜須町に転居。高知工業高校卒業後、自動車修理会社勤務を経てマルオカモータース入社。夜須町青年団団長(20歳)、夜須町商工会青年部長(34歳)、夜須小学校PTA会長、NPO法人YASU海の駅クラブ理事長などを務める。
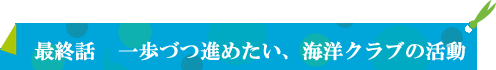
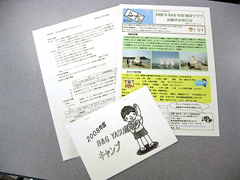
「ヨットやカヌーといったマリンスポーツばかりでなく、キャンプも子ども同士の交流を育むので、よく企画しています。昨年は、クラブメンバー全員で高知県の四万十町に行きました。
また、B&G四国ブロックの交流事業にも参画しており、昨年はクラブの子5名を愛媛県の海洋センターに連れて行き、他県同士で交流を深めました」
活発な活動を続けるB&G YASU海洋クラブですが、事業が増えれば増えるほど膨らむ悩みが出てきました。
「市町村が管理している海洋センター・クラブでは、キャンプなどの事業に行政から補助金が出たり、付き添いの職員にも休日出勤手当や出張手当てが支給されたりします。
ところが、私たちのような自主独立の海洋クラブでは、なかなかこうした予算を組むことができません。子どもたちが喜ぶほどに、資金面で頭を抱えてしまう状況が出るようになっていきました」 今年で3年目を迎えた「大人のヨット教室」。子どもの活動を大人にも理解してもらうことが大切です(写真:YASU海の駅クラブ)
今年で3年目を迎えた「大人のヨット教室」。子どもの活動を大人にも理解してもらうことが大切です(写真:YASU海の駅クラブ)「できることから始めようと思ったら、まずは保護者の存在に目が止まりました。海洋クラブで子どもを預かるだけでなく、その輪のなかにお父さんやお母さんたちも入ってもらって活動を手伝ってくれたら助かります」
海洋クラブの運営には、保護者の協力が不可欠だと述べる丸岡さん。OPヨットの活動が盛んなB&G別府海洋クラブでも、食料の買出しを手伝うなど、何らかのかたちで保護者がクラブ活動に関わっており、それがクラブを支える大きな力になっています。丸岡さんも、保護者をクラブ活動にどう絡めていくかが肝心であると指摘しました。
「地元の中学校ヨット部も同じ場所で練習しているので、ときには彼らにお願いして海洋クラブの子どもたちにヨットを教えてもらっています。ですから、ごく自然に子ども同士で交流の輪が広がっています。
また、地元の高校にヨット部はありませんが、ここで個人的に練習して国体に出た子もいて、皆の励みになっています。
このように、子どもたちを取り巻くヨットの環境は決して悪くはありませんから、焦らずに活動を続けていけば成果を上げることができるのではないかと思います」
旧国体施設に隣接している浜には、第1話でご紹介した海浜公園施設「ヤ・シィパーク」があって連日、大勢の来場者で賑わっています。丸岡さんは、ここでもヨット普及のための方策を考えました。
「かつてアメリカのマリーナ事情を視察した際、ある港町で30ドルほど払って帆船に乗ったことがありました。船内のキャビンで食事も出るというので割安だと思ったら、その帆船は生バンド演奏をしながら海に面したホテルの近くをゆっくり回っていきました。
つまり、割安の料金で人を集めて乗せる一方、生の音楽と帆船の姿をホテルのレストランに提供していたのです。
なるほどと思いましたが、帆船やヨットは絵になるわけです。時折、私たちも「ヤ・シィパーク」の沖合でヨットのデモンストレーション帆走を行い、一般の人たちから大きな関心を集めています。
B&G財団からいただいたアクセスディンギーも同じようにして大勢の人たちに見てもらっていますが、こうした活動は健常者、障害者を問わず、必ずヨットの普及に役立っていくと考えています」
どのようにして保護者の協力を仰いでいくか課題はあるものの、恵まれた海の環境を活かしながら、一歩づつ海洋クラブの活動を広めていきたいと語る丸岡さん。
うれしいことに、今年度は昨年度の倍近い22名もの子どもたちが海洋クラブに入会し、現在、夏に向けて元気に活動しています。(※完)