

 |
|||
 |
|||


工藤 祐直(すけなお)町長
1955年(昭和30年)生まれ。青森県南部町出身。大学卒業後、民間企業を経て青森県名川町役場に就職。海洋センター勤務となり、初代育成士として活躍。その後、農林課や企画課などを経て、平成12年に名川町町長に就任。
平成18年、合併による新生南部町の初代町長に就任し、現在に至る。野球、アイスホッケー、少林寺拳法などを愛するスポーツマン。B&G財団評議員。

 農林課時代、イベントで餅つきに励む工藤町長。1週間のイベント期間中、1日15回もついてヘトヘトになったそうです
農林課時代、イベントで餅つきに励む工藤町長。1週間のイベント期間中、1日15回もついてヘトヘトになったそうです「東北地方と言えば雪深いイメージが強いですが、名川町(現:南部町)ではあまり雪は降らず、果樹の栽培が盛んです。南国の作物であるバナナやパイナップル、みかんなどは無理ですが、それ以外なら何でも作れます」
町が果樹を中心にした農業で成り立っていることから、地域の農業支援に励んだ工藤町長。若手の農家を集めて果樹農業の勉強会を企画するほか、有志を募ってヨーロッパに遠征。農家に民泊するグリーン・ツーリズムを通じて、ヨーロッパの農業を学んだこともありました。
「ヨーロッパの農家の人たちは、昔の道具を大事にしながら現在もなお使い続けており、そのことに彼らは誇りを持っていました。私たちが泊まったのは、130年前に建てられた茅葺屋根の家で、地下水が流れる蔵を上手に使って冷蔵庫の代わりにしていました。日本なら、『古い家なんて恥ずかしくて人に見せられない』などと思う人もいるでしょうが、彼らの物の考え方はまったく逆でした。そのため、この旅では学ぶべきものがたくさんありました」
彼の地で行われている農業に感動した名川町の農家の人たちは、自分たちで資金を貯めて数年後に再び海外研修を実施。こうした経験を基に、名川町でも修学旅行の学生などが農家に泊まって農業を体験するグリーン・ツーリズム事業を企画するようになっていきました。
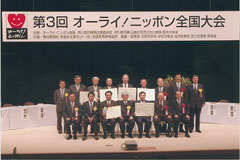 平成18年には、都市と農山漁村との交流に関する優れた取り組みを表彰する「オーライ!ニッポン」大賞を南部町が受賞。これまで行ってきた農業体験型観光が評価されました
平成18年には、都市と農山漁村との交流に関する優れた取り組みを表彰する「オーライ!ニッポン」大賞を南部町が受賞。これまで行ってきた農業体験型観光が評価されました「サクランボといえば、それまでは缶詰などの加工品向けの出荷が中心でした。そこで、リンゴのように生で食べていただこうと、昭和61年に『サクランボ祭り』を企画して観光農業に力を入れました。地元で取れるサクランボにはかなり自信があったのです。
すると、この祭りがマスコミで取り上げられて大反響を呼び、それから数年間は農園がサクランボ狩りの観光客で埋め尽くされました。駐車場や公衆トイレが足りなくなって、クレームの対応に追われたものです」
農家に泊まるグリーン・ツーリズムやサクランボ狩りの観光農業は、その後、新幹線が八戸まで延びるようになって、ますます注目されるようになっていきました。
 「オーライ!ニッポン」の表彰を受ける工藤町長
「オーライ!ニッポン」の表彰を受ける工藤町長「とても厳しい選挙でしたが、選挙運動で街角に立って声をからしていると、『がんばってー』という若い人たちの声援をよく耳にしました。いったいどんな人たちなのだろうかとよく見ると、それはかつて私が海洋センターで接した子たちでした。私が海洋センターにいるときに足繁く通ってくれた子どもたちも、このときはもう成人になっていたのです」
 小学校の運動会に参加する名川町時代の工藤町長。海洋センターに勤務した経験から、子どもたちが大好きです
小学校の運動会に参加する名川町時代の工藤町長。海洋センターに勤務した経験から、子どもたちが大好きです「当時は、できたばかりの海洋センターの運営を何とか軌道に乗せようと、私も必死でした。そのため、子どもたちを指導するにしても、かわいがったり持ち上げたりする気持ちの余裕はありませんでした。でも、一生懸命に面倒を見たことが彼らにも伝わっていたのでしょうか、私のことをよく覚えていてくれて選挙では大きな力になってくれました」
思わぬ支持者層を得た工藤町長。接戦となった選挙は、青年層の圧倒的な支持を得た工藤町長の勝利で終わりました。海洋センターで面倒を見た子の多くとは、いまでも交流が続いているという工藤町長。この記事のインタビューを受けているときも、「来週は、水泳を教えた子の結婚式に招かれているんです」と言って、笑顔を見せました。(※次回、最終話に続きます)