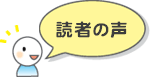
とてもよい記事だと思います。
中村真衣さんを応援している繋がりで、井本さんも以前から存じ上げていましたが、こちらを読みましてなおいっそう井本さんの素晴らしさがわかったような気がします。
現在井本さん活動に共感しまして unicef WSAM 等に小額ですが寄付させてもらっています。
子供達一人一人が笑顔で生活できるよう願っております。
 |
|||
 |
|||


井本 直歩子さん
1976年(昭和51年)生まれ。東京都出身。1996年、アトランタオリンピック4×200mリレー4位入賞。慶應義塾大学、米国サザンメソジスト大学卒業。国会議員秘書を経て、マンチェスター大学大学院で紛争・平和構築に関する修士号取得。2003年、JICA(独立行政法人 国際協力機構)のインターンとしてガーナで参加型開発に従事。04年からシエラレオネ、05年からルワンダで紛争復興支援に従事。07年からは国連児童基金(ユニセフ)のプログラム・オフィサーとしてスリランカで教育支援の仕事に就いている。

 現在、井本さんは国連児童基金(ユニセフ)のスリランカ事務所で、教育プログラム担当官として働いています
現在、井本さんは国連児童基金(ユニセフ)のスリランカ事務所で、教育プログラム担当官として働いています
「シエラレオネやガーナにいたとき、自分はマラリアにかかりませんでしたが、周りの人はみんな簡単にかかっていて、九死に一生を得た日本人の同僚もいます。シエラレオネでは、100人中27人の子どもが5歳まで生きられません。その大きな原因はマラリアですが、こうした問題は日本の人々の多くは知りません。
また、最初にWSMの話を聞いたときは、これを日本で広めるのは難しいなと思いました。日本人にとってのチャリティとは、単に募金することと一般的には思われがちだからです。ですから、『お金を集めるのが最終目的なのに、なぜ泳がなければいけないの』と、よく聞かれます。
チャリティマラソンなどは、ある目的のために誰かが完走を目指し、それを応援して募金する仕組みです。WSMの場合もこれと一緒ですが、多くの人にはなかなかピンと来ないと思います。目標は、同じ日に世界中のより多くの人がマラリア予防という共通の目的のために泳ぐことです。世界中のプールや海で、どこでどれだけ泳いでも構わないのです」
WSMに賛同して最初に泳いだ2005年は、ケニアの首都ナイロビのプールで10kmの遠泳にトライした井本さん。このときの感想は、WSMのホームページに「20年間自分のためだけに泳いできた私が、人のために泳ぐのはとても新鮮で、幸せなことでした」と記しています。
もちろん、井本さん本人が泳いだだけでは友人の頼みを受け入れたことにはなりません。井本さんは、中・高校時代にお世話になった大阪のスイミングクラブをはじめ、日本国内の主な有名スイミングクラブの経営者に会って、イベントへの協力をお願いしました。財団法人 日本水泳連盟も賛同し協力団体となり、さらに活動しやすくなりました。
 井本さんは、スリランカ各地に足を運んで学校を訪問して歩いています。この学校では教室が足りず、外で勉強している学年もあるそうです
井本さんは、スリランカ各地に足を運んで学校を訪問して歩いています。この学校では教室が足りず、外で勉強している学年もあるそうです現在、岩崎恭子さん、田中雅美さん、中村真衣さん、萩原智子さん、源 純夏さんなどのオリンピックスイマーがWSMのオフィシャルサポーターとして手伝ってくれていて、年々、参加者の数も増大。今年6月に開催されたジャパンオープン2008は、WSMの指定大会になりました(WSMのホームページはこちら )。
ちなみに、2008年4月5日前後を皮切りに同大会が開催された6月までの2ヵ月程度で2万821人が日本中のプールで泳ぎ、約150万円が集まりました。この募金のすべてで、およそ2800張の蚊帳を購入し、アフリカなどに届けられます。
ルワンダでの仕事を終えて帰国した井本さんは、外務省の試験を受けてジュニアプロフェッショナルオフィサー(JPO)の資格を得ました。JPOとは国連職員の登竜門で、この仕事の経験を経て国連の職員として働く人が少なくありません。井本さんは、国連児童基金(ユニセフ)のスリランカ事務所に昨年から赴き、現在、教育プログラム担当官として働いています。
 戦闘地域にあって先生が休みがちな学校もあります。足を使っていろいろな事情を聞いて回ります
戦闘地域にあって先生が休みがちな学校もあります。足を使っていろいろな事情を聞いて回ります
アフリカで活動したJICAの仕事は比較的短期でしたが、今度の仕事の任期は2年間です。昨年、赴任前には「腰を据えて仕事に取り組みたい」と井本さんは期待を膨らませていました。
「この仕事が天職かどうかは、いまのところ自分でも分かりません。60歳ぐらいにならないと分からないのかも知れません。とはいえ、スリランカでは2年の時間があるわけですから腰を据えて活動し、最後に成果が実感できるような仕事をしたいと思っています」
 訪れた学校の校長先生と会話が弾む井本さん。どんな人に会っても初対面から積極的に言葉を交わします
訪れた学校の校長先生と会話が弾む井本さん。どんな人に会っても初対面から積極的に言葉を交わします「特に私が積極的なのではなく、日本には引っ込み思案な人が多いのでしょうね。でも、人と会って臆していたら、お互いを知るチャンスを逃がすことになってしまうので、それは大変残念なことです。
また、英語が苦手だという人も多いですが、苦手だからといって英語圏の人たちより劣っているなんて思わないで欲しいですね。むしろ、英語しかしゃべれない国の人より片言でも英語をしゃべる日本人のほうが良いじゃないですか。ですから、とにかく間違ってもいいから、よくしゃべることが大切です。そうすることで、しだいに苦手意識もなくなると思います」
井本さんは、言葉の問題もさることながら世界を見る視野の広さが大切だと語ります。特に、将来を担う子どもたちには大きな目で世界を見て欲しいそうです。
「マスコミが発信するものばかりに目が向きやすい世の中になっていますが、日本のマスコミは視野が狭く、大切なことをあまり報道していないと思います。子どもたちには、まず好奇心を持って欲しい。そして、新聞を読むなどして自分なりに世界への関心を持って欲しいと願っています。芸能人ばかりを大きく取り上げるテレビを観るのも楽しいかも知れませんが、同時に、『いま、パレスチナではこんな動きが起きている』とか『海面上昇でキリバスが沈みかけている』といった世界のニュースにも目を向けて欲しいですね」
派手な話題ばかりに気を取られないで、世界中に自分のアンテナを張って欲しいと語る井本さん。自分なりの目で世界を見通す広い視野を持った子どもたちがたくさん出てくれば、食料やエネルギー、紛争、貧困といった世界を取り巻くさまざまな問題は将来、きっと解決の道に向かうことでしょう。
後に井本さんは、「何でもやってみることが大切。やってやれないことはないという気持ちで、できることからコツコツ積み上げていけば、徐々に自信がついていき、できないことはなくなっていくと思います」と、子どもたちへのメッセージを語ってくださいました。(※完)