

 |
|||
 |
|||


小野田 寛郎さん
1922年(大正11年)、和歌山県亀川村(現、海南市)生まれ。旧制海南中学校卒業後、商社員を経て陸軍予備士官学校、陸軍中野学校を卒業。1944年、敵地に残留し、味方の反撃に備えて諜報活動を行う特殊任務を受け、フィリピンのルバング島に派遣され、1974年、日本に帰還。翌1975年からブラジルに移住して牧場の開拓に尽力し、1984年以降は福島県で「小野田自然塾」を主宰。1999年、文部大臣・社会教育功労賞を受賞。2004年、ブラジル国空軍から民間最高勲章であるメリット・サントス・ドモントを授与されるほか、ブラジル国マットグロッソ州名誉州民に選ばれる。2005年、藍授褒賞を受賞。

 大人と子どもが力を合わせて食事の支度。親には、自分が知っている知恵を我が子に伝える義務があると小野田さんは強調します
大人と子どもが力を合わせて食事の支度。親には、自分が知っている知恵を我が子に伝える義務があると小野田さんは強調します「すでに社会に出ている親は、自分が世の中で生きていくうえで何をどうしたらいいのかを知っています。その知恵を我が子に授けなければなりません。言い換えれば、どうしたら自分の子が社会で生きていけるか、他人任せにしないで真剣に考えて教育してもらいたいのです」
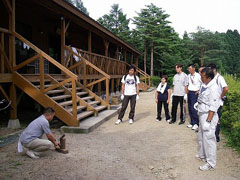 薪割りの仕方を再確認する親たち。生きる力を子どもたちに伝えるため、親たちにしても改めて学ぶことがたくさんあります
薪割りの仕方を再確認する親たち。生きる力を子どもたちに伝えるため、親たちにしても改めて学ぶことがたくさんあります「昔は、他人の子でも悪いことをしたら尻を叩いて叱ったりもしましたが、いまそのようなことをすれば、『余計なことをするな』と相手の親にねじ込まれ、最悪の場合は暴力を振るったなどと訴えられてしまいます。
現代社会がこうなった以上、親の役割はより大きなものになっています。単純に言って、子の尻を叩けるのは親しかいないからです。いまとなっては、尻を叩いて自分の子を叱ってくれる人なんて、家の外ではほとんど期待できません。ですから、ぜひ我が子が悪いことをしたら、心を鬼にしても尻を叩いて叱ってあげてほしいと思います」
 これからナイトウォークに挑戦です。最初は不安な様子の子も、しだいに暗闇に慣れていく我が眼の力に驚きます
これからナイトウォークに挑戦です。最初は不安な様子の子も、しだいに暗闇に慣れていく我が眼の力に驚きます ヨーイドンで、野原に隠された食材を探しに出るサバイバルゲームの参加者たち。どんな食事になるか、この時点では誰も想像がつきません
ヨーイドンで、野原に隠された食材を探しに出るサバイバルゲームの参加者たち。どんな食事になるか、この時点では誰も想像がつきません
一方、キャンプの終わりに実施する“サバイバルゲーム”では、“ナイトウォーク”と同じように個の可能性を求めるとともに、他人との協調性を学ぶ仕組みになっています。
これは、草むらに隠されたさまざまな食材をチームに分かれて探し求め、獲得した食材をどのように料理したら食べることができるかを考え、そして実際の夕食にするというプログラムです。
料理を考える際、見つけてきた食材のなかで不要になるものや、逆にどうしても足りないものが出てきます。
ですから、別のチームと食材を交換し合って料理を完成させなければ、夕食にありつけません。物々交換という最も原始的な社会的行為を通じて協調性を養います」
知らない間に、ゲームを通じていろいろなことを学ぶ子どもたち。一緒に行動する親たちもまた、そんな我が子の姿を通じて子育ての大切さを実感していきます。子どもたちと小野田さんとの会話1つ取っても、親にしてみれば大きな教材です。
「子どもからのお願い事や質問については、大人はしっかり聞いてあげることが大切です。最初から拒否してしまうのは、子どもにとってはわけも分からないまま怒鳴られているのと同じです。それでは子どもは必然的に親から離れていき、心を閉ざします。
 子どもの質問には、しっかり答えてあげる必要があると小野田さん。「君ならどうする?」と投げかけて、考えさせる工夫も必要です
子どもの質問には、しっかり答えてあげる必要があると小野田さん。「君ならどうする?」と投げかけて、考えさせる工夫も必要です
たとえば私の場合なら、『島で戦っていたとき、どうして村の人が飼っていた牛を取って食べちゃったの?』と聞いてくる子がいます。その際も、『他人のものを取れば泥棒だよね。だけど戦争で敵・味方だから、お金で売ってもらえないのだよ』と説明して、『君ならどうする?』といったやり取りをしていきます。
すると、『生きていくためには、やっぱりそれしか方法がなかったんだね』と言って納得してくれます。それに加えて『戦争』を考えるのです。
現代っ子は、有り余るほどの情報に囲まれているため、どれが正しいのか混乱することもよくあります。そのときこそ、遠回しではあるものの、こうした理論的なやり取りが必要です。正解を教えるのではく、考えさせることが大切です」
ちょっとした会話を通じて、人や社会の本質を学んでいく子どもたち。長く辛い経験を基に編み出された、“人間、一人で生きていくことはできない”という小野田さんの主張は、B&G「親と子のふれあいキャンプ」を含む自然塾のキャンプを通じて、大勢の親子に伝わり続けています。(※完)