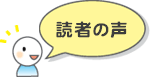
来年行けるか分からなぃけど また行きたぃです(*´∀`+◆!)
ありがとうございましたぁ♪
―1月11日書き込みの方―
 |
|||
 |
|||


小野田 寛郎さん
1922年(大正11年)、和歌山県亀川村(現、海南市)生まれ。旧制海南中学校卒業後、商社員を経て陸軍予備士官学校、陸軍中野学校を卒業。1944年、敵地に残留し、味方の反撃に備えて諜報活動を行う特殊任務を受け、フィリピンのルバング島に派遣され、1974年、日本に帰還。翌1975年からブラジルに移住して牧場の開拓に尽力し、1984年以降は福島県で「小野田自然塾」を主宰。1999年、文部大臣・社会教育功労賞を受賞。2004年、ブラジル国空軍から民間最高勲章であるメリット・サントス・ドモントを授与されるほか、ブラジル国マットグロッソ州名誉州民に選ばれる。2005年、藍授褒賞を受賞。
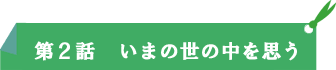
小野田さんは、ジャングルの戦いを通じて不思議な能力が発揮された経験を持っています。一度は、夕暮れ時に友軍の周囲を敵軍によって完全に包囲されてしまったときでした。本当に命を賭けなければいけないと必死になったその瞬間、頭が数倍の大きさに膨らんだ感じになって悪寒に襲われて身震いし、その直後、頭が元の大きさに戻ったと感じると、あたりがパーッと明るく鮮明に見えるようになったそうです。
 小野田自然塾でも定番のキャンプファイアー。火を使うことで人間は大きな進化を遂げましたが、小野田さんの体験を聞くと、太古に培った野生的な能力が体のどこかで眠っているような気がします
小野田自然塾でも定番のキャンプファイアー。火を使うことで人間は大きな進化を遂げましたが、小野田さんの体験を聞くと、太古に培った野生的な能力が体のどこかで眠っているような気がします命を賭ける場面が、命を賭けなくても大丈夫だという自信に変わった小野田さんは、難なくこのピンチを切り抜けることができました。
もう一度は、日本に帰還して検査のために入院していたときに分かったことでした。たとえ寝ていても、病室にやってくる人の気配を感じることができたのです。
「毎晩3回、巡寮の看護婦さんが部屋に入る前から気配を察し眼を覚ましていました。これは、島の生活を送るなかで知らぬ間に身についていた能力でした。初めての場所を偵察中、道の脇とは知らず仮眠をしてしまい、人の気配で眼を覚まし、別の場所に変えて、敵や住民をかわしたことが何度もありました。寝ていても警戒心は働いていたのです」
 力を合わせてテントを設営する子どもたち。自然のなかでいろいろな体験をすることによって、生きるための知恵や判断力が養われていきます
力を合わせてテントを設営する子どもたち。自然のなかでいろいろな体験をすることによって、生きるための知恵や判断力が養われていきます「特殊な能力は、本当に必死になったときでなければ表に出てきませんから、普通の生活を送るうえで必要はありません。しかし、少なくとも危険から身を守る能力や知恵、判断力は、子どものときに体験するさまざまな動作や遊びのなかで身についていくものだと思います。
あるとき保育園の人たちと会って、転ぶと決まって頭を打ってしまう子の話しが出ました。保育園の人たちは、どうしてこうなるのか困っていたのです。しかし、よく事情を聞いてみると、この子はかなり大きくなるまで歩行器を使っていたことが分かりました。つまり、ハイハイから自分で立つようになってヨチヨチ歩きに移る過程で、誰もが体験する“転んで痛い思いをする”、“転びそうになったら手をつく”といった転び方の動作がほとんどされていなかったというわけです。
転びそうになったら無意識のうちに手をついて身を守るという動作は、ヨチヨチ歩きのときに学習するものです。その経験がないまま歩けるようになってしまうと、転んでも無防備になってしまいます。また、手をついて身を守る動作は、思うように歩けないなかで学習するものなので、歩けるようになってからでは習得が難しくなってしまいます」
 セミの抜け殻を見つけて喜ぶ子どもたち。野外の生活を送るなかで、都会では体験できない楽しいことにたくさん出合えます
セミの抜け殻を見つけて喜ぶ子どもたち。野外の生活を送るなかで、都会では体験できない楽しいことにたくさん出合えますなぜ、体力が大事かといえば、体力が落ちて体がだるくなると集中力が続かなくなって、思考することが億劫になっていくからです。先日、石原東京都知事が『最近の子は、耐えることを知らなくなった』と語っていましたが、体力が落ちると、がんばれなくなって気持ちが折れてしまいます」
 キャンプサイトを出てトレッキングに向かう親子の参加者。小さい頃から十分に基礎的な体力を養っておくべきだと、小野田さんは力説しています
キャンプサイトを出てトレッキングに向かう親子の参加者。小さい頃から十分に基礎的な体力を養っておくべきだと、小野田さんは力説しています トレッキングで目的地に到着。地ベタリアンとは違って、汗をかいてひと休みする子どもたちは、すがすがしく見えます
トレッキングで目的地に到着。地ベタリアンとは違って、汗をかいてひと休みする子どもたちは、すがすがしく見えます
「地ベタリアンに関して言えば、実は軍隊で似たような経験をしたことがあります。作戦行動で雨のなかを40キロ歩いても、皆、泥沼になった道端に腰は降ろしませんが、引き続いて夜行軍になって夜中の2時を過ぎると、皆、泥沼の上でも腰を降ろして休んでしまいます。
要するに、疲れれば誰でも腰を降ろすということです。ですから、コンビニの脇にたむろする地ベタリアンは疲れているのです。朝シャンしないと気が済まないきれい好きな子でも、疲れてしまえば平気で汚れた地ベタに座り込んでしまうのです。結局、彼らは基礎的な体力に欠けているのです」
 火の起こし方を学ぶ子どもたち。自然のなかで生活するためには、なんでも自分たちで問題を解決していかねばなりません
火の起こし方を学ぶ子どもたち。自然のなかで生活するためには、なんでも自分たちで問題を解決していかねばなりません「キレるという言葉も、よく使われるようになりました。柳の枝のようにしなって耐えて、最後に折れるのではなく、いきなりポキッと折れてしまうわけです。つまり、最近の人たちには辛抱する訓練ができていないのです。
昔はみんな貧乏でしたから、子どもは何か買って欲しいものがあっても、親からダメだと言われて我慢しなければならない場面がよくありました。仕方なく泣き寝入りすることもありましたが、泣き寝入りすることで実は辛抱しているわけです。
子どものうちに何かを辛抱するということは、社会性を養う上で大切なことです。ですから、辛抱することを子どもの頃に経験しないまま、物事を理屈でしゃべる年齢に育ってしまうと、何か叱られても我慢ができず、理由をつけて社会に背くような行動に走ってしまうのです」
自然のなかに身を置けば、人に甘えることはできず、寒ければ耐え、水がなければ喉の渇きも我慢しなければなりません。多くの子どもたちを野外のキャンプに連れ出したいと考えた小野田さんの意図は、まさにここにありました。(※続きます)