

 |
|||
 |
|||
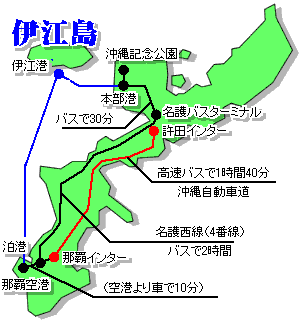
 お話いただいた伊江村役場の皆さん。中央は大城勝正村長です
お話いただいた伊江村役場の皆さん。中央は大城勝正村長です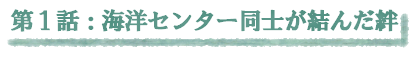
 島のシンボル城山を奥に控えたサトウキビ畑。ここでは、さまざまな農業が行われています
島のシンボル城山を奥に控えたサトウキビ畑。ここでは、さまざまな農業が行われています
「戦前の島の様子を知るお年寄りに聞くと、決まって『昔、この島はうっそうとした森で覆われていた』と話します。米軍が上陸する際、猛烈な艦砲射撃を受けて木々のほとんどが焼かれてしまい、島が丸裸にされてしまったのです」
緑を戻す仕事は、戦争が終わって各地から復員した島の人たちによって行われました。現在、海洋センターが隣接する「青少年旅行村」には、海辺のキャンプが楽しめる大きな森がありますが、これは戦後の植林事業によって生まれた場所です。
 キャンプ場や海水浴場などを持つ「青少年旅行村」。周囲を囲む森は戦後の植林事業によって生まれました
キャンプ場や海水浴場などを持つ「青少年旅行村」。周囲を囲む森は戦後の植林事業によって生まれました キャンプ場の木陰から望む美しい伊江島の海。日帰りレジャーではなく、ゆっくり楽しみたい場所です
キャンプ場の木陰から望む美しい伊江島の海。日帰りレジャーではなく、ゆっくり楽しみたい場所です
ところが、本島を縦断する高速道路ができたり、フェリーが就航して本島との間を30分で結ぶようになったりすると、島に遊びにやってくる人々の大半が日帰りのレジャーを楽しむようになりました。
「小さな島ですから、役場ぐらいしか勤めの仕事はありません。多くの住民が農業や漁業で生計を立てていますが、島の将来を考えたら、このような第一産業を大事にしながらも、何かもう1つ産業が欲しいところです」
自然豊かな島なので観光に力を入れたいところですが、日帰り客ばかりでは、あまり経済効果が期待できません。観光協会を中心に「見る観光」から「滞在して楽しむ観光」への移行が模索され始めると、できたばかりの伊江村B&G海洋センターのスタッフによって、実に興味深い企画が実施されるようになりました。
 キャンプ場に集まったB&G「親子ふれあい体験セミナー」の参加者たち。島の子どもたちが紹介され、これから一緒に遊ぶところです
キャンプ場に集まったB&G「親子ふれあい体験セミナー」の参加者たち。島の子どもたちが紹介され、これから一緒に遊ぶところですそんな2人が、いろいろな話を交わすなかで思いついたのが、海洋センター同士の交流でした。“海洋センターに通う子どもたちを、お互いの地元にホームスティさせてスポーツや体験学習で交流を深めよう。異なる土地の人たちと触れ合い、異なる文化や歴史を学ぶことで、相手をよく理解することの大切さを知ることができ、またそれは自分たちの郷土を大切にする思いを育むことにもつながっていく”
センター育成士となって地元に戻り、お互いの海洋センター事業が軌道に乗った平成6年、初めてのホームスティ交流が実施されました。この年の夏、旧高島町から41名の子どもたちが島を訪れ、2泊3日の日程でホームスティを楽しんだのです。宿泊先は、冬に旧高島町に行く島の子どもたちの家でした。
旧高島町の子どもたちを乗せたフェリーが伊江港に着くと、埠頭に集まっていた島の小学5、6年生全員が一斉にエイサーの踊りで迎えました。旧高島町の子どもたちは、びっくりしながらも大感激したそうです。
 「伊江村高島市青少年交流事業」で滋賀県のスキー場に行った伊江島の子どもたち。寒がる子は一人もいません!
「伊江村高島市青少年交流事業」で滋賀県のスキー場に行った伊江島の子どもたち。寒がる子は一人もいません!
島で生まれ育った子どもたちにとって、雪のなかで遊ぶのは初体験だったので、大喜び。スキーの上達も驚くほど早く、あっという間に雪に馴染んでいきました。
海洋センターのスタッフ同士のアイデアで始まった交流事業は、その後、毎年行われるようになっていきましたが、いくらホームスティとはいえ旅費などが必要なうえ、ホームスティ先に馴染めない子が出てくる懸念もあります。両海洋センター、そして伊江村や旧高島町の関係者は、こうした問題にどのように対処していったのでしょうか? 詳しい話は次回で紹介したいと思います。 (※続きます)