

 |
|||
 |
|||


本間 浩一さん
昭和30年(1955年)生まれ、東京都出身。日本体育大学に入学後、友人と始めたサーフィンに魅せられ、サーフィンのメッカとして知られる千葉県鴨川市に門を構える文理開成高等学校へ就職。1985年、生徒の要望を受けて全国初の高校サーフィン部を設立し、NSA(日本サーフィン連盟)の大会を中心に競技活動を展開。全日本ジュニア選手権4回制覇、2004世界ジュニア選手権優勝。現在、12名のOBがプロとして活躍中。
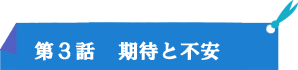
 学校の目の前に浜が広がり、毎日のように絶好の波が寄せます。生徒たちは自主的に練習を重ねて腕を磨きます
学校の目の前に浜が広がり、毎日のように絶好の波が寄せます。生徒たちは自主的に練習を重ねて腕を磨きます「部ができた当初は、いわゆる『体育会系のノリ』でしっかりメニューをこなす練習も考えましたが、海に出てしまうと生徒たちの行動はどうしてもバラバラになりがちでした」
刻々と変化する波に合わせて、それぞれが勝手に練習する生徒たち。陸から指示を出しても波の音にかき消されてしまうこともあり、結局、練習内容は個々の判断に委ねられていきました。
同じマリンスポーツでも、ヨットやカヌーはコースを設けて皆で同じ練習ができますが、個々の判断で波をつかまえ、臨機応変にパフォーマンス(演技)を決めるサーフィンでは、そうするしかないと本間さんは考えたのでした。
 総合的な学習の時間でサーフィンを体験する生徒たち。海に出ると浜からは声が届かないので、注意事項などは事前にしっかりと確認しておきます
総合的な学習の時間でサーフィンを体験する生徒たち。海に出ると浜からは声が届かないので、注意事項などは事前にしっかりと確認しておきますメニューや時間に縛られることなく、思う存分サーフィンを楽しむ生徒たち。本間さんの指導といえば、ときどき浜に戻る生徒にワンポイントでアドバイスを送るだけでしたが、彼らの腕は日ごとに上達していきました。
「鴨川の浜には、関東一円からたくさんのサーファーがやってくるので、彼らと同じフィールドで練習することも少なくありません。生徒たちは、常にさまざまなサーファーのパフォーマンスを見ており、プロと一緒に海に出ることもあって、いろいろな刺激を受けています。こうした恵まれた環境が、生徒たちの上達を大いに助けていると思います」
![]()
自主的な発想の練習、そして恵まれた環境。この2点がサーフィン部の活躍を支える大きな原動力になりましたが、恵まれた環境を地域学習に活かそうという発想で、6年前から今年度までにおいては、総合的な学習の時間でもサーフィンの授業が導入されました。
 総合的な学習の時間は男子のみでしたが、どうしても参加したいと願い出る女子は断り切れません。夏場になれば、ウェットスーツを持たない生徒も加わります
総合的な学習の時間は男子のみでしたが、どうしても参加したいと願い出る女子は断り切れません。夏場になれば、ウェットスーツを持たない生徒も加わります男子生徒に限ること。そして、生徒自らがウェットスーツを用意することが、サーフィンの授業に参加できる条件としましたが、女子や水着だけしか持たない生徒も集まりました。
「女子を断ったのは、着替えの世話ができないからですが、どうしてもやりたいという子に関しては入れてあげるしかありませんでした。また、ウェットスーツを持っていない子も、結局、夏場以外は見学ということで参加を認めることになりました。道具がないという理由だけで断るのも、ちょっとかわいそうな気がしたのです」
大変なことが分かっているにもかかわらず、授業に集まる生徒たちの世話を続けてきた本間さん。部活動についても同じことが言えますが、「学校の目の前でサーフィンができる、このすばらしい環境をできるだけ多くの生徒に体験してもらいたい」という気持ちに自分自身が押されてしまうのだそうです。
授業を任されつつ部活動に追われる本間さんには、生徒が知らない苦労がいろいろありました。
「同好会から部に昇格する際、『事故が起きた場合、学校には責任を求めない』という約束を学校側と交わしました。幸いにも、これまで人命に関わるような大きなケガは出ていませんが、もしそのような事態が起きたら、部は解散するしかありません。いまでも、絶えず頭のどこかでこの心配を抱えています」
 海に入る前は、極力、生徒と会話する機会を設けます。何気ない話でも、生徒の体調などを知ることができます
海に入る前は、極力、生徒と会話する機会を設けます。何気ない話でも、生徒の体調などを知ることができます「最近になってサーフィン部を持つ高校がいくつか出てきましたが、いまだに学校主体の大会は開催されていません。いま述べたような心配が学校にあるからです」
もっとも頭を悩ませるのは、波が高い日に練習するか、しないかを判断することだそうです。
「生徒たちに、『今日は波が大き過ぎるから、海に入るな』とはなかなか言えません。大きな波に挑戦することもサーフィンの魅力だからです。ですから、『海に入れてあげたいが、ケガをしたらどうしよう』と、いつも迷います」
悩みに悩んだ末、よほど荒れていなければ生徒たちを海に入れるという本間さん。しかし、このような経験を重ねてきた結果、いまでは生徒1人1人が自分の限界を考えて、適度なところで自主的に浜に戻ってくるそうです。
「自分の力量が分かる生徒ばかりで、助かります」という本間さん。生徒と接していれば、日々の苦労を忘れるひと時もいろいろあるそうです。(※最終回へ続きます)