

 |
|||
 |
|||


本間 浩一さん
昭和30年(1955年)生まれ、東京都出身。日本体育大学に入学後、友人と始めたサーフィンに魅せられ、サーフィンのメッカとして知られる千葉県鴨川市に門を構える文理開成高等学校へ就職。1985年、生徒の要望を受けて全国初の高校サーフィン部を設立し、NSA(日本サーフィン連盟)の大会を中心に競技活動を展開。全日本ジュニア選手権4回制覇、2004世界ジュニア選手権優勝。現在、12名のOBがプロとして活躍中。
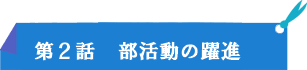
 練習の合間に撮影した部員たちの集合写真。現在、11名の部員が練習に励んでいます
練習の合間に撮影した部員たちの集合写真。現在、11名の部員が練習に励んでいます「取材されるのは仕方がないにしろ、有名になってしまったために、ちょっと困ったことも起きてしまいました。プロへの夢を抱く子どもたちや、我が子をプロにさせたいと願う親たちから、入学、入部の問い合わせを受けるようになっていったのです。
どんなスポーツも同じですが、プロというのは結果の1つに過ぎません。それを高校の部活動に求められてしまうと、あまりにも荷が重いし、そもそも高校の部活動の目的からすれば、少々的が外れています」
入部の問い合わせを受けるたびに、本間さんは「とにかく高校の3年間は、自分が納得するまで思う存分サーフィンを楽しんで欲しい」と説いて、最初からプロの道を考えている子や親をけん制しました。
「プロになれただけでは、食べていくことはできません。そこを踏まえたうえで、どんな目標を持って活動していくのかというビジョンを持たねば、プロになってもあまり意味がないのです。
しかし、プロになりたがっている子に、『プロになって、君は何をするの?』と聞くと、たいていの子は答えられません。つまり、プロになる夢だけしか目に入らず、現実が見えていないのです」
このような説明を受け入れられない子や親に対しては、入部を断り続けた本間さん。現在、同部からは12名ものプロが誕生していますが、それは部活動を通じて各部員が得た結果の1つに過ぎません。
![]()
 練習で巧みにボードを操る部員。学校の目の前に広がる鴨川の浜には、連日のように理想の波が寄せています
練習で巧みにボードを操る部員。学校の目の前に広がる鴨川の浜には、連日のように理想の波が寄せています「学校同士が競う大会はなかったものの、当時からNSA(日本サーフィン連盟)の競技は盛んに行われており、すでに中学生を対象にしたボーイズクラスや、高校生を対象にしたジュニアクラスなどが設けられていました」
サーフィン部の部員たちは、連盟の地方支部が行うジュニアクラスの予選会に挑みながら、その上に控える全国大会を目指していきました。
「NSAの大会では、何々支部の誰それという形で出場するので、エントリーリストに校名などは表記されません。ですから、競技で注目されると『彼は、どの支部?』という言葉が最初に交わされ、それから『どこの学校に通っているの?』となります」

「彼は地元周辺の浜でサーフィンに励み、中学時代には全国大会のボーイズクラスで優勝していたため、その実績から特待生で入学した子でした。他の競技では珍しくないスポーツ特待生ですが、彼はサーフィンで特待生になった日本初の高校生です」
部に昇格した後の入学だったことから、スポーツ特待生が認められた小川君。そんなプレッシャーに負けることなく、実力を存分に発揮してくれました。大会の表彰式で校旗がはためくことはありませんでしたが、会場の誰もが彼の母校を知っていました。

「私は同行することができませんでしたが、競技が終わるやいなや電子メールで知らせが届き、『これは大変なことになった!』と興奮してしまいました」
文理開成高等学校サーフィン部の名声は一気に上がりましたが、懸念も広がりました。4名もの全国チャンピオンを生むばかりか、世界も制覇したということばかりが注目されがちになっていったからです。
「私たちの部はプロの集団ではありませんし、インターハイのような高校スポーツの頂点をめざしているわけでもありません。それなのに周囲の期待は膨れる一方で、『この学校に入れたら有名な選手になれる! どうしても我が子にサーフィンをやらせたい!』と、親から泣きつかれてしまうケースも出るようになりました」
皮肉にも、部員が活躍すればするほど当初から抱えていた問題が高まっていきましたが、本間さんが考える部活動の方針には一点の変化もありませんでした。
「とにかくサーフィンを楽しむこと」。この単純かつ明快な発想は学校側にも理解されるようになり、やがて総合的な学習の時間でもサーフィンが選択科目の1つに取り上げられていきました。楽しむ先にあるさまざまな要素が、海に向かう生徒たちにいろいろなことを教えてくれるからでした。(続きます)