
高校時代、競技に集中して体調を崩してしまったものの、大学に入ってからはサークル的な活動も多かった水泳部に入って、仲間と一緒に泳ぐことの楽しさをみつけた鈴木さん。大学を卒業すると、地元に戻って3年ほど民間スイミングクラブで指導員のアルバイトを経験した後、鋸南町役場の職員になりました。

上手に用具を使い、浮かんで進む楽しさを体験する幼児たち。いろいろな教室で地道な活動が繰り広げられています
鈴木さんは、願い通りに海洋センター勤務の辞令を受け、施設の運営管理に従事するためB&Gアクア・インストラクターの指導者養成研修を受けることになりました。
「研修には泳げない人も参加していたので、それが私にとっては大いに勉強になりました。研修を通じて、泳げない人が泳げるようになっていく過程をしっかり目に留めることができたのです。
思えば、これまで私は泳げる人たちばかりの世界にいたこともあって、どうしたら泳げるのかということをすっかり忘れていました。ですから、泳げない人が疑問に思って教官に質問する内容はとても新鮮な意見に聞こえたし、参加者がいろいろな努力をしながらそれぞれの課題を克服していく姿は、指導者になるための自分にとっても大きな励みになりました」
アクア・インストラクターの指導者養成研修は、水泳の原点を再認識するとても良い経験になったという鈴木さん。研修が終わると、いよいよ地元の海洋センターで指導者としての生活が始まりました。


アクアキッズフェスティバルにも積極的に参加。単に泳ぐことだけでなく、さまざまな水遊びを楽しんでいます
「私が働いていた民間スイミングクラブでは、基準のタイムや定められた体の動かし方ができないかぎり、子どもたちは進級できませんでした。ですから、友だちがどんどんレベルの高い教室にステップアップしていくなかで、半年、1年経っても同じ教室にとどまる子も少なくありませんでした。
ところが、海洋センターの水泳教室では3カ月ごとに新しいクラスをつくっていたので、出席率が悪い子などは別にして、3カ月間しっかり通って毎回がんばって練習していた子は、タイムや泳ぎのフォームなどにこだわることなく、次のステップに進級させるようにしていました。
つまり、溺れない程度に泳げることが海洋センター事業の第一の目標であり、それができるようになった子どもたちに対しては、水泳を続ける努力の気持を進級の指標にしていたのです。こうした方針は、B&G財団のカリキュラムを基に海洋センターの先輩職員の皆さんがずっと継承し続けてきたものでした」
努力すれば進級できる。そんな仕組みは子どもたちの大きな励みとなり、いつもプールはたくさんの子どもたちで賑わっていました。鈴木さんにしても、進級して喜ぶ子どもたちの笑顔を見ることが、何よりの楽しみになっていきました。


アクアキッズフェスティバルに参加したときの様子は、壁新聞にしてプールのロビーに展示。次回、新たに参加する子どもたちへの参考材料にしています
「誰もが利用できる公共施設ということからすれば、教室に通う子どもを勝手に選抜して特別な教室をつくることはできませんし、仮に教室の回数を増やしたら保護者の金銭的な負担も増えてしまいます」
そこで鈴木さんが考えたのは、任意のクラブをつくって自主的な活動をすることでした。スポーツ団体ということであれば、プールの利用料金に関しても町から助成を受けることが可能でした。
「町の体育協会に協力してもらいながら、より水泳を学んでみたいという15名ほどの子の保護者と相談を重ねて、『鋸南スイミングクラブ』を立ち上げました。最初は週4回ほどの活動でしたが、現在ではほぼ毎日のように練習しています」

どこの施設でも経費節減が叫ばれていますが、ここではプールの再塗装も保護者などのボランティアで行いました

プールの底のラインも、手作業できれいに仕上げることができました
そのため、鈴木さんは体育協会などに呼びかけながら子どもたちの世話をしてくれるボランティアを集める一方、クラブの子どもたちにも協力してもらうことを考えました。
「海洋センターのプールはいろいろな人たちに利用されていて、泳げない人のためのコースも設けられています。そのため、幼児の頃から水泳教室に通って場慣れしている中学生などには、年下の子どもたちが別のコースに行かないよう声を掛けたり、自分たちのできる範囲で仲間に泳ぎを教えてあげたりするようお願いしました。私1人では限度が出てしまう部分を、クラブの子、皆が協力しあって補うようにしていきました」
これは、まさに鈴木さんが大学時代に経験した「できる人ができない人を教え、上級生が下級生の面倒をみながら、皆で水泳を楽しむ」発想と言えるでしょう。鈴木さんは、このような環境のなかで泳ぐ楽しさを再発見することができました。
鋸南スイミングクラブも、年上の子が年下の子の世話をしながら皆で泳ぐ楽しさを共有し、そしてまた、スポーツ団体として速く泳ぐことへの喜びを追い求めていきました。 (※続きます)
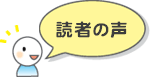


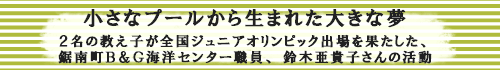



 上手に用具を使い、浮かんで進む楽しさを体験する幼児たち。いろいろな教室で地道な活動が繰り広げられています
上手に用具を使い、浮かんで進む楽しさを体験する幼児たち。いろいろな教室で地道な活動が繰り広げられています アクアキッズフェスティバルにも積極的に参加。単に泳ぐことだけでなく、さまざまな水遊びを楽しんでいます
アクアキッズフェスティバルにも積極的に参加。単に泳ぐことだけでなく、さまざまな水遊びを楽しんでいます
 どこの施設でも経費節減が叫ばれていますが、ここではプールの再塗装も保護者などのボランティアで行いました
どこの施設でも経費節減が叫ばれていますが、ここではプールの再塗装も保護者などのボランティアで行いました
 プールの底のラインも、手作業できれいに仕上げることができました
プールの底のラインも、手作業できれいに仕上げることができました

