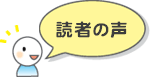
―H20年3月11日書き込みの方―
 |
|||
 |
|||

 針江地区の水田を見学する人々。地元では「針江生水の郷委員会」を立ち上げ、地域住民が交代でボランティアの案内役を務めています
針江地区の水田を見学する人々。地元では「針江生水の郷委員会」を立ち上げ、地域住民が交代でボランティアの案内役を務めています
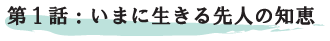
 「針江生水の郷委員会」の美濃部武彦会長(左)、ボランティアガイドの福田千代子さん
「針江生水の郷委員会」の美濃部武彦会長(左)、ボランティアガイドの福田千代子さん


この水路は、上流から下流に並ぶ数軒の家を経由して大きな水路へ向かうので、上流の家がゴミを流せば下流の家にすぐ知られてしまいます。そのため、どの家庭でも「水を大切にしないと『かばたろうさん』(河童)に連れていかれてしまうよ」と、我が子に言い聞かせてきました。
家の外に出ても、町中を流れる大きな水路の至るところに共同の洗い場が設けられているので、水を汚さないことは最低限のマナーです。針江の人たちは、幼い頃から家や地域の暮らしを通じて水を大切にする道徳心を身につけていました。
取材時は田植えの時期だったので、町中を流れる大きな水路は多少土が混ざって濁ってはいましたが、ゴミらしきものはまったく見当たらず、梅花藻(ばいかも)と呼ばれる藻が群生する水の流れは実に美しいものでした。
 町中を流れる大きな水路。田植えの時期なので濁っていますが、普段は透き通るような流れだそうです。左右に見える階段は共同の水場として使われています
町中を流れる大きな水路。田植えの時期なので濁っていますが、普段は透き通るような流れだそうです。左右に見える階段は共同の水場として使われています
そんな役に立つ魚たちですから、家の住人からすればペット以上に愛着が湧いてしまいます。先日も、30年間にわたって壺を守ってくれた鯉が死んでしまったため、家族を失ったかのように落ち込んでしまったお年寄りがいたそうです。

しかも、たえず流れる川端の水は台所自体の温度を調整する働きもあり、いまでも川端のある台所は冷蔵庫代わりに使われています。電気代もかからず、冷房のために排出する熱もない、これこそ環境にやさしい冷蔵庫であると言えるでしょう。
そんな針江の水文化に関心を寄せ、川端や水路のある家並みや周辺に広がる水辺の美しい風景をカメラに収め続けていたのが、写真家の今森光彦さんでした。今森さんの作品は地元でも話題になり、2001年に旧新旭町(現、高島市)が写真をふんだんに使って記念誌を発行すると、またたく間に県内外へ評判が広がり、2004年にはNHK総合テレビの番組で地域の水文化が紹介されることになりました。
 いまでも100年前の川端を大切に利用している田中三五郎さん宅の川端。大きな鯉を家族のように可愛がっています
いまでも100年前の川端を大切に利用している田中三五郎さん宅の川端。大きな鯉を家族のように可愛がっています
「川端や水路は昔から地域に根づいていた仕組みだったので、地元の人たちにしてみれば、特にこれが貴重な水文化であるという意識はありませんでした。ごく当たり前のこととして生活に溶け込んでいたのです。ですから、町の記念誌やNHKの番組を通じて、私たちも我が故郷の価値を再認識することができました」(針江生水の郷委員会会長、美濃部武彦さん)
自分たちの町が注目されるようになったことは喜ばしいことではありましたが、テレビの影響は大きく、放映と同時に全国からたくさんの人々が見学に訪れるようになりました。
「見学にやって来る人たちのなかには、地元の人に声をかけて湧水の水系や水路の構造などを詳しく尋ねる人もいて、聞かれる私たちが困惑してしまう場面も出るようになりました。また、川端は台所にありますから、たとえ外川端でも人家の敷地に入り込まなければなりません。そのため、見学者が増えることで地元の人たちとの間でトラブルが起きることも懸念されるようになりました」
これではいけないと、さっそく美濃部さんたち地元の住民が立ち上がりました。川端や水路を見学するルートを決め、地域住民がボランティアで案内役を務める「針江生水の郷委員会」を、行政の協力を得ながら発足させたのです。(※続きます)