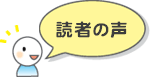
三豊市高瀬B&G海洋センター、身近な海洋センターの方が紹介されていたので興味シンシン楽しく読ませていただきました。―4月13日書き込みの方―
 |
|||
 |
|||

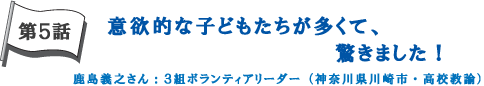


神奈川県川崎市の高校で英語を教えている鹿島義之さんは、これまでにボランティアで何度か研修事業に参加し、いろいろな子どもたちの世話をしてきました。
「昔からボランティアで働くことにとても興味がありました。そのため、大学時代には1年間休学し、客船で地球を一周しながら各寄港地の子どもたちにサッカーボールをプレゼントする企画に参加したこともありました」
船で地球を一周するチャンスなどは、めったにありません。この話を知ったとき、鹿島さんは一目散に応募したそうです。
「出港前からさまざまな仕事を手伝い、ツアー会社のスタッフとともに寄港地のイベントなども企画しました。世界中の子どもたちにサッカーボールをプレゼントし、その子たちと一緒にサッカーをして遊んだ思い出は貴重な体験となりました」

大学を出て高校の先生になってからも、鹿島さんは小学生たちを船に乗せて与論島へ行く研修事業に参加するなど、ボランティアの仕事にますます興味を抱いていきました。
「昨年、私が勤務している高校の先輩教師がB&G体験クルーズにボランティアリーダーとして参加しました。ですから、クルーズが終わった後にそのときの様子を聞かせてもらいましたが、そのなかで先輩の教師は『君は船旅の経験があるし、ボランティアに興味があるのだから、ぜひ来年は参加するといい。与論島もいいが、小笠原もいいところだぞ!』と勧めてくれました」
そんな話に心が動かされないわけがありません。鹿島さんは、何のためらいもなく今回のクルーズにボランティアリーダーとして乗船することを決めました。
船旅をする子どもたちの世話がどのようなものかは、おおよそ想像がついていたという鹿島さん。ところが実際に今回のクルーズが始まると、これまで携わったボランティアの仕事に比べて子どもたちの様子が少し異なることに気づきました。
「船酔いに苦しむ子も出て、それなりに大変な点はありましたが、とにかくたくさんの子がいつも元気にあいさつしてくれるので、驚くと同時にとても安心することできました。


これまでの経験からすれば、わがままを言う子が多く、プログラムをさせても、ちょっとしたことであきらめてしまう子が後を絶ちませんでした。ですから、ボランティアの仕事といえば、そんな子が出たら励ましなだめるといった役が多かったのです。
ところが、B&G体験クルーズでは、プログラムをするにしても自分からやってみようと努力する子が多かったので、なだめ役を覚悟していた私にとってはうれしい誤算でした。とにかく他の研修事業に比べて意欲的な子が多く、注意するようなことがあっても、それをすぐに守ってくれました」
子どもたちは、遊ぶときは大いに楽しみ、集合時間になれば頭を切り替えて身支度するといった、実にメリハリのある生活を送ることができたと語る鹿島さん。小笠原に着いてからは、子どもたちと一緒にカヌーで海に出て楽しいひと時を過ごしました。
「カヌーで沖に出ても、ずっと底まで見渡せるので驚きました。とてもきれいな小笠原の海で遊ぶことができたのは良い思い出です。
また、私の組に合流した小笠原の子と話をして感心しました。私の言うことをとても素直に聞いてくれるうえ、こちらが小笠原の動物や植物のことを尋ねれば、子どもながらにしっかりと語ってくれたからです。
家族や地域社会を通じて、ごく当たり前に大人と触れ合い、そして自分たちが暮らす小笠原という土地にとても愛着のあることが感じ取れました」
クルーズに参加した子どもたちの積極性に驚き、そして素直に育つ小笠原の子どもたちの姿に感動を覚えた鹿島さん。なんらかのかたちで、こうした体験を教師の仕事に活かしていきたいと語っていました。
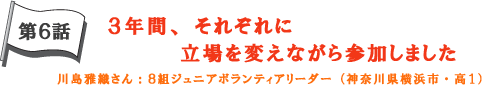


中学1年生のとき、「ふじ丸」を使った横浜市の少年洋上セミナーに参加した川島雅織さん。ふたたび「ふじ丸」に乗ってみたいと願っていると、翌年、ご両親が新聞でB&G体験クルーズの募集告知を見つけてくれました。
「少年洋上セミナーは中学生だけが対象でしたが、B&G体験クルーズは小学生も乗り込みます。ですから、出港前は自分より年下の子の面倒も見なければならないと考えて緊張しましたが、班長さんがいろいろ助けてくれて、すぐに班の仲間と打ち解けることができました」
このときの経験から、次は自分も班長として乗船したいと思った川島さん。翌年、班長になれる中学3年生になると、ふたたびご両親に頼んでクルーズに参加しました。
「最初にクルーズに参加したのは中学2年生のときでしたから、なにか心配事が起きたら中学3年生の班長さんを頼ることができました。ですから、今度は自分が班長として参加し、自分なりに努力しながら年下の子たちの世話をしてみたかったのです」

中学1年生の頃から、地元の社会福祉協議会を通じて、障害を持つ子どもたちと一緒に遊ぶボランティア活動に励んでいる川島さん。将来、看護士になりたいということから、いろいろな出会いを体験しながら人との接し方を学んでいるそうです。
ですから、クルーズで班長になった川島さんは、自分の班以外でも顔色がすぐれない子を見かけると積極的に介抱を手伝いました。船内の廊下でうずくまっている大人のスタッフを見かけ、「大丈夫ですか?」と声を掛けたこともありました。
「思うに、私は人が大好きなのだと思います。班長をしてみたかったのも、同じ班になった仲間のことを、より多く知りたかったのです。そんな気持ちが伝わったのでしょうか、班長としての仕事はスムーズに運び、年下の子を叱り付けるような場面は一度もありませんでした」
高校生になると、組リーダーを補助するジュニアボランティアリーダーの仕事が用意されています。昨年、この募集案内を手にした川島さんは迷わず手を挙げました。

「実は私、最初に参加したクルーズのとき、初日に熱を出してしまい、無理をしてプログラムに出ようとすると、組リーダーが『いましっかり休めば、明日から大丈夫だよ』と、笑顔を見せながら励ましてくれました。
ジュニアボランティアリーダー募集の案内をいただいたときは、このときの出来事を思い出し、今度は私が組リーダーのお役に立ちたいと思いました。
また、私はすでに2回もメンバーとして参加しているのですから、いよいよ私がメンバーになにかを伝える番がやって来たと感じました」
今回の乗船にあたっては、かつて自分を介抱してくれた組リーダーの笑顔を頭に浮かべたという川島さん。船酔いで苦しむ子や熱を出した子がいると、笑顔を意識し、いつも笑いながら子どもたちを励ましました。

「私が笑顔でいると、船酔いで苦しんでいる子も笑みを浮かべるようになり、それだけで自然に気分がすぐれていきました。
ただ、ジュニアボランティアリーダーは、あくまでもスタッフ側の仕事です。仕事の内容自体は班長とさほど変わりはないものの、プレッシャーの度合いがまったく違いました」
プレッシャーに圧されて落ち込んでしまうこともあったという川島さんですが、6日間、仕事をやり抜いたことは大きな自信につながりました。来年も参加して、今年以上に満足のいく仕事をしたいそうです。