|
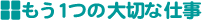
一年を通してクジラやイルカの生態を調べている森さんですが、こうした調査結果は協会に登録されているウォッチングのガイドさんたちへ常にフィードバックされています。前回に紹介したミナミバンドウイルカの社会構造などについても、1人1人のガイドさんたちにメールや勉強会を通じて伝えられ、その話がウォッチングにやってきた人々の好奇心を高めます。
 ガイドさんたちとの勉強会。イルカやクジラの肉をかじりとるダルマザメというサメの標本を見ながらデスカッションしています
ガイドさんたちとの勉強会。イルカやクジラの肉をかじりとるダルマザメというサメの標本を見ながらデスカッションしています
|
「私の仕事は、調査・研究ばかりではありません。ホエールウォッチング協会のスタッフとして働いているわけですから、ウォッチングのお客さんに情報を提供するほか、ガイドを育成することも大事な仕事です。ガイドさんは私以上にウォッチングのお客さんと接するわけですから、しっかりした知識を持って、それを分かりやすく人に説明する能力が求められます。ですから、常に調査・研究の成果を彼らにフィードバックしてあげる必要があるのです」
お客さんのなかには、とてもマニアックな質問を投げかける人もいて、驚くことがあるそうです。
「私のほかに、こんなにクジラに興味を持っている人がいるのかとびっくりします。クジラにしてもイルカにしても、いまだに謎の部分がたくさんあるわけですから、質問のなかには答がわかっていないものもたくさんあります。そんなときは、『分かりません』と答えるしかありません」
 夜の時間を利用してのナイトレクチャー。昼間ウォッチングしたことをスライドなどで解説し、クジラやイルカへの理解をより深めてもらう普及活動も実施しています
夜の時間を利用してのナイトレクチャー。昼間ウォッチングしたことをスライドなどで解説し、クジラやイルカへの理解をより深めてもらう普及活動も実施しています
|
答えられない質問が出ること自体に、ホエールウォッチングの魅力があるといいます。ただし、「分かりません」と突き放してしまったらそれまでですが、謎のベールに包まれたクジラやイルカをもっと一生懸命観察してみようと促せば、お客さんはさらに好奇心を高め、海洋生物の不思議な生態を通じて、躍動する地球の姿を垣間見ていきます。単に、お客さんを船に乗せてクジラを見せてあげるだけでなく、日頃の調査・研究で分かってきたことを情報として発信しながら、小笠原を含む地球環境の大切さを伝えていく。小笠原ホエールウォッチング協会は、そんな大事な仕事も担っているのです。
こうした地道な活動によって、小笠原のホエールウォッチングは全国に知れ渡り、現在では年間で延べ1万3,000人もの人がクジラを見にやってくるようになりました。
「サッカーのワールドカップなら1試合でこの何倍もの人を集めてしまいますが、小笠原に観光で訪れる人の数が年間1万7,000人ほどなので、島にやってくる人の多くがクジラやイルカのウォッチングを体験していることになると思います。1988年から始まった小笠原のホエールウォッチングは、90年代半ばで観客動員のピークに達し、その後、ほぼ横ばいで推移しており、成熟期を迎えて現在に至っています」
成熟期に入ったいま、どのようなホエールウォッチングの展開がクジラや人間にとって理想なのか、しっかり考えるときであると森さんは言います。
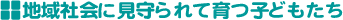
|
イルカウォッチングのルールの運用状況をモニタリング。イルカの生息環境の保全とウォッチングなどでの利用のバランスをうまく保つのも仕事の1つです
|
学生時代から調査・研究のため頻繁に足を運び、定住を決めて協会の仕事に打ち込むようになった森さん。当然のことながら、いまではすっかり地元の生活に溶け込んで、まさに公私ともに島の人となっています。
「私には10歳になる長女と7歳になる長男がいますが、2人とも小笠原で生まれ育っています。年に1回ぐらい、夏休みなどを利用して内地の実家に遊びに行っていますが、特に都会の暮らしに憧れている様子はありません。私としても、子どもたちを小笠原で育てることになって、とてもよかったと思っています。大学への進学など教育面を考えたら不便な点もありますが、いまの年頃なら自然豊かな島の環境で伸び伸びと育ってほしいものです」
子どもの生活を考えた場合、小笠原にはもう1つ大きな魅力があるそうです。それは、都会とは違って人と人との関係が希薄でなく、ほど良いつながりを地域として持っているため、心のゆとりを育んでくれるというのです。
「父島の小学校は各学年20人ほどです。そんなこともあって、校内でも校外でも年上の子は年下の子の面倒をよくみています。私の子どもたちも異なる年齢の子たちと仲良く遊んでおり、学校から家までは歩いて5分たらずの距離ですが、1時間近くかけて帰ってくることもしばしばです」
都会の場合、小学生が連絡もせずにそんな遅く帰ってきたら、親はさぞ心配することでしょう。しかし、小笠原ではそれが当たり前のことなので、親が気を揉むことはないそうです。
「なぜ、安心していられるかといえば、下校の道すがら島の誰かが子どもたちを目にしてくれているからです。危ない遊びをしようとしたら、他人の子どもでも注意してくれますし、転んでケガでもしたら声をかけて手当てをするなり、家に連絡してくれます。そもそも、地域の人たちはそこで暮す子どもたちの名前を知っていますから、何かあったら『誰々の家の何々ちゃんがたいへんだ』と声をかけあってくれることでしょう。また、困ったことが起きたら近くの家に行けばいいのです。子どもたちを地域社会が温かく見守ってくれている、島ではそんな助け合いの心が綿々と引き継がれているのです」
家庭の延長のような地域社会で、日々成長していく子どもたち。学校の帰り道に、ゲームセンターなどはありません。いったい、森さんの子どもたちはどんなことをしながら1時間も道草をしているのでしょうか。
「どんなことをしているのか私も気になったことがありましたが、よく考えてみると通学路を歩くだけで子どもの興味を引く自然がいっぱいあるわけです。グァバの実をとって食べたり、いろいろな木の実を拾ったりして遊んでいるようです。
私に言わせれば、道草ではなくて立派な自然観察や集団生活を身に付ける場ですね。また、夏休みになると毎日のように海で泳いでいます」
小笠原の自然のなかで、育つ子どもたち。そんな光景を目にしながら、森さんは海に出て調査・研究に励みます。「ここは、世界でもめずらしい場所です」と森さんが語る小笠原の海。そこにはクジラやイルカが集まるだけでない、とても大きな魅力が秘められているそうです。(※続きます)
|



