|
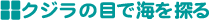
 休みの日も思わず海へ。小笠原の海はカヤックでも楽しめる小さな入江がたくさんあり、沖に出ればイルカやウミガメに遭遇することもあります
休みの日も思わず海へ。小笠原の海はカヤックでも楽しめる小さな入江がたくさんあり、沖に出ればイルカやウミガメに遭遇することもあります
|
クジラを調査・研究するために小笠原にやってきた森さんですが、この島にはクジラが集まるほかにもたくさんの魅力や不思議があるそうです。
「小笠原と言えば、いまやクジラやイルカウォッチングの代名詞のようになっていますが、夏になればアオウミガメや海鳥が繁殖のためにやってきます。小笠原は太平洋の真ん中にある本当に小さな島ですが、近くに陸地らしい陸地がないだけに、いろいろな生き物に恵をもたらす宝の島になっているのです。
大海原にポツンと浮かぶ生き物のオアシスという意味では、世界的でも数少ない場所と言えるでしょう。クジラやイルカといった鯨類の場合、いままで確認されただけでも20種以上が小笠原海域に分布・回遊することが知られています。こんな海、なかなか他では見当たりません」
クジラを調べ、クジラの目を通して海の中を覗いていくと、クジラ以外のいろいろなことが分かってくるそうです。このような着想も、クジラの調査・研究では大切な要素の1つです。クジラの生態を調べ、そこから掘り出されるさまざまな不思議を追うことによって、他の生物の生態をはじめ海や地球のメカニズムまでもが見えてくるのです。
「例えば、マッコウクジラは全長10メートルもあるダイオウイカを食べていることが分かっています。しかし、ダイオウイカについては、これまで死んで打ち上げられたごくわずかな記録しかありませんでした。深海に住んでいるので、なかなか生きた姿を目にすることができないのです。そのような人の目にほとんど触れることのない巨大なイカを、マッコウクジラたちはエサとして追いかけているのです。小笠原の沖合では、これまでにダイオウイカの破片が海面に浮かんでいるのが発見されています。1度や2度ではありません。何度もあるのです。全長10メートルのイカが深海を泳いでいる姿を想像してみてください。深い海の底で、マッコウクジラはそんな怪物と格闘しているのです」
ダイオウイカの生態を調べようと、森さんとB&G体験クルーズ(2004年実施)の講師を務めたこともある国立科学博物館の窪寺恒己博士は、水深1,000メートルまで耐圧カメラを降ろして深海生物を撮影する調査を行いました。3年越しの調査が実り、2004年の9月には、世界で初めて深海での生きたダイオウイカの撮影に成功しました。これまで、ダイオウイカはあまり活発に活動しないだろうと推測されていましたが、意外にも活動的であることなども判明しました。しかし、まだほんの少し、ダイオウイカのことがわかったに過ぎません。もし、ダイオウイカの姿を完全に捉えたいのなら、彼らを追いかけるクジラの背にカメラをつけてもらうしかないようです。
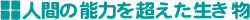
ここで、素朴な疑問が浮かんできます。思うようにカメラを操作することができない水深1,000メートルもの深海を、マッコウクジラやダイオウイカたちはなぜ自由に動き回ることができるのでしょうか。ダイオウイカは深海を住みかにしているため、その水圧だけに適応した体であることが想像できますが、マッコウクジラは水圧のかからない水面まで浮上して我々の目の前に現れます。水面から深海まで自在に泳ぐ彼らの体の仕組みはどうなっているのでしょうか?ちなみに水深1,000メートルとは、チタン合金でつくられた最新式の原子力潜水艦が、どうにか作戦行動できる範囲の深さです。
|
小笠原の海岸に打ちあがったクジラ(アカボウクジラ)の調査。このように漂着したクジラからもいろいろなことが分かります
|
「マッコウクジラは頭部に脳油器官という組織を持っており、この脳油の比重を変えることで深海までの潜航や浮上の補助をしているという説があります。また、水圧で体が押しつぶされても大丈夫なように、肋骨が可動式になっています」
人間が深い海でやっと行動できるようになった能力を、マッコウクジラは生まれながらにして持っています。このような謎解きに挑戦していると、誰でもどんどん興味が湧いてきてしまいます。
「よく、鯨類は頭がいいと言いますが、今のところどれだけいいのかは調べようがありません。ただ、海に適応する工夫は彼らなりにすごくしています。ですから、彼らがどんな方法でダイオウイカを仕留めているのか、とても知りたいですね。また、今年になってイルカが岸に打ち上げられる事件が続きましたが、なぜこのようなことが起きるのか、諸説はあるものの定かではありません」
人間にはない器官を持ち、それを巧みに利用しているクジラやイルカたち。私たちは、人間が地球上でもっとも進化した生き物であると自負していますが、物差しによっては、彼らのほうがはるかに進化した生き物になってしまいます。ひょっとしたら、クジラやイルカたちは、「人間って、潜るのが下手な生き物だな〜」なんて思っているかも知れません。

|
小笠原中学校2年生の総合的な学習の時間(2005年度)のテーマはイルカでした。自分たちが住む島の周りにいるイルカたちを知ろうと、レクチャーを受けたり、実際に海でイルカを観察したり。小笠原の島っ子ならではの授業となりました
|
毎年、B&G体験クルーズに参加した子どもたちは、森さんをはじめとする協会の人たちの案内でホエールウォッチングに出かけています。森さんは、どのような思いで、たくさんの子どもたちをクジラの海にいざなっているのでしょうか。
「まずは、こんな大きな生き物が海に泳いでいるということを実感してほしいですね。そして、少し気持ちに余裕が生まれたら、クジラが海でどんな生活をしているのか想像してみて、家に帰って自分なりに調べてもらえたらうれしいです。
そうすると、クジラと人間がこれからどのようにつきあっていったらいいのか、関心が湧いてくると思います。その答えは、1つではありません。それぞれの子が、それぞれに感じたことから勉強していけばいいのです。私がクジラから教えてもらったことは、私が自分で感じたことの結果なのですから、それは私がクジラからもらった答えでしかないのです。
ですから、その答えを子どもたちに押しつける気持ちはありません。クジラを通じて、自分が感じたこと、思ったことを大切にしながら自分なりの答えを見つける知的な旅に出てもらいたいのです」
|
総合的な学習の時間で、いろいろな質問を受ける森さん。小笠原の自然は、調べれば調べるほど、いろいろな興味が湧いてきます
|
自分の答えを押しつける気持ちはないそうですが、質問に対するヒントはどんどん出してあげたいと森さん。そのヒントから、自分なりに考える努力をしてもらいたいそうです。
「クジラや小笠原の自然に興味が湧いたら、どんどん島に来てください。クジラや小笠原の自然を思いやる気持ちを持つことによって、人の社会を思いやり、より良くするにはどうしたらいいのかという気持ちが育まれることと思います」
北の海から南の海まで、何千キロも移動しながら大海原を我が家のようにして生きているクジラたち。彼らの不思議は地球の不思議でもあります。その謎解きに取り組むことは、さまざまな意味において地球に暮す我々人間社会の未来につながる道でもあるのです。(完)
|



